 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

第109回:オーディオ処理のクラスタリングシステム
S/PDIFやadatで分散処理する「VST System Link」を検証する
S/PDIFやadatで分散処理する「VST System Link」を検証する
DTM・デジタルレコーディングの世界においては。プラグイン型のエフェクトやソフトシンセが数多く登場し、非常に便利に使えるようになった。
しかし、ものによってはかなりのCPU負荷がかかり、そこそこのCPUを搭載していても複数のプラグインを動かすと過負荷となってしまう。そこで登場したのが数台のPCを接続して分散処理させる「VST System Link」という技術だ。今回はこれを利用して、実際にどんなことができるのか、その仕組みがどうなっているのか検証した。
■ VST System Linkとは
コンピュータで負荷分散するためのクラスタリングという技術がある。これは、ネットワーク上に存在する複数のマシンで処理を分散させるという仕組みだ。デジタルレコーディングの世界にも、このクラスタリングのようなシステムが登場した。それがSteinbergが開発した「VST System Link」である。
これは複数のマシンを接続して処理を分散させるもので、たとえば2台のマシンを接続した場合、1台でレコーディングやミキシング、MIDIシーケンスといった処理を行ない、もう1台でエフェクト処理やソフトシンセの処理を行なう、といったことができる。それぞれが完全に同期の取れた状態で連携動作するので、タイミングなどに気を使うこともない。
ほぼ1年前にこの話をはじめて聞いたとき、ちょっとした勘違いをしていた。それは、EthernetでLAN接続した複数のマシンを使うものだと思っていたのだ。実は2、3年前に、筆者自身が「ネットワーク上でのリアルタイムセッション」というテーマでのソフト開発を数名で進めていたが、やはり同期をとることがあまりにも難しく断念したことがあったので、VST System Linkというものに非常に興味を持っていた。
しかし、実際にVST System Linkを見てみると、想像とは大きく異なる、Ethernetを使うのではなく、デジタルオーディオ接続を行なう仕組みとなっていた。つまり、LANケーブルの代わりにS/PDIFや、adatケーブルを用いて接続し、ネットワークを構築する。もちろん基本的にはオーディオデータが流れるのだが、そのオーディオデータとともにコンピュータ同士でやりとりする情報も流れるようになっている。そして、デジタルオーディオケーブルを利用しているため、サンプル単位での完全な同期を実現し、業務上でも十分活用できる分散処理のプラットフォームを構築したわけだ。
もう少し具体的に説明しよう。たとえばデータ形式が24bit/48kHzだった場合、24bitのうち下位1bitのみを使ってデータのやりとりをする。これならば23bit分は従来どおりオーディオを扱うことができ、ほとんど違いが感じられないものとなる。残り1bitでやり取りするのは、同期信号やポジションデータ、そしてMIDIデータなど。これによってお互い同期を取りながらデータをやりとりをし、分散処理を可能とする。
現在のところ、VST System Linkに対応している製品はすべてSteinberg製のもので、Cubase SX/SL、Nuendo、V-Stackの3種類。これらを接続することで、VST System Linkが実現するのだが、非常に面白いのは、Windows同士、Macintosh同士を接続できるのは当たり前として、WindowsとMacintoshを接続可能な点だ。
■ Mac-Win/Win-Win間で接続テスト
まず実際に、Mac OS上のCubase SXと、Windows XP上のCubase SXの接続を行なってみた。Macintosh側には「RME 96/8 PST」というオーディオカードを、Windows側にはFrontier Designの「WaveCenter/PCI」というオーディオカードが入っている。
共通点は、adatオプティカル対応のオーディオインターフェイスであること。adatに関する詳細は省くが、S/PDIFと同じくTOS-Linkのオプティカルケーブルを用いて接続するインターフェイスで、同時に8chのデータ送信が可能。今回はオプティカルケーブルでそれぞれのIN-OUTを2本のケーブルで往復させる形で接続した(図1)。
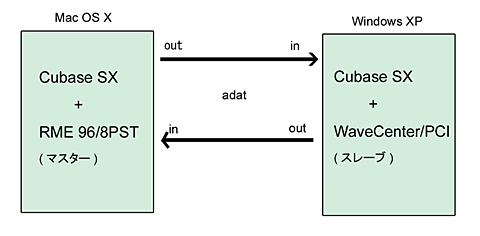 |
| 【図1】 |
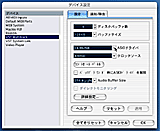 |
| オーディオデバイスの設定 |
物理的な接続はこれで終了だが、ソフトウェア上での設定がちょっとややこしい。まず、それぞれのCubase SXのオーディオデバイスをRME 96/8 PST、WaveCenterに設定するとともに、ASIOコントロールパネル(Macintoshの場合はドライバ設定画面)でRME 96/8 PSTをクロックマスターに設定後、バッファサイズを1,024sampleに、WaveCenterはスレーブにして128sampleに設定する。このバッファサイズはカードによって違うので、情報が公開されていればそれを利用し、なければ試行錯誤するしかないのが面倒なところだ。
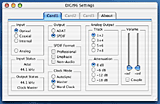 |
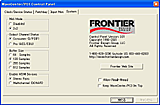 |
| RME 96/8 PSTをクロックマスターにし、バッファサイズを1,024sampleに設定 | WaveCenterはスレーブにして128sampleに設定 |
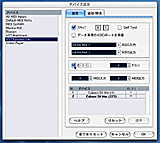 |
| 双方のマシンを認識 |
次にVST System Linkの設定項目において、お互いに接続する入力・出力ポートをそれぞれ設定する。もちろんこの際はお互いデータが届くよう同じポート番号を設定する必要がある。そして、VST System Linkをアクティブ状態にして、オンラインに設定すると、お互いのマシン名が表示されるようになる。これが見えればとりあえずリンクは成功だ。
またMIDI入力、MIDI出力という設定があるが、これを設定するとオーディオ以外の1bitの帯域にMIDI信号が流れるようになる。ただ、あまりにも流す情報量が増えるとオーバーフローしてタイミングにズレが生じる可能性もある。その場合は「データ専用のASIOポートを用意」にチェックをし、1bitだけでなく24bitをフルにデータ専用にしてしまうというのも手だ。
さて準備が整ったら、どちらをメインシーケンサとして利用してもいいのだが、ここではMacintoshをメインとし、Windows側でソフトシンセを動かすことにした。この場合、Macintosh側のMIDIトラックの出力先を一般のMIDIポートやソフトシンセではなく「System Link 1」とか「System Link 2」といったものに設定すると、Windows側にMIDI信号がリアルタイムに流れることになる。そして、このMIDI信号を受け取ったWindows側でソフトシンセを鳴らすわけだ。
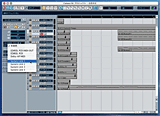 |
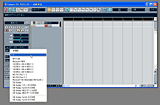 |
| Macintosh側のMIDIトラックの出力先を「System Link」に設定すると、Windows側にMIDI信号がリアルタイムに流れる | Windows側でソフトシンセの再生 |
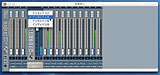 |
| Windows側の音をMacintosh上でミキシング可能 |
ここで鳴った音をWindows側でそのまま外部へ出力してもいいが、これをadat経由でMacintosh側に戻すことも可能。つまり、Windows側で鳴った音もすべてMacintoshでミキシングできるのだ。
実はこれがVST System Linkで、主にS/PDIFではなくadatが用いられるポイントになる。S/PDIFの場合LとRの2chしかないので、WindowsからMacintoshへ戻す際の制限があるが、8ポートあれば結構いろいろなことができる。もちろん、MacintoshからWindowsへオーディオデータを送って、Windows側でエフェクトを使って戻すといったことも可能だ。
ただし、adatはその規格上、最高48kHzまでしか利用することができない(2chを束ねて96kHzに対応するS/MUXという規格も存在するが、あまり一般的ではない)。場合によってはこれがネックになる可能性もあるが、8chがパラで利用できるというのは大きなメリット。もう1つの問題は、adatを往復接続させてしまうため、外部へadatで音を出すことができないということ。RME 96/8 PSTはアナログ出力が、WaveCenterにはS/PDIF出力が別途搭載されているので、ここからモニターできるものの、これはちょっと不便。SteinbergではVSL2020という2系統のadatを搭載しているが、こうしたものを利用するとさらに有効活用ができる。
さて、この設定において、MacintoshのMIDIトラックを再生し、WindowsへMIDIデータを送ってWindows上のソフトシンセを鳴らすとともにエフェクトをかけてMacintoshに送ってみたところ、実にスムーズにデータが流れた。しかもMacintosh側のCPU負荷はほとんどない状態。余っているマシンがあれば、こうした分散処理による活用は非常に有効的といえるだろう。もっとも、この分散処理は設定がすべて手動なのが面倒なところ。つまり、スレーブ側のマシンでソフトシンセやエフェクトを立ち上げ、それぞれのルーティングを設定しなくてはならない。まあ、1台のマシンでも同様の操作をするから当然のことかもしれないが、マスター側ですべてをコントロールできる分散処理ではないのが、多少まだるっこしく感じるところではある。
また、余っているマシンの有効活用にはなるが、そのマシンにadatを搭載する必要があるので、それなりの出費にはなってしまう。今後mLANがもっと普及し、IEEE 1394で接続するだけでVST System Linkが実現するようになると非常にうれしいところではあるが、その辺はどうなるのだろうか……。
そしてもう1つのネックはソフトウェアの価格。2台のマシンにCubase SXを入れるとなるとかなりの価格となってしまう。1ランク下のCubase SLでもVST System Linkは使えるが、それでも結構な価格だ。そんなユーザーのためにSteinbergはVST System Linkのスレーブ専用ソフトの「V-Stack」をリリースしている。オープン価格で実売9,000円弱なのでなかなか現実的だ。また前出のVSL2020というSteinbergのadatインターフェイスにもバンドルされているので、これを期に購入するというのも手だ。
V-Stackは今年はじめにリリースされていたが、筆者自身は今回はじめて使用する。今度はWindows同士の接続を試すためMacintoshからRME 96/8 PSTを抜いて別のWindowsマシンにセット。そしてやはりadatケーブルを往復で接続してみた(図2)。
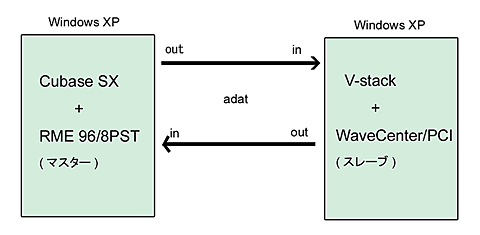 |
| 【図2】 |
V-Stackは日本語化されていないが、基本的な設定方法や画面構成などはCubase SXのものとほぼ同様。先ほどMacintoshとの接続で行なったのと同じ作業を繰り返したところ、すぐにお互いを認識し、同期させることができた。
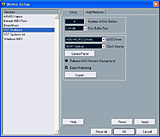 |
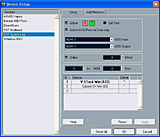 |
| V-Stackでも双方を認識し、同期が行なえる | |
しかし、スレーブ専用ソフトということでCubase SXを利用するのとちょっと違う点があった。それは、マスター側からスレーブ側へ送れるのはMIDI信号のみでオーディオ信号は送れないということ。V-StackはVSTプラグインのエフェクトも利用できるのだが、それはソフトシンセで鳴った音に対してのみであって、マスター側のトラックのデータにエフェクトをかけられるわけではない。VST System Linkを利用した人のほとんどが、ソフトシンセを利用するのを目的にしていると思われるので、大きな問題ではないだろう。
一方ラッキーな発見も1つできた。それはV-StackでCubase SXのプラグインがすべてそのまま利用できるということ。Cubase SXユーザーならご存知の方も多いと思うが、Cubase SXにバンドルされているVSTプラグイン、VSTインストゥルメントのほとんどは、ほかのホストプログラムから利用できない。無理に起動しようとすると、「このプラグインはCubase SXからしか起動できない」といった旨のメッセージが表示されてしまう。
しかし、V-Stackからは起動するとそうしたメッセージは表示されない。またCubase SXのプラグインはすべてVstpluginsというフォルダに収録されているが、そのフォルダをそのまま別のマシンに移しても利用することができた。これなら不法コピーには当たらないだろうし、Cubase SXで使っているソフトシンセ、エフェクトをそのまま利用したというユーザーも多いだろうから、それに応えられる形になっているようだ。
■ 軽快な動作感。今後の発展に期待
このように、2つの方法で接続して使ってみたが、結構面白い。レイテンシーも小さいし、お互いが完全に同期して動いてくれるのは軽快である。ただ、システムに多少の不安定さを感じたのも確か。それぞれ単独で動かしている分にはなんら問題ないのだが、VST System Linkで接続するといずれかのCubase SXが落ちてしまうことが何度かあった。もしかすると、オーディオインターフェイスに相性があるのかもしれない。Steinbergのサイトを見ると動作確認がとれているオーディオインターフェイスが掲載されているが、WaveCenter/PCIはそのリストにないので、これがネックだったのかもしれない。
今回検証はしなかったが、S/PDIFも試してみる価値はあるだろう。ただし、ASIO2.0に対応したドライバが必要であり、「MMEやDirectX、WDMドライバのみ対応のサウンドカードでは利用できない」とのことなので要注意。試しにASIO1.0対応のSound Blaster AudigyおよびAudigy2では接続したところ、うまく動作してくれなかった。今後、VST System Link関連で新しい情報があれば紹介していきたい。
□スタインバーグのホームページ
http://www.japan.steinberg.net/
□VST System Link解説ページ
http://www.japan.steinberg.net/news/new_release/vst_system_link/
(2003年7月28日)
| = 藤本健 = | ライター兼エディター。某大手出版社に勤務しつつ、MIDI、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆している。以前にはシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わったこともあるため、現在でも、システム周りの知識は深い。最近の著書に「ザ・ベスト・リファレンスブック Cubase SX/SL」(リットーミュージック)、「MASTER OF REASON」(BNN新社)などがある。また、All About JapanのDTM・デジタルレコーディング担当ガイドも勤めている。 |
 |
[Text by 藤本健]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|