 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第26回:ビクター独自デバイス「D-ILA」の実力は?
~ホームシアター参入第1弾「DLA-HX1D」~ |
 |
| 民生機初のD-ILAプロジェクタ「DLA-HX1D」。価格は120万円 |
今回は、長らく業務用製品として提供されてきたD-ILAプロジェクタのホームシアター向け第1号の実力を検証した。
■ 開口率が高く、画素間の隙間が少ないD-ILA
D-ILA(Direct-Drive Image Light Amplifier、ディ・アイ・エル・エーと読む)は、ビクターが'93年から開発を始めた映像素子で、量産は'97年から開始されている。
D-ILAはシリコン基板にアルミパッドを配列させ、これとガラス基板で液晶素子を挟み込んだ、反射型液晶素子だ。光を透過させるのではなく、液晶画素をシリコン基板の上に形成することからLCOS(Liquid Crystal on Silicon)とも呼ばれ、最近ではこちらの呼び名での認知度が高まっている。本連載で取りあげた日立製作所「CP-SX5600J」、ソニー「QUALIA Q004-R1」なども、LCOSデバイスを採用したプロジェクターだ。
一般的な液晶プロジェクタに採用されている透過型液晶素子では、光源からの光を液晶素子で「どのくらい通すか」を制御して映像の明暗、ひいては色表現を行なっている。透過型液晶素子では、液晶を駆動する回路やその配線が画素周辺を覆うことになり、これがいわゆる画素の格子目として投写されてしまう。いい方を変えれば、「画素開口率が低い」という弱点がある。
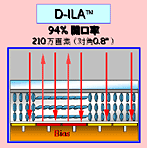 |
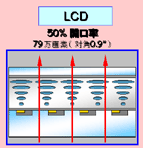 |
| D-ILA/反射型液晶素子(LCOS) | 透過型液晶素子 |
これに対し、LCOSデバイスのD-ILAでは、シリコン基板に鏡のような電極(反射画素電極)を配置し、その下に駆動回路を埋め込んだ構造になっている。図を見るとわかるが、D-ILAでは光を液晶で「どのくらい反射するか」を制御する。画素と画素を区切る隙間は反射画素電極の隙間しかないので、開口率は100%近くになるというわけだ。
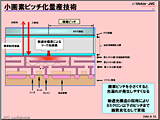 |
| 高密度画素LCOSパネルで問題となるリーク光を遮光する仕組み |
D-ILAの液晶モードは、多くの透過型液晶素子に使われる水平配向に対して、垂直配向を採用。これを無機配向膜で挟み込んだ構造になっている。無機配向膜は、耐光性に優れていることが知られているが、ビクター内での実験で寿命は10万時間以上と推察されている。
このD-ILAの製造には0.35μmプロセスルールが用いられているという。1、2世代前の枯れた半導体プロセスで製造することで、高歩留まりで低コストを実現している。高画素、高画質、長寿命、そしてローコスト。これがD-ILAの特徴なのだ。
D-ILA素子は現在、下図のようなラインナップがあり、これまでD-ILA採用製品は業務用のみだったが、今回紹介するDLA-HX1Dを皮切りに、今後は民生向け製品も意欲的に投入していく計画だという。
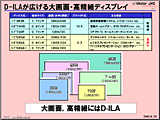 |
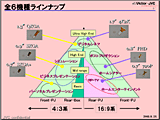 |
| D-ILAパネルのラインナップ | D-ILAパネルの種類ごとの用途 |
現在、開催中の「CEATEC JAPAN 2003」では1,920×1,080ドットのリアルHDTV解像度のD-ILAパネルを使った試作プロジェクターが展示中だ。
筆者も日本ビクター久里浜技術センターでこの試作機を見せて頂いたが、圧倒的なコントラスト性能と色再現性、階調の正確性に、正直、度肝を抜かれた。しかも、これはただのコンセプトモデルではなく、実際の製品化に向けての試作品とのことなので、D-ILAプロジェクタ導入を思案中の読者は、会場でその画質を確認してほしい。
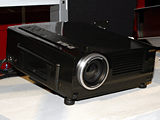 |
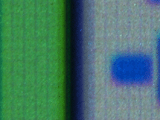 |
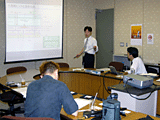 |
| CEATEC 2003のビクターブースで参考出品されたリアルHD対応モデル。投写デモも行なっている | ビクター久里浜技術センターにて、リアルHD解像度の試作機の投写画面を接写 | ILAセンター企画グループ長の柴田恭志氏(右)、デバイス部長の片山琢氏(中央) |
※資料提供:日本ビクター株式会社
■ 設置性チェック~D-ILAプロジェクタとしては最軽量
「DLA-HX1D」の本体重量は約6.0kg。ビクターが製品化したD-ILAプロジェクタとしては最軽量の部類に属する。本体側面に取っ手があり、持ち運びは容易。
本体サイズは298×360×134mm(幅×奥行き×高さ)で、設置面積はA4ファイルサイズノート並み。歴代のD-ILAプロジェクタと比べると随分コンパクトになった。
投写モードはフロント、リア、天吊り、台置きの全組み合わせに対応。天吊り金具は純正オプション「EF- SX21C」(7万円)が用意されている。天吊り金具と本体との総合重量は10kg前後、シャンデリア用の補強があれば天吊り設置は可能だと思うが、実際の施工には専門の業者との相談が必要不可欠だろう。
本体前方下部には無段階フットアジャスト機構を装備。左右片方ずつ上下させることで映像の回転角補正ができ、左右両方上げることで投写仰角を最大6度までプラスすることができる。垂直方向の台形補正は±30度まで可能なので、本などを本体前方の下に挟み込めばさらに打ち上げることが可能だ。また、水平方向の台形補正は左右±10度まで対応。よって、ある程度の斜め投写にも対応できる。ただし、垂直、水平方向ともにデジタル補正なので、補正が大きくなればなるほど画質は劣化する。
投写レンズは光学1.3倍ズームレンズを採用。100インチ(16:9)投影時の最短距離は約4.35mになる。数年前のホームシアター機としては標準的だが、最近の機種としてはやや長めだ。100インチ(16:9)投影には10畳から12畳以上の部屋の広さが必要になると考えた方がよい。
ズーム調整とフォーカス補正は本体上面に露出するリングを回すことで行なう。天吊り設置した場合も、このリングへのアクセス性は良好だ。
 |
 |
 |
| 正面。ボディカラーはブラックだが、形状はSX21Dとほぼ同じ | レンズ端にフォーカスリングを装備 | 操作パネルは本体上面の右側に配置されている |
投写映像は、ややあおり気味(約53.3%固定)に投影される。それほど上向きではないので台置き設置の場合、それなりの高さの台が必要になる。DLA-HX1D(DLA-SX21Dも同様だが)は、D-ILAプロジェクタとしては珍しくレンズシフトに未対応だ。よってスクリーン位置とプロジェクタ本体との位置関係は、設置前に入念にシミュレーションをしておく必要がある。
各ケーブルの接続面は本体側面に配置されているので、本体後部を壁に寄せて設置することで、投写距離を稼ぐことが可能のようにみえる。しかし、後部には排気スリットがあり、約300mmのスペースを取ることが奨励されている。よって「疑似天吊り設置」で良く使われる、本棚の中などへの設置は無理と考えた方がいい。
従来D-ILAプロジェクタは光源ランプとして色再現性に優れるキセノンランプを採用していたが、DLA-HX1DはDLA-SX21Dに続き、寿命とランニングコストに優れた高圧水銀ランプ(250W/NSHランプ)を採用する。交換ランプ「BHL-5006S」の価格は約4万円。キセノン系ランプの価格は10万円前後、寿命もキセノン系が1,000時間なのに対して、高圧水銀系は2,000時間ほどであることを考えると、D-ILAプロジェクタにしては低めのランニングコストといえるだろう。光源ランプは側面から脱着するタイプなので、天吊り設置の状態でも比較的容易に交換できる。
光漏れは背面と側面の吸排気スリットから若干ある程度。前面の吸気スリットからの光漏れはほとんど無し。ファンノイズは歴代のD-ILAプロジェクタと比較すると随分静かな方だが、最近のホームシアター機と比較するとまだまだ大きい。プレイステーション 2(SCPH-30000)と比較した場合でもだいぶ大きい。ユーザーの近くに設置した場合、かなり気になるだろう。静音性を重視したいユーザーは、視聴者の後方に天吊り設置するなどの対策が必要だ。
■ 接続性チェック~ビデオ系よりもPC入力系が充実
 |
| 本体右側に配置された入力端子部 |
BNC端子をコンポーネントビデオ入力として利用でき、コンポーネントビデオ入力も可能。ただし、できればヤマハ「DPX-1000」のようにBNC-RCA変換プラグを添付して欲しかった。
音声入力端子は、本機内蔵の1Wモノラルスピーカーを鳴らすためのもの。ただ音が鳴るというレベルのものなので臨時用やプレゼン用途以外で使用することはないだろう。TRIGGER端子は本機の電源投入中にDC+12V/100mAを出力するもの、主に電動スクリーンとの連動動作に用いる。REMOTE端子は別売りの有線リモコンを接続するためのものだ。RS-232C端子はPCと接続し、PC上のターミナルソフトから本機の設定変更や動作制御をするためのもの。
■ 操作性チェック~操作系、機能デザインはデータプロジェクター的
 |
| リモコン |
リモコンはDLA-SX21シリーズのものと同等品が付属する。単3電池を2本使ったタイプで手への収まりは良い。メニュー操作を行なう十字キーは、[ENTER]キーを楕円状に取り囲んだデザインで、指で触れただけで自分がどのボタンを押しているか把握できるようになっていて好印象だ。リモコン受光部は本体前面と背面の両方に実装。リモコンを直接本機に向けての操作はもちろん、スクリーンに反射させての操作レスポンスも良好だった。
しかし、リモコンのボタン自体に発光機能はないので、暗闇での操作性は悪い。また、DLA-SX21シリーズからの流用であるためか、リモコン上の[FOCUS]ボタン(2ボタン)、[SCREEN]ボタン(2ボタン)の計4つのボタンに何の機能も割り当てられていないのが何とも残念だ。
入力切り替えは[PC]、[VIDEO]の2つのボタンを使って行なう。[PC]ボタンでアナログRGB入力、DVI-D入力、BNC-アナログRGB入力の順次切り替え、[VIDEO]ボタンでコンポジットビデオ入力、Sビデオ入力の順次切り替えを行なう。コンポーネントビデオ入力は前述したようにBNC端子入力と兼用になっているため、[VIDEO]ボタンでなく、[PC]ボタンで切り替える。慣れてしまえば問題ないが、最初は戸惑うかもしれない。入力切り替え所要時間はコンポーネントビデオ入力→DVI-D入力で約1秒(実測)、Sビデオ入力→コンポーネントビデオ入力で約1秒(実測)と高速。
リモコンにアスペクト比切り替え用のボタンはなく、メニューの[設定]から行なう。リモコン上の[SCREEN]ボタンのうち[W]ボタンと[S]ボタンは、いかにもアスペクト比切り替えに使いそうだが、このボタンはDLA-SX21シリーズ用で、DLA-HX1Dでは使えない。ファームウェアのアップデートなどで対応できるものならば、是非有効活用できるようにしてもらいたい。
選択できるアスペクト比は[4:3]、[16:9]、[ズーム]の3種類。[ズーム]とは4:3画面の中に16:9を収めたレターボックス映像をフル表示させるもの。アスペクト比切り替えの所要時間はゼロに等しい。
画調パラメータは「コントラスト」、「明るさ」、「色の濃さ」、「色あい」、「シャープネス」、「色温度」があり、これらは各入力系統ごとに保存される。なお、色温度は6,500Kか、ノーマル、ユーザー設定の3種類しか選べない。メニュー画面の表示位置は投写画面の9カ所から選択でき、映像を画面に出しながら調整できる。
本機には映像種別に応じたカラープロファイル機能が搭載されており、「HDTV」、「NTSC」、「PAL」、「Mac RGB」を選択できる(貸出機は量産前のモデルだったため、SX21Dと同じ「sRGB」、「Mac RGB」、「EBU」などが選べた)。DVDで映画を鑑賞するには「NTSC」が最適とのことだ。
■ 画質チェック~最高レベルの色再現性と階調性。多少の調整で画質は上々に
 |
| 投写映像のアップ。ピンぼけなのではなく、こういう投写になる。若干、緑の色ズレが起こっている。パネル解像度が高いので映像全体では非常に微細なレベルだが、網目模様や縞模様が移動するシーンなどでチラつく場合もある |
映像エンジンは冒頭でも解説した反射型液晶パネルのD-ILAを3枚使って構成されている。使用パネルは0.64インチ、アスペクト比16:9の1,400×788ドット。
独特なパネル解像度だが、A4ノートPCなどで採用例が多くなっている、いわゆるSXGA+解像度と呼ばれる1,400×1,050ドットの横方向のみフルに使用している。なお、DLA-HX1Dの兄弟機ともいえるDLA-SX21Dは、SXGA+パネルの全域を使ったモデルだ。
100インチ(16:9)投影時でも、画素間の隙間はほとんど視認できず、中明色の単色領域でも、全く粒状感を感じない。解像感はかなりもので、画素間の隙間がほとんど視認できないことから、映像のリアリティは一般的な民生用プロジェクタを遙かに凌駕している。
ただし、白色領域のエッジに緑が見えることがある。投写レンズの色収差性能が良くないためか、色ずれが起きているのだ。様々な映像を見てみると、もともと色ばらつきの多い実写映像等では、パネル解像度が高いこともあって、表示映像の解像感にそれほど影響はないという印象だ。しかし、PC映像などのデスクトップに浮かぶ白い文字は、滲んだ感じになる(DVI-D入力であっても)。
コントラストは800:1。D-ILAプロジェクタとしては最上位にあたる。「黒浮きがない」とはいい切れないものの、明るい方のダイナミックレンジが高いので相対的な暗部の沈み込みは良好だ。
階調性は非常に優秀で、本連載で取り扱ってきたプロジェクタの中ではトップクラスといっていい。マッハバンドは皆無で、グラデーション表現はナチュラルでなだらか。暗部の階調表現も実に正確で「明るいところから暗いところまでがしっかりきっちりスクリーンに出ている」という手応え。
色深度も驚くほど深い。これも本連載で取り扱ってきたプロジェクタの中ではトップクラスだと思う。混合色のグラデーションも実に味わい深い自然さで、ビクターの画作りのこだわりが感じられる。後述する色補正を行なえば、純色の発色も鮮烈。色信号のポテンシャルを最大限に活かした投写が行なえる。
ただし、高圧水銀ランプの特性からか、緑が強く出る傾向にある。これは「色温度」調整パラメータで色温度を6,500Kにするか、ユーザー補正を行なうと格段に改善される。具体的には、強い緑を弱め、水色っぽい白を純白に近づける目的で、「RED」→0(デフォルト)、「GREEN」→-90~-70、「BLUE」→-20~-10にすると良くなる。
【入力ソースごとのインプレッション】
●DVDビデオ(コンポーネントビデオ入力) 映像は色表現のダイナミックレンジの広さからか、立体感にあふれている。人肌の発色もリアルで、プロジェクタの投写映像であることを忘れさせるほど美しい。暗部から明部までを正確に描写し、映像のディテールを余すことなく再現している印象。この画質は確かに「ホームシアター機」をうたうだけのことはある。 インタレース映像も問題なく2-3プルダウン処理されるため、ジャギーやコーミング、ちらつきもなく、映像が持っている本来の情報が過不足無く投写されている印象だ。
●S-VHSビデオデッキ(Sビデオ入力) ちらつきは全くなく、ジャギーも皆無で、見ているとインタレース映像であることを忘れてしまうほど自然な形でプログレッシブ化されている。縞模様や編み目など、周波数の高い映像ではクロスカラーに気がつくこともあるが、発色が鮮烈で、色ディテールの再現性も高いので、映像としての印象は良い。 ●ハイビジョン(コンポーネントビデオ入力) 1,920×1,080ドット(インタレース)の映像が1,400×788ドット(プログレッシブ)化される。画素数は約半分に減るが、ハイビジョン映像が持つ解像感はそれなりに出ている。1,280×720ドットパネルの採用機と比較した場合、解像感に関してそれほど大差はない。画素数の差を考えれば、1,280×720ドット採用機よりも、もうちょっと高い解像感が得られるべきだと思うが、これは前述した色ずれが起因しているのだろう。とはいえ、総合的に考えれば、ハイビジョン映像の表示クオリティは実用レベルに達している。 ●PC(DVI-D入力) PC入力時には「リサイズ」モードという設定を利用できる。
- 1:1……入力映像を変換せず、パネルの各画素に1:1で表示させる。アスペクト比は元ソースの解像度を維持する。
- パネル……入力画面を1,400×788ドットに強制的に拡大縮小して表示する。アスペクト比は16:9になる。
- アスペクト……元ソースのアスペクト比を維持しながら、1,400×788ドットパネルで表示できる最大サイズに拡大/縮小して表示する。
- ズーム……入力画面をアスペクト比4:3と仮定し、レターボックス範囲を1,400×788ドットに拡大/縮小表示する。
解像度 1:1 パネル アスペクト 640×480ドット ○ - - 800×600ドット ○ - ○ 848×480ドット - ○ - 1,024×768ドット ○ - ○ 1,152×864ドット - - ○ 1,280×720ドット - ○ - 1,280×768ドット - ○ - 1,280×960ドット - - ○ 1,280×1,024ドット - - ○ 1,360×768ドット - ○ - どの画面モードも表示は実用レベルで、つぶれや拡大縮小ミスもない。このあたりはさすがはデータプロジェクタという生い立ちを持つだけはある。パネル全域を使いつつ、もっとも解像度が高く、なおかつ表示品質が高いのは1,360×768ドットモードだ。
1つ気になったのは、アスペクト比16:9の画面モードでリサイズモード「1:1」が正しく動作しないという点。1,360×768ドットも1:1モードにすると表示がおかしくなる。この点は改善を望みたい。
●ゲーム(コンポーネントビデオ入力) 通常のラインダブラでプログレッシブ化された映像と違い、PS2のインタレース映像が高い解像感を保ったままプログレッシブ表示されている。非常にアナログ的な表示で、固定画素パネルでの表示であることを意識させない。インタレース映像特有のちらつきも上手く取り除かれている。画面が激しく動いても色ずれはなく、また残像も感じられない。
■ まとめ~荒削りな機能性の中に光る高画質
画質は一級品で文句はなし。画質さえよければいい……というユーザーはともかく、AV機器として見ていくと、細かいところで気になる点が多い。
まず、接続性、操作性などの機能デザインがデータプロジェクタそのままで、残念ながら「ホームシアター機のために登場した」という必然性があまり感じられない。また、決して安くはない価格の機器で、しかもホームシアター用途を訴えるのであれば、自発光機能付きの専用リモコンくらいは付けないと多くのユーザーが納得できないのではないかと思う。特に、使用不可のボタンが並ぶリモコンはあんまりだ。「D-ILA初のホームシアター機」という触れ込みで登場したDLA-HX1Dだが、本質的にはD-ILAパネルをワイドに使い、本体を黒塗りにしただけ……、という印象が拭えない。
とはいえ、色表現と映像の描写力については一級品だと保証できる。本文でも指摘したように、光学系のリファインを行ない、色収差を低減すればさらなる高画質化が望めることだろう。
さて、DLA-SX21DとDLA-HX1Dのどちらを購入すべきか? 公称最輝度はDLA-SX21Dが1,500ANSIルーメンと明るく、コントラスト比は同じ。パネル解像度はDLA-SX21Dが4:3の1,400×1,050ドット。16:9のDVDを見る際には、両機種共に1,400×788ドットで表示されるので互角。PCやゲームなどの4:3コンテンツ投写を重視し、もう少し明るさが欲しい人はデータ用のDLA-SX21Dを選択した方がよいだろう。
□ビクターのホームページ
(2003年10月10日)
[Reported by トライゼット西川善司]
http://www.jvc-victor.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.jvc-victor.co.jp/press/2003/dla-hx1d.html
□関連記事
【10月3日】ビクター、初のD-ILA搭載ホームシアタープロジェクタ
-1,400×788ドットのワイドパネルを採用
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20031003/victor.htm
【8月25日】ビクター、初のホームシアター向け高精細D-ILAパネルを開発
-フルHD対応プロジェクタを年内に投入予定
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030825/victor.htm
= 西川善司 =
ビクターの反射型液晶プロジェクタDLA-G10(1,000ANSIルーメン、1,365×1,024リアル)を中核にした10スピーカー、100インチシステムを4年前に構築。迫力の映像とサウンドに本人はご満悦のようだが、残された借金もサラウンド級(!?)らしい。
本誌では1月の2003 International CESをレポート。山のような米国盤DVDとともに帰国した。僚誌「GAME Watch」でもPCゲームや海外イベントを中心にレポートしている。

| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|