 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
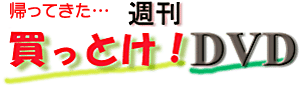 |
第190回:前回の映画は忘れてください |
| 怒涛のように発売されつづけるDVDタイトル。本当に購入価値のあるDVDはどれなのか? 「週刊 買っとけDVD!!」では、編集スタッフ各自が実際に購入したDVDタイトルを、思い入れたっぷりに紹介します。ご購入の参考にされるも良し、無駄遣いの反面教師とするも良し。「DVD発売日一覧」とともに、皆様のAVライフの一助となれば幸いです。 |
■ 映画で描かれるゲームの続編
| FF VII アドベントチルドレン 通常版 |

|
|
価格:4,800円 発売日:9月14日 品番:ACNM-34031 仕様:片面2層 収録時間:本編約100分 画面サイズ:ビスタ(スクイーズ) 音声:日本語(ドルビーデジタル5.1ch) 日本語(ドルビープロロジックII) 字幕:日本語 発売/販売:株式会社スクウェア・エニックス |
いずれもファミコン時代から、RPGの代名詞として人気を集める、両シリーズとも現在進行形で進化を続けている。物語の目的は世界の危機を救ったり、魔王からお姫様を助け出したりと色々だが、プレーヤーが主人公としてゲームの世界に参加し、仲間を集め、修行し、困難を乗り越えるという過程はどちらのシリーズも同じだ。
しかし、映像面のクオリティを重視し、常にプレーヤーを驚かせるようなクオリティの映像を見せてくれるのはFFシリーズの方だろう。プレイステーション以降のプラットフォームでは、メディアが大容量のCD-ROM/DVD-ROMとなり、CGムービーがふんだんに使われた。プレーヤーはドット絵から想像していた世界を、立体映像として気軽に見れるようになったわけだ。
また、幅広い展開もFFシリーズの特徴。ゲームボーイの「聖剣伝説」はFFの外伝としてアクションRPGとなり、「ファイナルファンタジータクティクス」シリーズはシミュレーションRPGとして高い評価を得た。
個人的には「ドラクエもFFも、第3作目が一番面白かったなぁ」と考えているような頭の古い人間なので、正直言って最近のFFシリーズには今ひとつついていけない。映像的には凄いと感じるのだが、血色の悪いジャニーズ顔の主人公が、前髪が無意味に長い美形のボスキャラと華麗に切り合うイメージが強く、トレンディドラマでも観ているような、全編に漂う“お洒落感”が肌に合わない。“たまねぎ剣士”がどうとか言っていた昔が懐かしく感じる。
また、ゲームとしての難易度や自由度は随分低くなったように思う。ストーリーの設定が複雑になっているため、キャラクター同士の会話やCGムービーが占める割合が大きくなり、ユーザーがプレイできる部分がどんどん減っている。何回かボタンを押すと会話が始まり、また少しボタンを押すとムービーが始まるといった状態。「ゲームじゃなくて最初から映画にしてくれよ」とウンザリした記憶もある。

|
| 初回限定版は通常版とパッケージが異なる |
そんな不満の声が届いたのか、FFシリーズは2001年に映画化。実写と見まごうほどのクオリティが話題となったが、内容はほとんどゲームとは関係無く、ハリウッドの大作SF映画といったイメージで「映像は凄いけど物語がイマイチ」、「そもそもファイナル・ファンタジーという名前にする意味がわからない」など、ゲームファンと映画ファンの双方から厳しい評価を受けてしまった。
それから4年。FFの最新作は再び映像作品として戻ってきた。それが「FF VII アドベントチルドレン」だ。タイトルを見てわかる通り、これは‘97年にプレイステーション用として発売された「FF VII」の続編に当たる物語だ。FF VIIはシリーズ初の300万本を突破した人気作であり、物語としての完成度も高いため、映像作品としての続編決定が決まったものと思われる。
情報が小出しにされていたため、発売までヤキモキしていた人も多いだろう。しかし、冷静に考えるとゲーム版は8年以上前の作品。CG的にもレベルが低かったプレイステーション時代の名作であり、現在の最新CG、しかもプリレンダリングの映像作品と比べると、表現力には天と地とも言える開きがある。よって“FF VIIとは名ばかりのイメージが違う作品”になっている可能性もある。そもそも、あの物語を多くのユーザーが覚えていてくれるのかという点も大きな賭けになるだろう。
もちろん、1本の映画である以上、ゲームをプレイしていない人にでも楽しめる作品でなくてはならない。果たしてFF VIIファンの記憶を呼び覚まし、ゲームをやったことの無い人でも楽しめる作品に仕上がっているのか? 期待と不安の半々で観賞を開始した。
ちなみに、UMD版(4,800円)も含めると、アドベントチルドレンは4種類のパッケージで発売されている。通常版(4,800円)と、初回限定版(4,800円)、フィギュアなどを同梱した「アドベント ピーシーズ:リミテッド」(29,500円)、そしてUMD版だ。
「アドベント ピーシーズ:リミテッド」は通常版と同じ本編ディスクに特典ディスクや特典グッズを追加しており、特典ディスクにはOVA「LAST ORDER FINAL FANTASY VII」、メイキング映像などを収録。さらに、プレイステーション用のゲームソフト「FINAL FANTASY VII INTERNATIONAL」や主人公・クラウドのフィギュア、各種グッズも同梱する豪華版だ。

|

|

|
| クラウディウルフをモチーフにしたブラックメタルのキーホルダー | ファッションブランド「LUZ」(ルース)とのコラボレーションによる メッシュキャップ | 同じく「LUZ」とのコラボレーションによるTシャツ |
| (C) 2005 SQUARE ENIX CO., LTD. ALL Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA | ||
発売から1週間以上経過していたため、新宿の量販店では「アドベント ピーシーズ:リミテッド」は売り切れ。初回限定版も残っていなかった。仕方なく通常版を購入したが、初回限定版との違いはパッケージのみ。なお通常版と初回限定版には特典ディスクは付属していない。3万円近い「アドベント ピーシーズ:リミテッド」の価格設定は正直言ってハードルが高いので、本編と特典ディスクの2枚組みで5,000円~6,000円程度のパッケージも用意して欲しかった。
■ “続編”と言うより“後日談”
舞台は「魔晄(まこう)」と呼ばれる謎のエネルギーの活用方法を編み出し、政治をも牛耳った巨大企業「神羅カンパニー」が支配する世界。だが、そのエネルギーの正体は、全ての生命の源であり、星そのものが持つエネルギーだった。「このままでは、いつか星そのものが死んでしまう」と危機感を抱いた人々は、神羅カンパニーに対抗する組織「アバランチ」を結成する。
主人公・クラウドは、元神羅の戦闘要員。感情もなく、主義主張もない彼はアバランチに傭兵として雇われ、世界の命運を左右する戦いに参加。多くの仲間を得る中で、自らの失われた過去や存在意義を求めていく。そして、世界を滅ぼし、神になろうとするセフィロスとの対決を迎える。
ゲーム版の大まかな物語は以上のようなもの。面白い設定としては、主人公のクラウドが元・敵側の人間だということ。そして、感情に乏しく、強い意志を持っていない青年だと言うことだ。
続編となる映画は、ゲームから2年後の世界。壮絶な戦いで廃墟と化した魔晄都市「ミッドガル」は再建への道を歩んでいた。しかし、「星痕症候群」と呼ばれる謎の奇病が蔓延し、人々を苦しめていた。そんなある日、2年前の戦いで心に傷を負ったクラウドに、謎の3人組が襲い掛かる。クラウドを“兄さん”と呼び、“ママを探している”という3人。凄まじい戦闘能力を持った彼らの登場は、再び人知を超えた戦いが始まることを意味していた。
物語のメインは、ゲーム版で仲間を失うなど、大きな代償を支払い、罪の意識に心を閉ざしていたクラウドが、再び立ち上がれるか否かに集約される。「今の俺には誰も助けられない」、「罪って許されるのか?」など、劇中のクラウドは世界を一度救った勇者とは思えぬほど憔悴している。だが、彼のピンチを救うため、かつて命を掛けて戦った仲間達が集結。クラウドは新たな敵と、今までの自分自身と決着をつけることになる。
なんといっても圧巻は映像だ。このインパクトだけで4,800円の価値はあると言って良い。前回の映画版も実写と見まごうばかりのリアルなCGに驚いたが、今回のアドベントチルドレンは、良い意味で“作り物感”が残っている。つまり、実在の人間ではなく、空想の産物であるゲームのキャラクターとしてのリアリティを追求している。限りなく人間に近い外観を持ちながら、髪型や衣装、瞳の色、顔つきなどはアニメ的に記号化され、ディフォルメされている。言わば「嘘の枠の中のリアル」だ。
これならば、ゲーム版のファンに素直に受け入れられるだろう。それにしても、肌の質感や手足に浮かぶ血管、細かすぎる衣装や小物など、CGとしてのクオリティはめまいがするほど高い。「FF VIIのキャラのコスプレ用衣装を作る時の参考になるだろうなぁ」などと、妙な事を考えながら鑑賞してしまった。
また、スピード感あふれる戦闘シーンも魅力だ。空中を自由自在に飛びまわり、剣や銃を使ったバトルが展開する。各キャラクターがあまりにも超人的に強いので「そもそもFF VIIのキャラクターって空飛べたっけ?」と首をかしげていたのだが、「全員レベル99という設定」という噂を耳にして苦笑してしまった。映画を見ながら「俺が育てたクラウドやティファはこんなに弱くないぞ!!」と怒らずに済むのは良いかもしれないが……。
ともかく、戦闘シーンこそゲームと映画の最大の違いと言えるだろう。例えば召還されたバハムート(ドラゴン)と戦うにしても、ゲームではドラゴンの吐き出した光弾に当たってプレーヤーキャラのHPゲージが減るだけの話だが、映画になるとまるで違う。光弾の衝撃波が街を揺さぶり、関係のない市民を巻き込み、崩れた瓦礫も飛び交う。数字の増減だけを見ながらRPGをやっていた人は、剣や魔法、銃による攻撃は実際にはこういうものだったのかと、軽いショックを受けるだろう。同じ物語でありながら、描き方を変えると新鮮だ。
ただ、映像が限りなくリアルになった代償として、動きの粗が目につく瞬間がある。戦闘シーンは“やり過ぎ”と言えるスピード感でごまかせるが、キャラクターがゆっくりと感情を表現するような部分で、肩や腕の動き、表情の動きに不自然さを感じることがある。また、アフレコ音声と口のズレが気になるキャラクター(特にティファ)もある。
これらはモーションキャプチャ時の過度な演技や、声優のテクニック的な要因も考えられる。個人的には、映像がリアルになり過ぎたため、視聴者がアニメの口パクよりも、生身の人間の口の動きとして知覚していることが原因だろうと思う。アニメキャラの口の開閉と音声が一瞬ズレてもさほど気にはならないが、生身の人間でズレると“いっこく堂”のように違和感を感じるのと同じだ。だがしかし、もはやそんな粗に目が行ってしまうほどのレベルに達した映像に賛辞を送るべきだろう。
設定は複雑だが、物語の密度ははっきりいって薄い。個人的には“続編”というよりも“後日談”の域は出ないと感じた。“ゲームの蛇足だ”と感じる人もいるようだが、クラウドという主人公がゲーム版の戦いに区切りを付け、次の一歩を踏み出すための過程として、これはこれでアリだと思う。
また、時が過ぎたとは言え、ゲームに熱中し、自らの手でキャラクターを育て、冒険したかつてのプレーヤーにとっては、仲間達が集結する場面でたまらない懐かしさと感動を覚えることだろう。さらに、敵味方を含め、これでもかと言うほどビジュアル系の美形男キャラが飛び交うので、そうした要素を待っていた女性ファンの期待にも沿う内容だろう。
前述の通り、クラウドというキャラクターの心情に焦点を絞って鑑賞したい映画だ。プレーヤーだけでなく、おそらくFF VIIを制作したスタッフの中にもあった消化不良のモヤモヤを、気持ちよく晴らしてくれる作品……そんなふうに感じた。
■ 文句無しの高画質。低音は今ひとつ
音声はドルビーデジタル5.1chとドルビープロロジックIIの2種類で収録。ビットレートはどちらも448kbps。5.1chはサラウンドチャンネルを積極的に使い、アクションシーンの縦横無尽のバトルを音声面でバックアップ。背後や頭上を飛び交う音像が楽しい。高音はクリアで質感も高く、つばぜり合いにも清涼感が漂う。
ただ、全体的に低音が不足がちで、付随して音場の広がりがあまり感じられない。環境音が不足しているからだろうか。また、バハムートのような巨大な怪物が舞い降りたり、口から炎を吐いても、期待していた地鳴りのような低音が無く、拍子抜けするシーンがいくつかある。
通常の殴り合い、切り合いのアクションシーンも低音が薄いため、アクション全体に重厚さや厚みが足りない。スピードだけはあるので、軽業師の戯れを見ているようで、あまり“痛み”を感じないアクションシーンが続く。低音が加わるか否かで映像の印象は随分変わってくるので、この点は少々残念だ。
DVD Bit Rate Viewerで見た平均ビットレートは7.42Mbps。片面2層ディスクで本編が100分なので、最近のDVDとしては平均的な数字だろう。画質は非常に高く、ブロックノイズやモスキートノイズなど、鑑賞の妨げになるような要素は皆無。激しい戦闘シーンでも破綻はない。
暗部の階調も豊か。カダージュら3人が着用している黒い革のジャンプスーツに目を凝らしても、革の質感が潰れずにしっかりと描写されている。また、遠景でも建造物の輪郭はクッキリとしており、安定した高画質が楽しめる。機器の再生能力を試すテストディスクとしても利用できるだろう。
 |
| DVD Bit Rate Viewerでみた平均ビットレート |
また、物語をしっかりと思い出すという意味で、プレイした人も一度は見ると良いだろう。物語だけでなく、プレイステーション時代のゲーム画面と、今回のアドベントチルドレンの映像を比較できるため、CGの進化度合いにあらためて驚くだろう。
■ これからのゲームと、これからの映画
映画とゲームの映像的な差は曖昧になっている。ゲームから派生したフル3DCG映画は、こうした現状を象徴した作品とも言えるだろう。今後、Xbox 360や任天堂「Revolution」(仮)、ブルーレイディスクを採用してHDMI出力を備えた「PLAYSTATION 3」などというハイスペックなゲーム機が当たり前になった時に、“見た目はほとんど映画”というゲームは珍しくなくなるはずだ。
その裏で、ゲーム開発にかかる費用は増え続けており、1本数百億円という製作費が必要になるハリウッド映画と同じような状況になりつつある。事実、7月に開催された「PlayStation Meeting 2005」では、久夛良木健代表取締役兼CEOが「PLAYSTATION 3」の開発環境を「いかに手軽でハードルの低いものにするかが重大な使命」と語っていた。
今後「BEFORE CRISIS FF VII」(携帯電話)、「CRISIS CORE FINAL FANTASY VII」(PSP)、「DIRGE OF CERBERUS FFVII」(PS2)など、FF VIIの世界やキャラクター達は、様々な舞台へ活躍の場を広げるようだ。確かに、クオリティの高い映像を観るのは楽しい。どうせなら美麗な映像でゲームがやりたいとも思う。
しかし、それはゲームを構成する要素の1つに過ぎない。映画とゲームの境界があやふやになった時、それをゲーム(RPG)だと規定する要素は、プレーヤーが主人公と共に物語を体験し、仲間と共に未来を掴むという基本スタンスにしかないだろう。今回は映画なので当然だが、プレーヤーが画面の外に置き去りにされ、画面の中で勝手に動きまわるクラウド達の姿に一抹の不安を覚えたのも確かだ。
| ●このDVDについて |
|---|
|
|
| 前回の「アビエイター プレミアムエディション」のアンケート結果 総投票数206票 | ||
|---|---|---|
| 購入済み 49票 23% | 買いたくなった 91票 44% | 買う気はない 66票 32% |
□スクウェア・エニックスのホームページ
http://www.square-enix.com/jp/
□アドベントチルドレンの公式サイト
http://www.square-enix.co.jp/dvd/ff7ac/
□関連記事
【6月30日】スクウェア・エニックス、「FF VII アドベントチルドレン」を発売
-2種類のDVD版と、UMDビデオ版を9月14日発売
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050630/squeni.htm
【6月21日】スクウェア・エニックス、DVD作品「FF VII アドベントチルドレン」
限定BOX「ADVENT PIECES: LIMITED」の内容を公開 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20050621/ffac.htm
【6月14日】スクウェア・エニックス、「スクウェア・エニックス パーティ 2005」
イベント概要を発表。チケットは6月20日より販売 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20050614/sep.htm
【5月16日】スクウェア・エニックス、9月14日発売決定!
「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20050516/ff7.htm
【2004年10月27日】スクウェア・エニックス、「FFVII アドベントチルドレン」
モントリオール国際ニューシネマフェスティバルで上映 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20041027/ffvii.htm
【2004年9月24日】スクウェア・エニックス、「BUSINESS CONFERENCE」開催
ニンテンドーDS「エッグモンスターHERO」など多数の新作を怒濤の発表 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20040924/se.htm
【2004年9月6日】スクウェア・エニックス、DVD映像作品
「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」
ヴェネチア国際映画祭にて上映、公式記者会見を開催 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20040906/ffac.htm
【2004年9月1日】スクウェア・エニックス、DVD映像作品
「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」
制作順調に進行中 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20040901/ffac.htm
【2004年7月30日】スクウェア・エニックス
「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」
ヴェネチア国際映画祭に出品 (GAME Watch)
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20040730/ffvii.htm
(2005年9月27日)
[AV Watch編集部/yamaza-k@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部 av-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.


