 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第113回:International CES特別編 2009年に注目したい映像最新技術 ~3D、有機EL、次世代高精細パネル、超解像~ |
今回はCESで見かけた、2009年に大きな動きが見られると思われる、最新技術トレンドをお伝えしよう。
■ 3D表示の基本をおさらい
今年のCESでは、各社が申し合わせたように立体視技術を展示していた。内容は革新的な立体視技術の発表よりも、既存の立体視技術を“いかにわかりやすく一般ユーザーに使ってもらうか”という視点での展示が多い。
立体視技術は大別すると、メガネをかけて見る「眼鏡立体視タイプ」と、裸眼の「裸眼立体視タイプ」がある。そして、「眼鏡立体視」でよく用いられる技術には「パッシブタイプ」と「アクティブタイプ」が存在する。パッシブタイプはメガネの左右に、異なる偏光を通す“偏光フィルタ”を採用したものだ。
左目用と右目用の映像が同時に表示されるが、偏光メガネを通すことで左右の目に見える映像をわけることができ、立体視ができるというもの。電気駆動のアクティブ装置のようなものが不要で、低コストでメガネを作れるというメリットがある。
アクティブタイプはメガネに電気駆動の液晶シャッター(レンズ全体を液晶の黒表示で覆うイメージ)を搭載したもので、画面に左目/右目用の映像を交互に表示。それに同期してメガネ側の液晶シャッターを左右交互に開閉。それぞれの目に違う映像を見せるもので、“時分割な立体視”とも表現できる。同期には赤外線がよく使われる。
裸眼の立体視は人間の両目の距離から生まれる視差を巧みに利用し、どちらかの目にだけ映像の画素を送り届ける微細光学系を組み合わせるのが常套手段となっている。最先端の裸眼立体視では、画面を別の視点から見た時に、その視点用の画像(視界)を見せるマルチビューに対応させることができるようになっている。
・Blu-rayソフトの3D化を目指すパナソニック

|
| パナソニックブース内に特設されたフルHDプラズマシアター |
パナソニックは、103V型のプラズマを使っての3D表示デモを、昨年のCEATECに引き続き展示した。技術的にはアクティブタイプの眼鏡立体視システムである。左目用と右目用を60Hz(毎秒60コマ)で交互に見せるため、フルHD解像度で毎秒60コマの立体視ができるのが特徴だ。
「PDPの高速応答性があってこそ実現できたシステム」と、最大手PDPメーカーとしての意地を見せている。また、BDビデオソフトでの3D技術の規格化や、立体視映像の伝送をHDMI規格に盛り込むための準備も積極的に進めており、気軽に家庭で立体視映像が観られる環境が整う日も近いかもしれない。
・2Dソフトをリアルタイムで3D化するサムスン
サムスンが開発したのは、2D映像を3Dへリアルタイム変換する「TV with Built in 3D Formatter」システムだ。映画だけでなく、ゲームなど、様々な映像をほぼ遅延無しで3D化するというもので、倍速駆動技術の動きベクトル検出アルゴリズムを応用して実現したものだという。
倍速駆動における補間フレーム生成では、映像内のどのピクセルが、どの方向に動いているかを大まかにだが認識している。この動き(速度)情報を奥行き情報に変換し、疑似的な立体視用フレームに変換している。エラーも多いのだが、人間の視覚はその辺りの矛盾を都合よく補うので意外に立体感が得られるのだとか。
ハードウェアとしてはPDPを用いたアクティブタイプの眼鏡立体視システムで、パナソニックと同じ。最大フレームレートは片目あたり95Hzで、両目合わせて190Hzまで対応できるとのこと。3D変換のレイテンシーはほとんど無視できるレベル……とは言うが、おそらく1~2フレームの遅延はあると思われる。

|

|

|
| 特別な3Dコンテンツを必要としないサムスンの立体視システム | Xbox360用の「NEED FOR SPEED:PRO STREET」を立体視プレイ。一般的に市販されている通常パッケージ版であり、カスタマイズ版ではないが、それなりに飛び出して見える | 映画にも当然対応。強い飛び出し感はないが、画面の奥方向に世界が広がっているような独特な視界になる |
レンチキュラーレンズを使った裸眼立体視システムも公開していた。映像パネル前面に、画素サイズよりちょっと大きい程度の微細光学系の凸レンズを貼り合わせたもの。左目と右目からの視線が、各凸レンズを見ることになり、その凸レンズの先にある左目用の画素と右目用の画素を見ることにより、全体として立体映像を知覚させるという仕組みだ。
デモシステムでは600cd/m2の高輝度52V型のフルHD液晶パネルを用いており、9視点の立体視に対応。しかし、デモは多視点多視界には対応しておらず、9視点の全てから同じ映像が見られるだけだ。なお、レンチキュラーレンズを用いた裸眼立体視では、観られる映像の解像度は視点数の逆数になる。つまり9視点では解像度が1/9になってしまう。そのため、映像観賞用というよりは業務用の広告ディスプレイなどを想定していると思われる。

|

|

|
| 52V型液晶を使った、レンチキュラーレンズ方式の裸眼立体視。9視点に対応している | 9視点に対応しているが、どの視点から見ても映像は同じ。多視点多視界には対応していない | |
・ソニーの場合~2D/3D兼用視聴スタイルを提案

|
| ソニーも立体視研究をしていることをアピール |
第107回でレポートしているが、ソニーはパッシブタイプの眼鏡立体視システムのデモを行なっている。映像パネルは液晶。偶数ラインと奇数ラインとが、それぞれ違った方向の偏光にて左目用と右目用の映像ラインを表示している。なお、この方式では表示解像度がパネルの半分になるが、アクティブタイプと違って映像と液晶シャッターの同期ミスや、シャッター開閉によるチラツキが少ないため、目が疲れにくいという利点もある。
ソニーのデモで印象的だったのは、立体用の視差を小さめにとることで、裸眼で見た場合には“ちょっとボけた程度の2D映像”に見えるところ。2D/3D兼用映像の提案であり、一般家庭におけるカジュアルなスポーツ視聴などでは、こういった楽しみ方は“あり”だろう。
・全方式を展示したLG電子
LG電子はパッシブ、アクティブ、裸眼立体視の3つ全て技術展示していた。パッシブの眼鏡立体視はソニーと同じで、55V型の液晶パネルの偶数/奇数ラインに左/右用映像を割り当て、偏光メガネで観る。パネルはフルHDで450cd/m2だが、3D映像では解像度が半分になるほか、輝度も約半分の200cd/m2に落ちるとのこと。アクティブの眼鏡立体視はパナソニックと同じで、60V型のプラズマで交互に左右の映像を表示している。

|

|
| パッシブ×液晶の立体視システム。液晶だとやはり応答速度の見地からパッシブが適している | パッシブ×LCDとアクティブ×PDPは隣り合わせで展示されていた |
裸眼立体視はサムスンと同じレンチキュラーレンズ方式だが、視点数は10個でサムスンよりもやや多い。フルHDパネルを使っているようだが、視点数が多いため、立体映像の解像度はVGA(640×480ドット)相当になるとのこと。やはり広告を初めとした業務用途を想定しているという。

|

|
| アクティブ×PDPの立体視システム。今期のPDPはサブフィールド数も増加したのでアクティブ式でも十分な階調表現ができるはずだ | 裸眼立体視の応用先は、その低解像度故に広告向け? LG電子のデモも多視点に対応しながら、視点ごとの視界は変わらず |
・PCゲームを強制的に3D化するNVIDIA

|
| NVIDIAもPCゲームのリアルタイム立体視化技術「GeForce 3D Vision」を公開 |
GPUメーカーのNVIDIAも、PCベースでアクティブタイプの眼鏡立体視システム「GeForce 3D Vision」を公開した。PC上で描かれる全ての3Dグラフィクスを立体視にリアルタイム変換するというもので、GeForceシリーズが使われているPCであれば、GPUドライバが描画時に自動的に立体視フレームを生成。ゲームソフト側が立体視に対応していなくても3D化できるのが特徴だ。
方式は左右目用の映像が交互に表示されるタイプで、フレームレートは各60Hz。よって、ディスプレイには120Hzの表示レート対応が求められる。だが、120Hz表示対応というと、ブラウン管ディスプレイくらいしかなく、一般的なPC向け液晶ディスプレイではほとんど対応製品がない。現在民生向けPCディスプレイで対応しているのはサムスンの「SyncMaster 2233RZ」のみで、使い勝手は簡単だが、導入までのハードルが高いのが難点だ。
■ 有機ELディスプレイ編

|
| ソニーの27V型フルHD有機EL、21V型標準ハイビジョン有機EL |
ソニーが2007年冬に世界初の11V型有機ELテレビ「XEL-1」を発売して以来、新しいディスプレイデバイスとして世界中から熱い視線が注がれている有機ELだが、ソニー自身も次の製品が続かない。ソニーの今年の展示は、昨年公開した試作機と「XEL-1」の実質的なリファイン版を展示したのみだった。詳しい内容は第107回でレポートしている。
他のメーカーの取り組みはどうだったのだろうか。サムスンは14V型と31V型の試作パネルを展示。どちらもフルHD(1,920×1,080ドット)だという。ソニーが11型で960×540ドット、最大画面サイズが27V型ということもあり、より高解像でサイズも大きい優位性をアピールしていた。ただし、最薄部15mm/最厚部18mmで、薄さについてはソニーが圧倒的に上回っている。発売時期や価格についての情報は一切無い。

|

|
| 14V型でフルHD解像度に対応するサムスン有機EL | 一般公開された試作パネルとしては世界最大の31V型フルHD有機EL |
LG電子も有機ELディスプレイを展示。サイズは15V型で、解像度は1,280×720ドットの720p相当。展示されていたのは15V型のみだが、市販モデルに近い厚さ2.5mmのものと、技術デモ用の厚さ0.85mmの2タイプが並べられていた。2.5mmのものは2009年末に発売を予定しているという。市販製品の第二号の有機ELテレビは、果たして韓国メーカーになるのか、注目される。

|
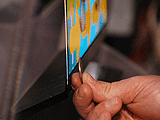
|
| 15V型の720p有機ELディスプレイ | 厚さは0.85mm。25セント玉との比較 |
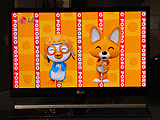
|

|
| 同じ15V型720pの有機ELだが、こちらは市販化の計画がある厚さ2.5mmのもの | この2.5mmでも十分薄いが、主戦場はアンダー1mmの世界へ |
仕組みの改良と製造技術の進化速度が著しい分野で、今後も進化ペースが緩む気配がない。現在の有機ELにおける有機材料は低分子材料と高分子材料にわかれ、さらに発光層の発光に至るエネルギー順位の経緯から発光減衰時間の短い「蛍光」と、長い「燐光」にわかれる。現在の主流は「低分子・燐光」材料となるが、技術革新により何が主流になるかは流動的だ。
ソニーは発光層の有機物質の形成に、これまでの「マスクパターン+インクジェット塗布方式」に代わるレーザー転写方式を新開発。大型パネル製造で問題となるマスクパターンの熱膨張問題から解放されるため、大型化に適した技術として注目されている。これまではドットピッチの小さい小型パネルが主流だったが、今後は、より大画面のものが登場してくるかもしれない。
■ 次世代高解像度パネルは「4x Full HD」か、「4K2K」か
民生にはフルHDがやっと浸透した段階だが、400インチオーバーの超大画面を前提とした映画館などの業務用の世界では、より高解像度な映像パネルへの移行が望まれている。その高解像度規格として認知が高まっているのがデジタルシネマ規格(DCI)の4,096×2,160ドットの4K2K解像度だ。
すでにソニーは業務用として4,096×2,160ドットのSXRDプロジェクタ「SRX-R220」を2007年春に発売。ビクターは2007年冬に4,096×2,400ドットのD-ILAプロジェクタ「DLA-SH4K」を発売しており、4K2Kへの移行が業務用の世界では始まりつつある。

|

|
| SRX-R220 | DLA-SH4K |
ただ、ビクターのDLA-SH4Kが4,096×2,400ドットを採用していることからもわかるように、4K2Kという解像度はイマイチ定義がふわふわしている。このふわふわ感は、同一メーカーにおいても漂い始めている。例えば、サムスンが超高解像度の次世代のLEDTVハイエンドモデルの試作機として公開した82V型では、DCI規格の4,096×2,160ドットではなく、フルHDのジャスト4倍となる3,840×2,160ドット(4x Full HD)を採用していた。
これと同じ展示スペースでは、63V型でDCI規格準拠の4,096×2,160ドットのPDPも披露しており、同一メーカー内で、次世代高解像度パネルの実解像度に統一感が無い。
ただ、サムスンの展示から、その決定方針を読み取れないこともない。82V型の4x Full HD液晶は民生向け製品の試作機と位置付けているようで、あえて解像度変換しやすい解像度を選択したようなのだ。その証拠に、試作機にはサムスンのハイエンド薄型テレビ製品ブランド「LUXIA」の「LEDTV」シリーズのロゴが付けられている。

|
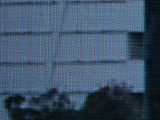
|

|
| サムスンは次世代LEDTV製品で4x Full HD解像度を採用する? | 表示映像を拡大撮影してみた。もともと30V型以下クラスでもフルHD解像度が実現できる液晶では、4x Full HDを製品化するかの争点は技術面ではなくマーケティング面にある | 63V型で4,096×2,160ドット解像度のPDPも公開 |
民生向けはフルHDの整数倍である3,840×2,160ドット、業務用はDCI準拠の4,096×2,160ドット。こういう流れになるのかもしれないが、ここしばらくは4K2Kという解像度の定義に振りまわされそうだ。ちなみに、2008年に初公開されたパナソニックの150V型プラズマは4,096×2,160ドット、2006年のCEATECなどで公開されたシャープの64V型液晶も4,096×2,160ドットであった。
■ 超解像技術の最新動向
現在は業務用だが、4K2Kのような超高解像度ディスプレイがいずれ、民生向けのテレビやディスプレイにも採用されるだろう。その際、DVDビデオをはじめとした480i/480p相当のSD解像度は、こうしたパネルで表示すると倍率の高い拡大解像度変換が行なわれることになる。そうなると重要度が増すのが、解像度情報を復元する方向に、アグレッシブな解像度変換処理を行なう「超解像」技術である。
東芝は3,840×2,160ドットで56型の「Cell TV」の試作モデルを公開した。早ければ2010年の製品化を目指すというモデルで、次世代超解像技術も実験的に搭載されている。
現在の実装では、現行REGZA「7000シリーズ」に搭載されている超解像プロセッサを4基搭載し、それぞれでフルHD解像度分の超解像処理を担当しているという。4K2KがほぼフルHD4面分の解像度なのでわかりやすい実装だが、ここからはCellプロセッサのみで4K2K超解像処理ができないという裏返しの事実も読み取れる。4K2K相当の解像度は、パネルやその解像度定義の問題以外に、映像処理の負荷の増加という課題もあるわけだ。

|

|

|
| フルHDを4K2Kへ超解像処理する技術 | 1,920×1,080ドット映像を4K2K相当解像度へ超解像処理するデモ | |
超解像関連ではもう一つアップデートがあった。入力された映像解像度を信号フォーマットで判別するのではなく、映像そのものの実体解像度を判別して適応型の超解像処理を行なう技術である。
これに対応させたのは日立の超解像技術と、東芝の次期REGZAに搭載される超解像技術だ。現状のREGZAでは、地デジ放送の1,440×1,080ドット映像か、DVDをはじめとした各種SD映像の720×480ドット映像を認識した場合に限って処理を行なっている。つまり、1,920×1,080ドットの映像信号に対しては超解像処理を施していないのだ。
何の問題もないように聞こえるが、最近の多くのレコーダやプレーヤーでは、機器自身がアップスケール機能を持っているため、そうした機器とHDMI接続して映像を表示すると、映像信号としては1,920×1,080ドットのフルHDになっているので超解像処理されないのだ。設定を変えればソースのネイティブ解像度で伝送することもできるが、そうはなっていない機種も多い。
そこで、新REGZAのリファイン版超解像処理では、入力映像の周波数解析を行ない、元信号の実体解像度を分析/認識する処理系を入れ、入力映像のソース信号に適応した超解像処理を行なうようになっている。
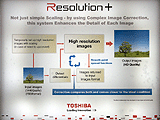
|

|

|
| リファイン版東芝超解像処理「RESOLUTION+」は実体解像度認識機能が追加された | 超解像が適用できる映像の種類が実質的に増えた | |
日立が試作した超解像処理技術は、これよりもさらにレベルの高い実体解像度の認識を行なっているという。担当者によれば、「『映像信号と実体解像度の不一致』の問題は、開発初期から認識しており、我々の超解像技術はこの問題に最適化したロジックになっている」とのこと。
特に、テレビの地上デジタル放送波は1,440×1,080ドットで伝送されてくるが、実体解像度の認識は一筋縄ではいかない。アナログ時代の再放送番組やSDカメラ撮影の番組は、実体解像度としてはSD映像だが放送波に乗せるときにアップスキャンコンバートされてHD映像信号になってしまう。さらに、アスペクト比4:3のSD映像番組の場合、左右にHD解像度の番組名などが書かれた装飾フレームが入るし、HD映像の中にSD映像が入る場合もある。
日立の超解像技術では、映像を細かく周波数解析して、実体解像度を映像のエリアごとに的確に捉え、適した超解像処理を目指すモノだ。日立の超解像処理アルゴリズムは関連技術の特許を押さえるのみで、実処理系は将来的にも非公開とするとのこと。現状で公開できるのは、「時間方向の映像解析はなく、同一フレーム内解析のみの処理」ということだけだという。また、高解像度化する際の推測ピクセルの生成には3Dグラフィックスのシェーディングにも似た技術が使われているとのこと。

|
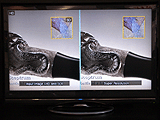
|

|
| 日立の超解像技術はSDとHD映像の混在にまで対応する | SDとHDの混在映像を超解像処理した結果。写真でもその違いがよく分かる | もちろん通常のSD映像をまるごと超解像処理してHD化することにも対応する |
超解像技術は、海外企業からも発表されつつある。サムスンは、DVDをBlu-rayと同等の解像感で楽しめると謳う「BD Wise」技術を発表。LG電子は同社の新世代映像エンジン「DUAL XD」エンジンに「ENHANCED SD PERFORMANCE」と呼ばれる超解像技術を搭載する。両者ともに動作原理についての説明が全くないが、少なくとも韓国勢も、超解像技術が今後重要になっていくと認識しているのだろう。

|

|
| サムスンの超解像技術「BD Wise」はDVDの再生に特化した設計 | もちろん通常のSD映像をまるごと超解像処理してHDかすることにも対応する |
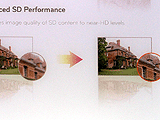
|

|

|
| LG電子は新世代映像エンジン「DUAL XD」エンジンに「ENHANCED SD PERFORMANCE」と呼ばれる超解像技術を搭載する | 左がオフ、右がオン。写真でも違いが分かる | |
今回のCESにおける海外勢の超解像技術で最も興味深かったのは、NVIDIAブースに展示を行なっていたMotionDSP社のものだ。ここまで紹介してきた超解像技術は、全て同一フレーム内解析で超解像処理を行なうのに対し、MotionDSPの超解像技術は、唯一時間軸方向の解析も行なう。MotionDSPでは、入力映像の複数フレームを前方向と、後ろ方向に探索し、ピクセル単位の動きベクトルを検出する。
そして時間軸方向にピクセルの追跡を行なって、撮影時に欠損したと仮定される画素情報を推測して復元するのだ。この方法だと、未来や過去のフレームから推測画素が作れるため圧倒的に精度の高い超解像処理が行なえる。

|

|
| MotionDSP社の超解像技術は時間方向への解析をして、ピクセル単位の動き追跡を行なう。適用前と適用後の文字の鮮明度の違いに注目 | |
その復元した画素の利用方法もユニークだ。普通の超解像処理のように、入力フレームに対して高解像度変換用に推測したピクセルを補間して高解像度化することはもちろん、ピクセル単位の動きベクトルまでを検出しているので、液晶の倍速駆動のような中間フレームを合成してフレームレートを上げたり、あるいはフレーム内、時間方向のノイズの除去までが行なえてしまう。
もちろん、時間方向への解析を行うことから、放送映像のリアルタイム視聴に対して、この技術を使うことはできないが、例えば録画したコンテンツに対して適用することはできる。ビデオレコーダなどに搭載されればかなり面白いことになりそうだ。
□2009 International CESのホームページ
http://www.cesweb.org/
【2009 International CESレポートリンク集】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/2009ces.htm
(2009年1月20日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 西川善司 | 大画面映像機器評論家兼テクニカルジャーナリスト。大画面マニアで映画マニア。本誌ではInternational CES他をレポート。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。映画DVDのタイトル所持数は1,000を超え、現在はBDのコレクションが増加中。ブログはこちら。近著には映像機器の仕組みや原理を解説した「図解 次世代ディスプレイがわかる」(技術評論社:ISBN:978-4774136769)がある。 | |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2009 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.