
 |
|


■迷信の多い、デジタルオーディオの世界
オーディオの世界には迷信とか嘘というのが非常に多い。デジタルオーディオの場合、仕組み的にはコンピュータと同じなのだから、アナログ時代よりも迷信は少なくなってもいいようなものなのだが、なんとなく増えているように感じる。
私自身は、長いことMIDIとかHDDレコーディングという分野の仕事に携わっている。MIDIをオーディオというかは別にしても、迷信という意味では同様だ。もう5年以上前になるが、私も記事を書いていたDTM系の雑誌の編集長(まあ、名前だけで実質DTMの話がわかっていた人ではないのだが)は「マクセルさんのフロッピーディスクはいいねぇ、某社のフロッピーディスクでMIDIを再生させると音質が悪くてしかたなかったけど、いやぁ、これはホントに音がいい」って褒めていた。確かにこの編集長、アナログ時代はオーディオ系でそれなりの知識をもっていた人だが、デジタルにはこれなかった人だ。
フロッピーディスクに保存したデータは、セクターに異常があって読み取りエラーを起こさない限り、基本的にどのメディアを使ってもデータは同じ。MIDIデータだって当然同じだから、どこのメディアを使おうが変わるわけがない。読み取りエラーを起こしたら、そもそもデータとして完全に壊れているから、演奏すらできないはずだ。したがって、音質が変化するなんてことは有り得ないのだ。
MIDIの場合、オーディオというよりもコンピュータに近い世界であるため、この話を聞いて“嘘だ”、“間違えている”と見抜ける人が大半だと思うが、オーディオとなってくると、どうも怪しくなってくる。なぜなら、オーディオでの表現には非常に曖昧なものが多いからだ。たとえば、「音質がいい」、「音の抜けがいい」、「音がこもっている」、「低音が弱い」、「解像感が高い」……と感性を表す言葉を使う。そのため、人に言われると「ああ、そうかなぁ」なんて思ってしまい、嘘が迷信として出回っていくのだ。
■迷信だらけのCDのサウンド
その迷信の多いものの代表がCDだろう。デジタルオーディオでもっとも普及しているのがCDなのだから、迷信が多いのは当然かもしれないが、どう考えても嘘というものから、なるほど確かにと感じるものまでいろいろとある。たとえば、CDの音質をよくする方法として、「盤面にカッターで十字に傷をつける」という方法が雑誌や本などにも書かれていたが、こんなものは、どう考えても嘘だ。
一方で、最近よく話題になるのがCDのコピーについて。PC用のCD-R/RWドライブが普及する現在、オーディオCDをCD-Rメディアにコピーすることも簡単になったのだが、ここでよく登場するのが音質の問題だ。つまり、オーディオCDをCD-Rにコピーすると音質が劣化するというのだ。しかもA社のCD-Rメディアは音がいいけど、B社のはノイズがのるとか、C社のは音がこもる……といった具合いに、いろいろな噂が飛び交っている。
また、こういった噂はユーザーが話しているばかりではない。先日も某CD-Rメディアメーカーの営業マンも「今回発売したこの音楽用CD-R製品、これすごくいいんですよ。最近はパソコンでコピーする人が多いようですが、やっぱり音質を求めるなら音楽用CD-Rに限ります。とくに今回の製品は非常に音質がいいように開発していますから……」と話していた。こういわれてしまったら、普通のユーザーは納得するしかないだろう。また、こういった営業マンが各ショップを回って販売員に説明しているのだから、噂は広まる一方だ。
CDがデジタルメディアであるということを考えると、先ほどのMIDIの例と同様にコピーしても、本来音質劣化ということは起こり得ない。でも、実際に試してみると、プチッというノイズがのったり、確かにどうも音質が変だと感じることがあったり、下手をするとまったく再生ができないなど問題は出てくる。でも、その原因はいろいろな要素があり、巷で言われている噂が、そのまま事実というわけではない。まさに迷信がいっぱいあるのだ。
■そもそもオーディオCDって何だ?
そこで、これから数回に渡って、このCDをCD-Rにコピーする際に生じる問題や、それにまつわる迷信を解き明かしていこうと思う。ただし、本当にいろいろな要因・要素があるので、一言で答えを出せるものではない。そのため、いくつかのテーマに区切って考えていきたい。
まず、第1回目の今回は、オーディオCDがどんなものなのか、その概要をつかみ、そこからわかる迷信の嘘を見抜いていこう。
オーディオCDは、単にCD(コンパクト・ディスク)といわれるほかに、音楽CD、CD-DAなどとも呼ばれる。この規格自体は'80年に制定されたものだから、もう20年以上も前の技術だ。それが、現在でも第一線で活躍しており、しかも大容量で最先端というイメージを保っているのだから、本当にすごい大発明だと感心するばかりだ。
その規格がまとめられた規格書の表紙が赤だったことから、オーディオCDのことをレッド・ブックと呼ぶこともある。ちなみにやはり表紙の色からCD-ROMをイエロー・ブック、CD-Rをオレンジ・ブック、CD-Iをグリーン・ブック……などと呼んでいる。
さて、12cmのCDは表面が銀色に光っており、一見金属の板のようではあるが、ここには膨大なデータが書き込まれている。音の長さとしては最大で74分さらには80分というデジタルオーディオデータを収録することができるのだ。
このデータ記録部分は、実は細い線が渦巻上になっており、ここにデータが刻まれている。これはちょうどアナログレコードの溝と同じ様なものである。ただし、アナログレコードは円盤の外側から内側に向かって刻まれているのに対し、CDでは内側から外側に向かって刻まれている。また、レコードでは、針とレコードの溝を直接接触させ、その摩擦振動によって音を出す仕組みになっているのに対し、CDはレーザー光を当てて、データを読み取る非接触型だ。もう少し具体的にいうと、レーザー光を当てた部分の反射率の違いによって0か1かを読み分ける仕組みになっている。
断面図を見ると、この溝部分には凹凸がある。下からレーザーを当てるわけだが、下から見て出っ張っている部分をピット、へこんでいる部分をランドと呼んでおり、ランドとピットを読み取ることによって、0か1かを認識する。
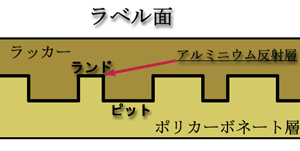
このようにCD上には0と1が羅列した細い線が渦巻上に延々と並んでいることになる。その長さはなんと5kmほどにもなる。1枚のCDを演奏させるというのは、5kmにもなる記録されたデータを読み込んで実現していると考えると、感心してしまう。
■オーディオCDに誤り訂正機能がないってホント?
5kmもの線に刻まれたデジタルデータを読み込むとなると、精度のほどが非常に心配になってくる。CDはこれほど細かくデータが刻まれたものなのに、考えてみれば普段ずいぶん乱暴に扱っているように思う。なるべく大切にとは思うものの、盤面に直接触って指紋をつけてしまうこともあるし、直に机の上において埃をつけてしまったり、微妙な傷をつけてしまったり……。光の反射率で0と1を読み分けているということは、こういった指紋、埃、傷は致命傷なはずだ。この辺はどうなっているのだろうか?
ここでちょっと本題に返ってみる。CDをCD-Rにコピーする際、ノイズがのったり、音質劣化を起こすのは、オーディオCDには誤り訂正機能がないからだという人がいるが本当だろうか?
結論から言ってしまうとこれは嘘。確かにコンピュータデータを扱うCD-ROMにはオーディオCDよりもさらに強力な誤り訂正機能を装備している。しかし、オーディオCDにも相当強力な誤り訂正機能が搭載されている。
| 値 | データビット | チャンネルビット |
|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 01001000100000 |
| 1 | 00000001 | 10000100000000 |
| 2 | 00000010 | 10010000100000 |
| 3 | 00000011 | 10001000100000 |
| 4 | 00000100 | 01000100000000 |
| 5 | 00000101 | 00000100010000 |
| 6 | 00000110 | 00010000100000 |
| 7 | 00000111 | 00100100000000 |
| 8 | 00001000 | 01001001000000 |
| : : | : : | : : |
| 255 | 11111111 | 00100000010010 |
ここでいうデータビットというのが本来の8ビット、チャンネルビットというのがそれを14ビット化したパターンだ。CDドライブにはこの変換テーブルが内蔵されているので、チャンネルビットを読み込んで、データビットに変換しているわけである。チャンネルビットを見て気がつくのは1の連続する部分が存在しないということ。実はここにも仕掛けがある。さきほどランドとピットがそれぞれ0と1であるような書き方をしたが、実はランドからピットへ、またピットからランドへ変わるところが1となるように表現されており、それに続くランドまたはピットの長さが0の個数を示しているのだ。
このようにして、1と0の数が平均的に出現するように14ビットで8ビットを表現し、安定した読み出しを実現している。さらに、誤りそのものを自分で発見し、修正してしまう機能も備えている。その仕組みを解説していくと数式がたくさんでてきて、非常にむずかしくなってしまうので、ここでは割愛するが、それがCIRC(サーク、Cross Interleaved Reed-Solomon Code)というものであり、かなり強力なものだ。これがあることによって多少の指紋があっても、場合によってはカッターによる十字の傷があっても、そのエラー部分を修正し、きちんとしたデータに復元し、再生することができるのだ。
つまり、十字に傷をつけて音が出るのはエラー補正されているからであり、間違ってもこれで音が良くなるというようなことはないこともわかるだろう。
以上、今回は第1回ということで、CDのもっともベースのところについて解説してみた。さらに詳しくCDの仕組みを知りたいという方がいたら、参考文献にもあげている「図解コンパクトディスク読本」をご覧になるといいだろう。
次回以降は、もう一歩踏み込み、CDからCD-Rへコピーする際の音質劣化の現象を検証していくことにする。
【参考文献】
□キーワード (PC Watch)
・CIRC
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000713/key127.htm#CIRC
・EFM
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000713/key127.htm#EFM
(2001年3月12日)
[Text by 藤本健]
| = 藤本健 = | ライター兼エディター。某大手出版社に勤務しつつ、MIDI、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆している。以前にはシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わったこともあるため、現在でも、システム周りの知識は深い。最近の著書に「ザ・ベスト・リファレンスブック Cubase VST for Windows」、「サウンドブラスターLive!音楽的活用マニュアル」(いずれもリットーミュージック)などがある。また、All About JapanのDTM担当ガイドも勤めている。 |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp