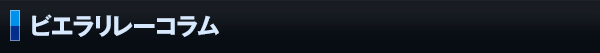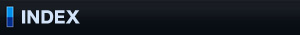- 2013年10月15日 UPDATE
- Reported by 本田雅一
フルHDの、その先へ。パナソニックの“生真面目な”取り組み
昨年末から注目を浴び始めている4Kテレビ。フルHDの4倍の画素を持つ高解像度パネルが魅力的な選択肢になってきた背景には、大きく分けて二つのトレンド変化がある。ひとつは超解像技術の進歩、もうひとつは撮影カメラやフィルムスキャンの解像度向上による高解像映像コンテンツの登場である。
そしてこの秋、4Kテレビの魅力を高めるもうひとつの技術トレンドが顕在化してきた。それは映像を伝送するインターフェイス規格の進化である。そして、そのトレンドを真っ先にキャッチアップしたのが、パナソニックの4KビエラWT600だ。
もっとも、本当に4Kなんて解像度に意味があるの?という疑問をぬぐいきれない読者もいるだろう。ここでは4Kテレビのトレンドを振り返るとともに、WT600がいかにして4Kパネルを活用しているかについて話を進めることにしよう。
“フルHDのその先”の存在意義
いったん4KビエラWT600から目線を外し、テレビ業界全体を見てみよう。
ご存知のように、テレビ放送の技術トレンドに”現時点では”大きな変化はない。もちろん、まったく動いていないわけではなく、たとえば衛星を通じて4K映像をHEVC(従来より高効率の最新映像圧縮技術)で放送しようと、一般消費者からは見えにくいところでの業界内では動きがある。日本でも来年、スカパー!が4K放送を行う予定であることを知っている方は多いだろう。しかし、”現時点で”というと、4K映像を放送を通じて楽しむ手段はない。
 4K対応ビエラの画質はいかに?
4K対応ビエラの画質はいかに?
それでも4Kテレビに注目が集まっているのは、フルHD解像度(あるいはそれ以下)の現在のデジタル放送やフルHDのブルーレイディスクでも、適切な処理を行うことで、より高精細なディスプレイの能力を活かせるようになってきたからだ。
これは単純に「映像処理でごまかして、よりよく見せるようになった」という話ではない。
現在、我々が楽しめるHD映像は、品位の面でザックリと三つの群に分けられる。
ひとつは720P制作だったり、あるいはフルHD制作、あるいはフィルムからのHDテレシネなのだけど、少し像が甘く情報量が少ないもの。日本のデジタル放送も、この群に入れていいだろう。
ふたつめは、フルHD制作なのだけど、かなり高品位というもの。フィルムならスキャナを用いてオリジナルネガをデジタル化し、制作過程にアナログフィルムを挟まないような最近のDI制作映画や比較的近年のデジタルシネマカメラで作られたような作品だ。一般に「高画質なブルーレイだなぁ」と思うようなタイトルは、この群に含まれる。
そして三つめ。70ミリなどの大判フィルムを6Kあるいは8Kスキャンして制作、あるいは4K以上のデジタルシネマカメラなどを使って撮影した作品など。これらのマスターは4K以上の解像度を持つため、ブルーレイディスクで入手する際にはフルHDにダウンコンバートすることになるが、ダウンコンバート時のフィルタを工夫することで、一般的なHD映像よりも多くの情報を盛り込むことができる。
超解像処理では、若干残る信号の折り返しを含む部分を復元しようとするため、三つめの群に属する映像は、元が高解像度であることを想定した復元を行うことで、単純にシャープネスを高めたような映像ではなく、情報としてディテールが増えた映像を取り出せる。
もちろん、それはネイティブの4K映像ほどではない。しかし、良いコンテンツと良い映像処理の組み合わせは、フルHDに慣れた目に新鮮さを与えるぐらいには、良い映像になる。
WT600で言えば、4Kファインリマスターエンジンと呼ばれているパートになる。この超解像処理は、映像内をパートごとに特徴抽出し、その特徴に合わせて(4Kカメラならば、こういった像になるといった相関処理に基づく)適切な映像処理を施す、データベース型超解像と呼ばれるものの一種だ。
パナソニックのデータベース型超解像で特徴的なのは、異なる解像度からの復元用データベースが収められていることである。DVDのような標準解像度映像、ブルーレイの高品位映像、放送レベルの映像、それにデジタルカメラで撮影した静止画。それぞれに適した情報を持ち、複数の特徴を持つ映像に適した設計になっているという。
さらに特徴抽出から適したデータベースを引けなかった場合には、適応的に精細感を引き出すデジタルフィルタをかける二段構えとすることで、映像全体に統一感のある超解像処理を行うことができる。
このため、放送レベルなら放送レベルなりに4Kらしい映像として見せつつ、本当に情報量の多い昨今の高画質映像ソフトに対しては、フルHDを越える情報量を4Kパネルに再現できるようになった。
不足する“ネイティブ”に対するパナソニックのアプローチ
もっとも“超解像”は、当面の間、フルHDが映像流通の主流である中で、高精細表示が得意な液晶パネルの長所を引き出すための、ひとつの手段、手法だ。将来を考えるならば、放送やブルーレイなどのパッケージソフトも4Kになっていくだろう。
厳密な規格の策定が必要となる放送とは異なり、インターネットのコンテンツならば、4Kでの映像配信も比較的簡単に行える。そこでパナソニックは4Kビエラ用のコンテンツをインターネット上のサービスとして用意し、簡単にアクセスできるようにした。コンテンツ数は限られているが、今後、徐々に増えていく予定という。
 パナソニックがインターネット上に用意した「Panasonic 4Kチャンネル」で、4Kコンテンツを簡単に楽しめる
パナソニックがインターネット上に用意した「Panasonic 4Kチャンネル」で、4Kコンテンツを簡単に楽しめる
もう一方の最新のインターフェイス搭載は、WT600をもっとも強く特徴付けている。なぜならライバル製品で、このアプローチを成功させているのは現時点でパナソニックだけだからである。
WT600には二つの最新デジタル映像インターフェイスが搭載された。ひとつはDisplayPort 1.2a、もうひとつはHDMI 2.0だ。両者とも4K映像を毎秒60フレームで送出できる実力がある。DisplayPortの民生用テレビへの搭載は初めてのことになる。
DisplayPortは主にパソコンの世界で使われている。パソコンを接続し、大型ディスプレイとして活用することもできるが、もっとも魅力的な使い方は4K解像度でPC用ゲームを遊べることではないだろうか。このためにWT600は低遅延のゲーム用モードを備えている。もちろん、写真を楽しむ上でもPCやMacとの接続が簡単な点は好ましい。
HDMI 2.0搭載に関しても、パナソニックだけの特徴がある。それは、現時点で(他社4:2:0対応に対し)4:4:4対応しているHDMI 2.0のフルスペック(映像送信帯域18Gbps)を満たしている唯一のディスプレイというところだ。HDMI 2.0は4K映像の60P伝送を実現するために決められた規格だが、現時点で他製品は色情報を減らすことで、毎秒60フレームの伝送を実現させている。
現在のところ、このHDMI 2.0のフルスペックに対応している、映像送出側の機器はパナソニック製のディーガ(ブルーレイレコーダ)のみだが、旬日、HDMI 2.0のフルスペックを持つ機器が増えていくことは間違いないだろう。
従来からのメディアをより高画質に楽しむ超解像の技術を磨き込むだけでなく、4Kネイティブの映像を楽しむための経路を、想定できる限りの手段で提供する。そのためにはDisplayPortも搭載する。こんなところにパナソニックならではの“生真面目さ”を感じることができる。