 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第148回:EPG搭載のエントリーモデル「DMR-E85H」登場
|
■ 今が旬なモデル
ここにきて、松下のDIGA新製品投入およびボブ・サップかき入れ時のサイクルが、どうやら見えてきた。一気に5ラインナップを展開したのが昨年春、そして9月にはハイエンドモデル2機種を投入。競合他社がサマーセールや年末商戦といった日本独自の商習慣に合わせて新製品を投入してくるが、それとはまったく関係ないタイミングである。日本だけで云々よりも、同モデルをワールドワイド展開する同社ならではの論理だろう。
この路線で行くと、春に廉価モデル、秋にハイエンドモデルというサイクルも何となく見えてくる。そして今年の春モデルとして市場投入されるハイブリッドレコーダが「DMR-E95H」と、「DMR-E85H」の2モデルだ。型番からしても、昨年春の時点での上位モデル、90Hと80Hの直系と見てもいいだろう。今回はこれら2モデルのうち、先に発売になる「DMR-E85H」(以下85H)を取り上げる。
4月1日から発売となるこの85H、上位モデル95Hとの差はすでにニュース記事でご存じかと思うが、カンタンにまとめるとHDDの容量差、デジタルカメラ、DVカメラ対応の有無ぐらいである。店頭予想価格は9万円前後となっているが、すでにネット通販では6万円台を掲げるショップも出ており、テレビ録画に集中したい人にとって、85Hはまさに旬な買い物だ。
「セカンドジェネレーション」と言われる新DIGAの実力、さっそくチェックしてみよう。
■ 低価格を感じさせないデザイン
 |
| ラインは複雑だが、うまくまとまったデザイン |
今回の85Hは、横から見ると二重の「<」状のせり出しを組み合わせた、やや複雑なデザイン。かといってゴチャゴチャした印象はなく、コストと上品さの間で、ユーザーが納得するあたりに落とし込んでいる。
正面左側には外部入力端子、右側に操作ボタン類がある。ボタン類は非常にシンプルで、ワンポイントとして大きく目立つ録画ボタンの他は、ボディライン内に収まるよう、さりげなく配置されている。

|

|
| 前面左側にある外部入力端子 | ボタン類はますますシンプルに |
中央部のドライブは、DVDレコーダでは初のDVD-RAM 3倍速ドライブを採用した。DVD-Rは4倍速となっている。DVD-RAMは既に5倍速の声が聞こえ始めており、2倍から3倍じゃあなぁという声もあるだろう。だが今後、CPRM対応メディアとして重要性を増してくるDVD-RAMが多少なりとも高速化されるのは、悪い話ではない。
HDD容量は160GBで、最近のレコーダとしては平均的。今回はEPモードが強化され、さらに高圧縮のモードを使用することができる。画質に関しては、後でサンプルを見て頂くことにしよう。
EL表示部は、数字は大柄でモードなどの表示は小柄。遠くからでも認識できるのは、現在表示中のチャンネルと録画残量だけだ。このあたりの大胆な割り切りが、家電に強いメーカーの本領だろう。またダビング中は、進行状況がパーセントで表示されるなど、数字をうまく使ってステータスを表わす工夫がなされている。
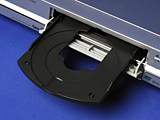
|

|
| DVDはDVD-RAM 3倍速ドライブを採用 | 大柄な数字が大胆なELディスプレイ部 |
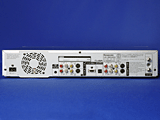
|
| ファンが出っ張っていないぶん、シンプルさがより際立つ |
背面に周ってみよう。従来からDIGAは他社製品に比べると奥行きが短かったが、そのぶん電源ファンが飛び出していた。だが今回はファンも内部に入っており、かなりすっきりした印象だ。
入出力端子は標準的。チューナはアナログ地上波のみで、BSチューナはない。補正機能では、3次元Y/C分離はあるが、GR(ゴスートリデューサ)はなし。AV入力は背面に2、前面に1。出力は2系統に加え、D1/D2端子と光デジタル出力がある。
また、従来シリーズ同様、地上波デジタルの録画にも対応している。おそらく販売店などでもこの点を強調したセールストークが展開されるだろう。だが対応したといっても、別途チューナや対応テレビからのアナログ入力が可能というだけで、HD画質をMPEG-TSで録れるわけではない。コピーワンスに対応しており、HDDに録画した番組はDVD-RAMにムーブできる。まだデジタル放送のメリットまでには至らず、とりあえずダークサイドをクリアといった程度であることに注意してほしい。

|
| アルミパネルをうまく使ったリモコンも健在 |
リモコンもチェックしておこう。基本的なデザインは80Hのものと変わらず、アルミ張りの綺麗なスタイル。だが機能が多少変化している。
大きな変更点は、十字キー左下に「サブメニュー」キーが作られたことだろう。そのほかEPGを搭載した関係で、200Hなどハイエンドモデルのリモコンにあったアルファベットの「A B C D」キーが付けられている。
■ 大きく変わったGUI
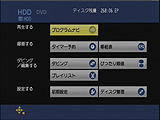 |
| 目的別に分けられたトップメニュー |
今回のDIGAは、セカンドジェネレーションを謳うだけあって、操作画面にも大きく手を入れてきた。トップメニューでは、以前のような機能が一面に表示されるスタイルではなく、目的別選択スタイルとなった。「再生する」、「録画する」といったやりたいこと別で分けられており、デジタルレコーダ初心者にも親切な作り。ただし、この画面を呼び出すリモコンのボタンには以前のモデル同様「機能選択」と書かれており、ちょっとコンセプトと合わない。
また、これらの機能の中には、HDDとDVDに対して別々に働くものがある。例えば「ディスク管理」などがそうだ。HDDモードになっているときにDVDのディスク管理をしようと思ったら、いったんこのメニューを抜けてドライブ選択ボタンでDVDに切り替え、再びこのメニューを表示させる必要がある。このあたりに、「HDDとDVDは同レベルで2 in 1」的ポリシーが色濃く残っている。
既に多くのメーカーでは、メインはHDD、DVDは保存用という分け方をしており、筆者もそれが正論だと思っている。しかし、松下としてはDVDもHDD並みに直接録画とか推進していこうみたいなところは、どうしても会社的に譲れないのだろう。そこを理解というか我慢できるかが、DIGAのキモなのかな、という気がする。
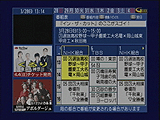
|
| この価格でEPG搭載は立派 |
GUIで変わった点といえば、録画した番組を一覧表示する「プログラムナビ」画面だろう。以前は文字だけの表組みで表示されていたものが、2行3列のサムネイルで表示されるようになった。番組を選択すると、サムネイルが音声付きで再生されるため、検索性はいい。さらに従来通りのリスト表示でも、選択した番組の内容がサムネイルで表示される。

|
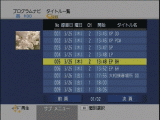
|
| プログラムナビはサムネイル表示となった | 従来型リスト表示でも、サムネイルで再生が可能 |
また、今回から新たに「サブメニュー」という考え方が導入された。例えば番組の編集などは、サブメニューから「タイトル編集」を選び、さらに「部分消去」を選ぶといった使い方になる。最小限の操作は上記のようなトップメニューでやらせておき、それ以上を求める人には階層化されたメニューで対応と、ユーザーを2層に分けたような格好だ。
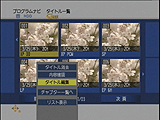
|
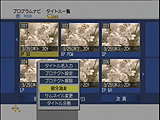
|
| サブメニューボタンで編集機能などが呼び出せる | 部分的にメニューは階層化されている |
だが階層メニューの出し方が、上位階層メニューの真上に出るのはどうだろうか。混乱を避けるために上位メニューを敢えて隠すのだ、という考え方なのだろうが、パソコンなどでメニュー操作に慣れていると、全体的な操作体系の見通しが悪い印象を受ける。
■ 低ビットレートモードが強化
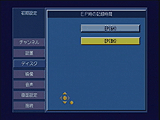 |
| EPモードは2種類のビットレートからいずれかを選択する |
| モード | 記録時間 HDD(160GB) |
記録時間 DVD(4.7GB) |
サンプル画像 |
|---|---|---|---|
| XP (DD) |
約36時間 | 約1時間 | 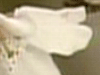 xp.mpg (20.3MB) |
| SP | 約70時間 | 約2時間 | 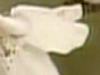 sp.mpg (12.4MB) |
| LP | 約138時間 | 約4時間 | 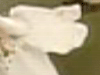 lp.mpg (6.86MB) |
| EP(6時間) | 約212時間 | 約6時間 | 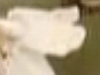 ep6h.mpg (4.43MB) |
| EP(8時間) | 約284時間 | 約8時間 | 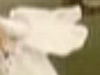 ep8h.mpg (3.56MB) |
| 編集部注:DVデッキ「WV-DR5」で再生したCREATIVECAST Professionalの映像をRF経由で入力し、HDD上に録画。その後、TDKのDVD-Rに高速ダビングした。録画時には3次元YC分離ONを選択している。掲載した静止画は、すべて800×600ドットで表示したものをキャプチャしている。(c)CREATIVECAST Professional | |||
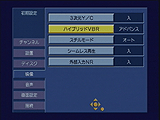 |
| 設定メニュー内にある「スーパーハイブリッドVBR」 |
EPモードでは確かに解像感は落ちるものの、以前のようにブロックバリバリという感じではなくなっている。テレビから数メートル離れて見る分には、さほど失望感は感じないだろう。
録画したものの再生に関しては、リモコンの「画面設定」ボタンを押すことで調整画面が現われる。画質設定として、ノーマル、ソフト、ファイン、シネマと4種類のプリセットの他、ユーザー設定が可能だ。ユーザー設定の内容は、コントラスト、ブライトネスといった一般的な設定のほか、ガンマやNRの設定も可能になっている。
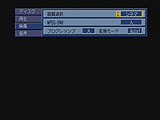
|
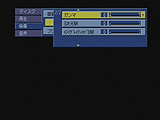
|
| 画質設定は、4つのプリセット、1つのユーザー設定が可能 | ユーザー設定ではガンマやNRのレベルを調整できる |
次は編集~ダビング系の機能を見てみよう。プレイリスト編集画面は、サムネイル表示が3段になっている。一番上がタイトル(番組)、その下が選択したタイトルのチャプタが表示される。最終段がプレイリストで、ここにはチャプタを入れてもいいし、タイトルをそのまま入れてもいい。チャプタの設定は、この画面内からサブメニューでチャプター作成画面へジャンプできる。作成した後は、またこの画面に戻ってくる。
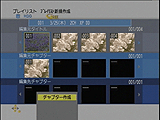
|

|
| プレイリスト作成は、3段表示になった | チャプター設定メニューにジャンプできる |
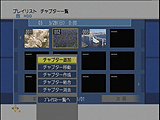 |
| プレイリストの変更は、なぜか「チャプター一覧」から行なう |
「プレイリスト編集」というメニューもあるが、これはプレイリスト再編集という意味ではなく、リストの削除や複製を行なうメニューなので、紛らわしい。なぜ「一覧」なのに編集できてしまうのか、このあたりメニュー名から来るイメージと機能がかみ合わない。
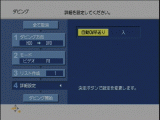 |
| 高速ダビング以外では、「自動CM早送り」機能が使える |
また、HDDからDVD、もしくはDVDからHDDへ高速ダビングをしながら、HDDの録画・再生ができるようになった。メニューやサムネイルなどの表示速度はそこそこだが、ダビング終了まで待たなくて良いというマルチタスク化の恩恵は大きい。待ちに待っていたというユーザーも多い機能だろう。
■ 総論
使い勝手の良さを売りにしてきたDIGAシリーズだが、今回のニューモデルによるGUI改変で、初心者にはさらに優しくなったのかなという気がする。その反面、編集などバリバリやる上級ユーザーには、使いづらくなった面もある。機能的にはそんなに悪くないのだが、特に感じるのは、メニューの作り方のマズさだ。
だがこの価格でEPGまで付いて、160GB HDD搭載は魅力的だ。今年はオリンピックも控えており、録画チャンスは多くなることだろう。これからレコーダを買うという人には、入門機として安心して勧められるマシンだ。また上級者には、画質面の訴求が地味ではあるが、とりあえず地上デジタル放送が録画できることだし、裏番組録画用サブ機として、機能的にはこなれている1台である。
2003年のシェアは40%にも上るというDIGAシリーズ今年の春モデルは、新提案や大きな変革はない。だがこれだけの機能をこれだけの価格でやってのけたという意味で、家電業界に投げかける影響は小さくないだろう。
□松下電器のホームページ
http://matsushita.co.jp/
□ニュースリリース
http://matsushita.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn040309-5/jn040309-5.html
□製品情報
http://panasonic.jp/dvd/products/e95h-e85h/spec/01.html
□関連記事
【3月9日】松下、NEWディーガエンジン搭載「DIGA」ハイブリッド機
-EPGを新搭載。最上位モデルは250GB HDD搭載
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040309/pana2.htm
(2004年3月31日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|