 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第238回:拡張を続ける米国のデジタル放送サービス
|
■ 歩きやすくなった最終日
2006 International CESの最終日は日曜日。来場者もかなり少なくなっただけでなく、プレス関係者も初日の1/4程度しか残っていない。普段はほとんど繋がらないプレスルームの無線LANも、かなり快適に利用できるようになった。本日のZooma!は、日本からは見えてこない米国の放送事業に関連する製品の情報をお伝えしよう。放送関係のショーとしては、毎年4月にNABが開催されているが、こちらは事業者側から放送を見ることになる。
今回はCESらしく、コンシューマの側から放送サービスの利用形態を見ていくことにする。
■ IPとのシームレスな融合を果たすTiVo

|
| 台湾TGC製TiVoと台湾でのサービスを展示 |
HDDレコーダのTiVoは、米国シェアNo.1と言われながらも、日本からではなかなか動向が掴めないものの1つだ。レコーダのブランドでありながらも、統一されたGUIと徹底した番組情報サービスの提供をベースに売り上げを伸ばし、最近では使用ユーザーの動向などをリサーチして統計を販売するといった事業も軌道に乗せている。
これまで米国のみで事業展開していたTiVoだが、昨年11月からは、台湾でも事業をスタート。実際に運用を行なっているのは現地パートナーのTGCだが、TiVoのミーティングルームでは、そのTGC製TiVoとサービスを初めて見ることができた。
もちろん全米規模に比べれば放送規模は小さいが、番組情報サービスを含め、十分に受け入れられているようだ。
米国向けハードウェアの新情報としては、今年中に新しいTiVoマシン、Series3をリリースするという。価格、発売時期などは未定だが、HD対応デジタルチューナを2機搭載し、ダブル録画も可能。約300時間の録画が可能だという。また米国独自のCATV受信の仕組みである、「ケーブルカード」にも対応している。

|

|
| HD放送対応の「TiVo Series 3」 | Series 3に接続できる、ウエスタンデジタル製外部ストレージ |
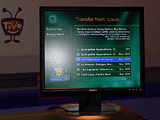
|
| Viivマシン用に新開発したGUIで、PCでもTiVoと同じ操作感を実現 |
ホームネットワーク関連技術としては、Intel ViivマシンとTiVoをホームネットワークで接続し、コンテンツを転送できるようになった。ViivマシンはWindows XP MCE搭載であるため、MCE用リモコンを使って、TiVoとほぼ同じ10フィートGUIで動作するソフトウェアを新たに開発したという。
番組の録画はTiVoで行なって、再生は部屋のPCで見る、といった使い方ができる。ただ、ネットワーク越しにストリーミングで見るのではなく、あらかじめPCにコンテンツを転送しておく必要がある。
米国では結局ブロードキャストフラグの導入が行なわれなかったため、デジタル放送であっても日本のようなDRMはなく、フェアユースという概念に沿って自由に事業展開ができる。だからこそできるソリューションだと言えるだろう。
またモバイル機器に対する転送もサポートした。PC上で番組コンテンツをMPEG-4 AACに変換し、PSPやiPodに転送できる。
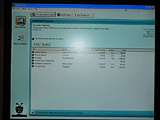
|
| ポータブル機転送のターミナルとなる「TiVo Desttop」 |
さきほどのViivマシンでもそうだが、PC側のプラットフォームとなるTiVo Desltopというアプリケーションに、TiVoのユニークIDを入力しておく。そのPCを使ってポータブル機に転送すれば、ポータブル機側では再生時にIDなどを入力することなく再生が可能。コンテンツ流出防止技術としては、ウォーターマークを採用しているという。
基本的には、管理技術としてのDRMに頼るのではく、フェアユースという、言わば運用方法による解決方法として、今後日本でも参考になる部分は多い。
IPとの連携に関しては、TiVoのメイン画面である「TiVo Central」の画面から10フィートGUIのWEBサービスが利用できる。具体的にはYahoo!などのポータルへ接続して、天気予報や渋滞情報といったサービスが利用できるほか、アップロードした写真をスライドショーで見たりすることが可能。
写真はともかく、日本ではデータ放送で行っているような分野の情報サービスだが、米国には放送としてこのようなサービスがないため、こういうことがIPの役割となるようだ。
またインターネットラジオやオンラインの簡単なゲームも、リモコン操作で楽しむことができるというのは面白い。ユーザーの目の前にはコンテンツがあるだけで、それが放送から来るのかIPから来るのかの区別がないわけである。
ショッピングという面では、映画の予告CMからリンクして、映画館のチケットが買えるというシステムも開発した。リモコンを使ってクレジットカード決済までできる。映画館へはクレジットカードを持っていけば、その場で発券してくれる仕組みだと言う。
イメージとしては、日本では飛行機の国内線で行なっている、チケットレスチェックインのようなものだと考えればいいだろう。
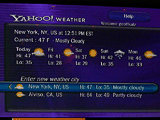
|
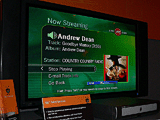
|
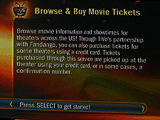
|
| TiVo上でYahoo!のコンテンツが利用できる | インターネットラジオの再生もシームレスに可能 | オンラインで映画のチケットが決済できる |
またビデオブログを登録しておいて、自動ダウンロードできるような仕組みも開発しているという。例えば放送コンテンツでも、電波に乗せるほどでもないようなコンテンツ、例えば試合前のロッカールームの模様や、試合後のダイジェストなどを放送局が用意し、それをTiVoにダウンロードさせる、といった使い方を想定しているようだ。
局としては、本来の放送をより多くの人に見て貰うための番組宣伝の一環として、これらのコンテンツを制作するということで話が付いているという。
もちろん純粋にビデオブログのようなものも登録できる。例えば今米国で一番人気のあるビデオブログは、「RocketBoom」だそうだが、これも今まではいわゆるホビーでやっていたブログが、広告モデルでプロとしてやれそうな状況になってきているという。
RocketBoomはたった2人で制作しているらしいが、こういうコンテンツがレコーダであるTiVoに載り、テレビとシームレスにアクセスできることで、カタチ的には放送免許いらずで放送と同等のことが、個人ベースでも可能ということを示唆している。
こういう動きが可能なのは、TiVoというレコーダだからできるということではなく、各メーカーのレコーダのフロントエンドとして、TiVoのGUIなり仕様なりが載っているという、ちょっと変わった構造だからできる話なのである。
メーカー主導型というか、メーカーごとにレコーダの仕様がバラバラの日本市場では、こういう大きな枠組みの話は規格化などを行なわなければならないため、なかなか難しいかもしれない。
今日本では、放送とIPの融合として、放送をIPに載せるということに終止しているが、その先に来るべきビジョンとして、TiVoの動向は参考になるだろう。
■ パイオニアとSamsung、ポータブルXMレシーバを発表
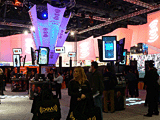
|
| ノースホールにあるXM Satellite Radioのブース |
米国ですでに大きな存在となりつつあるのが、衛星デジタルラジオ放送だ。これは専用衛星を使って全米に100を超えるチャンネルを提供するラジオ放送で、移動体受信が可能であるため、車載ラジオとして大きなマーケットになっている。XMとSeriusというのが、2大放送事業者である。日本ではこれらを参考にして、「モバHO!」がスタートしたわけである。
その1つ、XM Satellite Radioでは、MP3プレーヤー兼用のポータブルレシーバー2モデルを発表した。1つはパイオニアの「inno」、もう一つはサムスンの「HELIX」である。
どちらも仕様としてはほぼ同じで、MP3+WMAプレーヤーの機能に加えて、XMラジオの受信と音楽配信サービスであるNapsterにも対応している。またXMラジオの内容を録音することもできる。
今回のポータブルレシーバを使えば、徒歩での移動中でもXMラジオが楽しめるほか、車載キットやホームキットを利用すれば、車内でも家庭内でも楽しむことができる。
パイオニア innoを例に取ると、1GBメモリ搭載し、180×180ドットのフルカラーTFTを備えたメモリーオーディオプレーヤーといった風情だ。約50時間分のコンテンツを収録でき、バッテリは連続5時間使用可能。価格は399.99ドルで、今年3月の発売を予定しているという。

|
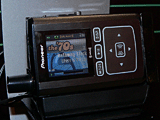
|
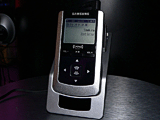
|
| パイオニア製XMレシーバ「inno」 | 横向きでも使用可能 | Samsung製XMレシーバ「HELIX」 |
ノースホールにあるXMのブースでは、実際の放送波を会場外で受信して有線で引っ張ってきていたため、ポータブルでの受信感度などはわからなかったが、試聴してみたところ音質は結構いい。一般的なMP3プレーヤーの音質と比較しても、十分だろう。
以前は米国カーオーディオの大手Delphiが、カーオーディオだけどチューナ部を外して家庭でも聴ける、というXMチューナを出していたが、バッテリでは駆動できなかった。今回の2製品は、完全にポータブルを意識した製品となっており、車だけではない新しい顧客層を呼び込むことだろう。
というのは、現在のXM放送は、コマーシャルなしの放送となっているというところが大きい。XMは有料放送で、以前はコマーシャルが入るものの、基本料金がライバル社のSeriusより安いというのがウリになってた。だがこの4月に基本料金を値上げして、Seriusと同じ月額12.95ドルとなった。
タテマエ的にはそれまで別料金だったインターネットラジオサービスとコミの値段ということだったが、放送アナリストの意見では広告収入の減少が原因ではないかとされている。
つまり、日本におけるFM放送みたいな感覚でXMラジオのコンテンツを捉えてしまうと、ただのポータブルラジオかよ、という話になってしまって、このソリューションの面白さが見えてこない。160チャンネルの中から、お気に入りのジャンルを放送するチャンネルをかけっぱなしで聴くというのは、他人の作ったプレイリストの音楽を聴くという感覚に近く、日本で言えば「有線放送」の無線化といえるかもしれない。
両レシーバーにはXMラジオの録音機能も付いているが、常にリアルタイムで流れっぱなしなわけだから、あまり録音することには意味がない。もっとも、電波の届かない場所に備えて録音するという用途は考えられる。
放送とIPの融合という意味では、ラジオ放送で流れた曲をNapsterで購入するという流れを、どういう具合に仕掛けていくのか。あるいはこのレシーバーの登場で、ローカルで音楽ファイルを持つ意味とは何かを、具体的に問われる段階に入ってきたのではないかという気がする。
日本でのサービスに置き換えて考えると、モバHO!がこのようなソリューションを提供できるとは思えない。どちらかといえば、ライブドアが仕掛けているような無線LANネットワークを使ったインターネットラジオの利用、といったところのほうが、現実味があるように思える。
日本では放送事業者がまったくIP音痴なので、なかなかこのようなビジョンを持つことができないというところが、最大の問題点であろう。
□2006 International CESのホームページ(英文)
http://www.cesweb.org/default_flash.asp
□関連記事
【2005年1月10日】【EZ】2005 International CESレポート【米オリジナルと新技術篇】
~ TiVoの新サービス、松下のHD対応SDカムなど ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050110/zooma188.htm
(2006年1月10日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.