 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |
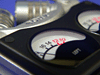
|
第232回:ナマ録マニア垂涎の逸品、ソニー「PCM-D1」
|
■ ナマ録、次世代へ
11月25日発表の、「ソニー、DAT製品の国内出荷を終了」のニュースは、1つの時代が終わったという感慨とともに、現実問題として困ったという人も少なからずいたようだ。DAT最大のメリットといえば、リニアPCMで長時間録音可能なポータブル機である、という点に尽きる。今ポータブルのデジタル録音機といえばHi-MDや、MD、ボイスレコーダが主流であるが、圧縮記録(Hi-MDはリニアPCMでも録音可能ではあるが)ではどれもDATの代わりにはならない。
そんな中、なぜかこれまでナマ録に対してあまり興味を持たなかった層にまで関心を持たれているのが、11月21日に発売されたソニー「PCM-D1」である。高性能内蔵マイクを装備し、アナログメーターまで備えたそのルックスにヤラレた人も多いようだ。
内部に4GBのメモリを備え、リニアPCMは最高で24bit/96kHzで録音できる。リニアPCMのポータブル録音機では、24bit/44.1kHzで録音できるEDIROLの「R-1」や、M-AUDIOの24bit/96kHz対応「MicroTrack 24/96」が登場しているが、PCM-D1は少なくともコンシューマ機では間違いなくトップクラスのスペックだろう。
もちろん値段もトップクラスで、店頭予想価格は20万円前後だという。一説にはもともとクオリアシリーズとして開発していたという話もあり、それならば値段の方も納得してしまう。
現在趣味としてはどのぐらいの規模になっているのかよくわからない「ナマ録市場」だが、趣味の領域に止まらず、コンテンツ制作などの業務で必要という人も少なくないはずだ。
音響工学を勉強していた学生時代、「オープンデンスケ」担いで録音実習にいそしんだ筆者だが、20数年前を思い出しながら、PCM-D1を試してみた。
■ 丁寧な作りはさすがハイエンド
ではまずルックスから見ていこう。ボディはチタン製で、持ち上げると大きさの割にはずっしりと重い。昨今のポータブルプレーヤーやボイスレコーダのようなつもりで持ち上げると、驚くだろう。本体の重さに加えて、単三電池4本で駆動することもあって、全体で約525g。外装部では、電池蓋部分のみ樹脂製のようだ。

|
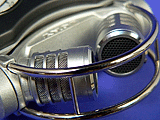
|
| 見た目も重さも重厚 | 新開発のマイクロホンを変形X-Y型に配置 |
新開発のエレクトレットコンデンサーマイクロホンは、真鍮削りだしで、左右のユニットが中央に向かって傾いている。つまり左のマイクが右の音を拾い、右のマイクが左の音を拾うのである。
左右のマイクの距離を近づけることで、「点的」な集音が可能になる。つまり音の位相差を極力無くすことで、中抜けしない集音が可能というわけだ。ステレオ録音のマイクアレンジにもいろいろな考え方があるが、こういうセッティングで固定してある製品というのは珍しい。
マイクのガード部はステンレス製となっている。本体・マイク・ガードにそれぞれ違う素材を使うことで、特定の共振周波数が発生しないようになっているという。またこのガード部に被せる形のウインドスクリーンも付属している。このマイク部分は、上に30度、下に45度傾けることができる。

|
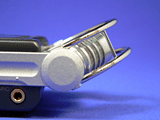
|
| 専用ウインドスクリーンが付属 | マイク部は上下に傾けることができる |

|
| 表示部に和紙を配したアナログメータ。バックライトがオレンジ色に透過する |
マイク部分の下には、アナログ式のメーターがある。よく見て貰えばおわかりのように、アナログ式とはいっても、いわゆる基準値を0VUにしたVU計ではなく、-12dBを基準としたデジタル対応メーター(デジベル計)となっている。
液晶部分には-60dBから0dBまでのピークレベルが表示されるのだが、音量的に細かく監視したい-20dBから10dBぐらいをメーターの振れで見ることができる。アナログ式メーターの良さは、ピークメーターのようにリニアに反応しないので、人間の聴感に近い感覚で音量レベルを監視できるところにある。なおメーター部にはLEDもあり、ピークが-12dBを超えるとグリーンに、-1dBを超えると赤に点灯する。
液晶表示部はモノクロだが、視野角が非常に広く、本体をかなり寝かした状態でも表示が確認できる。表示部左のボリュームはヘッドホンのモニタ音量、右のボリュームが録音レベルだ。録音レベルボリュームは二連になっており、腕時計のリューズのように引き出すことで、左右別々のレベルに設定できる。
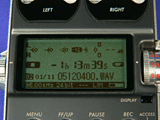
|

|
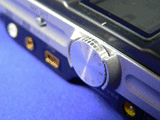
|
| 液晶表示は視野角が広く、視認性がいい | 大きめの録音レベルボリュームは二連になっている | モニタ音量ボリュームにも手抜きはない |
また両ボリュームとも、底部方向からも露出しているので、本体の下から指を回して調整することができる点は、よく考えられている。さらに無音で動作するため、録音中のレベル変更も可能だ。本機はマイク内蔵であるため、特にこういった点が重要になるわけだ。また録音ボリュームの下側には、メモリースティックPROスロットがある。
ボタン類はやや小振りで、表面からあまり出っ張っていない。REC、PAUSE、PLAYボタンにはLEDが仕込まれており、押下時に点灯する。
バッテリは、単三型のニッケル水素充電池が4本付属し、24bit/96kHz録音時は連続で約4時間の収録が可能。一方アルカリ電池では、約2時間となっている。緊急時には役に立つが、普段は二次電池を使うべきなのだろう。
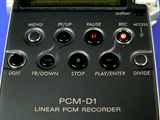
|

|
| ボタン類はやや小振りで、出っ張りが少ない | バッテリは単三電池4本で駆動 |
製品には専用の小型三脚も付属しており、底面の三脚穴にセットできる。この三脚は、足を閉じると綺麗な棒状になるので、そのままグリップとしても使えるようになっている。また本機底面の三脚穴は一般的なサイズとなっており、カメラ用三脚やマイク用ブームなどもそのまま利用できるだろう。

|

|
| 小型三脚も付属する | キャリングケースも付属しており、ケース内には三脚収納部もある |
■ すべては録音のため
つぎに機能的な部分を見ていこう。本機は内部マイクでも十分な音質が得られるが、外部マイクも使用できる。ただし入力がステレオミニジャックとなっていることから、業務クラスのマイクはそのままでは接続できない。もっともこの本体にキャノンコネクタを付けるというのもキビシイ話で、致し方ないところだろうか。

|

|
| 外部マイクも使用可能だが、バランス入力がない | アッテネータを装備し、大音量の現場にも対応 |
内部マイクには-20dBのアッテネータが付いている。大音量の現場での収録は、アッテネータを入れることで録音レベル操作がやりやすくなるわけだ。またそれとは別途、メニューで設定するデジタルリミッタもある。
外部入力もあるが、アナログ入力のみ。これでデジタル入力があれば、モロにDATの変わりとなったところだが、惜しい。だがデジタル入力を付けることで変なDRM制限に巻き込まれるぐらいなら、いっそない方がマシだろう。
一方出力のほうは、アナログ・デジタル兼用となっている。デジタル出力の場合は、光デジタル出力となる。
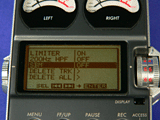
|
| メニュー項目はさほど多くなく、いずれもベーシックな機能ばかりだ |
USB端子は2.0対応で、マスストレージにも対応しているため、PCに接続しただけでマウントされる。ファイル名は年月日+2ケタの連番になるようだ。本機は時計機能を内蔵しているため、ファイル名に時刻まで入れることもできただろうが、ファイル名が冗長になるという判断だろうか。
メニューボタンを押すと、各種設定が行なえる。早送り/巻き戻しボタンで上下移動、PLAYがENTER、STOPまたはMENUがCancelとなる。
録音モードと4GB内蔵メモリへの記録時間は以下の通りで、デフォルトはCDと同じ44.1kHz/16bitとなっている。リニアPCM以外、例えばMP3のような日和ったモードが全くないというところも、割り切った作りだ。
| REC MODE | 録音時間 |
| 22.05kHz/16bit | 約13時間10分 |
| 44.10kHz/16bit | 約6時間35分 |
| 44.10kHz/24bit | 約4時間20分 |
| 48.00kHz/16bit | 約6時間 |
| 48.00kHz/24bit | 約4時間 |
| 96.00kHz/16bit | 約3時間 |
| 96.00kHz/24bit | 約2時間 |
そのほか設定らしい設定といえば、デジタルリミッタのON/OFF、200HzのハイパスフィルタのON/OFFぐらいである。ソニーらしい機能といえば、SBM(Super Bit Mapping)機能が使えることだ。これはソニーが独自に開発した、20bitのオーディオデータをうまく16bitに変換する機能である。
通常20bitから16bitの変換は、下位4bitを捨ててしまうだけなのだが、SBMでは20bitのデータを16bitに再レンダリングする、というイメージで理解して貰っていいだろう。この機能は、同社VAIOに付属のSonicStage Mastering Studioにも搭載されており、VAIOユーザーにはお馴染みの機能である。
本機でこの機能を使うには、いったんREC MODEの設定を16bitにする必要がある。この後SBMをONにすることで、20bit相当の16bit録音ができるというわけである。高音質で少しでも長時間録音したいときには、便利な機能だろう。
■ 中抜けのない自然なステレオ感

|
| PCM-D1とEDIROL R-1 |
では実際にナマ録してみよう。手元にEDIROLのR-1もあるので、一部の音は両方で録ってみた。ただし多くのパソコンでは、16bit/48kHzまでしか再生をサポートしていないため、双方のサンプルが試聴できないケースも多いだろう。サンプルを試聴するためには、Intel HD Audio対応PCか、別途ハイビット/ハイサンプリング周波数に対応したサウンドカードやUSBオーディオデバイス、再生ソフトウェアが必要になる点は、あらかじめお断わりしておく。
まず本体の堅牢性だが、チタン製ということで、かなりハードな現場でも問題なさそうだ。だが振動を与えると電池ケース部分がカチャカチャ言う。車載など移動しながらの集音は、その点に気をつけたほうがいいだろう。
またマイクが本体内蔵ということで、グリップノイズはかなり拾いやすい。録音中に持ち替えるといった動作は厳禁だ。付属の三脚をグリップ代わりに使えば、本体を直接持っている時よりも多少グリップノイズは軽減できるが、それでも持ち替えたりすればノイズが入る。
メーター類は、液晶のピークメーターとアナログ式メーターがあるので、直感的に監視しやすい。ただアナログ式メータは、いわゆるVU計とくらべてスケールが狭いので、そのつもりで見ているとレベルオーバーしがち。感覚的に音量を設定できるようになるまでは、しばらく慣れが必要だろう。
とはいうものの、デジタルリミッタを入れておけば、歪んで使い物にならないということにはならない。アナログ時代はリミッタなど使うのは邪道という風潮もあったが、デジタル時代になってピークも綺麗に拾えるようになってくると、あるものは利用した方が得だ。
独特の変型X-Yマイクレイアウトは、集音してみると確かに中抜けがなく、しっかり芯のある音が録れている。ナチュラルなステレオ感は、本機特有のテイストだろう。一方過度なステレオ感を期待する人には、もの足りなく感じてしまうかもしれない。
| PCM-D1 (96kHz/24bit) |
EDIROL R-1 (44.1kHz/24bit) |
|
| 鳥の鳴き声、 小雨 |
sample1.wav (9.88MB) |
sample2.wav (6.30MB) |
| サッカー練習 | sample3.wav (1.70B) |
sample4.wav (7.82MB) |
| 都電荒川線 踏みきり |
sample5.wav (26.9MB) |
sample6.wav (13.6MB) |
| 銀座雑踏 | sample7.wav (14.8MB) |
R-1はピークレベルが確認しづらいため、若干録音レベルを低めに設定した。その分を差し引いて聴き比べて欲しい |
| ちんどんや | sample8.wav (19.7MB) |
|
| 編集部注:試聴するためには、Intel HD Audio対応PCまたは、別途ハイビット/ハイサンプリング周波数に対応したサウンドカードやUSBオーディオデバイス、再生ソフトウェアが必要になります。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 | ||
集音中に気になったのは、ヘッドホン端子が右側にあるところだ。最近ヘッドホンも、ケーブルが左側方出しのものも多くなっている。そういう場合にはいったん本体の後ろにぐるっとケーブルが回ることになり、邪魔だ。モニター用のボリュームも左側にあることだし、ヘッドホン端子は左側にあっても良かったのではないだろうか。
もう一点気になったのは、寒い日の収録に難があるというところか。本来ならば、本体付属の充電池を使うべきなのだが、あいにく貸出機には充電池が同梱されていなかった。そのため新品のアルカリ電池を入れて収録に出かけたのだが、収録日は冷たい小雨が降る、冷え込みの激しい日であった。
本機は本体が金属製であるため、こういう寒い日はボディがものすごく冷たくなってしまい、素手で持っているのが辛いほどだ。だが手袋をして操作するには、ボタン類があまり出っ張っていないので、操作しづらい。
また本体の温度が急激に下がることで、電池の電圧もどんどん下がってしまい、ものの10分足らずでバッテリ切れの表示が出てしまった。マニュアルには、アルカリ電池使用の際はバッテリメーターの表示は正確ではないとの注意書きがあるが、結局電池交換の目安にもならなかった。
■ 総論
「ナマ録」というのは、おそらく女性のほとんどと、男性でも大多数は1ミクロンも理解できない趣味であろう。なにせ20万も出した結果が、「音がリアルに録れるだけ」なんである。だがかつてのラジカセ全盛の時代、多くのメーカーが本気でパラボラマイクなどを搭載して、ナマ録を高尚な趣味へと持ち上げた時代があったのだ。思い返してみれば、当時いい歳のオジサンがラジカセかついでナマ録していたところなど見たことがない。やはりあれは、子供から青年程度ぐらいをターゲットにしていたんだろう。
だが例えコドモダマシにしろ、日本の大企業がこぞって大まじめにナマ録用ラジカセを発売し、それを真に受けていそしんだ子供が今や40~50歳になっているわけである。そういう意味では、ナマ録という趣味は意外に裾野が広いのかもしれない。
マイク内蔵のリニアPCM録音機としては、既にEDIROLのR-1もあるが、実際に比べてみると数多くのエフェクトやフィルタを搭載してなかなか高機能ではあるものの、レベルメーターが見えづらかったりすることもあって、千載一遇の音を録る、というタイプの製品ではないように思う。まあ失敗したらもっかい録ってくださいみたいな、割と楽器っぽい思想が垣間見える。
一方PCM-D1は、デジタル的に余計な機能はほとんどなく、ただひたすら音を録るだけのために生まれたような作りだ。ある意味、かつてのデンスケを彷彿とさせるような、プロ機にも通じるストイックさを持ち合わせている。
ただマイクを内蔵しているというところで、グリップノイズや振動によるノイズを拾いやすいのは惜しい。例えばマイクユニットをフローティング構造にするとか、もう少し内蔵マイクだけで十分完結できる工夫があると、さらに良かっただろう。
ナマ録という市場、さらに20万円という価格からしても、PCM-D1はそうそう数が出るモデルでもないと思われる。さらに後継機が作られる可能性も、ほとんどないだろう。そういう意味では、登場した瞬間からもう「幻の名器」となっているようなものである。
普段我々は、生活の中で「録りたい音」に巡り会うチャンスは、あまり多くない。だがもし「鑑賞に値する音」が回りにあるのならば、ぜひ録音しておくことをお勧めしたい。値段が高いPCM-D1を買ってまで、というのはなかなか難しいかもしれないが、音を記録するという趣味は、もうそろそろ復権してもいいのかなという気がしている。
□ソニーのホームページ
http://www.sony.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200511/05-1109/
□関連記事
【11月28日】ソニー、DAT製品の国内出荷を終了
-12月初旬にレコーダ出荷を停止。テープ販売は継続
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051128/sony.htm
【11月9日】ソニー、24bit/96kHz対応のリニアPCMレコーダ
-生録用の携帯録音機。4GBメモリ内蔵で実売20万円
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051109/sony1.htm
【2004年10月18日】【DAL】RolandのWAVE/MP3レコーダ「R-1」を試す
~ 24bit/44.1kHzのPCM録音が可能 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20041018/dal164.htm
(2005年12月7日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2005 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.