 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】
|
|
西田宗千佳の ― RandomTracking ― ビクターが語る「倍速駆動」の秘密
|
今年の液晶テレビのトレンドは、なんといっても「120Hz駆動」(倍速駆動)。液晶の弱点である動画ぶれを抑制し、画質を向上するものとして、いまやハイエンド機には必須の機能となった。
ビクターは、「倍速駆動」を最初に製品化したメーカーである。2005年11月に発売した「LT-37LC70」に搭載して以降、2006年中は、「倍速といえばビクター」という状況を作り上げていた。7月には、フルHDパネルかつ倍速駆動を採用した「LH805」シリーズを投入、WXGAモデルの「LC95」シリーズとあわせて、トータルなラインナップを構築している。
今回は、倍速駆動の先駆者であるビクターに、倍速駆動にまつわる秘密を聞いた。
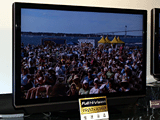 |
 |
| ビクター「LT-47LH805」 | LC95シリーズ |
■ 「ホールド型」の強みを生かす「倍速駆動」
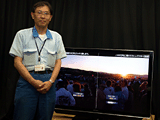 |
| ディスプレイ事業グループ・先行開発グループの相羽英樹主席技師 |
「自然界の絵というのは、点滅していないですよね。ディスプレイが点滅するというのは、本来不自然な話です。だから、液晶はある意味自然な絵ができているわけです。ですがもちろん、自然の映像は『ホールド』しません。ですから液晶にとっては、いかにホールド時間を短くするか、というのが重要なわけです」
ビクターで倍速駆動技術を開発する、ディスプレイ事業グループ・先行開発グループの相羽英樹主席技師はそう説明する。
液晶は、基本的に「ホールド型」と呼ばれる技術。動画像が表示されている時でも、コマとコマの間は、前のコマの映像がそのまま表示され続けている。その結果、ちらつきなどを感じにくいわけだが、逆に、書き換え後も目に残像が残り、違和感を感じることがある。
これまで液晶の残像感を低減するには、液晶パネルの応答速度、すなわち、映像そのものが書き換わるまでの反応速度を上げれば良い、とされ、液晶パネルを評価する時にも、「色変化時の応答速度は何ミリ秒か」といったことが重視されてきた。
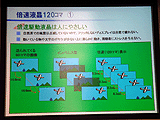 |
| 倍速駆動の表示概念 |
だが、相羽氏はその発想が「もう限界に来ている」と語る。人間の目に対する、ディスプレイの動画の応答特性を調べた「MPRT」値の計測例を示しながら、次のように説明した。
「60Hzだと、いくら液晶の応答速度を上げても意味がありません。MPRTを計測したところ、結果が飽和してしまって、仮に応答速度がゼロのものを使ったとしても、8ミリ秒程度のパネルと差が出ない。すなわち、液晶の改善だけでなく、再生レートを変えないとどうしようもない、ということです」
これこそが、ビクターが液晶に倍速駆動技術を導入した理由である。
パネルの応答速度に依存した改善に限界があることは、ビクター以外も認識していたことである。解決策として黒挿入や90Hz駆動を採用しているメーカーもあった。
そんな中でビクターが採用したのが、コマとコマの間の映像を生成し、120コマにして表示する「120Hz駆動」(倍速駆動)である。
「黒挿入は、輝度が落ちるという欠点があります。画像生成方式による倍速ですと、MPRTもいいし、輝度低下もない。ネックなのは、倍速変換回路が必要ということです。我々はそれを、パネルと並行して先行開発することで、コストを抑えることを狙いました」(相羽氏)
 |
 |
| 人間の視覚特性上ブレて見えてしまう映像(左)を、中間フレームを挿入し、動きを見せることで実感される「ボケ」を低減する。(イメージ図。提供:ビクター) | |
現在、倍速駆動技術の主流は、ビクターが先鞭をつけた画像生成方式になっている。画像生成ではなく、黒挿入などを用いた間欠方式(インパルス方式)を採用しているメーカーは日立などに限られ減少傾向といえる。コスト的には不利だが、画質を評価し、多くのメーカーが画像生成方式の採用を決めたのである。そういう意味では、ビクターの狙いは当たっていた、ということになる。
聞くところによると、現在国内メーカーのほとんどが、オリジナルの倍速駆動用LSIを開発し、採用しているという。「我々が最初に倍速駆動を出せた理由は、回路をいかに効率的に作るか、ということも注力したからです。この種の機能は、高価にしたくない。倍速でネックなのは、コストが上がってしまうことです。我々は、コストが極力高くならない方法を採っています。そこにノウハウがある、と思っています」(相羽氏)
■ 同じ「倍速」でも、「動き予測精度」で差が生まれる
今回の取材では、ビクターの新型「LH805」と、いくつかのライバル製品を見比べながら説明を受けることができた。
ビクターの液晶テレビでの絵作り技術を担当する豊嶋智主席技師は、「今の段階で、他社との比較では、弱みはないと思います」と、自社の技術を評価する。
実際、デモを見てみると、同じように見える倍速技術でも、かなりの差が存在するのがわかる。例えば、黒挿入方式を使っているものの場合、輝度が低下するデメリットを緩和するために、輝度の高い画面、例えば白いテロップが高速に流れるような場合には、黒挿入を切ってしまう。当然輝度低下はないものの、動画ぶれは従来のままだ。輝度を判断して黒挿入をコントロールする発想は面白いが、「動画ぶれ防止」という意味では、効果が限定される。
また、あるメーカーのものでは、右から左へバスが動いた直後に、左から右へと別のバスが動き出すと、補間の予測に失敗し、文字の輪郭などが崩れてしまうものがあった。だが、ビクターのものは問題ない。
なぜこのような違いがあるのだろうか? 相羽氏は、「動き予測の精度の差だ」と話す。「我々は、画面の1ドット1ドットすべて予測を行なっています。全画面分演算するため、それだけ演算コストはかかりますが、画質を考えれば、そのくらいやるのは最低限のことだと思っています。店頭などで流すデモモードでは、上にテロップを流しながら、下に全然別の映像を流す、ということをやっています。そうした映像でも補間ミスが無い、というのは、全画面でまじめに演算しているからなんですよ」(相羽氏)
倍速駆動では、実際の映像には存在しない映像のコマを作り出す。前後のコマの間をとるだけでは不完全であるため、作り出すコマより前の映像を、時間軸を追ってたどり、「どんな映像になりうるのか」を演算して作り上げる。これが、相羽氏の言う「動き予測」である。
動き予測には、時間軸のデータだけでなく、計算中のドットの周囲がどんな映像なのか、というデータも使われている。倍速駆動対応のWXGAモデルの場合には、周囲1,600ドット分の情報が使われている。だが、フルHDの新型では、周囲8,000ドット分もの情報が使われているという。WXGAからフルHDにするだけなら、ドット数は2倍程度上げれば十分なはず。だが、ビクターが選んだのは、一気に5倍程度まで拡大することであった。
「実際のところ、2倍程度あれば画素数的には事足りますが、それでは不満足だったんです」と相羽氏は語る。
理由は、ビクターの行なったリサーチの結果だ。相羽氏のチームは、動き予測の精度向上を狙うため、ハイビジョン動画像の中に、どのような動きが多いのかを分析したのだという。
「単純に全方向を細かく見ると、処理能力的に無駄になりやすいので、分析から得られた情報を元に、集中的に検知するようにしています」と語る。この検知領域を、単純な四角形から、分析にあわせた形に変更し、精度を上げるために、動き予測用の監視領域を広げたのである。広告やプレス資料などでは、単なる四角で表現されているのだが、実際には幾何学的な模様ではないという。
動き補間の仕組みを作る上で大切なことを、相羽氏は「人間の予測と一致していることだ」と語る。「結局、人間が見ない、予測しない部分については補間する必要があまりありません。そもそも、動画ぶれというのは、人間の目が動きを追いかけるから発生します。映像を見ていると、思わず中の動きにあわせて視線を動かしてしまうわけですが、それがどのくらいの速度なのか、そしてどんな方向へ動かしているのか、といった部分も、入れ込んでいかなければなりません。そこの追求は今後も必要なので、さらに切磋琢磨しようと思っています」(相羽氏)
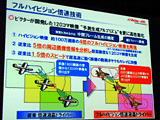 |
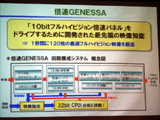 |
| 従来の5倍の周辺画像情報の分析を行なうことで、フルHDでも高精度な中間フレーム生成を可能とし、違和感のない映像表現を可能とした | 倍速GENNESAを搭載し、フルHDでの倍速駆動に対応 |
豊嶋氏も、チューニングの方向性を次のように語る。「まずは、文字が読みやすいかどうかに注力してチューニングしています。テロップの流れるスピードは、上下左右で異なります。番組制作側が『読ませよう』と思っている文字は、ゆっくり表示するので、精度が上がろうが上がるまいが、そんなに変わりません。しっかり読めます。問題は左右です。おそらく、読んでもらわなくてもいい、というつもりで、高速に流しているものが増えているのですが、これがぼけたままだと、とにかく目が疲れるんです」
■ VA方式とIPSでは異なる「ぶれ」方、発色にも違い
「倍速駆動回路があれば、動画ぶれがなくなる、というわけではありません。実際には、液晶の駆動方式によっても、ちょっと違ってくるんですよ」と豊嶋氏は語る。
現在、液晶パネルの駆動方式としては、VA(Vertical Alignment)方式と、IPS(In-Place-Switching)方式がある。豊嶋氏によれば、IPSとVAでは、動画ぶれの傾向がかなり異なるのだという。
「IPSは、どの色も均質に出るため、白でも黒でも残像感は同じです。しかしVAは、振幅が大きく違う色、白と黒などでは、残像の尾の引き方が大きく異なってきます」
ビクターは、フルHDハイエンドモデル「LH805シリーズ」ではIPS方式を採用した。だがそれ以前の倍速駆動モデルでは、VA方式を採用していた。最終的な効果や絵としては大きな差が出ないようにチューニングを行なっているが、IPSにはオーバードライブのしやすいなどのメリットがあるという。
オーバードライブとは、液晶の応答速度を上げるために、映像を切り替える際、電圧を一瞬だけ高めにかけること。現在、多くのテレビ向け液晶パネルで採用されている技術ではあるが、こと「動画ぶれ」の低減という部分では、様々なノウハウが必要になる、という。
「60Hz駆動で動画ぶれを防止するには、オーバードライブを強めにかける発想になりがちですが、そうすると、逆にギラっとした絵になってしまうことも有るのです」(豊嶋氏)
倍速になり、無理なオーバードライブが不要になることで、映像は「自然に見えるようになる」という。「本来は、予測補間+オーバードライブのかけ方のチューニングで、最終的な倍速駆動の絵が出来ている、と考えてください。原理的に、120Hzだけを作ろうと思ったら、そんなに難しい話ではありません。でも、精度を上げようと思うと、かなりのノウハウ蓄積が必要になるのです。昔、プログレッシブ対応テレビが出始めの頃、IP変換の精度で、各社に差がありましたよね。それと同じことだと思っています」と豊嶋氏は話す。
ビクターは、倍速駆動により、「色もきれいになる」とアピールしている。無理なオーバードライブが不要になること、動画ぶれによって、視界内で色が「混ざる」ことが少なくなることで、瑞々しい色を再現できるようになったからだ。デモでは、ハイビジョン撮影した寿司や、女性の肌などで違いをアピールしている。「おもしろいことに、男性はお寿司に、女性は肌に反応する」(相羽氏)のだとか。
また、画像生成の方式によって、色の違いも出てくるのだという。「中には、『輝度信号だけは倍速補間するけれど、色差信号は補間しないよ』という製品もあるようです。そうすれば、倍速駆動LSIのメモリー量を大幅に削減できますから。これでも、白い文字テロップの動画ぶれなどは改善できるのですが、『色』は動画ぶれしてしまいます。高画質化にはマイナスです」(豊嶋氏)
ビクターが採っているのは、もちろん、輝度・色差すべてを補間する方式だ。
■ 「3倍速」、「4倍速」はコスト的に合わない?
このままいけば、画像補間による倍速駆動技術は、年末までに、すべての大手メーカーの上位機種に採用される、当たり前の機能になっていくだろう。「普通に使ってストレスのないテレビを普及させる」というテーマに添うなら、結構なことではあるのだが、ビクターという企業としては、差別化要因が少なくなる、と見ることもできる。
となると、容易に思いつくのが、「倍」ではなく、もっと速い速度で書き換える、という方法である。豊嶋氏は次のように語る。
「180Hzとか240Hzをどうするかは難しいところですね。メモリーを2倍、4倍使っただけの効果があるかというと……。60Hzと120Hzの差ほどは、わからないんじゃないかと思います。結局は、許容限界と検知限界、という話になるでしょうね。180Hzとか240Hzになればさらにいいけれど、120Hzくらいでも許容範囲内、というところだと思います」
この意見に、相羽氏も同意する。
「180Hz駆動や240Hz駆動は、コストとのバランスが良くないかも知れません。時間をかけて技術革新していけば変わるかもしれませんが、結局今後は、液晶の応答速度と一緒に改善していかないと、大きな効果を期待するのは難しいかもしれません」
技術的には別の方向性もある。松下は昨年までのモデルで、バックライトの明滅を制御することで、ホールド型である液晶の欠点を緩和し、動画ぶれを抑える技術を使っていた。画像生成方式の倍速駆動にバックライト制御を組み合わせれば、さらに高画質化が見込めそうな気もする。ただ、これもそう簡単なことではないようだ。
「バックライトについては、蛍光管の残光の問題があります。60、90Hzなら問題ありませんが、120Hzを超え、あまり速く切り替えると、追従できなくて残像になる可能性が高い。もちろん、LEDなら問題ないわけですが。生産やコスト面での兼ね合いもあります」(相羽氏)
現時点では、倍速に続く技術はすぐに出てくるわけではなさそうだ。当面は、地道に遅延の少なさや動画補間予測の確かさ、といった強みを伸ばしていくことが重要、ということになるのだろう。
■ 「倍速はゲームに向かない」は間違っている!
相羽氏は、「倍速駆動」に関し、ちまたで流布している、ある噂に、不満を持っている。
「よく、倍速にすると『時間遅延がある』という話がありますが、倍速だからということはありません。『ゲームモード』を用意して、倍速駆動を切る代わりに時間遅延をなくす、と言っているメーカーさんもいるので、問題視されるようですが、私は、ゲームの時こそ、倍速補間をオンにしていただきたい、と思っているんです。効果が一番はっきりしますから。我々は、倍速を使いつつも、遅延が一番少なくなるような方法を採っているんです」
実際、ビクターの製品と、いくつかの倍速駆動テレビを比べてみた。両方共に「倍速駆動モード」の場合、私の体感では、もっとも遅い製品で、ビクターの製品に比べ、コンマ数秒の遅延が見られた。ゲームでいえば、およそ4、5フレームというところだろうか。驚いたことに、「ゲームモード」をオンにしても、まだビクターの方が速かった。
「ゲームする時に、いちいちメニューに入って切り替えなきゃいけないのは面倒です。なにもしなくてOKならば、それが一番だと思っています」と相羽氏は語る。
そんなこともあってか、ビクターのテレビは、遅延の少なさに関し、ゲームファンからは比較的評判がいい。「アーケードゲームメーカーでも使って欲しいと願っています」(相羽氏)。
残念ながら現状では、表示遅延時間が何ミリ秒くらいなのか、スペック面での公表はなされていない。「業界で共通して出していればいいのですが……。自信はありますが、ビクターだけが公表しても、『それが速いのか遅いのか』はわからないですよね。難しいところだと思います」(相羽氏)
気にしている人も少なくないだけに、「動画ぶれの度合い」の指針も含め、業界での統一的な表記が必要な時期ではないだろうか。
■ 倍速駆動も遅延の少なさも「優しいテレビ」のため
遅延の少ない倍速駆動は、ビクターのテレビ作りのポリシーを表すものでもある。豊嶋氏は、倍速駆動に込められた想いを次のように説明する。
「今回、フルHDからWXGAまで、倍速駆動モデルをそろえたわけですが、これは技術的にどうこう、ハイエンドモデルを作りたい、というより、倍速を毎日使って欲しいからなんです。上のモデルだけにつけて、一番売れるモデルにないのではダメじゃないか、と。うちは、『普段使っても疲れない、優しいテレビですよ』という発想です。動画ぶれの一番悪いところは、見ていて目が疲れること。毎日使ってストレスを感じない製品に仕上げたつもりです。また、あまり機能を気にせずに使って欲しい、と思っています。なにかやるたびにメニューを選んでボタンを押す、という形ではなく、簡単に使って欲しいですね」
この考え方は、相羽氏の担当する、倍速駆動にも通じている。「例えばゲーム。レースゲームをやると、普通は車や前の道に注視しているので、周囲のぼけに気づきません。でも実際に、周囲の風景を見ると、かなりぼけてます。だから、人に運転させて背景を見続けていると、動画ぶれで酔ってしまうんですよね。われわれの製品は、その辺もかなり改善されていると思います」
ビクターのテレビの発色も、「疲れない、優しいテレビ」という考え方に基づいている。色を派手にするのでもなく、いたずらに輝度を上げるのでもない。他社に比べると、比較的落ち着いた色合いである。
テレビというと、どうしても「美しい」という言葉で語りがちである。もちろん、ビクターも「美しさ」を追求しているが、「それだけでないテレビ」も求められてくることだろう。
□ビクターのホームページ
http://www.victor.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.victor.co.jp/press/2007/lt-47lh805.html
□関連記事
【5月24日】ビクター、倍速駆動/10bitパネル搭載フルHD液晶テレビ
-IPSパネル採用の37/42/47型。「倍速」でシェア10%へ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070524/victor.htm
(2007年6月21日)
| = 西田宗千佳 = | 1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に、取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、「ウルトラONE」(宝島社)、家電情報サイト「教えて!家電」(ALBELT社)などに寄稿する他、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。 |
[Reported by 西田宗千佳]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.