 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |
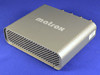
|
第299回:DVI出力をビデオ信号に変換、Matrox「MXO」を試す |
■ 1年越しの企画
昨年のNABで、発表されたMatroxの「MXO」。MacのDVI出力を各種ビデオ出力に変換するボックスだが、いつか使ってみたいと思っている間に、もうじき2007年のNABが開催されようという今頃になってしまった。約1年越しのレビュー企画である。MXOはオープン価格で、店頭予想価格は16万円前後。したがって一般の方が買うようなものではなく、業務ユーザー以上になるだろう。
今さらながらではあるが、丁度今週から最新ドライバのVer1.2が公開されたばかりというタイミングだ。また日本のビデオ制作の現場でも、改めてMacの導入が高まりつつある。これらのことをふまえて、今回はMatroxのMXOをテストしてみることにした。
■ ノンリニアシステムはモニタが難しい
そもそもなぜこのような変換BOXが必要になるのか。理由は大きく2つに集約されるのではないかと思う。まず1つは、現在のノンリニア編集システムは、HD時代、そしてフラットテレビ時代になって、モニタ環境の整備が遅れていることだ。業務レベルのビデオ編集を行なう場合には、PCモニタ上だけではなく、ビデオ用モニタを使って映像を監視する必要がある。PCモニタとビデオモニタではガンマカーブが違うし、オーバースキャン/アンダースキャンの違いもある。さらにはプログレッシブスキャンとインターレーススキャンの違いもある。見え具合が全然違うのである。
過去アナログ入力によるキャプチャが主流だった時代には、ノンリニアシステムには必ず各種アナログ入出力端子を備えていた。したがってアナログ出力を利用したモニタリングは、比較的容易であった。
だがDV専用の簡易的なシステムでは、デジタルストリームを直接IEEE 1394で受け渡しするだけなので、ビデオ規格の入出力を持たない。この頃からすでにモニタリングの不便さは指摘されていたのだが、主にこのクラスのユーザーがアマチュアということもあって、さほど問題視されないまま今日に至っている。
一方デジタル時代になって、放送用ビデオモニタのほうも変化した。アナログはコンポーネント入力が主流になり、デジタルではSDIが主流になった。さらにHD時代になって、この傾向はより顕著になった。
したがってモニタ出力まで備えたHDのノンリニアシステムは、たとえ映像ソースの入力がIEEE 1394であっても、モニタ出力及び放送用VTR書き出しのためにHD SDI端子を備えなければならず、どうしてもハードウェアとして大がかりになってしまう。CPUパワーこそ格段に上がって、ノートPCクラスでもHDVの編集ができるようになったが、モニタ環境は二の次となってしまっているのが現状だ。
例えば報道など、とりあえず編集するだけという業務であれば、ビデオカメラできちんと放送規格内の映像が撮られているという前提で、ビデオモニタを見ずに編集してしまうという運用は、考えられなくもない。だが画像合成やカラーコレクション、スーパーインポーズなど自分で色を作るような作業では、きちんとビデオ用モニタで見え具合を確認しないと、異常やミスがあっても見つけられないことがある。
もう一つの問題は、業務用として使えるフルHD解像度のモニタが少ないという点である。ブラウン管の放送用モニタはもちろんフルHD対応なのだが、今ほとんどのメーカーが製造を終了してしまっている。
一方で液晶パネルを使った業務用モニタもいくつかのメーカーから出ているが、フルHDパネルではないため、縮小して見ることになる。一般の人がテレビとして見る分にはそれでも問題ないかもしれないが、仕事で使う分にはやはり等倍のスケールで見ないと、細かい部分の精度が保証できなくなってしまう。もちろんメーカーのほうもそれはわかっていて、決してマスターモニタとは謳っておらず、ラインモニタという言い方をしている。
こうして考えると、今HD用ノンリニアシステムにフィットするHDビデオモニタというのは、ほとんど選択肢がないのである。これはもちろんモニタメーカーの対応が急務なわけだが、放送用モニタというのは高い精度と信頼性が求められる割にはあまり数が出ないし、従来のブラウン管より高いと売れないということもあって、各メーカーとも尻込みしている状態だ。
両方の問題は、端的に言えば「コスト」である。ノンリニア編集は特殊なマシンではなく、ソフトウェアだけで可能になったから今日の趨勢がある。放送用モニタは、手がかかる割には儲からないから作らない。
この両方の理由により、モニタ環境は急速に劣化することになったのである。
■ これまでになかった「外付け」という発想
MXOが画期的なのは、これらの問題を解決する点である。MXOを使うことで、選択肢がないHDビデオモニタを、PCモニタで肩代わりさせることができる。ご存じのように今PC用液晶モニタというのは、かなり価格が下がっている。また画面の大型化が進み、ピクセル数で言えば1,920×1,200ドット程度の解像度も珍しくない。テレビ的な視点で見ればこの解像度は、HDの1,920×1,080ドットを十分カバーできるわけである。
もちろんビデオ用モニタとPC用モニタには、様々な違いがあるため、そのままではビデオモニタとしては利用できない。ざっと拾い上げただけでも、ガンマカーブ、色温度、色空間、応答速度、フレームレート、IP変換の有無などがある。
MXOは、可能な限りこれらの違いを吸収して、PCモニタの表示をビデオモニタに近い状態に変換してくれるのである。ただ応答速度だけは液晶パネル固有の問題なので、MXOでは解決しない。
前置きが長くなったが、さっそくMXOとはどういうものかを見てみよう。本体のサイズは女性用お弁当箱程度の、据え置き型ボックスである。前面はパンチンググリルになっているが、内部にファンなどがあるわけではなく、動作は無音だ。ただ内部チップの放熱口であるため、塞がないように設置する必要がある。
主要部分は、むしろ背面である。DVI端子が2つあり、DVI INにMacからDVI出力を繋ぎ、DVI OUTにPC用モニタを接続する。つまり外部モニタへの結線の間に挟み込むわけだ。またMacとはUSB接続しておく必要がある。
 |
 |
| 一般的なブレイクアウトボックスぐらいのサイズ | DVI接続の間に挟み込むように結線する |
電源としてACアダプタが付属するが、本体に電源スイッチなどはない。MXOはホットスワップ可能なので、そのあたりの作りはかなり簡易になっている。電源とUSBを接続すると、前面左下に青いLEDが点灯する。
ビデオ出力はコネクタを兼用しているため、コンポーネントか、コンポジットとY/Cの切り替えとなる。REF INとは、同期信号の入力である。最近はデジタルのリファレンスも増えてきたが、MXOはアナログ信号のみに対応となる。まあ機材のグレード的には、妥当だろう。
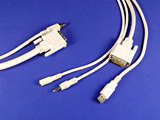 |
 |
| 付属のマルチケーブル。DVIとUSB、アナログ音声などが一緒になっている | S-Video変換ケーブル。YとC端子からS-Video端子に変換する |
一方デジタル出力は、SDIとHD SDIに対応。デジタルオーディオは、このラインに8chまでエンベッデッド(重畳)することができる。そのほかアナログ音声出力も、2ch分を備えている。
■ 上質な表示機能
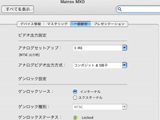 |
| 「システム環境設定」内にMXOの設定がある |
MXOには、編集ソフトなどの使用時に外部モニタをプレビューに使う「マスタリング」モードと、プレゼンテーションソフトなどを使用するときに、メイン画面のミラー出力をビデオフォーマットで出力する「プレゼンテーション」モードがある。それぞれの動作セッティングは、専用ドライバで設定する。
今回はマスタリングモードをテストしてみることにした。使用するソフトは、Final Cut Pro Ver5.1.4(以下FCP)である。FCPは、メイン画面に編集操作のGUIを出したままで、もう一つの外部ディスプレイに映像プレビューを出力する機能がある。
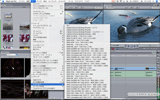 |
| 「ビデオ再生」部分に大量のプリセットが現われる |
MXOのソフトウェアインストール後には、この部分にMXO用の出力プリセットが大量に現われる。今回は以前ソニーHDR-HC7で撮影した時のHDV素材でテストを行なうことにした。MXOを使った場合と、バイパスした場合の表示を比べてみよう。
PCモニタを再撮したので若干フリッカーが出ているがそれは見えないことにしていただいて、MXOをバイパスすると動きが激しい部分は、インターレースノイズが出ている。また動画の動きにリアリティがなく、時折時間軸がズレて引っかかるような動きになる。これは60Hzという液晶モニタのリフレッシュレートに対して、ビデオのフレームレートが59.94Hzという、微妙な違いによるしわ寄せが現われる現象である。
一方MXO出力ではインターレースノイズがなく、ビデオらしい滑らかな表示が行なわれているのがわかる。またMXOはモニタのリフレッシュレートをビデオのフレームレートに強制的に合わせるため、映像の引っかかりがなく最後まで滑らかだ。さらに映像全体の解像感が高く、動きがある部分でも液晶特有のフリッカブルな表現にならない。
| MXOバイパス | ||
 ezsm01.m2t (41MB) |
 ezsm02.m2t (21.7MB) |
 |
| 動きの途中でときおりひっかかりがある | 水の部分のアップ。インターレースノイズが顕著 | 静止状態。色味が不自然で、鼻のあたりに解像度の悪さが目立つ |
| MXO使用 | ||
 ezsm03.m2t (41MB) |
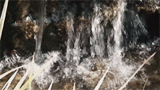 ezsm04.m2t (23.3MB) |
 |
| ひっかかりもなく滑らかに表示される | 激しい動きでもインターレースノイズが出ない | 静止状態。色味が自然で、鼻のラインも滑らか |
| 編集部注:再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 | ||
ご存じのようにHC7は、色空間を大幅に拡大したx.v.Colorでの撮影モードを備えている。両方の映像出力を比較してみたところ、ビデオ用の色空間にリミッタをかけるようなことはなく、そのままの違いが表示された。
■ リアルタイム収録にも使える
MXOには、もう一つのメリットがある。DVI端子を使ったモニタ出力が可能になるだけでなく、リアルタイムのビデオ信号出力も得られるため、このプレビュー再生をそのままVTRなどに収録して、完成品とすることができる。もし通常の手順で書き出しを行なうとしたら、完成した編集結果をいったん1つのファイルとして書き出し、それをテープデッキなどに出力することになる。短いコンテンツ、例えば3分、5分程度のものであればこの方法でも大して時間はかからないが、30分や1時間番組ともなると、このファイル書きだしの手間がものすごく無駄のような気になる。ヘタすればそこで半日待ちとなってしまうのである。
だがMXOの出力を使えば、最後にファイルとして書き出さなくても、とりあえずリアルタイムでプレビューが動くように合成箇所などのレンダリングを済ませておくだけで、最終書き出しが可能になる。もともとMatroxの製品は、この部分をメインフィーチャーとした製品群で知られている。
ただDVやHDVのようなi.LINKではなく、HDCAMやBetaCamのようなシリアル制御のVTRに対してタイムコードを指定して書き出す場合は、USBとRS-422の変換インターフェイスが必要になるので、多少大がかりになる。まあこのようなVTRを使用するのはプロユーザーだけなので、そのぐらいの大がかり感はやむをえないだろう。
もっとも手軽なところで、コンポジット出力を試してみた。HDで撮影・制作したコンテンツでも、リアルタイムでSDにダウンコンバートしながら出力することができる。
これはこれで使える機能なのだが、x.v.Colorのように従来のNTSC規格から外れてしまう映像も、そのまま制限なしに出力されてしまう。てっきりホワイトクリップやクロマ制限のようなビデオプロセッサ機能もMXOにあるのかと思っていたら、残念ながらそれはないようだ。
またFCPには、規格を超える信号に対してリミッタをかける「レンジチェック」という機能がある。だがこれが利くのは映像が静止しているときだけで、動画として再生すると、元の信号レンジで出力されてしまう。
| モニタ再撮画像 | 波形モニタ表示 | コメント | |
| 静止状態 | 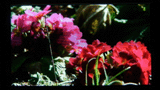 |
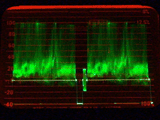 |
レンジチェックを使用した静止状態。クロマとビデオゲインにリミッタがかかっている |
| 再生状態 | 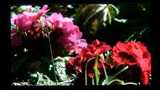 |
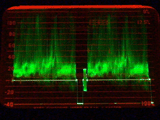 |
再生開始した状態。リミッタが外れてNTSC規格を超えた信号が出力される |
MXOはx.v.Colorに対応していないため、結果だけ見ると酷な評価のように見えるが、x.v.Colorの映像に限らず自分でカラーコレクションなどを行なった場合は、同じ状態になりうる。したがってMXOを使うだけで、放送規格にバッチリ適合、というわけにはいかないようだ。やはり最終的には波形モニタなどを見ながら、自分で適切なレベルに持っていかなければならない。
またMXOには、FCPの「無制限のRT」(Dynamic RT)出力をハードウェアでアクセラレーションする機能がある。このモードは、本来ならばレンダリングが必要な部分を、解像度を落としてリアルタイムレンダリングすることで、本来の時間軸で再生ができるというモードだ。
MXOの有無で比較してみたところ、多少の改善は見られるものの、とても放送品質で使用できるレベルにはない。あくまでもプレビューで使える程度という機能なのだろう。やはり最終出力の前には、エフェクト部分はレンダリングしておく必要がある。
■ 総論
今回はマスタリングモードのみで、プレゼンテーションモードは評価しなかった。というのも、昨今プレゼンはDVI端子付きのデータプロジェクタで行なえるよう環境が急速に整いつつあり、モニタがテレビしかないという状況は少なくなっている。またMXOの価格も約16万円ということもあって、なかなかプレゼンのためだけにこれだけの機材を購入する人は少ないだろうと思われる。そうなると必然的に業務~プロユーザーがマスタリングモードで使用するというのが、MXOのもっとも多い使われ方だろう。今回は特にPCモニタを使ったプレビュー出力で、かなりクオリティが上がるのが確認できた。
仕事でノンリニア編集を行なうユーザーであっても、なかなか個人ベースではHDの放送クラスのモニタを用意できないのが現実だ。確かに16万円という値段は安くはないが、そこそこのコンシューマ用テレビや業務用ラインモニタを購入するよりも安い。なかなかこの価値が理解できる層が少ないのが難点だが、モニタがネックになっていた人にはいい選択だろう。
もう一つのネックは、現在のところMac専用であるというところだ。いくらノンリニアシステムでMacが増えているとはいっても、製品のバリエーションとしてはWindowsの方が多い。MXOのWindows版があれば、もっと多くの編集マンに恩恵があることだろう。
もともとコンピュータとビデオの描画は、根本が違う部分が少なくない。MXOのような整合性を取る製品がもっと出てきても良さそうなのだが、コンシューマではノンリニアビデオ編集も市場があるんだかないんだかよくわからなくなってきた分野でもある。それが差別化に繋がるのなら別だが、やはりこのようなニッチな専門分野の機器でなければ成立しないのかもしれない。
□Matroxのホームページ
http://www.matrox.com/video/jp/home.cfm
□製品情報
http://www.matrox.com/video/jp/products/mxo/home.cfm
□国内総販売元アスクの製品情報
http://www.ask-dcc.jp/content/blogsection/28/142/
□関連記事
【2006年5月1日】【EZ】NAB2006レポート その2
~ HD次世代へ転身するための改革 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060501/zooma255.htm
(2007年3月14日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.