 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第103回:REGZAの超解像技術の実力を試す
~ 地デジ画質に明確な違い。東芝「46FH7000」 ~ |
倍速駆動に続くテレビの高画質化技術の次のトレンドになると予測される「超解像」技術については、前回の「大画面☆マニア」で紹介した。
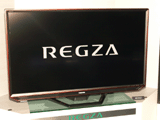 |
| 46FH7000 |
今回は、実際にこの超解像技術を世界で初めて搭載したREGZA 7000シリーズを紹介する。REGZA 7000シリーズのうち、超解像技術を搭載するのは、ZH7000、Z7000、FH7000の3シリーズ。ZH7000とZ7000は画質周り、ネット連動機能などの基本機能を同じくするが、ZH7000にのみ、300GBの録画用HDDを内蔵する。ZH7000、Z7000ともにUSB/LAN接続の外部HDDには録画が行なえる。
今回取り上げるFH7000は、ZH/Z7000と画質周りの機能はほぼ同じながら、デザインにこだわった超解像技術搭載の普及モデル。300GBのHDDを搭載するほか、eSATA接続の外部HDD録画にも対応するが、ZH/Z7000に搭載されるDLNA、アクトビラ、インターネットなどのネット連動機能が省略されている。今回は46V型モデルの46FH7000を取り上げた。
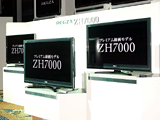 |
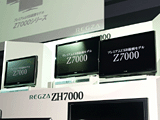 |
 |
| ZH7000シリーズ | Z7000シリーズ | FH7000シリーズ |
■ 設置性チェック
~狭額縁のスマートデザイン。TOSHIBAロゴもライトアップ!
 |
| 狭額縁デザインが特徴的な46FH7000 |
FH7000は46V型と40V型の2サイズモデルのみをラインナップするシリーズで、他シリーズと比べて画面バリエーションが少ない。これは最も売れ筋の40V型と46V型にサイズを絞った変わりに、カラーバリエーションで展開させた商品のためなのだという。そのためFH7000には「デザインコンシャス・モデル」(デザイン重視モデル)というキャッチコピーが与えられている。
カラーバリエーションは3色。銀系のアルミナス・シルバー、赤系のカッパーレッド、青系のブルーブラックで、今回評価したのはカッパーレッドモデルになる。実機を見た感じではアルミナスシルバーは白に近いイメージ、ブルーブラックは黒に近いイメージで、カッパーレッドは茶に近いイメージとなる。
デザイン重視ということで、色だけでなく、外観デザインもZH/Zシリーズよりも洗練されている印象だ。まず画面の額縁部が狭く表示面が本体一杯に広げられているようなワイド感がある。実際、同じ表示画面サイズの46V型モデルで比較すると、46ZH7000が横幅111.3cmなのに対し、今回評価した46FH7000では106.8cmで、横幅だけで4.5cmもFH7000の方がコンパクトだ。コーナー設置時などのケースではより奥に設置できる。
 |
| 3色のカラーバリエーションを用意する「FH7000」 |
スタンド部もおしゃれな中抜きのバーフレームタイプでテレビ台のたたずまいが美しい。このスタンドの奥行きは28.2cmで、こちらも46ZH7000よりも4cmほどスマートだ。また、スタンド部にはスイーベル機構も与えられている。
設定で消すことも出来るがTOSHIBAのロゴが電源オン時にライトアップされ、さらに設定によっては視聴時にも常時自発光させることもできるのもおもしろい。こういう自己主張はソニーがやりそうな発想だが、個人的には、TOSHIBAロゴよりもREGZAロゴの方をライトアップしたほうがスマートだったように思える。
 |
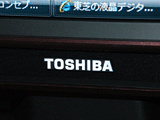 |
| おしゃれなバー・フレームタイプのスタンド部 | 本体下部中央のTOSHIBAロゴが点灯する |
スタンド部を含めた総重量は26.5kg。46V型という画面サイズからするとかなり軽い部類に属する。46ZH7000が29.5kgなので同じ録画対応モデルながら3kgも軽い。テレビ台への上げ下げくらいならば、成人男性一人で行なえるほど。
 |
| スピーカーもコンパクトに実装されたため音質は上位モデルのZHシリーズには及ばない |
壁掛け設置金具は従来モデルに対応してきた純正オプションの「FPT-TA10B」(オープンプライス)がそのまま利用できる。いくら46FH7000が軽いとはいっても総重量は約33kgにもなるため、壁掛け設置では壁補強が必要になる。
消費電力は317W。同画面サイズの他社液晶TV製品と比べるとやや高めだが、これは録画対応でHDD内蔵のためだろう。同画面サイズのプラズマTVが大体550W前後なので、プラズマと比較すればまだまだ低い。
スピーカーは本体左右下部に設置されるアンダースピーカーデザインとなっている。スリムデザインに注力した関係で、スピーカー部は簡略化されており、最上位シリーズの「46ZH7000」では3Wayで10W×2ch+13Wという2.1ch構成だが、46FH7000ではフルレンジユニット×2で、出力は10W×2chとなっている。なおZH7000でも42型はフルレンジユニットのみだ。
筆者は46ZH7000を、46FH7000の評価前に試用していたのだが、音質の違いは明確にあると気づかされた。再生音質は明らかに46ZH7000の方がフラットで上質。特に音量を上げたときには中音域のみが上がっていく46FH7000に対し、46ZH7000はどの音量でもフラットな音質を維持できている。音質を求める場合は、ZH7000を選択するか、あるいはオーディオシステムで補った方がよいだろう。
■ 接続性チェック
~HDMI 3系統装備。アナログビデオ入力端子は最低限
接続端子パネルは背面と、画面正面に向かって右側面に実装されている。
側面の接続端子パネルは、46ZH7000からSDカードスロットとUSB端子が省略されたくらいでほぼ同じだが、背面の接続端子パネルは46ZH7000と比較するとだいぶ端子数が少なくシンプルになっており、上位モデルと下位モデルの格差が見た目にわかりやすく現れている。
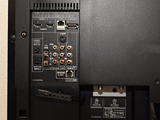 |
 |
| 背面接続端子。アナログ系の入力端子はかなり省略されている | 側面にもHDMI端子はある |
HDMI端子は背面2系統、側面1系統で合計3系統。全HDMI端子はVer.1.3aに対応しており、24pの1080p、広色域のx.v.Color、ハイダイナミックレンジのDeep Colorにも対応する最新仕様だ。
アナログビデオ入力端子は「ビデオ1~3」というくくりで3系統に集約される。ビデオ1はコンポーネントビデオ系のD4端子とコンポジットビデオ端子の排他仕様、ビデオ2はS2ビデオ端子とコンポジットビデオ端子の排他仕様で側面と背面に1系統ずつ実装される。
コンポジットビデオ端子とS2ビデオ端子が排他仕様で集約されているのはいいが、コンポーネントビデオ系がD4端子1系統というのは思い切った省略だ。最近はほとんどのAV機器がHDMI端子を持っているとはいえ、HDMIの無いコンポーネントビデオ出力までの対応のAV機器を持っている人は、この点は要注意だと言える。
Ethernet端子を備えているが、これはデジタル放送の双方向サービスとアナログテレビ放送の電子番組表ダウンロード用のもので、ZH、Zシリーズで対応しているDLNA、アクトビラ、インターネットなどのネット連動機能には対応していない。
 |
| 録画用内蔵HDDは正面向かって左側側面にある。ユーザーによる交換も可能で、こちらはメーカー純正オプション製品にのみ対応 |
eSATA端子を1系統備えるが、これは録画用の外部HDDのインターフェースとして利用される。ZH、Zシリーズは外部ハードディスクインターフェイスとしてUSBを採用している。eSATA HDDは最大8台までFH7000に登録が可能で、各HDDは2TBにまで対応する。なお、録画内容は録画したREGZA単体でのみ再生可能で、著作権保護の観点からたとえ同一モデルであっても異なる本体では再生できない。
いろいろと端子省略が目立つFH7000だが、外部オーディオ出力用の光デジタル音声出力端子、デジタル放送録画出力端子(コンポジットビデオ+ステレオアナログ音声)は実装されている。
PC入力はHDMI経由での接続に対応している。とくに[HDMI2]での接続を奨励しており、HDMI2に連動するアナログ音声入力端子(ステレオミニ)を実装しているため、ここにPCからの音声出力を接続すれば、PCの映像表示時に音声も再生できる。PCモニタとして46FH7000を活用したい人はこの機能を是非活用したい。
■ 操作性チェック
超解像制御にも対応した「おまかせドンピシャ高画質・プロ」
基本的な操作系は先代REGZAとほぼ同じだ。用意されているアスペクトモードについての詳解、二画面機能やサウンド機能のインプレッション、画質調整機能の詳細、録画機能の仕様などについては本連載「46ZH500編」の方を参照していただきたい。ここでは46FH7000で変更されたポイントに絞って評価した。
リモコンは、ここ最近のREGZAのものをそのまま踏襲するが、ZH、Zシリーズなどの上位機ではリモコン右上にレイアウトされている[ブロードバンド]ボタンが、46FH7000ではアスペクト比切替を行なう[画面サイズ]に置き換わっている。ネット連動機能が省略されているためであるが、実際にブロードバンド機能よりも、アスペクト比切り替えのほうが使用頻度は高いという人も多いだろう。この割り当ては悪くない。
 |
 |
| リモコンはここ最近のREGZAに採用されているものを継承 | 右上に[画面サイズ]ボタンが配されている。ZH、Zシリーズではここは[ブロードバンド]ボタンになっている |
電源オン操作から地デジ放送の映像が出るまでの所要時間は4.5秒。まずまずの速さだ。
入力切り替えは、リモコン最上段にあるシーソー式の[入力切換]ボタンで行なう仕組み。このボタンの左を押すと入力系統が1番上がり、右を押すことで1番下がる。ここはやはり使いにくいままだ。入力切換ボタンが左右押しなのに、画面に表示される入力系統一覧は上下に表示されるため直感的なカーソルの上げ下げがわかりにくいのだ。これは入力系統一覧表示を左右に展開するか、あるいは逆にボタンを上下縦配置にすべきだと考える。切換所要時間はHDMI1→HDMI3で約4.5秒、HDMI1→地デジ放送で約2.5秒、HDMI1→D4ビデオで約3.5秒。そして地デジ放送のチャンネル切り替えの所要時間は約2.0秒。全体的に入力切り替えはややもたつく感じだ。
アスペクト比切り替え所要時間はほぼゼロ秒で、[画面サイズ]ボタンを押した瞬間に切り替わるわるので順送り式切換でも待たされる感覚はない。
プリセット画調モードの切り替えは、リモコン下部の蓋を開けたところにある右上の「おまかせ映像」ボタンで行なう。他社製のテレビユーザーがREGZAに移行してきたときにはきっとどのボタンが画調切り替え操作を行なうのか戸惑うことだろう。なお、画調モードの切り替え所要時間はほぼゼロ秒で押した瞬間に切り替わる。
東芝が推すこの「おまかせ映像」とは、視聴環境にリアルタイムに呼応して高画質化機能を動的に働かせてくれる動的画質調整機能のこと。
 |
| 赤く点灯している電源ランプの右側にある矩形の小窓のようなものが照度センサー |
具体的には画面右下にある照度センサーでその時点での照度を計測し、事前に設定した室内照明色にも配慮して階調補正、色温度補正、バックライト制御を行なってくれる機能となっている。この動的画質調整機能に対し、東芝は先代のREGZA 500シリーズで「おまかせドンピシャ高画質」という名前を与えていたが、今回のREGZA 7000シリーズでは「おまかせドンピシャ高画質・プロ」として「プロ」を後ろに付け足している。
視聴環境が明るい場合にはバックライト輝度を上げ最明部基準で映像を作り込み、視聴環境が暗い場合はバックライトを下げて最暗部基準で映像を作り込むという基本特性は先代から受け継ぐも、3つの点において進化を盛り込んだことが「プロ」を付け足した理由である、と東芝は説明している。
1つは、毎秒24コマの映像コンテンツを認識したときには「映画プロ」に近い画調で見えるように色温度と階調カーブを調整する。
2つ目は視聴環境の明暗変化ではなく、映像側の明暗が急激に変化したときに一定の画調で見られるようなバックライト制御と階調補正を行なう。これは音で言うところのラウドネスコントロールに相当するダイナミックレンジ補正になる。
3つ目は、この動的画質調整機構の制御項目に、新要素として後述する「超解像」技術を加えたことだ。筆者が視聴環境の照度を変えてテストした感じでは、視聴環境が明るいほどバックライト輝度が上げて階調表現のダイナミックレンジを高くし、これに同調させる形で超解像の効き方を強くする補正を掛けているようだ。制御自体は理にかなっているし不自然さはない。
いずれにせよ、この「おまかせドンピシャ高画質・プロ」の完成度は上がっており、日中だろうが深夜だろうが、見ていて違和感がない。映画視聴やゲームプレイなど、特定の映像ソースを固定の環境照度で視聴する場合には、他の画調モードを選ぶのもいいが、デジタル放送番組を見る限りは、この「おまかせドンピシャ高画質・プロ」の常用をお勧めする。
 |
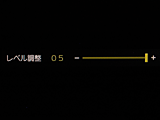 |
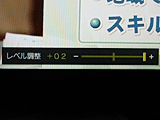 |
| 新設された超解像機能の設定メニュー。超解像処理のオン/オフの設定の他、処理レベルの設定が行なえる | 外部入力端子経由の映像に対しては01~05までの5段階設定 | デジタル放送の映像に対しては-02~+02までの5段階設定。01~05と-02~+02までのパラメータの与え方の違いの説明はない。一応、超解像の効きは、ゲージ左端が最弱、右端が最強となる |
画調関連に関して1つ、細かいことだが、ユーザーにとっては重要な改良点について補足しておこう。
先代機までのREGZAではPCやゲーム機をHDMI接続したときにもビデオ信号として認識していたため、映像をYUV=4:2:2処理してメタブレインの映像処理ロジックへ流していた。これがユーザーコミュニティで指摘され議論を呼んだが、この問題は46FH7000を含む全REGZA 7000シリーズから対策されたとしている。具体的には、画調モードの「ゲームモード」「PCファイン」に設定したときに限っては、映像をYUV=4:4:4のフルレンジ処理をしてメタブレイン・プレミアムの映像処理をバイパスして表示するようになっている。つまり、PCモニターと同等の表示が可能となり、ノイズリダクション処理などの介入による映像の滲みが解消された。
これはREGZAをPCモニタやゲームモニタとして活用しようとしているユーザーには朗報だろう。
■ 画質チェック
~ディテール表現を自信ありげに描画してくれる超解像処理
3万:1は数字のマジックなのでおいておくとしても、実際にコントラスト感は良好だ。高輝度でコントラストを稼ぐ液晶特有のコントラストチューニングではあるが、暗部の沈み込みも液晶にしては立派で、暗部階調色が一様にグレーに見えてしまうようなことはなくなっている。最暗部付近の色表現も、迷光による薄明かりよりも、明らかに強く色味が感じられ暗部の色深度ポテンシャルは非常に高い。
46FH7000はバックライトに広色域バックライトを採用しており、これを活かすための広色域規格x.v.Colorにも対応する。さらにこの広色域規格を多ビット制御するためのDeep Color規格にも対応する。現状でx.v.ColorとDeep Colorに対応したメジャーな機器というとビデオカメラやPLAYSTATION 3くらいしかないが、現行のデジタル放送やBD/DVDといったAVソースでも、この広色域性能の恩恵にはあずかれる。それは「色空間」設定を「ワイド」にすると、現行の標準色域ITU-R BT709(sRGB相当)との互換性を採りながら色ダイナミックレンジを広く取って描画してくれるようになる。
この色域ワイドモードにすると特に青の色ダイナミックレンジが向上し、緑の色純度が高くなる。人肌に影響が大きい赤についてはあまり大きく影響しないので違和感は少ないため、無理なく常用できる。注意深く見ると人肌表現は色域ワイドの方が黄味がとれ若干ナチュラルに見えるようだ。
階調表現は液晶パネルが10bit、1,024階調駆動であり、また映像処理部での内部演算精度を14bitととして、階調分解性能に優れるため空のグラデーションもなだらかに決まる。人肌のハイライト周辺のグラデーションも柔らかく美しく、肌の半透明な質感がよく表現できている。これはパネル駆動精度だけでなく、東芝REGZAの映像エンジン「メタブレイン・プレミアム」に含まれる「新・パワー質感リアライザー」との相乗効果によるものと見るべきだろう。
さて、この「メタブレイン・プレミアム」だが、基本機能部分は先代のZH500と同じで、液晶パネル自体も先代から大きく変わらない。このため、ZH500にも搭載されていた各高画質化処理に対するインプレッション、プリセット画調モードに対するインプレッションについては本連載「46ZH500編」の方を参照して欲しい。
本稿では、一番気になる超解像技術についてのインプレッションを述べておこう。
超解像技術の技術的な解説は前回を参照して欲しいが、簡単に言うと入力映像を低解像度に変換された映像と仮定して、高解像度映像に再構成する技術になる。広義には解像度変換技術ということができるが、解像度変換は元の映像を自然な形で解像度変換を行なうものなのに対し、超解像処理は元の映像に復元することを目指すものだ。
超解像技術として様々な論文が発表されているが、東芝が採用した超解像技術には「レゾリューション・プラス」というブランド名が付けられている。これは入力映像を低解像度化された映像として捉え、仮定した低解像度化アルゴリズムを逆変換するアプローチで高解像度映像を算術合成する「再構成」法と呼ばれるメソッドになる。
なお、東芝のレゾリューション・プラスでは、超解像処理を画面全体にむやみにかけない工夫がなされているので、グラデーション表現に疑似輪郭が現れたり、特定の輪郭表現が妙に際だってしまうようなことはない。具体的には、映像のリアルタイムスペクトラム解析を行なって高周波のディテール表現のみに超解像を適用し、低周波のグラデーション表現には「新パワー質感リアライザー」「シャープネス・オプティマイザー」を適用するようにしている。いうなれば、高画質化処理の適材適所適用をしているわけだ。結論だけに着目すれば、REGZAの超解像処理はディテール表現に対して主に適用されると言うことになる。
さて、東芝のレゾリューション・プラス対応REGZAでは、基本的には入力映像が1,920×1,080ドット未満の映像に対し、1,920×1,080ドット解像度に変換する際に超解像技術を適用するような働きをする。
筆者がテストして見たところ、1,920×1,080ドットのプログレッシブ(1080p)/インターレース(1080i)の映像には超解像の項目自体が選択不能となり効かせることができなかった。1080p映像に対しては効かせられないとは予想していたが、1080iも未対応なのは意外であった。1080i映像に対しては普通にプログレッシブ化をして表示するだけのようだ。
| 放送波 | 放送局 | フォーマット |
|---|---|---|
| 地上デジタル | NHK総合 | 1,440×1,080 |
| NHK教育 | ||
| 日本テレビ | ||
| TBS | ||
| フジ | ||
| テレビ朝日 | ||
| テレビ東京 | ||
| BSデジタル | NHKハイビジョン | 1,920×1,080 |
| NHK1 | 720×480 | |
| NHK2 | 720×480 | |
| BS日テレ | 1,920×1,080 | |
| BS朝日 | 1,920×1,080 | |
| BS-i | 1,440×1,080 | |
| BSJ | 1,920×1,080 | |
| BSフジ | 1,920×1,080 | |
| WOWOW | 1,920×1,080 | |
| BS11 | 1,920×1,080 | |
| TwellV(BS12) | 1,440×1,080 |
ビデオ系映像で超解像が有効だったのは480i、480p、720pとデジタル放送の1,440×1,080ドットのインターレース映像のみ。また、REGZAで録画した1,440の地デジ番組にも超解像処理が適用できる。
なお、デジタル放送における伝送解像度は表のようになっており、超解像を効かせられるのは地デジ放送の全局とBSデジタル放送の一部の局ということになる。ゲームプレイでどうしても超解像を効かせたいという場合には、あえて1080pでは出力せず、720pで出力するようにゲーム機側を設定するといい。
PCとのHDMI接続時も、720×480ドット(480p相当)、1,280×720ドット(720p相当)にすると有効だったが、それ以外の解像度、たとえば800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット、1,280×960ドットでは効かせることができなかった。PC接続時のテストで意外な結果だったのは1,176×664ドット、1,024×576ドット、960×600ドットといったやや変わった解像度で効かせられたのに対し、1,360×768ドットというそこそこメジャーな16:9解像度で効かせることができなかったこと。ゲーム機の場合と同様に、PCゲームプレイやPCでの映像再生時にどうしても超解像処理を効かせたいという人は1,280×720ドットでプレイするといい。
実際に映像を見てのインプレッションは、超解像の効果がわかりやすいといわれるゴルフ中継の視聴から始めた。映し出されるグリーン上の芝目の見え方が超解像のオン/オフで全く違う。オフではボヤっとした明暗の反復模様でしかない芝目が、オンにすると縦方向に植わっている芝の葉として見えるようになる。まさに「画面上でも芝目が見える」といった風情。
バラエティ番組でも出演者の着ている服の布の編目模様が、超解像オンではよく見えるようになるし、肌の肌理の陰影、木々の葉の形、水面のさざ波や岩肌の微細凹凸など、ディテール表現が、自信ありげに描き出される。
言うなれば、視力が向上したような見え方をするのだ。
DVDビデオについても同様で、ぼやっとしていたディテール表現が力強く詳細に描き出されるようになる。それでいて、エッジ部の過度な強調もないので、本当に解像度が向上して見える。輪郭強調やシャープネス強調とは異質な、解像感向上の効果を、たしかに超解像はもたらしてくれる。
ゲームプレイで効果が高かったのはWii、そしてPS2以前の非ハイビジョンゲーム機の映像だ。こうした低解像度のゲーム機映像は最新のフルHD液晶テレビに映すと、とても眠い感じの映像になってしまうものなのだが、超解像オンにした状態だと、ブラウン管テレビで映したときに近い、ぼけすぎずカクカク過ぎない、丁度いい具合のドット描画をしてくれる。これはお勧めだ。
なお、以下に参考までに1080p(超解像適用不可)、720p(超解像処理オフ)、720p(超解像処理オン)、480p(超解像処理オフ)、480p(超解像処理オン)の映像を撮影したものを示しておく。なお、超解像レベルは効果を際立たせるためにあえて最大設定にしている。
480pになってしまうと超解像処理後の映像はさすがに1080pとはかけ離れたものになるが、720pへの超解像処理後の映像は陰影の出方自体は1080pにそこそこ近いものになっている。
 |
 |
| 全体 | 1080p(超解像オフ) |
 |
 |
| 720p、超解像処理オフ | 720p、超解像処理オン |
 |
 |
| 480p、超解像処理オフ | 480p、超解像処理オン |
■ まとめ
今回の評価で、超解像処理が予想外に効果が大きいことが分かった。今秋冬モデルのREGZAを狙うのであれば、超解像は欲しい。
超解像機能を搭載したZH、Z、FHのうち、全シリーズに存在する46V型で比較すると、11月中旬現在で46ZH7000が約37万円、46Z7000が約34万円、46FH7000が約33万円前後。ZHはやや高価になっているが、ZとFHはほぼ拮抗している。機能全部入りのZHは特別な存在として、多くの人は46Z7000と46FH7000とで迷うことだろう。
ZとFHは共にスピーカー性能に関してZHに水を空けられているものの、画質性能はZH、Z、FHで同一。であれば、ZとFH、それぞれの特徴に重みを付けて選べばいい。既にビデオレコーダを持っているのであればネット連動機能が充実している46Z7000を、持っていないのであれば内蔵HDDを搭載する46FH7000がいいだろう。また、Z、FH共に外部接続HDDで録画は出来るので、後付けが出来ないネット連動機能を重視したいというのであれば46Z7000がいいだろう。アクトビラ視聴、ひかりTVやDTCP-IP対応などの次世代ネットテレビ機能を利用したり、録画内容をDLNAベースでダビングするようなシステム拡張はZとZHの特権だ。
個人的には、デザイン的にも優れ、価格も少し安く録画機能搭載で色まで選べる、今回評価した46FH7000を強く推す。
□東芝のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/index_j2.htm
□ニュースリリース
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2008_09/pr_j1806.htm
□製品情報
http://www.regza.jp/product/tv/lineup/fh7000/concept.html
□関連記事
【10月30日】【大マ】超解像技術とはなにか?
~ 各社が取り組む新映像技術を解説 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081030/dg102.htm
【9月18日】東芝、超解像で画質を向上したREGZA最上位機「ZH7000」
-VARDIAへのLANダビング可能。デザインモデルFH7000も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080918/toshiba3.htm
(2008年11月14日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 西川善司 | 大画面映像機器評論家兼テクニカルライター。大画面マニアで映画マニア。本誌ではInternational CES他をレポート。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。映画DVDのタイトル所持数は1,000を超え、去年からはBDのコレクションを開始したようだ。次世代DVD一本化を喜ぶユーザーの1人。ブログはこちら |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.





