 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
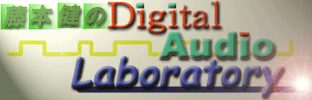
第103回:CDDBの運営元、「Gracenote」の歴史と今後
~ 日本法人設立の意図と新技術「MusicID」 ~
~ 日本法人設立の意図と新技術「MusicID」 ~
 |
| 左からPR担当の山本氏、米Gracenote 社長兼CEOのPalmer氏、グレースノートの渡辺取締役、小玉社長 |
設立にあたって、Gracenoteの社長兼CEOであるCraig L. Palmer氏が来日。Palmer氏と、日本法人グレースノート株式会社の代表取締役社長・小玉章文氏、取締役最高技術責任者・渡辺泰光氏に、会社設立の背景や、そもそもCDDBがどのような仕組みで運営されているのか、また今後の展開などについて話をうかがった(以下敬称略)。
■ 日本のマーケットは同社で最大の売上規模
藤本:CDDBを知っていても、Gracenoteという企業を知らない人も多いと思います。まずはGracenoteがどんな企業なのか教えていただけますか?
Palmer:当社はCDDBの運営をメインの業務として、'98年に創業しました。今回東京にオフィスができたため、これからは米カリフォルニア州のバークレイと東京の2箇所が拠点になります。
CDDBについては、現在30社以上の家電メーカー、4,000社以上のPC関連企業にライセンスしています。具体的にはケンウッド、オンキヨー、ソニー、アルパイン、パイオニア、パナソニック、AOL、モトローラ……といった企業です。
藤本:CDDBは一般ユーザーは無料で使え、登録されていないCDの情報はユーザー自身が登録を行なうことで、情報が蓄積されるデータベースであるため、なんとなくボランティア精神で成り立っているシステムというイメージがありました。でもCDDBはGracenoteという企業が運営しているわけですね?
Palmer:その通りです。確かに、これまでエンドユーザーから課金したことはありませんでしたし、今後もエンドユーザーからお金を取ることはありません。メーカーにCDDBのインフラを提供することでビジネスをしており、1ユニットあたりいくらというロイヤリティ契約が収益の基です。今どんどん成長しており、取引企業の数も増えています。
藤本:MP3ユーティリティソフトなどには、CDDB対応しているものが多いですが、これらのソフトメーカーと契約しているわけですね。でも、先ほど挙がった企業名は、ソフトメーカーというよりも家電メーカー、オーディオメーカーが中心でした。これらの企業はどのような形でCDDBを利用しているのですか?
小玉:主にカーナビでの利用となります。ご存知のとおり、現在カーナビの主流はHDD内蔵タイプです。HDDにCDDBのデータベースを収録しているため、CDを挿入すればすぐに認識します。
藤本:なるほど。でも、その仕組みだとオフラインでのCDDBへのアクセスとなるため、旧譜はいいでしょうが、新譜は認識できないということになりますよね。
小玉:その通りです。新譜に対してのアプローチはメーカーさんによってまちまちですが、多くのメーカーは携帯電話経由でインターネット上のCDDBにアクセスすることで対応しています。中には差分ファイルをPCでダウンロードし、それをPCカード経由でカーナビに転送するものもありますし、カーナビの地図データを有償でアップデートする際に、CDDBも最新のものに入れ替えているところもあります。
藤本:そのような方法でCDDBを利用しているとすると、PCのソフトで単にCDDBへアクセスするのとは異なり、ライセンス料も高くなりそうですよね。実際、日本での売上はGracenote全体のうち、どのくらいを占めるのでしょうか。
Palmer:ライセンス料金はプロダクト内容やボリュームによって違ってくるので一概には答えられませんが、われわれにとって日本のマーケットは非常に大きく、すでに当社においては最大の売上となっています。
藤本:でも、これまでは日本の代理店であったレインボーパートナーズが日本のメーカーを担当していました。今、この時期にあえて日本法人を設立した背景には何があるのでしょうか?
Palmer:これまでレインボーパートナーズとは親密なやりとりをさせていただき、日本市場を大きく育ててくれました。その意味では非常に感謝しています。ただ、ここまで大きくなるとすべてを代理店に任せておくことができなくなってきたのです。日本のお客さんのほとんどがハードメーカーであり、これらメーカーのニーズに合わせた開発をしなくてはなりません。
小玉:現在メーカーで開発しているのは2005年に発売される製品ですからね。HDD対応の製品が数多く出てきたこともあって、とにかくお客さんからの要望も増えてきているのが実情です。これまで開発はすべて米国で行なっていたわけですが、日本でお客さんと一緒になって開発の方向性をみていく必要があると考えています。これによって米国の方針も大きく変わる可能性がありますから。
■ 日本語対応のCDDB、「KCDB」と「CDDB2」の関連性
藤本:ところで、このCDDBについていくつか疑問があります。現在は邦楽CDも何ら問題なく認識するようになり、日本語で表示されます。しかし、数年前まで英語というか1byteコードしか通りませんでした。そのため邦楽はほとんど認識されず、仮に認識されてもローマ字で表示される状態でした。その後、「KCDB」という日本語対応のCDDBが登場し、それに対応したアプリケーションがいくつかあったように記憶しています。でも、気が付くとKCDBではなくCDDB2という名前になり、どのアプリケーションでも日本語が普通に使えるようになりました。この辺の経緯と関連性を教えてください。
渡辺:CDDBはGracenote設立前から米国で運営をしていました。そして、そのデータベース自体どんどんと成長していたのです。私は'87年に株式会社エイムを設立し、現在でも運営しているのですが、CDを認識するソフトを作りたいと考えていました。そんな中、CDDBについて知り、'97年にCDDBの開発チームにコンタクトを取りました。すると、彼らは我々のプロジェクトに興味を持ってくれ、その結果彼らの公認のもと、日本語対応CDDBができあがったのです。これがKCDBです。
仕組み的にはCDDBとまったく同じでしたが、米国のCDDBとは別運営となっていました。しかし、GracenoteがCDDBをバージョンアップし、CDDB2とした際、従来のCDDBとKCDBのデータをすべて統合し、CDDB2サーバーへと移したのです。
藤本:そうだったんですか。つまり初期バージョンであるCDDBとそれの日本語版のKCDB、それにCDDB2の3種類がある、と。CDDB2ができたときに、CDDBとKCDBは消滅したわけですか?
渡辺:古いソフトのユーザーがまだいますから、実は古いCDDBサーバーもKCDBサーバーも現在動いています。もちろんユーザー数はともにどんどん減っているのですが、ある時期からそれ以上減らなくなってしまったんですよ。ただ、いずれは終了させたいと思っています。
藤本:よくわかりました。CDDBはCDのTOCを認識してCDを判別する技術ですよね。これと似たことを行なっているメーカーもあります。MicrosoftのWindows Media Playerも、CDDBではなく、他の技術を使っていると思うのですが。
渡辺:そうですね。マイクロソフトも以前はCDDBを使っていたんですが、現在は独自のものを使っています。
Palmer:CDDBとWindows Media Playerとの認識率の違いや情報量の違いは比べてみればすぐにわかると思います。弊社では、やはり圧倒的にCDDBの方が上と考えています。
藤本:それらはGracenoteの特許に抵触しないんですか?
Palmer:我々としても主張はしています。ただ、法廷での争いにはなっていません。やはりMicrosoftにも様々な言い分があり、彼らも正当性を主張しています。まあ、下手に法廷で争うよりも、お互い主張しあっているほうが健全だろうと考えています。
■ 音楽認識技術「MusicID」を年末に投入
藤本:ところで、Gracenoteは今後もCDDB 1本でビジネスを展開していくのですか?
Palmer:いいえ。我々は現在、様々なソリューションを確立しています。まずメディア認識技術としてはCDDBのほかに、音楽そのものを認識する「MusicID」に、DVDビデオを認識する「VideoID」という技術があります。
またメディア・マネージメント技術として「Clean」と「Playlist」を持っています。Cleanはバラバラになっているファイル名やMetaデータ(ID3タグ)を統合し反映していく技術、Playlistは曲やジャンルなどからプレイリストを生成していく技術で、パラメータを動かすことで、似たような曲のプレイリストを作ることを可能にしたものです。
さらにコンテンツ統合技術として、「Link」、「CDKey」、「DVDKey」というものもあります。Linkは関連のあるニュース、バイオグラフィ、ファンサイトとマッチングさせる技術で、CDKeyやDVDKeyは、CDやDVDから自動的にネットにアクセスし、そのメディアのユーザーであることを認識させる技術です。
藤本:いろいろとあるんですね。このうちMusicIDとは、具体的にはどんな技術なのでしょうか?
小玉:CDDBはCDを元にして曲名などを認識する技術ですが、MusicIDはすでにMP3やWAVなど音楽データとなっているものから曲名などを認識する技術です。
藤本:ソニーのVAIOに搭載された「SonicStage Mastering Studio」で、追加アップグレードが予定されている「MoodLogic」とよく似ていますね。
Palmer:MusicIDはもともとCantametrixを買収したことで得た技術で、これと近い技術を開発した企業は日本メーカーを含めいくつかあるようです。しかし、我々はCDDBとの連携を含め、さまざまな展開を予定しており、他社に対して大きな差別化が図れると確信しています。MusicID用に300万曲のデータベースがすでに用意されており、現在、最終チェックをしている段階で、SDKも配布していす。
藤本:MoodLogicはアナログで録音したデータにも対応しており、曲の波形の特徴を元にキーを作り、これをデータベースと照合させると聞きました。MusicIDも同じような方式なんですか?
Palmer:近い方法だとは思います。MusicIDでは、特徴を抽出したキーが64byteとコンパクトなものになっていますが、これで97%以上の精度で曲を認識しています。
藤本:64byteはすごいですね。MusicID搭載ソフトはいつごろ登場するのでしょうか。
Palmer:年末にはPCのアプリケーションソフトとして登場すると思います。
小玉:ただし日本語への対応はもうしばらくかかるでしょう。なるべく早い時期に対応できるよう準備をしたいと思っています。
藤本:楽しみですね。最後に1つ要望があります。CDDBは非常に便利ですが、日本人の立場で見ると、曲名やアーティスト名が、カタカナで表示されたり、英語で表示されたり、半角だったり全角だったりと統一性がありません。ボランティアで運営されているのであればともかく、企業が運営しているのであれば、せめてこうした状況は改善してもらいたいと思います。
小玉:おっしゃるとおりです。Gracenoteとしてもこの問題はいち早く解決すべきものと認識しており、現在統一にむけての準備を進めています。日本法人を設立した背景にはそうしたこともあるんです。もう、しらばくお待ちください、より使いやすいものにしていきます。
□グレースノート株式会社のホームページ
http://www.gracenote.com/gn_japan/
□関連記事
【5月29日】CDDBのGracenoteが日本法人を設立
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030529/grace.htm
(2003年6月9日)
| = 藤本健 = | ライター兼エディター。某大手出版社に勤務しつつ、MIDI、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆している。以前にはシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わったこともあるため、現在でも、システム周りの知識は深い。最近の著書に「ザ・ベスト・リファレンスブック Cubase SX/SL」(リットーミュージック)、「MASTER OF REASON」(BNN新社)などがある。また、All About JapanのDTM・デジタルレコーディング担当ガイドも勤めている。 |
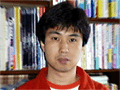 |
[Text by 藤本健]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|