 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
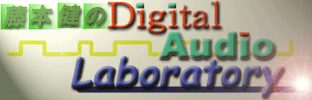
第242回:Skypeとレコーディング機材でPodcast制作にトライ その2
~ 低価格コンデンサマイクを活用し、音質向上 ~
~ 低価格コンデンサマイクを活用し、音質向上 ~
前回に引き続き、Skypeを利用したPodcast番組の制作について、今回は、実際どんな機材を使い、どのようなセッティングで番組のレコーディングをしたのか、またその編集方法などを紹介する。
■ Skypeの実用性を確認
前回もお伝えしたとおり、沖縄系ヒーリングミュージックの音楽ユニット「TINGARA」の実験的なPodcast番組の制作に参加させてもらった。彼らがPodcastの番組、「radio TINGARA」の番組作りをスタートさせた背景などはすでに紹介したが、今年4月5日の開始以来、15~30分程度の番組をすでに40回近く収録しているなど、かなりハイペースで番組作りを進めている。
 |
 |
 |
| 沖縄系ヒーリングミュージックのユニット「TINGARA」 | iTMSの「site TINGARA」紹介ページ | |
基本的にTINGARAのメンバーであるHIDEO氏とTSUGUMI氏の2名のトークと音楽という構成であるが、番組作りの都度、二人で顔を合わせてレコーディングというのではなかなか大変。そこでSkypeを導入したという。
「radio TINGARAをスタートした当初は特にSkypeには興味もなかったんですよ。もちろんSkypeの存在は知っていましたが、NetmeetingとかYahoo!メッセンジャーなどと同様のものだろうと思っていたので、ただのオモチャ、という認識でいました。実際、Netmeetingなどには、いち早く飛びついたのですが、音は悪いし、途切れるし、何よりもマシンに負荷がかかったという記憶があって、未来は感じるけれど、実用には程遠いという感覚を持っていたんです。ところが、自分たちでPodcastをスタートさせて以来、人の作ったPodcast番組をよく聞くようになると、Skypeでやり取りしているという番組をしばしば見つけるようになったのです。で、実際その番組を聴く限り、かなりしっかりしている。それならちょっと試してみようか、ということになったのです」とHIDEO氏は語る。そして試してみた結果、非常に使えるツールであることがわかり、今ではSkypeはHIDEO氏にとって必須のツールとなっている。
■ M-Audio製I/Fと低価格コンデンサマイクを活用
そもそもTINGARAの音楽制作は、これまでも二人が会わないで仕事をすることが多かった。
「常にお互いデータのやりとりはしているけれど、別々に作業をすることのほうが多いんですよね。とはいえ、コミュニケーションをとる必要はあるので、これまでもインターネットはかなり駆使してきました。でも、Skypeに関しては、誤った思い込みがあって、出遅れてしまいました。今は、Podcast番組作りはもちろんですが、普段の仕事用にもかなり便利に使っています。モニタースピーカーとコンデンサマイクをお互いに使っているからでしょうか、電話という感覚ではなく、つながった空間で仕事をしている感じになりますね。音は本当にそこにいるように聞こえるけれど、姿が見えないのでちょっと不思議ではありますが、自分の作業に没頭していると、『これ、どうなってんの?』なんて言われて、あぁ繋がっていたんだなんてビックリすることもありますよ」
HIDEO氏の仕事部屋であるスタジオでのSkypeの環境を見せてもらうと、確かに一般的なSkypeユーザーの環境とはちょっと違う。Skype用のオーディオインターフェイスとしてM-Audioの「FW410」が使われ、そこにMackieの小さいミキサー経由でGENELICのモニタースピーカーに繋がっている。一方、マイクにはべリンガー(BEHRINGER)の「C-1」というコンデンサマイクがやはりMackie経由でFW410に接続されている。
「マイクについては、いろいろと試してみたんです。最初はAKGのコンデンサマイクを立ててみたら、非常によかった。一方でNEUMANNの“U-87”を使うと、Podcastの番組を作るにはちょっと違うなという感覚を持ちました。ただ、Skypeを単にPodcastの番組制作用というのではなく、普段いろいろと活用するため、常にセッティングしておけるマイクが欲しかったんです。さすがにボーカルのレコーディングに使うAKGのマイクを外に出しっぱなしにしておくと、湿気で痛んでしまいそうでもったいない。そんな時、楽器店で5,000円もしないコンデンサマイクとしてBEHRINGERのC-1というものを見つけたんです。この値段なら、壊れてもいいか、と使ってみたところなかなかいい。コンデンサマイクのクセに、感度が悪くて、マイクにかなり寄らないとしっかり音を拾わないという難点はあるものの、Skype用としては十分。マイク用の保管庫にはいれず、外に出しっぱなしにしていますが、今のところ問題なく動いています」とHIDEO氏。
 |
| BEHRINGERのコンデンサマイク、C-1。4~5,000円程度の価格の割には使い勝手は良好 |
一方のTSUGUMI氏のほうにも同じC-1を導入。彼女のほうは、オーディオインターフェイスにM-AudioのPCI接続のオーディオインターフェイス「Delta1010」を使っている。この環境でSkype接続すると、電話とは異次元の音声コミュニケーションがとれるというのだ。
ちょうど、HIDEO氏のスタジオで話をしていたとき、PCの画面上でTSUGUMI氏がオンラインになって、接続。ちょっと驚くぐらいにクリアな音で声が聞こえてくる。GENELICのスピーカーとマイクの間には1m程度の距離はあるが、確実に音を拾いそうな場所にあるのに、ハウリングするようなこともない。確かに同じ空間にいるように錯覚するほどだった。
実はこのC-1というマイク。偶然ではあるが個人的に数カ月前に購入していた。某オンラインショップで4,000円程度で売られているのを見て、購入してしまった。C-1の利用目的は、壊れてもいい感じで使える実験用のコンデンサマイク。さまざまなオーディオインターフェイスをチェックする際、ファンタム電源がしっかり機能しているのか、マイクからの音はきちんと録れるのかなどを確認するための素材として購入し、便利に活用している。
それならこちらもということで、帰宅後、同じくM-Audioオーディオインターフェイスで揃えようと、「ProjectMix I/O」にC-1をつなぎ、Skypeをセッティング。SONYのモニターヘッドフォン「MDR-CD900ST」を使ってHIDEO氏とつないでみた結果、ビックリ。気持ち悪いほどにキレイに相手の声が聞こえてくる。明らかに電話とはまったく違う世界だ。
 |
 |
| M-Audio ProjectMix I/OにC-1を接続 | Skypeの使用するオーディオデバイスにはProjectMix I/Oを設定 |
ちなみに、ネット環境はHIDEO氏がUSENの光、こちらもTEPCOの光ということもあってトラフィックスピードにはまったく問題ない。そこにADSL環境のTSUGUMI氏が三者通話の形で参加。3人とも別々のところにいるのに、同じ場所にいるような感じで会話ができる。
ただ、TSUGUMI氏の音声だけ、微妙に遅れて感じられた。夜中の12時前後のやりとりだったが、反応から見て200~500msecといった感覚。HIDEO氏によれば、夜間などトラフィックが多そうな時間帯でより遅れが顕著になるという。正確な理由は分からないが、やはり回線速度なども含めたトラフィック速度が問題なのだろうか。
■ 収録開始。ルーティングに問題も
Skype上で10分程度打ち合わせをした後に、Podcastの番組収録本番へと入った。この収録自体はHIDEO氏が行なったのだが、そのレコーディングにはCubase SX2が使われており、SkypeとCubase SX2を同じマシン上で同時に起動させている。ただし、音声のルーティングはアナログを介したちょっと原始的な方法。
「本当は3者の音声をバラバラにトラックに入れて、後から音量調整などができるといいんですが、いいツールがなくて、今のところアナログを介在させています。つまり、Skypeの音声出力を一旦FW410の1つのチャンネルから出力して、Mackieのミキサーへ入力。そして、Mackie上に入っているC-1のマイクとアナログ的にミックスさせた上で、再度FW410に戻して、Cubase SX2へと入力します。つまり、3者の音声をあらかじめミキサー上で調整してから1つのトラックへまとめて突っ込んでいるんです」
 |
| レコーディングや編集にはCubase SX2を使用する |
FW410の場合、アナログ入力が2chしかないので、この接続においても余裕はない。もっとも、複数チャンネルの入力があったとしても3者通話のうちSkype先の2名のバランスをとることはできないので、FW410で必要十分な性能を備えているともいえる。一方、アナログを介在させないでこの録音を行なうとしたら、ドライバ上でうまくパッチングできるといいのだが、SkypeがMMEドライバを使っているのに対しCubase SX2はASIOドライバなので、その意味でもなかなか難しそうだ。もしかしたらEGOSYSのオーディオインターフェイスを用いて、E-WDMドライバを活用するとうまくいきそうな気もするが、現状においては、アナログを介すのが最善策なのかもしれない。
そんなわけで打ち合わせ中に行なったのは音量調整。ただ、マイクの利用に不慣れなことと、C-1がコンデンサマイクのくせに、ちょっと離れると非常に音量レベルが落ちてしまうこともあって、音量バランスがイマイチうまくとれなかった。自分の声のレベルが小さくなりがちだったのだ。しかし、今回のシステムの仕組み上、後からの個別の音量調整は不可能。この辺が現状における限界点なのかもしれない。
結局、話し始めるとお互いマニアックな話が止まらず、30分で終わらせるはずが1時間に伸びてしまった。一応、約30分後に休憩というか打ち合わせを挟んだのだが、その打ち合わせでHIDEO氏からもっとマイクに近づいてという指示があったため2回目のほうが若干は音量バランスがよくなったようだ。
■ 無事に収録終了。編集もCubase SX2で行なう
このようにしてCubase SX2に収録したトーク内容を後でHIDEO氏が編集を行なった。ここではジングルを入れたり、BGMを入れたり、拍手などの効果音を入れたりする。そしてもちろん主目的ともいえるJupiterという曲を入れるのも重要な編集作業だ。
「編集作業自体はとっても簡単ですよ。多少各トラックのフェーダー処理をするくらいですね。トーク内容にNG項目があったりしたらそこをなんとかカットするように処理しますが、通常はまるまる入れていますから簡単です。ただし、ジングルもBGMもJASRAC登録してしまった既存の作品は使うことができません。そのため両方ともオリジナルをPodcastのために作りました」と語る。JASRAC登録の問題は、やはりいろいろなところに出てきているわけだ。
そんなこんなで、このSkypeでのトーク番組終了した半日後にはPodcastでの配信がスタート。個人的には自分の声を聞くのも恥ずかしいので、しっかりは聞いていないのだが、興味のある方はSkypeとM-Audio機材で、どの程度の音が作れるのかチェックしてみてほしい。
□TINGARAのホームページ
http://www.tingara.com/
□Radio TINGARA
http://www.TINGARA.com/mt/archives/060_podcast/index.php
□関連記事
【6月26日】【DAL】Skypeとレコーディング機材でPodcast制作にトライ その1
~ 音楽CD低迷時代に実験的活動を試みる「TINGARA」 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060626/dal241.htm
【2005年12月26日】【DAL】M-Audio初のフィジカルコントローラ「ProjectMix I/O」
~ 音質/互換性ともに高く、設定も意外に簡単 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051226/dal218.htm
(2006年6月26日)
| = 藤本健 = | リクルートに15年勤務した後、2004年に有限会社フラクタル・デザインを設立。リクルート在籍時代からMIDI、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆している。以前にはシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わったこともあるため、現在でも、システム周りの知識は深い。 最近の著書に「ザ・ベスト・リファレンスブック Cubase SX/SL 2.X」(リットーミュージック)、「音楽・映像デジタル化Professionalテクニック 」(インプレス)、「サウンド圧縮テクニカルガイド 」(BNN新社)などがある。また、All About JapanのDTM・デジタルレコーディング担当ガイドも勤めている。 |
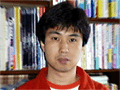 |
[Text by 藤本健]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2006 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.