 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
|
西田宗千佳の ― RandomTracking ― ソフトの熟成で大幅進化
|
今回は、パナソニックの「ブルーレイDIGA」の商品企画者および開発者に、新機種DMR-BW930/830/730について聞いた。これらの機種は、発売から1カ月が経過し、手に入れた読者の方も少なくないのではないのだろうか。
高機能化のポイントやハードウエアの詳細、開発のコンセプトまで、発売後だから話せるより詳細な情報をお伝えしたい。
 |
 |
| DMR-BW930 | DMR-BW930(上)とDMR-BW830(下) |
■ さらに進化した「クロマアップサンプリング」
BDだけでなく放送やDVDも「高画質」に
 |
| (左奥より)ビデオビジネスユニット 商品企画グループ ビデオ商品第一グループ 主事 神高知子氏、商品技術グループ HD/BDソフト設計チーム 主任技師 川崎弘二郎氏(崎は「立」に「奇」)、(右手前より) 商品技術グループ 先行開発チーム 主幹技師 甲野和彦氏、商品技術グループ HD/BDハード設計チーム 主任技師 梅迫実氏 |
BDへと世代が移行してから、DIGAがAVファンに支持されている理由は、なにより画質にある。画質へのこだわりは、もちろん新機種にも引き継がれている。画質向上に関する技術を開発しているのは、AVCネットワークス社・ビデオビジネスユニット・商品技術グループ の甲野和彦主幹技師。数年にわたり、DIGAの画質周りを担当している。
DMR-BW900は、パナソニックハリウッド研究所(PHL)の技術を採り入れたクロマアップサンプリング技術を導入した結果、素直ですっきりとした発色と精細感が評価され、人気となった。
だがそれでも、新機種であるDMR-BW930世代と比べると、まだまだ改善の余地があったことに気づかされる。特に、グレインの多い映画などを見ると、DMR-BW930世代ではさらさらと自然な印象を受けるのに対し、BW900では、見比べるとべたっとした、重い表現に感じる。
変化の理由は、前回同様「クロマ(色)処理」にある。
「DIGAの再生系は、原画を忠実に再生する事を基本思想としています。その観点で、特にBD-ROMでは、輝度信号はしっかりと入っていますから安易に加工すべきではないと考えています。ですが、色信号は必ずアップサンプリングする必要があり、この処理の良し悪しによって色信号の再生帯域が決まります。これはまさに基本性能です。ここに手をかけているメーカーは少ないと思いますが、我々は色信号のアップサンプリングこそが、原画忠実再生の観点で高画質化の決め手であると考えて、商品開発を行なってきました」。甲野氏はそう説明する。
映像フォーマットに詳しくない方のために、「クロマアップサンプリング」の重要性についてここで説明しておこう。
人間は、輝度の変化には敏感であるものの、色の変化には意外と鈍い。そこで、データ量を減らすため、ディスクメディアや放送では、色情報を4画素に1つ分しか記録しない、という形を採っている。これが、俗にいう「4:2:0」という形式である。すべての信号をフルに扱う「4:4:4」に比べると、細かな色変化に関する情報は削減されているわけだ。
一方で、これをディスプレイで表示する際には、全ての画素に色情報をのせる必要があり、そのためビデオプレーヤー/レコーダでは、色情報を補完する処理が必要となる。もっとも一般的なのは、隣り合う2つの色信号からシンプルに線形補完する「2タップ」という方式である。パナソニックの初代BDレコーダ「DMR-BW200」で使われていたのも、この2タップ方式である。
だが、それではまだ不自然さが残る。そこで登場したのが、PHLのノウハウを生かした「マルチタップ・クロマアップサンプリング」技術である。DMR-BW900世代で導入されたことにより、「色が生み出す解像度」が生まれ、画質ははっきりと向上した。
だが、DMR-BW900世代のマルチタップ・クロマアップサンプリングにも、まだ改良点が存在した。「BW900では垂直方向のマルチタップ処理を行なっていたのですが、BW930(世代)では、この精度を更に向上させると共に、水平方向でも同様の処理を行なっています」と甲野氏は説明する。このように進化した色信号処理を、パナソニックでは「新リアル・クロマ・プロセッサ」と呼んでいる。前出のような、BW900からBW930への画質進化は、この「新リアル・クロマ・プロセッサ」に負うところが多い。
この進化は、テストパターンでみるとはっきりわかる。DMR-BW200、BW900、BW930の3機種で、赤と青の色信号を同心円状に配置した映像を表示していただいたが、その差ははっきりと出ていた。2タップであったBW200では、線の間隔が短くなってくると、正しい色再現ができず灰色がかって見えるが、BW900ではそれが大きく緩和される。BW930の場合には、さらに改善され、リングがかなり正確に描写されるようになっている。
BW900世代に比べ、もうひとつ大きな改良が行なわれている点は、クロマアップサンプリングに関する改良が、BW930から表示される様々な映像に働くという点である。
「BW900の時には、マルチタップクロマアップサンプリングはBD-ROMの映像タイトルを再生する時にしか働きませんでしたが、今回の新機種は違います。DVDビデオやデジタル放送でも同様の効果が得られ、画質が向上しました」と甲野氏は話す。
DVDでは元々の解像度が低いため、クロマアップサンプリングの効果はBDとは異なる。しかしそれでも、前機種と新機種の違いは大きい。DVDからのアップコンバートのロジックも改良されており、クロマ処理とアップコンバート処理両方の改善効果で、DVDの表示画質はさらに高くなっている。DVDの高画質アップコンバートではPS3も評判がいいが、BW930世代のアップコンバート性能は、PS3と比較しても負けていない。特に色表現の緻密さでは、確実にBW930世代が上を行っている。甲野氏も、「全体のコントラスト感があがり、精細度が増しているはず」と話す。
またDVDの再生という点では、もう一つ面白い機能が追加されている。
BDタイトルではおなじみとなった24p再生が、DVDビデオディスクの再生で可能となったのである。同様の機能は、東芝のHD DVDプレーヤーやDVDレコーダにも搭載されており、新しい機能とはいえないが、DVDに収録されたタイトルも、24p再生を行なうことで、より映画的なイメージで楽しめる。ただし、DVDビデオの規格内では24pでの収録が保証されておらず、100%破綻なく再生できる、というわけではないため、甲野氏も「特性をご理解いただいた上でお楽しみいただきたい」と話す。
個人的には、ぜひ「テレビドラマ」を24p再生で見てもらいたい。昔はフィルム撮影であり、現在はビデオ撮影に変わっている長寿番組の場合、「今のものはなんとなく軽い」と感じることが多い。そんな番組を24pで見ると、妙な懐かしさを感じる映像に変わるのだ。今の水戸黄門が昭和の時代に逆戻り、というと言い過ぎだが、ちょっと面白い感覚を楽しめる。
■ AVCのアルゴリズムはゼロから見直し
「解像感とS/Nを両立する」調整を目指す
| 録画モード | コーデック | ビットレート |
|---|---|---|
| DR | MPEG-2 | ストリーム記録 |
| HG | AVC | 12.9Mbps |
| HX | 8.6Mbps | |
| HE | 5.7Mbps | |
| HL | 4.3Mbps |
画質という点では、AVCエンコードに関する変更も見逃せないところだ。新たに長時間録画用の「HLモード」を追加したほか、BW930世代では、AVCエンコードの画質も向上している。特に、低ビットレート設定での画質向上を目指した改良が行なわれているという。
「アルゴリズムをゼロから見直し、解像度感や精細感を更に向上しながら、同時に符合化ノイズも低減する事を狙いました。その結果、低いビットレートでも精細感やコントラストを保ちながら、かつノイズもかなり減らすことができたと思います」。甲野氏はそう説明する。
従来のアルゴリズムでは、ハイビジョンの精細感を保つ事を第一に、各設定で符号化パラメータを決め打ちにしていた結果、「ビットレートが低い際、ノイジーになる場合もあった」(甲野氏)という。今回は、映像の動きに応じてAVCの符号化パラメータを制御することで、精細感とSN比を両立した形で、全般的な高画質化を実現した。BW930世代では、4.3Mbpsという狭い帯域でも、フルHDでかなりクオリティの高い映像を再現することに成功している。低ビットレートの大敵ともいえるサッカーの映像でも、きちんと「見られる」映像になっているから驚きだ。
「もちろん、低レートのモードではDRモードに比べ画質が低下することは避けられません。しかし、従来と比べると、例えばサッカーなら、芝生のディテールをぼかすことなく、肝心なプレーヤーやボールにまとわりつくノイズをかなり低減できたと思います」と甲野氏は説明する。
更にDIGAには、「平均ビットレートをできる限り安定させる」という思想がある。今回の新アルゴリズムのようにAVCの符号化パラメータを最大限に生かせば、動きが大きく、ビットレートを大きく割り当てないと厳しい映像でも、帯域を必要以上に大きく割り当てなくて済む。VBRでは、シーンによってビットレートが変化するが、製品によっては、設定ビットレートから大幅にビットレートが上がる時間が長くなり、最終的な録画容量が大きくなってしまう場合がある。
「録画時間を守るためには、平均ビットレートはできる限り目標値に収める必要があります。特にDIGAの場合、HDDだけでなく、BDやDVDディスクにも直接AVC録画が可能ですので、なおさらです」と甲野氏は話す。
■ コンセプトは「AVアンプを選ばない高音質化」
LSIに手を入れてジッタを大幅削減
新機種では、映像だけでなく、音声の面でも大きな改良が加えられている。特に、最上位機種であるBW930は、「これまで以上に、音にこだわった機器になるよう」コストがかけられている。
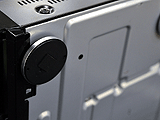 |
| 底部のインシュレータはDMR-BW930のみの特徴 |
音質面での技術開発を担当する、商品技術グループ・HD/BDハード設計チーム 主任技師の梅迫実氏は、「BW900は、BW800とほとんど差がない、と言われて納得できなかった。そこでBW930は、音質面ではっきりと上になるよう差別化しました」と話す。
BW900は、BW800とほぼ同じボディを使っていた。そのため、音質的な差を生み出すのが難しい面もあった。BW930でも、「同じ箱」を使うという点は変わらない。だが、少しでも音が良くなるよう、BW930だけは底面にインシュレーターが装備されている。その形状はもちろん、インシュレータの底にあるダンパーの材質や形状に至るまで、「製品化直前まで試行錯誤して、日程ギリギリまでがんばって何度も手を加えた」と梅迫氏は話す。むろん、低ノイズ・低インピーダンスを目指し、各種コンデンサやレギュレータIC、端子類などに特別なスペックのものを搭載、信号面でもハイクオリティを目指した。
こういった点を勘案すると、ホームシアターを指向するユーザーならば、やはりBW830/730よりもBW930の方がより満足できる画質・音質を得られるのは間違いなさそうだ。
だが、その高音質化も、BW730/830との共通設計部の高音質化あってのものである。今回の高音質化は、おもに3つのパートから構成されている。
ひとつめは、TrueHDやDTS-HD Master Audioといったロスレス・コーデックのフルデコード対応。つまり、リニアPCMに変換して、HDMI出力が可能となったのだ。
従来はビットストリーム伝送のみだったため、ロスレス未対応のアンプでは、コアストリームのみの再生となっていた。フルデコードに対応した理由は、「AVアンプ側を選ばすに高音質化するため」と梅迫氏は話す。フルデコードに対応したため、ボディ上部には、それを示すロゴがつけられるようになった。もちろんロスレスのフルデコードも、UniPhierですべて処理している。
ただし、BDのインタラクティブ機能を使っている場合など、一部の状況では、ビットストリーム伝送になるという制限が残っている。
 |
 |
| BW930の背面。端子が金メッキになっているのは、この機種のみ。BW900と違い、ファン部が内蔵され、出っ張りがなくなった | BW930の天板には、「DTS-HD MasterAudio Essential」のロゴが。これは、ロスレスのフルデコードに対応する機器につけられるものである |
二つ目は、「新マルチチャンネル デジタル リ.マスター」の採用だ。DIGAでは、BW200世代以降、圧縮時に切り捨てられた高音域を補間し、より自然な音として再生する「マルチチャンネル デジタル リ.マスター」を搭載していた。BW930世代では、周波数帯域を2倍の40KHz超に拡大、ドルビー・デジタルやDTSの音声だけでなくリニアPCMでもより高音質になっている。このあたりも、ロスレスのフルデコードと同じく、「AVアンプを選ばずに高音質化する」ための工夫といえる。
そして最後が、HDMI伝送LSIの最適化によるジッタ(揺れ)の改善だ。HDMIの高音質化に、ジッタ低減が効く、というのはよく知られているが、その手法はメーカーによって異なる。BW900では、伝送パラメータを最適化し、AVアンプ側でのジッタを低減したが、今回のDIGAでは、HDMIの伝送LSIの内部にあるPLL(位相同期回路)に手を入れ、本体から信号が「出て行く」段階で、出来る限りジッタを減らす、という手法を取り入れている。
「パナソニックでは、HDMIの伝送LSIを自社で開発しています。ですから、半導体部門に情報をフィードバックし、共同でLSI内部回路のジッタを低減しました。他社の場合には、HDMI伝送LSIの前までは改善できますが、内部までできるのは我々だけでしょう」。梅迫氏はそう胸を張る。
調整結果は、計測結果にも現れている。図は、パナソニックより提供された、BW930とBW900のHDMI信号における、クロックのジッタとデータのジッタの状況を可視化したものである。クロックジッタはざっくりと半分になっているのがすぐにわかるが、データジッタは少し説明が必要だろう。
このデータでは、同じ箇所に信号が多く重なるほど、赤→橙→黄→白と色が変わるようになっている。データジッタの図版にて、斜め線がクロスしている部分に注目していただきたい。BW900では赤色になっている面積が多いのに対し、BW930は、橙になっている面積が増えている。これは、データが同じ周期で同じ箇所に重なるようになっていることを示す。すなわち、時間軸上のでデータの変動が少なく、ジッタが少ない、ということである。
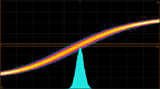 |
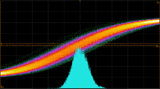 |
| BW930のクロックジッタ | BW900のクロックジッタ |
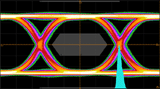 |
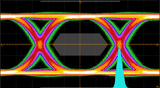 |
| BW930のデータジッタ | BW900のデータジッタ |
| DMR-BW930とBW900のジッタの違い。特に、音質に大きな影響を与えると言われているクロックジッタが大きく減っている点に注目(データ提供:パナソニック) | |
■オートチャプターは「2チューナ同時」実現で初めて導入へ
BW930世代は、「機能」面での改善が大きいのも特徴だ。中でも大きいのは、いわゆる「オートチャプター」機能の導入だ。
DIGAの商品企画を担当する、ビデオ商品第一チーム主事の神高知子氏は、導入の経緯を次のように語る。
「オートチャプターを、というご要望はずいぶんいただいていました。ですが、DIGAのコンセプトは“わかりやすさ”。難しいことを考えず、意識せず使えるようにならないと、成立しないと考えていました。今回は、“録画1・2”といった制限を気にせずとも使えるものができあがったので、搭載することになりました」
神高氏の語る通り、BW930世代のオートチャプターと、他機種のオートチャプターの最大の違いは、「どのチューナで録画しているか」を気にすることなく、すべてのチューナでオートチャプターが設定される、という点である。技術開発を担当した、ネットワーク事業グループ・HD/BDソフト設計グループ 主任技師の川崎弘二郎氏は、その秘密を説明する。
「チャプタの判定は、音圧レベルの変化やシーン変化を元に行なっています。デコーダ/エンコーダがすべてのチューナ分内蔵されていれば、判定は簡単な話です。しかし、UniPhierといえどそこまでの処理は負担が重い。そこで、映像を完全にデコードしてしまわずとも判定できるアルゴリズムを作り、対応しました。もちろん後発ですから、精度で劣るわけにもいきません。完全にデコードせずに判定する方法でも、他社に負けない精度を実現するものを導入しています」
このあたりの事情については、少し補足説明が必要だろう。
一般的にオートチャプタの機能は、MPEG-2で伝送されてくる映像をデコードし、再びAVCやMPEG-2でエンコードする過程で得られる情報を使って行なわれる。再エンコードを行わず記録する場合も、映像解析のためにこのパスを通ることになる。エンコーダやデコーダを「独立したLSI」で実装している機種の場合、これらのLSIを複数搭載しない限り、2つのチューナから来る映像に、同時にチャプタをつけることは難しい。もう一方のチューナからの録画が、ストリームを直接記録する「DRモード」になるのもこのためだ。
BW930世代のDIGAの場合には、すべての処理を、中核LSIであるUniPhierひとつで行ない、しかも、オートチャプターに関しては「完全にデコードしない」状態で行なうため、複数の録画ストリームが存在しても、それぞれで扱いを変えることなく動作できる。ユーザー側から見れば、それは「操作制限の少なさ」となり、わかりやすさとなって反映される。
■ ユーザーインターフェイス刷新は「コンテンツ増加」への対策
次に望まれるのは「操作感」の向上
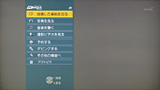 |
| 新たに搭載したスタートメニュー |
わかりやすさの追求、という点は他にもある。今回より、DIGAのユーザーインターフェイスは大幅な刷新が行なわれた。各機能を呼びだす「スタートメニュー」を搭載した他、番組をEPGで指定された「ジャンル」情報を元に自動分類、タブに似たインターフェイスで表示するようになった。
こういった変更は、主に「ハードディスク内のコンテンツの増加に伴うもので、録画する量が増えると、従来のままではわかりづらくなります。また、カムコーダの映像などを取り込んだ場合も同様です。それらを自動的に整理してくれるインターフェイスが必要と考えたためのもの」(神高氏)だという。
特にカムコーダ連携については、需要がどんどんと高まっている。旧機種ではSDカード経由でのみの連携だったが、今回よりUSBでの接続も可能となっている。この点については、特にユーザーからの要望が多かったようだ。
他方、要望を先回りする形で実装したのが、アクトビラ・フルの映像配信への対応だ。
「レコーダは買い換えても、テレビはなかなか買い換えていただけませんよね。とすれば、レコーダでの対応をするのが、ユーザーの皆さんにはやさしいと考えました。DIGAを買って、LANにつなげばすぐ見られますし。それに、ダウンロード形式での配信ならば、回線が細くとも、待っていれば見られますしね」と神高氏は話す。
サービスは12月からスタートの予定で、詳細はまだ未定だ。アクトビラといえばテレビ、という印象が強かったが、むしろレコーダの方が現実的なサービス、ということもいえるのかもしれない。
 |
| DMR-BW930のリモコン |
ここまで説明してきたように、BW930世代では、旧世代に比べ様々な機能が向上している。だが、UniPhierを中心としたLSI関連については、「旧機種と大きくは変わっていない」(川崎氏)という。すなわち、画質向上もオートチャプターも、ソフトウエアの改善・熟成によって実現しているのである。甲野氏も、「UniPhierは、ソフトウエアで内部のアルゴリズムや処理を柔軟に変える事ができます。同じ世代のLSIを長く使う事によってこれだけの熟成ができたとも言えます」と話す。BW900世代では、時間などの制約で実現できなかったことが、BW930世代で実現できた、と考えればいいだろうか。
ソフトの熟成で機能追加、という考え方は、デジタル家電の物作りとして、非常に重要な考え方である。とはいうものの、「操作性」という点では、諸手を挙げて賞賛できると言いづらいのも事実である。動作速度や反応速度、さらにはリモコンの使い勝手といった部分については、まだまだ改善の余地がある。
神高氏はこの点について、「ご要望は理解しており、今後の検討課題」と語る。次機種では、画質・音質と同レベルで、「気持ちいい使い勝手」を目指して欲しいところだ。
□松下電器産業のホームページ
http://panasonic.co.jp/index3.html
□DIGAのホームページ
http://diga.jp/
□製品情報
http://panasonic.jp/diga/products/bw/index.html
□関連記事
【9月17日】【EZ】突然ITに目覚めたPanasonic DIGA
~ 音質にもこだわったフラッグシップ機 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080917/zooma377.htm
【8月25日】松下、2層BDに24時間録画可能な新「ブルーレイDIGA」
-6倍速BD-R、5.5倍録画、データ放送カット、DLNAなど
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080825/pana1.htm
【2007年11月16日】【RT】開発陣が語る「新DIGA」の能力
- 「新Uniphier」で「PHLチューニング」が生きる
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071116/rt047.htm
(2008年10月9日)
| = 西田宗千佳 = | 1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に、取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、読売新聞、月刊宝島、週刊朝日、週刊東洋経済、PCfan(毎日コミュニケーションズ)、家電情報サイト「教えて!家電」(ALBELT社)などに寄稿する他、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。 |
[Reported by 西田宗千佳]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.