 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |

AV機器初の「ドルビーバーチャルスピーカー」搭載DVDシステム
デノン
「ADV-M71」
発売日:7月上旬 標準価格:77,000円
 | ||
| AV機器初の「ドルビーバーチャルスピーカー」搭載DVDシステム | ||
| ||
| 発売日:7月上旬 標準価格:77,000円 | ||
■ DVD対応ミニコンポ界の異端児
 |
| ADV-M71 |
ADV-M71のユニークな点は、バーチャルサラウンド機能として「ドルビーバーチャルスピーカー(DVS)」を採用したこと。DVSはすでにPC用DVDプレーヤーで採用済みなので、試した人も多いだろう。DVSについての詳細は、ADV-M71の発表記事を参照してほしい。単純なクロストークキャンセル処理だけでなく、膨大な直接音、間接音をシミュレートすることで、5.1ch時の頭内伝達関数を2chで再現する技術だ。
ADV-M71の場合、同社のAVアンプに搭載されている32bit DSP「Hammer Head SHARC」の力でDVSを実現している。こうしたハイエンド機器向けのデバイスが、ミニコンポスタイルの機器に搭載される例は少ない。DVSの演算の複雑さがうかがえる。
今回は、同時に発表された3ウェイ3スピーカー「SC-M31LTD」(16,000円/ペア)を組み合わせ、DVSによるサラウンドの再現性を確認してみた。また、同じく同時発表のサブウーファ「DSW-3.1」(22,000円)、サラウンドスピーカーとセンタースピーカーのセット「SYS-3.1」(1万円)も試用し、リアルスピーカーによる5.1chサラウンドも試聴した。DSW-3.1は、ADV-M71からのセンター、サラウンド、サブウーファチャンネルの各信号をアナログで入力でき、SYS-3.1の各スピーカーに出力することができる。
 |
 |
 |
| SC-M31LTD(ペア16,000円)。ウーファはグラファイト製の140mmコーン型。一番上のユニットはスーパーツイータ | アクティブサブウーファのDSW-3.1(22,000円)。SYS-3.1などをつなぐためのスピーカー出力を装備する | SYS-3.1(1万円)。サラウンドスピーカー×2(上段)、センタースピーカー(下段)のセット |
■ DVS以外の機能は一般的
前面パネルには、トレイ、表示窓、ボリュームノブ、ファンクション切替ノブなどを装備。ボタンが金属で、ボリュームノブやファンクション切替ノブが重かったりと、オーディオ機器的な満足度は高い。77,000円と高価だが、オーディオメーカーの製品だけに、細かいところへのこだわりが感じられる。
再生可能なディスクは、DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD、CD-R/RW。CD-R/RWに記録したMP3やWMA、JPEGも再生できる。ただし、MP3のIDタグ表示には対応していない。JPEGは自動的にスライドショーを始めるタイプ。表示は比較的高速で、1,600×1,200ドット以上の大き目の画像でも実用的だと感じた。
サラウンドフォーマットは、ドルビーデジタル、DTS、AAC、ドルビープロロジック、ドルビープロロジック II(PL II)に対応。PL IIは「シアター」と「ミュージック」を選択できる。最近のサラウンドシステムとしては一般的なスペックといえる。
 |
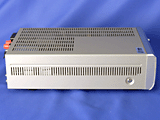 |
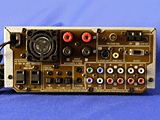 |
| 正面 | 側面 | 背面 |
映像出力はD2端子を装備し、プログレッシブ出力にも対応。プログレッシブ化モードとして、「オート 」、「フィルム」、「ビデオ」を選択できる。画質について細かい不満はない。ガンマは明るめで、比較的すっきりした印象。色のりも悪くなく、ノイズも抑え込まれている。
音声入力は光デジタル×2、アナログ2ch×2を搭載。音声出力は光デジタル×1、アナログ2ch×2のほかに、センター、サラウンドL、サラウンドR、サブウーファのプリアウトを備えている。これにより、リアルスピーカーを使った5.1chへも発展が可能。
もちろん、SC-M31LTD以外のスピーカーやサブウーファを組み合わせてもかまわない。すでに好みの2chスピーカーを所有する人は、それを使ってDVSから始めるのも手だ。古いスピーカーシリーズだと、センタースピーカーやサラウンドスピーカーが用意されていないので、なかなかサラウンド構築に踏み出せないケースが多いと聞く。
2ch以外の3.1chを外部にゆだねるというアイデアは、「とりあえず2chでバーチャルサラウンドを試し、ゆくゆくはリアルスピーカーで5.1ch」という、サラウンド初心者の取り込みを狙ったものだ。ミニコンポスタイルの筐体や高品位なデザインといい、市場の拡大を願うデノンの積極的な姿勢がうかがえる。
|
||||||||||||||||||
|
■ ちゃんと後方から音がするDVS
 |
|||
| DVS動作時の画面表示。リモコンの方向キーでほかのサラウンドプログラムに設定可能 | |||
| (c)CREATIVECAST Professional | |||
まずはADV-M71とSC-M31LTDの組み合わせで、5.1chのDVDビデオでDVSを試してみた。DVSは「標準」と「ワイド」を選択可能で、標準ではほとんどストレートデコードと音質の差は感じられない。それでいて、サラウンド感はしっかりしている。「グラディエーター」でのコロシアムの歓声など、包囲感はリアルスピーカーと同じ印象。また「キャストアウェイ」の環境音も自然。特に、斜め後方の音が濃密だ。ただし、真横の音が少し引っ込む印象も受ける。センターの定位感もあるにはあるが、リアルスピーカーのビシッとした定位にはかなわないようだ。
また、効果音の移動感もそれなりにある。前方から後方へ抜ける音も、移動を確認できる程度には再現している。ただし、リアルスピーカーに比べると若干移動感が粗雑な印象。「スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス」のポッドレースや、「グラディエーター」の矢が後方に放たれるシーンでは、多少の物足りなさを感じた。
なかでも、サラウンドチャンネル間の移動音はほとんど判別できない。「U-571」では、敵の魚雷が潜水艦の舷側をこすりながら遠ざかるシーンがあり、魚雷の音がサラウンドチャンネルの左から右にかけて移動する。DVSでは後方で音が鳴っているのがわかる程度で、音の移動を再現するまでには至っていない。
とはいえ、従来のバーチャルサラウンドに比べると後方の定位は格段に優秀だ。また、中域が大きく荒れたり、極端に帯域が狭くなることもない。ただし、「ワイド」にすると、とたんに中域がつまった音になるのが残念。ただ、標準でも十分なサラウンド感が得られるので、さほど問題にはならないだろう。
なお、オリジナル音場プログラムとして「5ch Stereo」、「Mono Movie」、「Rock Arena」、「Jazz Club」、「Video game」、「Matrix」が用意されている。これらも5.1ch、2chに関わらず適用可能。ディレイ値などを変更・記憶できるので、好みのエフェクトに仕立て上げることも可能だ。
推奨スピーカーのSC-M31LTDは、スーパーツイータを含む3ウェイ3スピーカー。ラピシアシリーズの1つ、「SC-M31」の改良版で、クロスオーバーネットワークを変更し、スイートスポットも拡大したという。250円/mのスピーカーケーブル「AK-1000」が付属している。
 |
 |
 |
| 各スピーカーの背面。SC-M31LTD(左)はバナナプラグ対応のネジ式ターミナルを採用。DSW-3.1(中央)とSYS-3.1(右)はバネ式なので、太目のケーブルは使用できない | ||
ADV-M71、SC-M31LTDの組み合わせでは、ハリがあって元気な音。ダイナミックレンジや解像力もそれなりに感じられ、ペア16,000円という価格以上に立派な音に感じた。
ADV-M71のライン入力に正弦波のスイープ信号を入力すると、50Hzからかすかに聴こえ始め、130Hzあたりで一定音量に落ち着く。13kHzまではほぼフラットで、150Hzあたりで聴こえなくなった。
次に、サブウーファのDSW-3.1と、センターおよびサラウンドスピーカーのSYS-3.1を接続してみた。リアルスピーカーを使った5.1ch再生とあって、さすがに後方のサラウンド感は申し分ない。しかし、SYS-3.1のセンタースピーカーが力不足なのか、センターチャンネルが弱々しくなり、音もこもる。リアルスピーカーよりDVSの方が良い結果になったとは、皮肉な結果といえる。
DSW-3.1を加えると、45Hzからかすかに音が聴こえ始め、実用域は80Hzあたりから(クロスオーバー設定は120Hz、STEREOモード)に拡張される。22,000円のコンパクトなサブウーファだと考えると、コストパフォーマンスはそれなりに高い。
なお、ADV-M71はドルビーヘッドフォン機能も搭載している。これもPC用DVDプレーヤーソフトでおなじみの装備だ。大きな音が出せない状態でもサラウンドを楽しめるため、利用価値は高い。
■ リモコンは蓄光ボタンを採用
リモコンのボタンは、家電メーカーの製品ではあまり見かけないさらっとした質感。ボタンのレイアウトにも大きな不満はない。主要ボタンが蓄光するのもポイント。大きさの割には軽く、主要操作の使い勝手は良かった。ただし、ディスク取り出しボタンを装備しないのが残念。
DVDビデオ再生時には、字幕を表示したままコマ送り、スロー送り、早送りが可能。リモコンの操作性もあわせ、トリックプレイは得意な方だ。ただし、音声付きの早送り/早戻しは不可能。音楽CDでは可能だが、デジタル機器なのにピッチが高くなる(2倍速時)。
 |
 |
 |
| 前面の操作部 | トレイ | リモコン |
DVDディスクのリジューム再生も可能だが、トレイから取り出しても再生位置を記憶する「ディスクリジューム」には非対応。最近は搭載機種が多いだけに残念だ。さらに、音楽CDはリジューム再生すら不可能。一度停止してしまうと、必ずトラック1からの再生になる。
また、ディスプレイタイプとして「NTSC」、「PAL」、「マルチ」を選択できるなど、世界出荷モデルらしい機能も目に付く。
なお、ディスク再生中の動作音はほとんどない。たまに、ディスク停止時にキュルキュルという音が持続する場合があったが、視聴中、騒音と呼べるものはほとんど感じられなかった。
■ メニュー画面例
ほぼすべての機能はOSDから設定が可能。OSDの壁紙には「青色」、「灰色」、「黒色」を選択できるほか、再生中の画像が透けて見える「ピクチャー」も指定できる。また、再生中、初期設定メニュー(SETUP)に入ると再生が一時停止し、初期設定メニューを抜けると再生を再開するという仕様となっている。
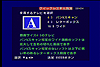 |
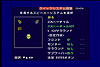 |
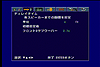 |
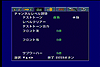 |
| クイック設定(テレビの選択) | クイック設定(スピーカーの選択) | ディレイタイム | チャンネルレベル設定 |
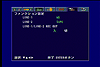 |
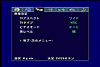 |
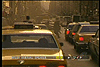 |
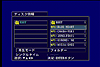 |
| ファンクション設定 | 映像設定 | サラウンドプログラムの選択 | ディスク情報(MP3) |
 |
 |
||
| 画面表示(DVDビデオ) | 画質モード | ||
| (c)CREATIVECAST Professional | |||
■ まとめ
完全にリアルスピーカーと同じ臨場感とはいえないものの、DVSの実力は予想以上に高い。個人的にバーチャルサラウンドといえば、「ちゃんとサラウンドで聴こえるまで、ある程度慣れが必要」という思い込みがあったが、DVSではいきなり後方から音が聴こえて驚いた。とりわけ、教会内や雨のシーンといった環境音の再現性が優れており、場合によっては、設定のうまくいっていないリアルスピーカーより有利かもしれない。
とにかく、リアスピーカーを使わない手軽なサラウンド再生を実現したいなら、現在最右翼の製品といって良い。すでにリビングにサラウンドを構築している人が、プライベートルームで利用するのも良いだろう。デノンの目論見通り、サラウンド人口の増加に寄与できるのか、今後が楽しみな製品だ。
| 再生可能ディスク | DVDビデオ、ビデオCD、音楽CD、CD-R/RW(WMA、MP3、JPEG可) |
| アンプ出力(8Ω) | 35W×2ch(実用最大)、20W×2ch(定格) |
| SN比 | 98dB(2chダイレクトモード時) |
| 再生周波数特性 | 10Hz~50kHz(+0/-3dB、2chダイレクトモード時) |
| 適合インピーダンス | 6~16Ω |
| 映像出力 | D2、S2、コンポジット各1 |
| 音声入力 | 光デジタル入力×2、アナログ入力×2 |
| 音声出力 | 光デジタル入力×1、アナログ入力×2、プリアウト×4(センター、サブウーファ、サラウンド×2 |
| 消費電力 | 65W(待機時0.6W) |
| 外形寸法 | 210×369×95mm(幅×奥行き×高さ) |
| 重量 | 3.5kg |
| 形式 | 3ウェイ3スピーカーバスレフ型 |
| 使用ユニット | 140mmコーン形ウーファ×1、25mmソフトドーム形ツイータ×1、19mmドーム形スーパーツイータ×1 |
| 最大許容入力 | 60W(EIAJ)、120W(PEAK) |
| 再生周波数帯域 | 45Hz~80kHz |
| インピーダンス | 6Ω |
| 平均出力音圧レベル | 89dB(1W/1m) |
| 外形寸法 | 170×217×281mm(幅×奥行き×高さ) |
| 重量 | 3.6kg(1台) |
| 実用最大出力 | 30W×3(8Ω、EIAJ)、60W×1ch(PEAK) |
| 形式 | 1スピーカーバスレフ型、アンプ内蔵 |
| 使用ユニット | 160mmコーン型×1 |
| 再生周波数帯域 | 30~200Hz |
| 音声入力 | アナログ×4 |
| 外形寸法 | 210×380×314mm(幅×奥行き×高さ) |
| 重量 | 10.2kg |
| 形式 | フルレンジ1スピーカー密閉型 |
| 使用ユニット | 80mmコーン型×2(センター)、同×1(サラウンド) |
| 最大許容入力 | 40W(EIAJ)、80W(PEAK) |
| 再生周波数帯域 | 120Hz~20kHz |
| インピーダンス | 8Ω |
| 平均出力音圧レベル | 89dB(センター・1W/1m)、87dB(サラウンド・1W/1m) |
| 外形寸法 | 210×115×95mm(センター、幅×奥行き×高さ)、95×115×95mm(サラウンド、同) |
| 重量 | 1.4kg(センター)、0.7kg(サラウンド、1台) |
□デノンのホームページ
http://denon.jp/
□ニュースリリース
http://denon.jp/company/release/advm71.html
□ドルビーラボラトリーズのホームページ
http://www.dolby.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.dolby.co.jp/AV/topics/DenonPress.html
□関連記事
【6月12日】デノン、民生機初の「ドルビーバーチャルスピーカー」採用
-Hammer Head SHARCを搭載したDVDシステム
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030612/denon.htm
【5月7日】デノン、アルミパネル採用のミニコンポ「ラピシアM31」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030507/denon.htm
【2002年10月16日】【WPC EXPO 2002レポート Dolby編】
ドルビーラボ、「ドルビーバーチャルスピーカー」を発表
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20021016/wpc04.htm
(2003年7月24日)
[AV Watch編集部/orimoto@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.