 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |
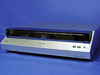
|
第164回:現実味を帯びてきたBDレコーダ「DMR-E700BD」
|
■ ようやく登場した第2の選択肢
家電業界では、昨年から徐々にオリンピックに向けていろいろなAV商品を投入すべく準備を進めてきたが、ここに来てフォーカスの中心を大画面テレビからレコーダに切り替えて来ているようだ。事情はいろいろ考えられるが、買う側に取ってみれば、まだ値段が高く、今後低価格化が進むと言われている大画面テレビよりも、価格低下が著しいレコーダから先に、というのが本音だろう。さらに今度のアテネオリンピックは、生放送の時間帯が夜中になるため、いくらHD放送でもリアルタイムではそうそう見られない、ということも、この傾向に拍車をかけているのかもしれない。
だが既にHD対応テレビを持っている人にとっては、ニセHD放送が横行している地上デジタルでもホンモノのHD放送を、と期待していることだろう。HD放送が録画できるレコーダの選択肢としてはD-VHSがあるが、現状のSDレコーダが一斉にディスクメディアに移行しつつある今、その選択には辛いものがある。
ディスクメディアでHD記録と言えば、もちろんアイ・オー・データのRec-POT……いやもう引っ張るのもこれぐらいにしよう、ソニーのBDレコーダ「BDZ-S77」が既に昨年4月に発売されている。だが、そのあとがなかなか続かない。ショーやイベントでは各社とも試作モデルを展示するものの、実際の製品化はいつなのか、長い間水面下で腹の探り合いといった感じであった。
そしてついに、「アテネに間に合いました」をキャッチフレーズ(?)に、松下電器のBDレコーダ「DMR-E700BD」(以下E700)が今月末に発売される。新規格が製品化されて、2台目のマシンが出るまで異例の1年3カ月。様々な規格の策定タイミングを見計らいながら、製品投入のタイミングはやはりオリンピックであったわけだ。
期待のBDレコーダを、さっそくチェックしてみよう。
■ ガタイはデカいがシンプルな外観
まず外観から見てみよう。「BDZ-S77」のときもそのデカさにまいったものだったが、E700BDはそれより小さくなったとはいえ、最近のハイブリッドレコーダのイメージと比べれば、まだまだデカい。430×406×120mm(幅×奥行き×高さ)、重量約9.1kgである。
フロントパネルは非常にシンプルで、斜めに切り落とされたような厚みのあるアルミ板から、黒いハーフミラーのブロックがせり出しており、ボタン類といえば、電源、ストップ、プレイ、イジェクトの4つしかない。下部のパネルを開けると、横一列にならんだコントロール系のボタンと外部入力コネクタ、B-CASカードスロットが現われる。
 |
 |
| 斜めに切り落とされたようなフロントパネル | 下部のパネルを開けると、B-CASカードスロットやボタン類が現われる |
 |
 |
| 左側には電源ボタンのみ。その下は赤外線受光部 | 右側にはボタンが3つだけと、非常にシンプル |
起動は結構遅く、電源を入れてから映像出力がモニターに出るまで、30秒弱かかる。ステータスディスプレイ表示はかなり大きめで、広い部屋で使うもの、といった前提を自ずから発しているようだ。ディスクをイジェクトすると、ディスプレイを覆っているアクリルパネルが下に沈み込み、トレイが出てくるといった演出が施されている。録画用メディアとしては、BDの1層/2層、DVD-RAM、DVD-Rが使用できる。パッケージメディアの再生はDVDビデオと音楽CDに対応する。
 |
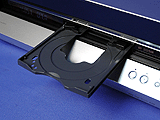 |
| ステータスディスプレイは、かなり文字が大きい | ドライブのトレイは、ケースありなし共用タイプ |
BDのディスクは、初期の頃は全面ケースに覆われたタイプしかなかったが、松下主導で上面が大きく開いたトレイタイプのものも現われた。本機ではどちらのディスクも使うことができる。
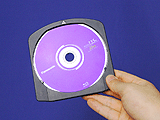 |
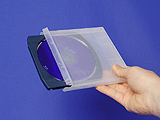 |
| 松下が提唱する、上面が大きく開いたトレイタイプのBDメディア | フタ付きの密閉ケースで、長期保存にも問題なさそうだ |
中味が簡単に取り外せるわけではないが、確かにトレイタイプのほうがほぼ天板の部材分まるまるいらないので、メディアコストは下げられそうな感じがする。またディスクのケースは、挿入口にフタまで付いて完全に密閉できるようになっているため、上が開いているからといってホコリに弱いということもなさそうだ。
 |
| 大型ファン2基が目に付く |
背面に回ってみよう。まず目に付くのが、大型のファン2基だ。消費電力約60Wの電源ユニットもさることながら、内部チップの放熱も相当あるということだろう。だがこれも、また筐体の大きさも、まだBDに必要な回路が本格的に集積化されていないからで、普及の見通しが立てば、小型化・省電力化が進むことだろう。
搭載チューナは、地上波・BS・110度CSのデジタルと、地上アナログの4つ。このうちBSとCSは入力を兼用しているため、RF端子は合計3つだ。もちろん全部繋いでもいいのだが、地デジが入る人はわざわざアナログも繋ぐ必要はないだろう。地デジがまだの人はアナログのみ繋ぐことになる。いずれにしても、繋ぐ線は2系統で済む。
AV入力は3系統、出力2系統に、D3端子と光デジタル音声出力がある。HD対応なのでD3端子になっているが、入出力数は一般的なハイブリッドレコーダと同じだ。そのほか、デジタル放送特有のサービスを利用するためのモデム端子と、10BASE-TのLAN端子がある。
 |
| デザイン的にはDIGAのものと似ているが、長さがかなり違う |
ただし本機はi.LINK端子を搭載していないので、CATVのSTB経由やD-VHSなどとの併用はできない。あくまでも自前のアンテナで、シンプルにデジタル放送の録画ができる、という趣旨の製品だ。
リモコンも見てみよう。BDとは言ってもラインナップ的にはDIGAの最上位モデルという位置づけであるので、リモコンの形状もDIGAのそれとよく似ている。ただし長さはかなり長く、1ドライブ機のためにドライブ選択ボタンがない代わりに、デジタル放送特有の青、赤、緑、黄の4色ボタンが追加されている。
■ 使用感は思ったよりシンプル
では実際に使ってみよう。HDDがなく1ドライブのレコーダなので、ダビングやメディア選択といった機能がないため、使い方はシンプルだ。放送波の切り替えは、リモコンの「放送切替」ボタンを押すたびに、「地上アナログ-同デジタル-BSデジタル-CS1-CS2」とローテーションする。
番組表は、「番組表」ボタンを押すと、現在視聴中の放送波ものを表示する。番組表の表示中に「放送切替」ボタンを押すと、各放送波のものに切り替えることができるのは便利だ。地上アナログの番組表はGガイドで、従来のDIGAがTBS系列で放送されているデータ放送を受信しているのだが、E700BDはBSデジタルのデータ放送BS900ch(メガポート放送)を使用する。つまり、地上波EPGを使うには、BSデジタルの受信環境が必要になる。
番組表の新しい見せ方としては、表示のズームイン・アウトができるのは実用的だ。例えばデジタル放送では、1つの放送局が3チャンネル分にまたがっている。したがって従来のように1画面で3チャンネル程度の表示では、1つの放送局のスケジュールしか把握できないことになる。だが番組表ズームを使えば、最大9チャンネルまで同時に表示できるため、複雑になりがちなデジタル放送の放送スケジュールも、把握しやすくなる。ただ番組表の縦横移動に若干もたつきがあるところは、もう少し改善の余地があるだろう。
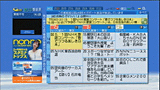 |
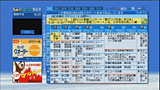 |
| 番組表をズームインした状態。詳細は読みやすいが、全体的な見通しは悪い | 番組表をズームアウトした状態。広い範囲で番組編成が確認できる |
ジャンル検索では、各放送波にまたがった検索が可能だ。メインジャンル、サブジャンルも充実しており、特定ジャンルに強いCSの番組も含めて検索できるのは、なかなか強力。また人名検索も備えており、好きなタレントがある人には便利だろう。惜しいのは、ここまでの検索機能がありながら、やはり録画容量が限られているためか、おまかせ録画みたいな機能がないところだ。
「キーワード検索」は、自分で好きなものが入力できるというわけでもなく、お勧めのカテゴリから選んでいくというタイプのもので、趣旨としては若干ジャンル検索とダブる部分があるのかなという気もする。
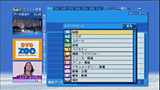 |
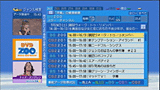 |
| ジャンル検索では、メインジャンル、サブジャンルも充実 | 放送波にまたがって検索できるのは強力 |
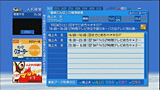 |
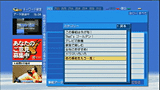 |
| 人名検索で目的の俳優やタレントの出演番組を押さえる | キーワード検索は、プリセットされた項目から選ぶだけ |
予約録画の際には、デジタル放送ならではの機能を使うことができる。「時間変更追従」は、番組の放送時間が変更されたり延長されたりした場合に、自動的に追従する機能だ。アナログ放送のEPGでは番組表更新のタイミングが限られるため、なかなか実現が難しかった機能だが、うまくハマれば便利な機能だろう。
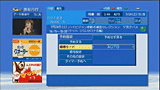 |
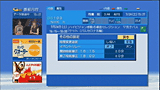 |
| EPGで番組録画予約したところ。「その他の設定」にデジタル放送ならではの機能が | 「時間変更追従」や「イベントリレー」は、ユーザーが待ち望んだ機能 |
もう1つ「イベントリレー」も便利そうな機能だ。これは延長番組が他のチャンネルで放送されるときに、自動的にチャンネルを変更して録画を続行してくれる機能だ。あいにく筆者の試用期間中には、これらの機能が動作するところは確認できなかったが、高校野球やオリンピックなど、一日中放送しているようなものを追っかけて録画する際に重宝しそうだ。
■ 録画および編集機能をチェック
番組の録画には、いくつかの画質モードがある。AUTOに設定すれば、MPEG-2 TSストリームをそのまま録画するので、画質劣化のない録画が楽しめる。HD放送に対しては、このモードで録らないと意味がないだろう。
またHD放送でもSDにダウンコンバートしながら、圧縮して録画することもできる。この方法であれば、BDディスクではなくDVD-RAMも利用できる。一方DVD-Rは、現在発売されているメディアがCPRMに対応していないので、もっぱらアナログ放送に対して使うことになるが、なんせ1ドライブだ。別メディアに録ってダビングすることもできないため、実際には使うチャンスはあまりないだろう。
| 録画モード | BD1層 (25GB) |
BD2層 (50GB) |
DVD-RAM/R (4.7GB) |
|---|---|---|---|
| AUTO(BSデジタル-HD) | 2.25時間 | 4.5時間 | - |
| AUTO(BSデジタル-SD) | 4.5時間 | 9時間 | - |
| AUTO(地上デジタル-HD) | 3時間 | 6時間 | - |
| BXP(Dolby Digital) | 3.25時間 | 6.5時間 | - |
| BXP(LPCM) | 3時間 | 6時間 | - |
| XP | 5.25時間 | 10.5時間 | 1時間 |
| SP | 10.5時間 | 21時間 | 2時間 |
| LP | 21時間 | 42時間 | 4時間 |
| EP | 31.5時間 | 42時間 | 6時間 |
試しににHD放送を各モードで記録してみた。BXPは、ダウンコンバートの絵としてはかなりいい。もちろんHDの解像度は望めないが、SDの画像としてみれば良質である。ただAUTO記録に対して時間的なメリットはあまり大きくない。XPは、BXPに比べれば輪郭のキレは劣るが、まずまず良好。ただ平坦な壁などでは、若干の色むらを感じるケースもある。
SPは、画質と録画時間を天秤にかければ、もっともリーズナブルなところだ。LPでは解像度が半減し、いかにも長時間モードといった感じ。EPではLPからさらに1段階落ち、縦の解像度も半分になるため、フレーム動画になる。
録画する番組に対しては、一応CMスキップ機能も使えるが、デジタル放送ではほとんどがステレオ放送なので、あまり役に立たない。なにか音声モード以外の方法でCM検知を実現しない限り、この機能は「アナログ時代の良き思い出」で終わってしまいそうである。またBDへの録画では、おっかけ再生やタイムワープなどの機能が使えない(DVD-RAMのみ可能)。そう言う意味では、録画中はまだディスクメディアとしてのメリットは発揮されていない。
録画番組を見るには、「プログラムナビ」を使う。番組リスト表示では、録画した番組が録画日順に並び、選択中のものは左に動画サムネイルが表示される。画像リスト表示では、大きめのサムネイルで1画面に6番組表示される。このサムネイルは、選択しても静止画のままだ。
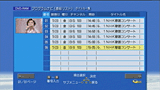 |
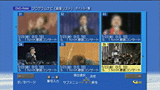 |
| プログラムナビは「番組リスト表示」(左)、「画面リスト表示画面」(右)を切替可能 | |
本機には編集機能もある。ダビング機能はないのだが、不要部分を消去して整理すれば、その分録画容量が増えるため、まんざら意味がないわけではない。方法は2つあり、番組内にチャプタを設定したのちそのチャプタ部分を消去する方法、もう1つはタイトル分割したのち、不要なほうを消去するという方法だ。
ここではチャプタの作成を試してみよう。映像操作としては、早送り・早戻しが5段階、前後スローが5段階の他に、コマ送り・コマ戻しボタンも追加された。編集時のレスポンスは、まあ「普通」。すばらしく良いわけでもないが、新メディアのわりには実用上問題ないレベルにまとめている。
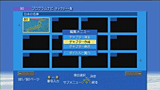 |
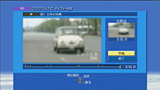 |
| チャプタ操作による映像編集機能を備える | チャプタ設定時のレスポンスは、まずまず |
「チャプタ作成」では、間違って作ってしまったチャプタポイントをこの場でやり直す機能がないのは惜しい。この場合はいったんこのモードを抜けて、「チャプタ結合」を行なう必要がある。チャプタ一覧画面に戻ると、チャプタのサムネイル作成に少し待たされるが、消去などのレスポンスは悪くない。ただチャプタのサムネイルは動くわけではないので、削除するときに内容の確認ができない。
| 画質モード | 解像度 | 音声 | サンプル |
|---|---|---|---|
| XP | 704×480ドット | ドルビーデジタル256kpbs | 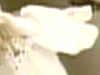 xp.mpg(21.6MB) |
| SP | 704×480ドット | ドルビーデジタル256kpbs | 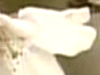 sp.mpg(15.0MB) |
| LP | 352×480ドット | ドルビーデジタル256kpbs |  lp.mpg(8.27MB) |
| EP | 352×240ドット | ドルビーデジタル256kpbs | 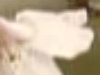 ep.mpg(5.36MB) |
| 編集部注:DVデッキ「WV-DR5」で再生したRF出力し、CREATIVECAST Professionalの映像をRF経由で録画した。掲載した静止画のキャプチャは800×600ドットでキャプチャした。(c)CREATIVECAST Professional | |||
| MPEG-2の再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |
■ 総論
|
||||||||||||||||||||||||
|
史上初のBDレコーダ登場から約1年以上空いてしまったものの、DMR-E700BDは次世代の放送とレコーダの雛形を見せてくれたという点で、重要なマイルストーンとなる製品だろう。価格が30万円前後と、まだお買い得というほどの値頃感でもないが、それでもBDレコーダが、機能としても技術としても現実味を帯びてきたことは感じる。特にパナソニックでは、BDを別ブランドとして立ち上げるのではなく、あくまでもDIGAブランドの延長線上に据えたことからも、今後の低価格化に期待したいところだ。
今後の課題としては、やはり現状のハイブリッドレコーダのようにHDD録画→BD保存といった流れは必要だろう。使い勝手の面でも、動画サムネイルがないなど、HDが記録できるぶん、今のハイブリッドレコーダより機能的に劣る部分も残っている。さらにi.LINK端子による他機種とのリンクなど、コピーコントロール関係での課題が多い。この辺りに関しては、コピーワンスで本当に満足できる状況になるのか、不便なら不便とユーザーがしっかり声を上げる必要があるだろう。
新世代のメディアやレコーダ普及のもう1つのカギは、コンテンツにもある。誰でもホンモノのHD放送を見てしまえば、この画質がそのまま録画できる機材が欲しくなるだろう。だが現在のデジタル放送、特に地上デジタルは、HDと言いながらもその実態は、SDからのアップコンバートであったり、HD素材とSD素材を混在させて1本の番組にしたりといった状況にある。なかなか本来の画質が、ストレートに放送の魅力として繋がっていないのが現実だ。
アテネオリンピックでそんな状況が少しでも打破できれば、そしてオリンピック以降もその魅力を持続することができれば、新世代レコーダへのニーズも本格的に加速することだろう。
□松下電器のホームページ
http://matsushita.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.matsushita.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn040630-2/jn040630-2.html
□製品情報
http://panasonic.jp/dvd/products/bd/spec/01.html
□関連記事
【6月30日】松下、同社初のデジタルチューナ搭載ブルーレイレコーダ
-地上/BS/110度CSデジタルチューナ搭載。DVD録画対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040630/pana.htm
(2004年7月28日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|