 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第171回:DV史上最高峰のカメラ「キヤノン XL2」
|
■ あのXLが新しくなった
レンズ交換が可能なハイエンドDVカメラ、キヤノンのXLシリーズは、デビュー当初から大きな反響をもって迎えられた。ハイアマからプロにかけて興味を持っている人も多く、業界人に聞けば知らない人はいないほどの知名度を誇っているのだが、じゃあ実際にプロの現場で使われているかというと、国内ではそういう話はほとんど聞いたことがない。
ところがそういう事情は、海外に行くと全く違っている。NABなどでは多くのサードパーティがXL用のアクセサリ類をいろいろ作っていたり、海外で見かける撮影クルーが実際に使っていたりと、欧米ではかなりプロの閒で信頼されているカメラなのである。
そんなXLシリーズだが、約3年ぶりに新モデル「XL2」が登場した。24P撮影、シネマライクガンマを備えるなどフィルム撮影のテイストを意識した作りは、Panasonic「AG-DVX100」の登場以降、クリエイターが意識し始めた流れに沿っている。
奇しくも今月7日、ソニーのHDVカメラが発表され、HDの足音がひたひたと迫ってきているのを感じるこのタイミングで、SDフォーマットのDVハイエンドの存在はどういう意味をもたらすのか。
今回はいつものカメラレビューに加えて、開発陣にもお話を伺った。では早速DVカメラの最高峰、XL2を使ってみよう。
■ テイストを継承しながら改良
実は初代XL1からXL1Sに進化したときにも一度取り上げているが、そのときはデザイン的な変更はほとんどなかった。だが今回のXL2は、白黒に赤のアクセント、ヒップアップボディといったXL特有のデザインキーワードを継承しつつ、形状も変化している。全体的なサイズ感はあまり変わらないが、ショルダーパッドが折りたたみではなく固定になったことで、シルエットもシンプルになっている。

|

|
| 初代のイメージを踏襲しつつ新しいフォルムとなった | 普段から使う機能は全部表面にスイッチとして実装している |
よく使うと思われる機能はボタンやスイッチとしてすべて表面に出ている点は変わらず、今回のモデルの特徴であるフレームレートやアスペクトの切り替えも、ロータリースイッチで行なう。
またモード切替のロータリースイッチも、モードの並び順が見直され、フルオートモードが一番端に変更されている。このクラスのカメラならフルオートで使うことはほとんどないわけだし、使うときはよほど緊急の場合なので、ダイアルを回して突き当たった場所にこのモードがあるというのは、使う側にとっては安心できるだろう。また新たにローライトモードも新設されている。

|

|
| ロータリースイッチのモード配列も見直されている | ビデオアウトにBNCを採用し、プロ機器とも繋ぎやすい |
ゲインは-3から+18dBまで減/増感可能で、ホワイトバランスにユーザープリセットが3つ使えるあたりは、前モデルからそのまま継承されている。
CCDは新開発1/3インチ3CCDで、しかもプログレッシブ型のものを採用したのは新しい試みだ。本機には24Pと30Pのプログレッシブモードがあるが、そちらのほうにターゲットを絞っているということかもしれない。

|
| ビューファインダと液晶モニタを兼用するアイデアはユニーク |
ビューファインダもユニークで、アイカップ部を跳ね上げると液晶モニタとしても使えるような作りになっている。サイズが2インチと小さいのが難点だが、数人で画角を検討するときなど交代で覗かなくて済むため、実用性は高いと思われる。
このカメラ、レンズが別売なのだが、今回は同時発売の「20×ズーム XL 5.4-108mm L IS」をお借りしてある。こちらも見てみよう。光学手ぶれ補正付きの20倍ズームレンズで、XL2装着時の35mm判換算の画角は、16:9では42.2mm~844mm、4:3では51.8~1036mm(35mm換算)である。光学20倍は立派だが、4:3で使うとちょっとワイド端が狭い感じだ。解放F値は1.6から3.5。NDは1/6と1/32の2つが付いている。
| アスペクト比 | ワイド側 | テレ側 |
| 16:9 | 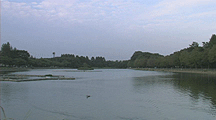 |
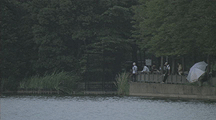 |
| 4:3 |  |
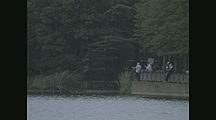 |
このレンズには新しい試みとして、フォーカス値とズーム値が記憶できる「ポジションプリセット」機能が付いている。例えばズーム値が記憶できれば、いつでも同じサイズに寄れるわけで、ヒキとヨリを交互に使うインタビュー収録などには便利だろう。レンズ制御は電子式だが、そのメリットを上手く使った機能だと言える。

|

|
| フォーカス値とズーム値が記憶できるポジションプリセットを搭載 | ズームレバーに速度リミッタを設けて、定速でのズームがやりやすくなった |
またズームレバーの後ろには、ズームスピードの上限を決められるダイヤルが付いた。今までは高速から低速まで、指先の感覚一つでコントロールしていたわけだが、スピードのリミッタが付けば、もっと正確なコントロールが可能になる。また完全に一定スピードでズームするCONSTANTモードへの切り替えも可能になった。アマチュアっぽくなったということではなく、プロでもこういう機能はあれば便利に使うだろう。
■ 細かい設定が可能なカスタムプリセット

|
| 今回も同行していただいたプロカメラマンの前島一男氏 |
さて肝心のシネライクガンマだが、XL2の場合は、AG-DVX100Aのようにいくつかタイプやプリセットを選ぶだけ、といった単純なものではない。ガンマも含めて、15項目のパラメータを設定でき、それらの組み合わせを自分でプリセットしなければならないのだ。したがって簡単にフィルムライクな撮影が楽しめるというよりも、かなりカメラのパラメータに詳しい人じゃないと全然使いこなせない。
そこで今回は、「AG-DVX100」レビューの時にも同行して頂いたプロのCFカメラマン、前島一男氏の指導を仰ぎながら、テストしてみることにした。まずはその15項目と可変範囲を見て頂こう。
| 項目 | 可変範囲 |
| ガンマ | ビデオ/シネマ |
| ニー | ハイ/ミドル/ロー |
| ブラック | ストレッチ/ミドル/プレス |
| カラーマトリクス | ビデオ/シネマ |
| カラーゲイン | ±6段階 |
| 色相 | G-Rの閒で12段階 |
| Rゲイン | ±6段階 |
| Gゲイン | ±6段階 |
| Bゲイン | ±6段階 |
| Vディテール | ノーマル/ロー |
| シャープネス | ±6段階 |
| コアリング | ±6段階 |
| セットアップレベル | ±6段階 |
| マスターペデスタル | ±6段階 |
| NR | ハイ/ミドル/ロー/切 |
前島氏によると、「RGBゲインで色味を積極的に作れる点はGood」だという。「今はみんなシネガンマだけに集中してるけど、ブラックを始め、セットアップやペデスタルを使って黒の締め具合を細かくコントロールできる。夕景なんか撮るときに、黒を締めて色味を出したりということができる点は、プロ機並み」ということだ。
ただしこれらの設定をロケ現場で行なうためには、別途ピクチャモニタや波形モニタなどを用意する必要があるし、時間もかかる。実際にはスタジオや自宅でじっくり時間をかけて自分の好きなトーンを作り込んでおき、それを呼び出して使うといった使い方になるのでは、ということだった。
このプリセットは3つ設定できる。そこで筆者の独断と偏見で、上記のパラメータを駆使してプレーンなシネマトーンをプリセット1に、敢えて極端に濃いトーンをプリセット2に作ってみた。カスタム設定を使わないノーマルなビデオトーンと合わせて、絵作りとしてはここからここまでできるという参考になるだろうか。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | プリセット 1 | プリセット 2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
新開発のCCDは、かなり無茶な条件でもスミアが出ず、格段に良くなっている。レンズのほうもフレアが少なく、良質だ。20倍のテレ端でも色収差が少ないのは、やはり蛍石レンズの威力だろう。

|

|

|
| フレアやスミアには相当強くなっている | テレ端でも色収差が少ない | ワイド端でマクロ撮影。花はほとんどレンズフードの内側に入っている |
フレームレートに関しては、24Pもいいのだが、30Pがあるのは非常に重要だ。というのも、コマーシャルなどフィルム撮影であっても最終的にテレビ作品になるものは、ほとんど30コマで撮影している。24コマだと編集も大変だし、ビデオに慣れた目からすれば、動きの解像度が粗すぎて、違和感を感じるからだ。あとでキネコするとか、オーバーにフィルムライクな表現が欲しいというとき以外は、30Pのほうが使い勝手がいいだろう。
 |
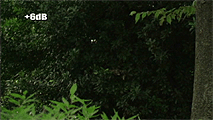 |
| 24Pで撮影した動画サンプル sample.mpg(約25.1MB) |
増感のテスト。プログレッシブでは+18dBには設定できないので、+12dBまでとローライトを試してみた zoukan.mpg(約14.8MB) |
| MPEG-2の再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |
■ なぜ今DVのハイエンドなのか

|
| キヤノン本社にて、開発者の皆さんにお話しを伺った |
コンシューマのDVフォーマットでありながら、機能的にはプロ用カメラ並みのXL2だが、そもそもXLシリーズというのは、どういうユーザー層が使っているのだろうか。下丸子にあるキヤノン本社にお邪魔して、国内ではあまりユーザーの情報がないXLシリーズのお話を伺うことにした。電子映像事業企画部課長の大谷 智氏はこう語る。(以下敬称略)
大谷:「国内では残念ながら、ユーザー層を分析するまでの販売規模はありませんでした。しかし米国では既にかなりの数が出ていまして、実際には3/4ぐらいはプロユーザーです。主にコマーシャルやニュース、あるいは会社関係といったところが多いようです。今回のXL2で、国内市場をもっと拡大していければと思っています」
ソニーがHDVのカメラを発表したことで、コンシューマハイエンド市場ではHDソリューションへの期待が高まっている。キヤノンもHDV賛同メーカーの一つであるが、ここでなぜハイエンドのDVカメラなのだろうか。
大谷:「HDVも技術的な方向性は見えてきているんですが、実際に需要が盛り上がるのにはもう少し時間があると見ています。それよりも先に、まだまだSDの画質でやらなければいけないことが沢山残っています。まずそれをきちっとやって、SDの最終形としてキヤノンの保ちうる技術を全部出していく。それからでも遅くはないと思っています」
イメージコミュニケーション事業本部 製品開発担当部長の近本 浩一氏は、
近本:「米国では我々の想像以上にいろんな使われ方をしているようで、実際にヒアリングしてみると、16:9の需要が高いことがわかりました。必ずしもHDではなく、SDでいいと。またドキュメンタリー、ドラマといったシネマ系の人たちのニーズを吸い上げて、24Pを搭載しています」
XLシリーズは、カメラ本体の性能のさることながら、レンズ交換式というところに大きな特徴がある。この点に関して、キヤノン光学技術研究所レンズ第二開発部 部長の金田 直也氏はこんな話しをしてくれた。
金田:「EFレンズが使えるので、ターゲットは既にレンズを持っている人、という話になりがちなんですが、もともとの開発経緯は逆なんです。プロ用ビデオカメラはレンズが変えられて当たり前。それをアマチュアでも楽しめるようにということで、XLシリーズは始まったんです。ちょうど当社にはEFレンズという資産がありましたから、それを利用したという流れなんです。つまり当初はハイアマを狙っていたわけですが、実際にはプロが飛びついたというのが現状です」
■ 総論
いまさらSDやってもなー、という風潮が最近の日本の放送業界にはあるのは事実だ。だがフォーマットを画一化するよりも、コンテンツによってメリットがあるフォーマットを使い分けるという米国のような考え方も、あっていい。
例えば日本のテレビ番組では、スタッフが1週間ぐらい集まってわーっと撮って、それでドキュメンタリーということになっている。だがそんな調子では、海外のドキュメンタリーのレベルとは比較にならないのもまた事実で、もっとじっくり腰を落ち着けて撮り続けるという世界があってもいいはず。
XL2は、本体とレンズ込みでも100万円を切る。あとEFレンズをいくつか買っても、うまくヤリクリすれば番組予算内でペイできてしまうはずである。長期に渡ってビデオカメラのレンタル料を払うよりも、買ってしまって自由なタイミングでじっくり撮った方がいいという考え方の番組なりプロダクションのスタッフにまで、このXL2が届くだろうか。
XL2は、AEシフトなどスチルカメラ的な発想の部分もいくつか見受けられるが、SDの画質としてはプロ機とほぼ同等だと言っていいだろう。あとは使う側がどう割り切っていくかだけ、というところまで来たのは確かだ。
□キヤノンのホームページ
http://canon.jp/
□ニュースリリース
http://www.canon-sales.co.jp/newsrelease/2004-07/pr-xl2.html
□製品情報
http://www.canon-sales.co.jp/dv/lineup/xl2kit/index.html
□関連記事
【7月13日】キヤノン、シネルックを実現したレンズ交換式DVカメラ
-ワイドモードや、24p記録に新対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040713/canon.htm
【2001年8月22日】【EZ】コンシューマDVの最高峰「CANON XL1s」で撮る!
~ 超望遠2,160mmの世界も覗きました ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010822/zooma23.htm
【2001年7月16日】キヤノン、レンズ交換可能なプロニーズ対応MiniDVカメラ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010716/canon.htm
(2004年9月15日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|