 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
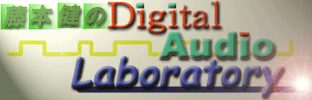
第352回:
オーディオエンジンを改良したCakewalkのDAW「SONAR 8」
~ 動作が軽く、使い勝手も向上。プラグインも充実 ~
~ 動作が軽く、使い勝手も向上。プラグインも充実 ~
年末はDAWリリースの季節というのが、ここ何年間かのトレンドとなっているが、今年もいろいろ登場してくる。すでに発表されているとおり、CakewalkのSONAR 8、DigidesignのPro Tools 8、そしてACID Pro 7が登場する。その中で一番手となったのがCakewalkのSONAR 8だ。
すでに、このDigital Audio Laboratoryの第344回で、発表会での内容を紹介しているが、ようやく製品バージョンであるGolden Master版が完成し、それを入手することができたので、どんなものなのか紹介していこう。
■ 前作に比べて“軽い”SONAR 8
毎年1回のバージョンアップを繰り返しているCakewalkのSONAR。今年も昨年とほぼ同時期の発売となり、やはり上下2つのラインナップとなる。SONAR 8 PRODUCERとSONAR 8 STUDIO。従来の製品名からEditionという単語が抜け落ちたが、実売価格的にもそれぞれ85,000円前後、50,000円前後と変わらない。
 |
 |
| SONAR 8 PRODUCER | SONAR 8 STUDIO |
今回はSONAR 8 PRODUCERを使ったが、インストールに用いるメディアは計4枚のDVD-ROMで、そのうち2枚はダブルレイヤーのメディアとなっており、全部インストールするのに30分以上を要する。
デモ曲のデータを除いてインストールした結果、Cドライブの容量は31.1GBとSONAR 7の18.1GBと比較して13GBほど増えている。そのほとんどは後で紹介するソフトシンセの音色データによるものと思われるが、それなりの空き容量を持つHDDを用意する必要はありそうだ。
起動してみると、最初どこが変わったのかほとんど気づかないほど、見た目はSONAR 7と変わらない。ユーザーインターフェイス自体はほとんど変わっていないため、これまでSONARを使ってきたユーザーであれば、まったく違和感なく使うことができるはずだ。
 |
 |
| 見た目はSONAR 7と変わらない | |
しかし、SONAR 7を使い込んできた人であれば、触っていると、おや?と感じることがある。昔のMIDIシーケンサ時代のCakewalkのように……とまでいうと大げさだが、とにかく動作が軽くなっているのだ。
SONARも当初はほかのDAWと比較して非常に軽いのがウリだったが、徐々に機能を増やすとともに、重くなってきたのは否定できない事実だ。今回のバージョンアップでは、これを改善するためにオーディオエンジンを大幅に改良しているというのだ。
そこで、本当に軽くなっているのか簡単なベンチマークを行なってみた。ThrottleWatch 2.01というベンチマークソフトで、CPU負荷を測定しながら同じ曲をSONAR 7とSONAR 8で再生させるというものだ。
テストに使ったのはCore2Duo E6400(2.13GHz)のCPUを搭載したWindows Vistaマシン。従来のSONARもそうだが、バージョンが異なっても曲データそのものは、互換性を持っているため、SONAR 8に入っていたデモ曲をSONAR 7、SONAR 8に読み込んで再生させた。
設定の異なる3曲を試してみたが、それぞれ1曲を通して毎秒1回のペースで負荷を測定した平均を出してみた。
| 曲数 | SONER 7 | SONER 8 |
| 1曲目 | 61% | 52% |
| 2曲目 | 24% | 13% |
| 3曲目 | 71% | 29% | 編集部注:編集部では測定結果についての個別のご質問には お答えいたしかねますのでご了承下さい。 |
曲によって違いはあるものの、明らかにSONAR 8のほうが負荷が軽くなっているのが分かるだろう。一番差が大きかった3曲目の負荷をグラフ表示させてみたが、こうすると視覚的にも違いがよくわかるはずだ。
 |
 |
| 左がSONER 7、右がSONER 8。明らかにSONAR 8のほうが負荷が軽くなっているのが分かる | |
1曲目では差がそれほど大きく出なかったが、これはプラグインのソフトシンセ、エフェクトを多用した曲。それに対して2曲目、3曲目はオーディオのトラック数が多い曲だったことを考えると、オーディオトラックの処理が非常に軽くなったということなのかもしれない。
また、とりあえず3曲ともSONAR 7でも最後まで演奏できたものの、1曲目と3曲目は途中で負荷が100%に達し、ビリビリビリというノイズが乗ってしまった。
もちろんCore i7など、より高いスペックのPCを導入することで、負荷の問題はある程度解決できるはずだが、やはりオーディオエンジン性能が向上しているというのはうれしいポイントだ。
■ そのほかの改善点
このオーディオエンジンの改良、処理速度だけでなく、使い勝手の面でもひとつ大きく改善したところがある。それは、オーディオの設定を変更しても、ソフトの再起動が不要になり、すぐに反映されるようになったことだ。従来SONARでは、設定しているオーディオインターフェイスを切り替えたり、WDMドライバからASIOドライバに変更したりすると、必ずSONARを再起動する必要があり、結構面倒だった。些細な点ではあるが、個人的には非常に気に入っている。
 |
| オーディオドライバに新たにWASAPIが対応 |
さらに、今回オーディオドライバのモードに新たな種類が加わった。これまで、WDM/KS、ASIO、MME(32bit)の3モードだったが、それにWASAPIというのが加わったのだ。
WASAPIとはWindows Audio Session APIの略で、Windows Vistaで実装されたもの。これはASIOやWDM/KSのようにWindowsのカーネルミキサーを介さずに直接ハードウェアを叩く構造となっているため、レイテンシーを低く抑えることができるというものだ。
Windows VistaではOSのドライバ周りが大きく改変され、DirectSoundやMMEなど従来からのドライバもWASAPIを用いてエミュレーションしているという。ただし、初期のVistaではかなり問題があったため、実際にはVista SP1で使えるようになったものだ。
すでにフリーウェアのプレイヤーソフト、foober2000などではWASAPIに対応していたが、SONAR 8でもこのWASAPIをサポート。
これまでASIOやWDM/KSで利用してきたオーディオインターフェイスのモードをWASAPIに切り換える必要性はまったくないが、メリットがあるのが、これまでASIOやWDM/KSをサポートしていなかったデバイス。具体的にはオンボードのサウンド機能や古いサウンドカードなど。WASAPIやOS側がサポートした機能であるため、基本的にどんなサウンド機能でも利用することができ、レイテンシーを小さくすることができるとともに、カーネルミキサーを通さないため音質の向上も期待できる。
たとえば、普段はデスクトップPCにオーディオインターフェイスを接続して使っているが、デモ用にノートPCで動かし、オーディオインターフェイスがない場合などにWASAPIを用いて鳴らすといった使い方が考えられそうだ。
が、まだ新しいドライバモードであるために問題も多い。実際、今回使ったマシンのマザーボード上のサウンド機能、RealtekのHigh Difinition Audioを試してみたところ、うまく動作しなかった。RolandによるとRealtekのすべてがダメというわけではなく、環境によって動作したり、しなかったりするようで、安定していないようだ。
■ プラグインも充実
ここまでSONAR 8のシステム的な面にフォーカスを当てて見てきたが、もちろん機能面でもプラグインの追加を中心にいろいろと強化されている。まずはソフトシンセから見ていこう。今回の目玉といえるのがサンプリングベースのシンセサイザであるD-Proだ。ご存知の方も多いと思うが、D-Proはこれまでとおり、Cakewalk Insturmentsシリーズとして単体発売されてきたもので、実売価格が3万円前後というもの。
SteinbergのHALionに対してCakewalkのD-Proがある、といった位置づけであり、前バージョンのSONAR 7でもD-Proの機能削減版であるD-Pro LEがバンドルされていた。
しかし、今回は機能制限のないものになるとともに、ライブラリが大幅に増加しているのがポイント。標準のD-ProだけでもダブルレイヤーのDVD-ROMに収録されており、7GBのメディアで提供されているが、それに加えて拡張音色ライブラリが別のダブルレイヤーのDVD-ROMに収められているのだ。
 |
 |
| サンプリングベースのシンセサイザソフト「D-Pro」 | 拡張音色ライブラリが別のDVD-ROMに収められている |
具体的にはRhodesやB3などのビンテージものやピアノ、オルガン、シンセサイザなど300プログラムを搭載した「Digital Sound Factory Volume 2 Classic Keys」、雨や雷、虫の声などのSFサウンドを収録した「Hollywood Edge」、そしてドラム、ベース、ギター、オーケストラサウンドなど約700種類のライブラリを収めた「D-Pro Expantion Pack 1&2」などとなっている。
またTRUE PIANOS AMBERは4Front社のアコースティックピアノ音源で、ピアノ音源として定評のあるもの。サンプリングと物理モデリングを行なっている音源で、かなりリアルなアコースティックサウンドが得られる。
 |
 |
| アコースティックピアノ音源ソフト「TRUE PIANOS AMBER」 | リアルなアコースティックサウンドが得られるという |
 |
| 音源ソフト「BEATSCAPE」 |
そして、もうひとつ追加されたのがBEATSCAPEという音源。こちらは従来からあったCycloneを発展させたような音源で、ループサウンドを利用して、新たなグルーブを簡単に作り出すことができるというユニークなものだ。
ACIDizedループとREXファイルに対応しており、16個のパッドにループサウンドを割り当てて、内蔵ステップエディタで鳴らしていくというものだ。スライスごとにトリガーすることができたり、音色を時間軸で変化させるなど、かなりユニークなプレイが可能となっている。ここに取り上げた3つのソフトシンセはいずれもSONAR 8 PRODUCERにのみバンドルされている。
次にエフェクトのほうを見てみよう。これも新たなものがいろいろと追加されている。まずはTS-64 Transient Shaper。これはドラム、ギターなどパーカッシブでダイナミックに音が変化する音源に最適なシェイパーで内部演算64bit倍精度でサウンド処理を行なうというもの。周波数帯域に分割し検出を行ない、再構築することで精度の高いコントロールを実現している。
また、TL-64 Tube Levelerも内部演算64bit倍精度処理をするエフェクト。こちらは真空管モデリング・アルゴリズムのリニアドライバー/レベリング・ プロセッサーでクラシックなレコーディングサウンドを再現するというものだ。このTL-64のモデリングの元になっているのは名機として知られるTeletronixのLA-2A。これをパーツ・回路レベルからモデリングしているとのことで、ビンテージ機材ならではの温かいサウンドが得られる。
さらにCHANNEL TOOLSは音の広がりをコントロールできるステレオ・イメージャー。ステレオ・ソースのパン、ワイズ、ディレイ、フェーズなどの調整ができ、左右のインプット入れ替えも可能となっている。M/S方式でレコーディングされた素材のデコード処理にも対応している。
 |
||
| 「TS-64 Transient Shaper」 | 「TL-64 Tube Leveler」 | 「CHANNEL TOOLS」 |
 |
| 「Native InsturmentsのGuitar Rig 3 LE」もバンドルされている |
そのほか、Native InsturmentsのGuitar Rig 3 LEもバンドルされている。このGuitar Rig 3 LEはSONAR 8のプラグインとしてはもちろん、スタンドアロンのギターアンプ・シミュレータとしても使えるようになっている。このようにとくにSONAR 8 PRODUCERにおいてはプラグインソフト目的でアップグレードしても十分に元がとれる内容となっている。
そのほかプラグイン以外の機能強化ポイントをいくつかピックアップしておこう。まずは、なぜ今までなかったのか不思議な点でもあるが、トランスポートパネルに巻戻し・早送りが追加された。またループエクスプローラが一新し、オーディオループだけでなくMIDIループも同様に扱えるようになている。
さらに、シンセラックからソフトシンセを追加する際、シンプル・インストゥルメント・トラックというモードが標準となり、追加されるトラックとしてソフトシンセのみとなり、すっきりするようになった。
 |
 |
|
| トランスポートパネルに巻戻し・早送りが追加 | ループエクスプローラが一新。MIDIループも扱える | シンセラックからソフトシンセを追加する場合、シンプルインストゥルメントトラックというモードが標準になった |
以上、SONAR 8について見てきたがいかがだっただろうか?
実はもうひとつ、大きなトピックスとしてSONAR 8を業務用のレコーディングシステムへアップグレードするためのSONAR V-STUDIO 700の存在があるが、これは1月に発売される予定だ。
個人的には、SONAR 8の公式ガイドブックである「MASTER OF SONAR 8」(1月にBNN新社から発売の予定)を執筆するために、ベータ版を借りて先日使ったが、かなり強力なシステムだった。これについては、ドライバ類が完全に調整された正式版が出たところで、また改めて取り上げる予定だ。
□Rolandのホームページ
http://www.roland.co.jp/
□cake walkのホームページ
http://www.cakewalk.jp/
□製品情報
http://www.cakewalk.jp/Products/SONAR8/index.shtml
□関連記事
【10月20日】【DAL】戦略価格のDAW、Roland「SONAR V-STUDIO 700」
~ 「ProToolsからのリプレイスを狙う」意欲作 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081006/dal344.htm
【2007年12月10日】【DAL】CakewalkのDAW最新版「SONAR 7 Producer Edition」
~ 使い勝手を改善。マスタリングエフェクトも充実 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071210/dal307.htm
(2008年12月15日)
| = 藤本健 = | リクルートに15年勤務した後、2004年に有限会社フラクタル・デザインを設立。リクルート在籍時代からMIDI、オーディオ、レコーディング関連の記事を中心に執筆している。以前にはシーケンスソフトの開発やMIDIインターフェイス、パソコン用音源の開発に携わったこともあるため、現在でも、システム周りの知識は深い。 著書に「コンプリートDTMガイドブック」(リットーミュージック)、「できる初音ミク&鏡音リン・レン 」(インプレスジャパン)、「MASTER OF SONAR」(BNN新社)などがある。また、アサヒコムでオーディオステーションの連載。All Aboutでは、DTM・デジタルレコーディング担当ガイドも務めている。 |
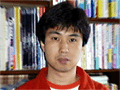 |
[Text by 藤本健]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部 Copyright (c) 2008 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.