 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
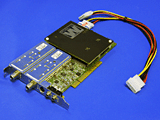
初のダブルチューナ搭載で2画面表示や裏番組視聴にも対応
カノープス「MTV3000W」
発売日/2月中旬
価格/オープンプライス(実売価格5~6万円前後)
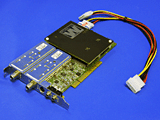 |
| 初のダブルチューナ搭載で2画面表示や裏番組視聴にも対応 |
| カノープス「MTV3000W」 |
| 発売日/2月中旬 価格/オープンプライス(実売価格5~6万円前後) |
■ 主な特徴
「MTV3000W」は、テレビキャプチャカードとして、初めてダブルチューナを搭載したMPEG-1/2キャプチャカード。非圧縮オーバーレイ表示機能のほか、ゴーストリデューサ、3次元YC分離回路、ノイズリダクション回路も搭載し、実質上、2002年6月に発売された「MTV2000」の後継機に当たる。
 |
| パッケージ |
また、多くのテレビが備える「2画面同時表示機能」も利用できるようになった。これまでにも、一定間隔で更新するマルチ表示機能はあったが、MTV3000Wは2画面とも滑らかな動画表示を行なえる点で新しい。
さらに、従来シリーズでは排他選択式だった「3次元YC分離」と「3次元ノイズリダクション」が併用できるようになったのもポイント。画質に定評あるシリーズだけに、W3Dモードについてはダブルチューナ以上に期待している読者も多いだろう。
ソフトは、MTV1200HXから標準添付となった「FEATHER G-Spec.」。2画面表示やW3Dモードに対応したVer.3.0が付属する。FEATHER G-Spec.については、以前週刊デバイス・バイキングで取り上げたので、そちらを参照していただきたい。また、MTVシリーズ専用のリモコン「CRM-1」にも対応している。
2画面表示するには、カード上の2つのチューナそれぞれにアンテナ線をつなぐ必要がある。一般的に、電気のコンセントは複数あっても、アンテナの引き込みが複数ある部屋は少ない。そのため、アンテナ分配器を使用するケースも多いだろう。分配による損失も考えられるので、カノープスでは、場合によってはブースタの使用を勧めている。
なおカード上には、従来のMTVシリーズにはなかった電源コネクタが付いてるが、接続しなくても動作は可能。同社では「接続することでより安定した動作が可能になる」と説明している。
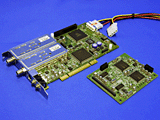 |
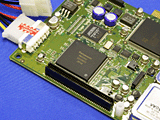 |
 |
| 基板の上部を外したところ。DSPなども2系統搭載している | エンコーダチップは松下電器製「MN85560」。MTV2000と同じものを採用 | 左からアンテナ入力×2、外部映像入力端子、ライン入力、ライン出力 |
■ ファイルとライブ映像の同時表示は不可能
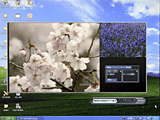 |
| 2画面モードの状態。左側がメインスクリーン、右側上部がサブスクリーン。サブスクリーンの下にあるのが2画面コントロールパネル |
1画面モードと2画面モードの切り替えは、リモコンを模した「FEATHER」上のL3ボタンで行なう。Pentium 4 1.6GHz、256MBのテストマシンの場合、1秒前後で切り替えることができた。
2画面モード時のウィンドウは、左が「メインウィンドウ」、右が「サブウィンドウ」と名づけられている。サブウィンドウはメインウィンドウのほぼ4分の1の大きさで、メインとサブの位置関係や、大小関係は変更できない。選択可能な表示解像度は720×480/640×480/320×240/160×120ドット。ただし、解像度を指定できるのはメインウィンドウだけで、サブウィンドウの解像度はメインウィンドウに追随して変化する。フル画面での2画面表示も可能だが、この場合もメイン、サブの大小関係は固定されたままだ。
メイン、サブそれぞれのチャンネル切り替えは、ホイール付きマウスだと簡単に行なえる。メイン、サブとも表示領域の右半分にマウスカーソルを持って行くとカーソルが変化し、「CH」と表記されたカーソルになる。その状態でホイールを動かすと、チャンネルが変更される。一方、左半分の領域では、同じ操作でボリュームを調整できる。FEATHER G-Spec.の軽快さも手伝ってか、チャンネル選択時の待ち時間はほとんどない。直感的で、パソコンならではの使いやすいインターフェイスだと感じた。
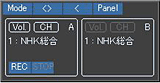 |
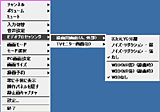 |
| 2画面コントロールパネル。メインウィンドウ、サブウィンドウのどちらで録画が行なわれているか確認できる。ディスプレイ上のどこにでも配置が可能 | メインウィンドウ、サブウィンドウはそれぞれ画質を調整できる。「W3D」が選べるのはメインウィンドウのみ |
しかし、マウスにホイールがない場合、若干煩雑な操作を強いられる。チャンネル選択の場合、2画面モードにすると現れる「2画面コントロールパネル」上で、メインなら左側、サブなら右側の「CH」ボタンをクリックし、その後FEATHER上のテンキー、またはカーソルボタンの左右で変更する。ボリュームは2画面コントロールパネルの「VOL」をクリック、その後カーソルボタンの上下で調整が可能。変えたい画面をリモコンのカーソルキーで指定できるテレビの2画面機能に比べると、慣れるまで多少とまどいを感じる。なお、CRM-1の場合は、リモコン下部のP3でチャンネルフォーカス、P3ボタンで音声フォーカスになる。
なお、メイン、サブのアスペクト比の変更は可能。ただし、メイン、サブとも同じアスペクト比になってしまう。また、解像度を「自動」にすると、2画面状態の場合、最小で126×96ドット程度まで縮小できる(枠などを含む)。
録画操作を行なうと、メインウィンドウに表示中の番組が録画される。録画中の番組表示をサブウィンドウに移したい場合は、2画面コントロールパネルの「<>」ボタンをクリックする。サブウィンドウの番組と、メインウィンドウの録画映像が交換され、その後1画面モードにすれば、いわゆる「裏番組視聴」の状態になる。逆に、サブウィンドウの番組を録画したい場合は、メインウィンドウに表示させる必要がある。
なお、録画ファイルの再生時は、強制的に1画面モードになる。つまり、「録画した番組を確認しながら、放送中の番組を視聴する」といった使い方はできない。また、タイムシフトや追いかけ再生も1画面モードでしか動作せず、自動的に1画面モードに移行する。外部入力の映像は、1画面モード、またはメインウィンドウにのみ表示が可能だ。
「ビデオをつないだテレビの2画面表示機能」だと考えると、意外に制限が多いことに気付く。普段からテレビの2画面表示機能を多用している人ほど、違和感を受けるかもしれない。メイン、サブで表示できるものを表にしてみたので参考にして欲しい。
| 2画面モード | 1画面 モード |
||
|---|---|---|---|
| メイン | サブ | ||
| 放送中の番組 | ○ | ○ | ○ |
| 外部ビデオ入力 | ○ | × | ○ |
| 録画中の番組 | ○ | ○ | ○ |
| 録画中の裏番組 | ○ | ○ | ○ |
| 録画中の外部ビデオ入力 | ○ | × | ○ |
| 録画ファイル | × | × | ○ |
| タイムシフト/追いかけ再生 | × | × | ○ |
■ W3Dモードは効果あり。ただし1画面モードのみ
デジタル3次元YC分離とノイズリダクションを併用できるW3Dモードは、1画面モードでのみ動作する。そのため、設定メニュー中の「W3Dを使用する」にチェックを入れていても、2画面モードだとW3Dモードが適用されない。2画面の利便性をとるか、W3Dの高画質をとるかの2者択一になる。
W3Dモードは、「W3D(弱)」と「W3D(強)」の2種類が選択できる。2つの違いはノイズリダクションのかかり具合で、非W3D時の「ノイズダクション(弱)」、「ノイズリダクション(強)」の効き具合とほぼ同じだ。W3Dモードにすると、確かにノイズがかなり軽減される。ゴーストリデューサも搭載しているので、録画画質に関しては問題ないレベルといっていいだろう。
なお、「W3Dモードを使用する」にチェックを入れると、「1画面モードはW3D(強)」、「2画面モードは3次元YC」といった具合に、モードごとに異なるビデオプロセッシングを設定できる。この場合、2画面状態で録画を開始すると、「W3D(強)」ではなく、「3次元YC」で録画されてしまう。また、「W3Dモードを使用する」にチェックを入れ、2画面モードの状態で予約録画が始まると、2画面モードのまま録画されてしまう。つまり、この場合もW3Dモードでの録画が適用されないことになる。
■ まとめ
録画中の裏番組が視聴できるようになったのは、テレビキャプチャカードとして大きな進歩。家電製品でいえば「テレビデオ」と同じ使い勝手を再現できる。また、W3Dによる高画質やすばやい操作感を考えると、テレビキャプチャカードとしてのレベルも高い。
しかし、新フィーチャーの2画面表示については不満な点がいくつかある。まず、サブウィンドウをメインウィンドウと同じ大きさにできない点。また、ホイールのないマウスだと、音声フォーカス、チャンネルフォーカスが直感的にわかりにくい。何よりも、アンテナ線を2系統入力する必要があるのは、テレビでは考えられない仕様だ。もっとも、信号をカード上で分配するより、外部の分配器を使った方が画質的には有利なのかもしれない。
また、放送中の映像と録画ファイルの同時表示に対応していないのは不便を感じる。予約録画が主体のユーザーにとって使い勝手が良くない。エンコーダチップの価格やCPUパワーの問題もあるが、2番組同時録画も含め、今後の展開に期待したい。
なお、カノープスによると、MatroxのG400/G450ビデオチップ搭載カードやIntel製グラフィックチップセット搭載マザーボードのVGA機能では2画面表示が行なえない。動作確認済みのビデオカードは、同社サイト内の「2画面表示モードの動作について」に公開されている。
| 受信可能チャンネル | VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV C13~C35 | |
| MPEGエンコード部 | 記録解像度 | 720×480/352×480/352×240ドット |
| 映像ビットレート | 2~15Mbps(MPEG-2) 1~1.8Mbps(MPEG-1) |
|
| GOP構成 | IBBP、またはIフレームのみ | |
| 音声圧縮 | MPEG-1 Layer 2、リニアPCM | |
| 音声ビットレート | 128/160/192/224/256/320/384kbps | |
| 入出力端子 | RF×2(F型コネクタ)、ミニDIN×1(S映像/コンポジット)、ライン入力(ステレオミニ)×1、ライン出力(ステレオミニ)×1 | |
| カードサイズ | 183×107mm | |
□カノープスのホームページ
http://www.canopus.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.canopus.co.jp/press/2003/mtv3000w.htm
□製品情報
http://www.canopus.co.jp/catalog/mtv3000/mtv3000w_index.htm
□関連記事
【2月15日】TVチューナー2個搭載のキャプチャカード「MTV3000W」登場(AKIBA PC Hotline!)
世界初のダブルチューナー搭載、ただし裏番組録画は不可
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030215/mt3000w.html
【1月15日】カノープス、世界初のWチューナ搭載キャプチャカード「MTV3000W」
-2番組同時表示や、3次元Y/C分離とNRの併用が可能に
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030115/canopus.htm
【2002年12月13日】【デバ】新ソフト「Feather G-Spec.」と小型化で正常進化した超人気モデルの後継製品
カノープス「MTV1200HX」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20021213/dev006.htm
(2003年2月20日)
[AV Watch編集部/orimoto@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|