 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第70回:50型フルHD「VIERA」はコントラストで勝負 ~ プラズマもフルHD時代。「松下 TH-50PZ600」 ~ |
32型以下を液晶、37型以上の大画面サイズをプラズマで製品展開するパナソニックの薄型テレビ「VIERA」シリーズ。しかし、「画素セルの微細化が難しい」→「高解像度化に伴い開口率が低下」→「適切な輝度が確保できない」というプラズマの構造上の制約から、1,920×1,080ドットのフルハイビジョン解像度のVIERAは昨年11月に発売された「TH-65PX500」のみ、というラインナップとなっていた。
そして待つこと約1年、ついにフルHDプラズマのラインナップ拡充が行なわれた。民生向け市販製品として世界最大の103V型の「TH-103PZ600」を筆頭に、2代目の65V型モデル「TH-65PZ600」が登場。そして注目は、多くのユーザーに購入意欲をそそらせることになるだろう、現実的な画面サイズの50V型「TH-50PZ600」と58V型「TH-58PZ600」の2製品だ。
今回の大画面☆マニアでは、50V型モデルの「TH-50PZ600」を評価した。
 |
 |
| VIERA PZ600シリーズ | TH-50PZ600 |
■ 設置性チェック
~オプションで多様な設置に対応。消費電力は598W
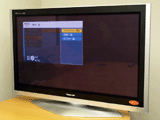 |
| TH-50PZ600 |
外形寸法で1,266×95×802mm(幅×奥行き×高さ)、画面表示サイズは1,106×622mm(幅×高さ)で、額縁の太さはそこそこある。運搬用の取っ手は背面の下部左右にあるが、1m近く離れているうえ、本体重量が約48kgもあるので一人で持つのは不可能だ。今回は成人男性2人で階上の評価室へ階段でなんとか運ぶことはできたが、設置は2人以上で行なうべきだ。
今回の評価では設置スタンドとして、純正オプションとして設定されている据え置きスタンド「TY-ST50PX600」(24,150円)を利用した。48kgを支えるスタンドだけにかなり堅固な作りになっており、スタンドだけでも10kg以上の重さがある。スタンドの組み付けは、設置場所近辺で行なった方がいい。
なお、このスタンド自身にはスイーベル機構がないので、設置後、スタンドを固定したままの画面向きの変更は出来ない。設置位置や設置向きには事前に入念なシミュレーションをしておきたい。
 |
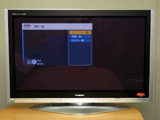 |
| 50V型という画面サイズ、なおかつチューナー一体型という事で本体重量は48kgとかなり重い | 「TY-ST50OX600」との組み合わせ。画面もでかいがスタンドも大きい。「どこに置くか」に加え、「どう置くか」のシミュレーションも入念にすべし |
多くのユーザーは床置きではなく、何らかのテレビ台の上に置くことになるだろう。スタンドの横幅は、平均的なプラズマテレビ向けスタンドよりもやや幅広く、888mmもあるので、32インチクラスのブラウン管テレビ向けの設置台では左右にはみ出してしまう。奥行きも399mmあるので、設置台についても事前に検討しておく必要がある。
ちなみに、ブラウン管テレビは32インチクラスで50kg以上あるので、このクラスのブラウン管テレビを置けている台であれば流用もできるだろう。新たに設置台の購入を考えている場合、純正オプションの「TY-S50PX600」(79,800円)も検討してもいいかもしれない。TY-S50PX600にはキャスターが付いているので移動が可能となる。
壁掛け設置にも対応しており、リジッド設置の「TY-WK42PV3U」(44,100円)と角度調整式設置対応の「TY-WK42PR3U」(52,500円)の2タイプが用意されている。設置金具と合わせて総重量50kgのものを壁に固定することになるので、かなり強固な壁補強が必要になるのはいうまでもない。
 |
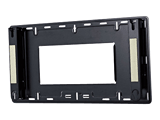 |
| スタンドと設置台が一体化した「TY-S50PX600」 | 角度調整式壁掛け設置金具「TY-WK42PR2U」 |
背面には6個の冷却ファンが取り付けられており、稼働中には回転しているが、非常に静かだ。一方で、視聴を妨げるほどではないにせよ、プラズマ特有の「ジー」という動作音は耳を澄ますと聞こえる。電動ファンよりもプラズマノイズの「ジー」という音の方が聞こえるというのは、初期のPDPからするとちょっと感慨深い。
消費電力は公称598W。同じ50V型の1,366×768ドット(WXGA)モデルのTH-50PX600の455Wと比較すると約150Wも高い。これはTH-50PZ600が、画面サイズは同じ50V型でも、画素駆動用のドライバモジュールがTH-50PZ600の倍の200万画素を駆動することが大きな要因となっている(ドライバブロックが2倍)。
約600Wの消費電力というと10~12畳クラス向けのエアコン(冷房能力2.8kW)程度と同じだ。見落としがちだが、電力会社の契約アンペア数を確認しておかないと、エアコンと同時に使うとブレーカーが落ちると言うことにもなりかねない。
■ 接続性チェック
~HDMI 3系統装備。メインモニタとしてのポテンシャルも十分
さすがは最新モデルの上級機。テレビ製品でありながらも、接続端子はモニタ並に充実している。接続端子は背面パネルと、抜き差し頻度の高い機器を接続するための前面パネルにまとめられている。
 |
| 背面の接続端子パネル。付属の専用カバーで覆って隠すことができる |
まずは背面パネルを見てみよう。目を惹くのはなんといっても2系統のHDMI端子だ。Blu-rayやHD DVDといった次世代DVD機器は、HDMIを前提としていることもあり、2系統装備はユーザーにとってもうれしい要素だ。
アナログビデオ入力端子は3系統。3系統全てにコンポジットビデオ入力とステレオアナログ音声入力端子があり、このうち2系統は排他接続扱いでS2ビデオ入力も配備されている。
ビデオ入力2、3のアナログステレオ音声入力は前述のHDMI[1、2]のアナログ音声入力としても兼用利用できる。その際には「初期設定」-「ビデオ入力接続設定」-「HDMI音声入力設定」を「アナログ」とする必要がある(デフォルトは音声も「HDMI」伝送設定)。
通常、TH-50PZ600へHDMI伝送された5.1chや7.1ch音声はミックスダウンされて再生されてしまうが、このアナログ音声出力機能を使えば、AVアンプからセリフ用センターチャンネルのみを意図的にTH-50PZ600のスピーカーから出力させ、ここをマルチスピーカシステムのセンタースピーカーに割り当てるといった設定も可能だろう。
コンポーネントビデオ入力としてはD4入力端子を2系統装備する。PC入力はD-Sub15ピン端子によるアナログRGB入力で、ステレオミニプラグ端子による専用の音声入力も備え、別途PCスピーカーを用意しなくてもTH-50OZ600側のスピーカーでPCサウンドを楽しめる。最近ではPCをジュークボックス的に活用したり、ビデオプレイヤー的に活用する人が増えているが、そうした用途にはうってつけの機能だといえる。
デジタルRGB接続用のDVI端子は備えていないが、市販のHDMI-DVI変換アダプタなどを用いてPC接続も行なえた。これについての詳細は後述する。
光デジタル音声出力端子も装備。また、視聴中や予約録画指定された番組の出力を行なう、アナログビデオ出力(モニター出力)も1系統装備し、S2映像、コンポジット、アナログ音声の各出力が利用可能。
アンテナ入力端子は地上アナログ入力、地上デジタル入力、BSデジタル/110度CSデジタル入力の3系統を実装。商品セットにはアンテナ分配機付ケーブルが付属してくるので、地上波とBS波を混合しているユーザーはこれを活用して接続するといい。チューナモジュールの配置や設計上の問題からか、地上アナログ入力はデジタル放送のアンテナ入力から離れた位置にあるのが不思議な感じがする。
i.LINK端子は2系統装備。テレビ向けの生活情報ネットワークサービス「Tナビ」用のLAN端子も装備する。
前面パネルにはステレオアナログ音声入力とコンポジットビデオ端子に加え、なんと、ここにもHDMI端子を装備する。PLAYSTATION 3はHDMI端子を装備し、最近はPCでもHDMIを備えた製品が増えてきている。こうした抜き差し頻度の高い機器のHDMI対応増加を見据えての装備だろう。
ヘッドフォン端子は左右に並ぶ格好で2系統が実装されており、それぞれ左右2画面表示の音声が聞けるようになっている。二人で異なるコンテンツを楽しむ際、自身が楽しんでいるコンテンツの音声だけを聞くことができる。
接続端子ではないが、前面にはSDカードスロットも装備する。現時点でSDHC 4GBまでの容量に対応しており、3,840×2,160ドットまでのJPEG静止画像、SD-Viedeo規格Ver.1.2のMPEG-2動画の再生が可能となっている。
全体として接続端子には妥協が無く、その接続性の高さは、テレビとしてだけではなく、ホームシアターなどにおけるメインモニターとしてみても必要十分だ。AV機器への接続性を配慮しただけでなく、PC接続機能にも対応し、SDカードスロットにも対応するといった徹底振りは、あらゆるメディアを表示するためのテレビを超えたマルチユースディプレイとして松下が志向していると感じる。
 |
 |
| 面側、中央下部の扉を開くと前面接続端子パネルが現れる。ここにもHDMI端子がある | 前面右下部にあるSDカードスロットは、静止画や動画を記録したSDカードの再生に対応する |
■ 操作性チェック
~デジタル放送2画面表示。電子マニュアルも装備
 |
| リモコンは最近のテレビにしては大きいボタンを採用している。ボタンの個数よりもみやすさとシンプルさを重視したデザイン |
前面の接続端子パネルの左横にはいくつかのボタンがレイアウトされていて、ここでチャンネル操作、音量調整、入力切り替えやメニュー操作が行なえる。リモコンが見つからない時でも、ここを直接操作することでもTH-50PZ600の基本操作は行なえる。
リモコンは銀色のプラスチックボディが印象的で、特徴的だ。一見縦長のバー形状なのかと思いきや、左側にせり出した部位があり、そこに特殊機能操作用やメニュー操作ボタンがレイアウトされている。
リモコンの大きさは、最近の高機能テレビとしては標準的。しかしボタンは大きめで、印字されている文字も大きく読みやすい。[アナログ][デジタル][BS][CS]といった放送種別ボタンは押すと赤い光で点滅する発光機構が搭載されているが、それ以外の発光部はなし。シャープのAQUOSシリーズなど、一部のメーカーのリモコンではチャンネル切り替えの数字キーなどに蓄光式の発光ボタンを備えたものもある。画面がやや暗いこともあり、照明を落とした環境で使われることも多いはず。リモコンには発光ボタンをもう少し増やしても良かったような気がする。
簡単にリモコンの主要ボタンから機能を紹介すると、[入力切換]は前面や背面の接続端子パネルに接続された外部機器からの入力映像へ切り替えるための操作ボタン。一度押すと入力切り換えメニューが呼び出され、その後はリモコン上の十字キーの上下で希望入力を選択するという操作系。連続で[入力切換]ボタンを押すことで順送り式の切換にも対応している。入力切換の所要時間はHDMI→地デジで約1.8秒、S2ビデオ→HDMIで約2.0秒と、標準的な早さといったところ。
[画面モード]ボタンはアスペクト比が、押すたびに順送り式に切り替わる。切換所要時間は約0.8秒でなかなかの速さ。用意されているアスペクト比モードは以下の通り。
| セルフワイド | 自動的にアスペクトモードを認識して最適なアスペクト比に切り換える |
|---|---|
| ノーマル | アスペクト比4:3映像のアスペクト比を維持して表示。左右に非表示の黒帯が出る |
| ジャスト | アスペクト比4:3映像の中央付近はアスペクト比を維持し、左右外郭付近を引き延ばして表示する。表示パネル全域を活用してなるべく違和感なく4:3映像を表示するためのモード |
| ズーム | アスペクト比4:3映像にレターボックス記録されたアスペクト比16:9映像を切り出してパネル全域に表示するためのモード |
| フル | パネル全域に映像を表示する。アスペクト比16:9映像向きのモード |
この他、ハイビジョン映像やデジタル放送視聴時の映像に黒帯がある場合に、これをクリップアウトして映像パネルに表示する「サイドカット」を組み合わせたアスペクトモードも搭載されている。
リモコン中央にはメニュー操作用の十字キー、[アナログ][デジタル][BS][CS]といた放送種別切換ボタン、チャンネル切換用の数字キーなどがレイアウトされている。使用頻度の高いチャンネル切換用の数字キーや音量調整用の[+][-]ボタンは大きく押しやすい。チャンネル切換の所要時間は地デジ、BSデジタル、共に約2.0秒で、こちらも早さは標準的。
[元の画面]ボタンは、オンラインマニュアルやメニュー画面、PC画面や各種ビデオ入力などの画面から、テレビ画面へ一発復帰する操作を行なうものだ。他人に見られたくない映像や情報を見ていた時に、とっさのパニックボタンとしても使えるだろう。
[サウンド]ボタンは音声再生モードの切換を行ない、用意されているサウンドモードは以下の5つ。
| スタンダード | 全音域をフラットに再生する標準的なモード |
|---|---|
| スタジアム | ステレオ感を強調した音場モード。コンサートなどのライブ映像向け |
| ミュージック | 中音域から高音域に重点をおいた再生特性になる。いわゆるドンシャリ系ではなく全体的にはバランスが取れており汎用性は高い |
| シネマ | ワイド感溢れる音場モード。ワイド感の強さはスタジアムに似ているが定位がしっかりしているのが特徴。中音域が強めでセリフも聞きやすい |
| ニュース | 人の声の音域をやや強調気味にしたモード。ニュース番組はもちろん、バラエティ番組との相性も良い |
サウンド性能は、フルレンジユニットとウーハーの2ウェイスピーカーを左右に内蔵する構成だが、この音質がかなり優秀だ。音量を高めに設定しても、低音域から高音域までのバランスが崩れず、ビビリ音もない。12畳程度までの部屋ならば、外部スピーカー無しで音を部屋に満たすことができるほどパワフルだ。前述したように、マルチスピーカーのサラウンドシステムに、TH-50PZ600のスピーカーを参加させるのは悪くない。
リモコンの左上から張り出した黒いボタン群についても着目したいのが[?]と表記されたガイドボタン。パソコンでいうヘルプボタンに相当するもので、メニュー操作でよく分からない調整項目があった時、この[?]ボタンを押すと、電子マニュアルを画面に呼び出してくれるのだ。各ページはフルHDパネルを前提にした情報量の高い作りで見やすい。その代わり、付属の紙マニュアルの情報量が少ない。例えば前述のアスペクト比モードの具体的な映り方など説明は紙マニュアルには載っておらず、この電子マニュアルにしか掲載されていない。ついにテレビ製品にもマニュアルの電子化が押し寄せたと言うことだろうか。
 |
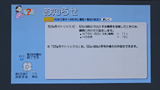 |
| [?]ボタンを押すことで呼び出されるオンラインマニュアル。情報量としては十分。紙マニュアルは情報量不足 | |
 |
| 2画面を等サイズで表示。2画面表示はピクチャー・イン・ピクチャー・モードはなく、このサイド・バイ・サイド・モードに限定されている |
リモコン最下部は蓋が開くようになっていて、これを開くことで、より高度な操作を行なうためのボタンへのアクセスできる。
最近の薄型テレビでは標準機能ともいえる「2画面表示機能」の操作ボタンもここにある。[2画面]ボタンを押すことで2画面表示モードに移行する。
HDMI入力同士の組み合わせが不可であること、PC画面、SDカード画面、電子マニュアル画面と組み合わせられない以外に制限はなく、2画面の組み合わせの自由度は比較的高い。アナログRGB接続したPC画面は2画面にできないが、HDMI経由でデジタルRGB接続した場合は2画面表示も可能だ。TH-50PZ600はデジタルチューナーを2基搭載しているため、異なる地デジ番組の2画面表示も行なえる。
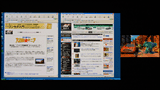 |
| 2画面を大小サイズで表示 |
意外なことに、TH-50PZ600の2画面表示モードは左右に画面を並べたサイド・バイ・サイド(SbS)表示に限定されており、いわゆる親子画面といわれるピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)表示には対応していない。2画面表示モード状態で、通常時アスペクト比切換ボタンだった[画面モード]を押すと左右の画面の大きさの比率を変えることが可能。[左右入替]ボタンは読んで字のごとく2画面の表示位置を入れ替えるもの。[右画面操作]では、このボタンを押したあとに、[入力切換]ボタンを押したり、数字キーを押すことで右側画面の入力変更やチャンネル変更を行うことができる。
2画面表示時、スピーカーからの音声は片側画面のものからしか聞こえてこないが、どちらの画面の音声を出すかはメニューを呼び出して操作しないと変更できない。これは少々不便であり、改善が望まれる。
リモコンを使っていて気になったことが3点ある。1つは、最近の他社製品と比較するとリモコンの受光感度があまりよくないというところ。リモコンをキッチリ水平に画面正面に向けていないと反応してくれないため、横になって見ているときや、斜め見している時などは、上手く操作を受け付けてくれず結構ストレスが溜まる。
また、2点目は、メニュー操作のレスポンスが遅いという点。メニュー上のカーソル移動やページ切換がモタモタしている。特に電子マニュアルが遅い。次期モデルでは高速化を期待したいところだ。
3点目は、プリセット画調モードの切換がメニュー操作によってしか行なえないという点。マルチユースディスプレイとしてTH-50PZ600の活用を考えている中級者以上のユーザーにとって、これはツライ。
チャンネルを切り換えて番組ジャンルが異なった場合など、例えばスポーツ中継を見たあとに映画を見る時などはプリセット画調モードの切換をしたくなるものだ。プリセット画調モードの切り換え操作のたびに、感度のあまりよくないリモコンを使って、遅いメニュー操作を駆使して毎回変更操作をしなければならないのはストレスを感じる。せめて順送りでいいから切換操作ボタンを設けて欲しかったと思う。
画調パラメータの調整はメニューの「画質の調整」から行なうことになる。基本的な画調傾向は「映像メニュー」で指定する「スタンダード」「シネマ」「ダイナミック」の3つのプリセット画調モードから選ぶことになり、そこからさらに調整したい場合には、「ピクチャー(コントラスト)」「黒レベル(ブライトネス)」「色の濃さ」「色合い」「シャープネス」といた基本パラメータを追い込んでいくことになる。「色温度」も調整可能だがK(ケルビン指定)ではなく高中低の3段階指定方式。あくまで見た感じでの推測だが、低が6,500K程度、中が7,500K前後、高が9,000K前後といったところだろう。
この他、VIERA特有の画調調整パラメータも用意されている。「ビビッド」は発色の傾向を記憶色に合わせる形でエンハンスするもの。青や緑がより鮮烈になり南国の風景の映像やCGアニメなどとの相性がいい。
「明るさオート」は部屋の明るさに応じて最適な輝度で画面をドライブするモード。「オン」とすると、たとえば暗い部屋では輝度を控えめにするようになり、省電力に貢献する。
この他、プリセット画調モードが「シネマ」「ユーザー」の時に限り、「テクニカル」を「入」設定とすることで、上級者用の画調パラメータ項目が出現するようになる。出現項目は輝度モードの「輝度設定」、縦線の輪郭強調度合いを設定する「輪郭強調」、ガンマカーブの変更を行なう「ガンマ補正」、中明部よりも暗い階調の沈み込ませ加減を設定する「黒伸張」、赤(R)と青(B)の発色におけるオフセットとゲインの設定を行なう「R・Bドライブ/R・Bカットオフ」、最明部の階調補正を行なう「明るさ補正」など。
ユーザーモードのメモリは「ユーザー」として各入力系統ごとに1個ずつ用意されているので、調整の追い込みはこのメモリーを活用したい。「輝度設定」はお好みで、「輪郭強調」は「オフ」、「ガンマ補正」は「中」、「黒伸張」は0のまま、「R/Bドライブ」と「R/Bカットオフ」はそのまま「明るさ補正」は「オン」が個人的なおススメの設定だ。
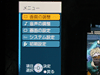 |
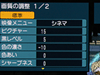 |
 |
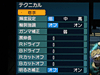 |
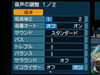 |
| メニュー起動画面 | 「画質の調整」 1ページ目 | 「画質の調整」 2ページ目 | 上級者向けの画調設定メニュー「テクニカル」 | 「音声の調整」 |
 |
 |
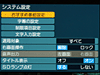 |
 |
|
| 「画面の設定」1ページ目。ノイズ低減機能やオーバースキャン設定などを行なう | 「画面の設定」2ページ目 | 「システム設定」 | 「初期設定」 |
■画質チェック
~やや暗くはなったが、発色/階調が劇的に改善
TH-50PZ600の映像パネルはパナソニックの50V型としては初めての1,920×1,080ドット、フルハイビジョン解像度パネルとなる。
プラズマパネルは画素隔壁の微細化に物理的限界があり、高解像度化が難しいとされてきた。しかし、画素成形技術の向上や駆動方式の改良などの技術的ブレークスルーにより、パナソニックではついに50V型のフルハイビジョン解像度のプラズマパネルの開発に成功したのだという。
 |
| 非常に画素密度が高く、サブピクセルの分離感はほとんど感じられない |
パイオニアの「高純度クリスタル層」のように、その“新技術”にはキャッチーな名前を打ち出しておらず、カタログにも技術概念の説明はない。しかし、パナソニック広報担当によれば「PZ600シリーズのパネルはパナソニックのプラズマ技術の集大成」というほどで、解像度が上がっただけでなく、パネル世代としてもPX60/600よりも新しいという。
実際に表示を見てみると気が付くのは、圧倒的な高精細感だ。一般的なプラズマパネルでは、RGB(赤青緑)のサブピクセルの分離感が気になったものだが、TH-50PZ600のパネルはサブピクセルが非常に緻密な配列になっており近くで見ても不自然さのないフルカラー表示が得られていた。
ただし、従来のプラズマテレビのイメージから比べるとTH-50PZ600はやや暗い。同サイズの1,366×768ドット/WXGAクラスのプラズマと比較するとその対比がよく分かる。最新の同型クラスの液晶テレビよりも暗い。
これは、技術ブレークスルーがあったとはいえ、高解像度化に伴い画素開口率が低下しているためだ。同じ50V型でWXGA機とTH-50PZ600のようなフルHD機と比較した場合、TH-50PZ600は単純計算で画素数は2倍になっており、画素隔壁の幅を同じと仮定すれば開口率は半分となるわけで、発光効率も半分になってしまう。技術ブレークスルーでも、さすがに発光効率を2倍に高めることはできなかったようで、その暗さはここから来るものだろう。
いずれにせよ、表示映像に「絶対的な輝度を求める」のであれば、より画面サイズの大きく、そのため画素開口率も高い「TH-58PZ600」や「TH-65PZ600」を検討した方がいい。
また、公称コントラスト性能は4,000:1を達成しているとされるが、これは前述の技術ブレークスルーが功を奏した結果である。画素セル内の放電速度を高速化したことで、黒表示時の予備放電の「種火」を抑えることにつながり、これにより黒の沈み込みを増したことで、高コントラスト化が実現されているのだ。実際に表示映像を見ると、そのコントラスト性能の優秀さには納得する。
輝度はやや暗いとはいえ、発色はプラズマとしてはかなり良好。特に青と緑の純色系の深みと鋭さが素晴らしい。プラズマの苦手な赤については朱色の傾向が見られ及第点といったところだが、それでもプラズマとしては優秀な方だと思う。
映像全体としては記憶色再現に振ったパナソニックらしい鮮烈な色遣いで、一般ユーザーの満足度は高いはずだ。過度な派手さが鼻につくこともないく、ブラウン管に近い色遣いを目指しているような感じだ。
なお、TH-50PZ600は、色域としてNTSC規格だけではなく、ハイビジョン規格(ITU-R BT.709)をカバーすることを前提に設計されたという。デジタル放送をはじめとするハイビジョン映像は、青方向に広い色域を前提とした色表現になっているので、これを再現しようという狙いだ。見慣れた映像ソースでも、TH-50PZ600で見ると、空や水の表現に深みが感じられ、「なるほど、こちらの方が正しいかも知れない」という気にさせられる。ちなみに、ITU-R BT.709の色域とsRGBの色域は同一のものだ。
このハイビジョン色域はハイビジョン映像のためのものだが、TH-50PZ600では、SD映像に対しても強制適用できるオプションを用意している。それが「525p色マトリックス」機能だ。これを「2」として有効にすると本来ならばNTSC色域で表示されるべきSD映像がハイビジョン色域で描き出されるようになり青に深みが出るようになる。実際に試してみたが不自然さはないので、常用してもいいだろう。
色再現に関してはもう一つ、「ビビッドカラークリエーション」機能と呼ばれる機能を搭載している。輝度と色合いのバランスに配慮したながら、青や緑を記憶色再現に振って色補正を行なうものだ。悪くはないのだが、ややわざとらしい感触もあるので、積極的な使用はお勧めはしないが、シニア層には歓迎されるかもしれない。
階調表現も、以前のプラズマVIERAから飛躍的に改善されている。プラズマ特有の暗部階調のディザリングノイズは、皆無ではないものの、劇的に低減されており、「暗い色」が、ただのざわつきではなく、ちゃんと「発色」していることが知覚できる。これは、前述したような画素駆動の高速化と、動的ガンマ補正の演算などを従来の最大14ビット精度から、最大16ビット精度に拡張したこととの相乗効果によるものだろう。
ただ、最暗部付近の階調は意図的に沈ませており、このあたりの階調性はパイオニアの高純度クリスタル層パネルや、液晶に一歩及ばない。コントラスト重視の画作りのためなのかもしれないが、暗部階調によりリニア感を求めるモニター志向なユーザーは黒レベルを若干持ち上げる調整を行なった方がよいかも知れない。
 |
 |
| 画調モード「スタンダード」、ビビッド「オフ」 | 画調モード「スタンダード」、ビビッド「オン」。緑に深みが増していることが分かる。赤にはほとんど影響なし |
| DVDビデオ「Mr.インクレディブル」 (C)2005Disney/Pixar |
|
【各種高画質化機能のインプレッション】
●NR 画面全体を覆う高周波のざわつきを平滑化する働きをするフィルタ。強めにかけると陰影のディテールが潰れ気味になるので、気にならないときは外しておくべき
デジタル放送にも活用できるが、どちらかといえば地上アナログ放送向けの機能だ。デジタル放送やDVDなどのデジタルAV機器からの映像に対しては基本オフでいいだろう。
●MPEG NR デジタル放送やDVDなどのデジタルAV機器向けのノイズフィルタ。エンコード時のビットレート不足で見えてしまう矩形状の境界模様「ブロックノイズ」を低減する。デジタル放送でも(特に地デジ)、動きの激しいスポーツ中継では、比較的よくブロックノイズは見かけるので用途に応じて使うといい。常用するならば「弱」か「中」程度だろう。「強」設定にすると色ディテールが死に気味になるので注意。
●モスキートNR デジタル放送やデジタルAV機器のMPEG映像特有のノイズである「モスキートノイズ」を低減するためのフィルタ。ブロックノイズとは違い、色境界付近で慢性的に見える湯気のような、半透明の毛羽立ちのような揺らぎを低減できる。こちらも強く掛けすぎると色ディテールが潰れて見た目としての解像感が低くなってしまうので、常用するならば「弱」か「中」程度だろう。
【映像ソースごとのインプレッション】
●Sビデオ(NEC PK-AX20、Sビデオ接続) SDビデオのスケーリング品質が非常に高い。ぼやけも少なく、エッジも鋭く出ており、固定画素系への拡大表示には思えないほど美しい。動きのある映像でもコーミングも見えず、プログレッシブ化の品質も高い。
●DVDビデオ(DENON DVD-2910、HDMI接続) 最暗部付近の階調表現にはプラズマ特有のざわつき感はまだあるが、少し離れてみれば気にならないというレベル。
色深度が驚くほど深く、中明部以下から暗部においても、ちゃんとした色の深みが感じられる色再現能力は素晴らしい。
MPEG NRやモスキートノイズ低減機能といった各種ノイズリダクション機能の効果も優秀で、DVDビデオであることを忘れてしまいそうなほど、フレーム単位で映像が美しい。
惜しむらくは、やはり、明るい部屋で見るには最明部に力不足を感じるところか。やはり、同サイズのWXGA対応プラズマや液晶と比べると暗めの印象が拭えない。部屋を暗くすれば逆にしっとりとした味わいで楽しめるので、映画を見るときは照明を落とすことをお勧めする。
●デジタルハイビジョン放送(内蔵チューナ) フルHD解像度による表示はさすが圧巻。間引き感がないのは当然として、出演者達の服の布の縦横に交差する織り目までが見えたり、角度の浅い細い線描写でもぼやけやジャギーがなく、720pテレビとはやはり一線を画した解像感が得られている。
デジタル放送では、映像がMPEG-2伝送されているので、DVDなどと同様、ややもすれば、モスキートノイズが出たり、画面全体が早く動くシーンでブロックノイズが出たりするが、TH-50PZ600では、前述のノイズリダクション機能が効果的に働くためだろうか、かなり上手く低減されている。TH-50PZ600シリーズが初めてのデジタルテレビ製品というユーザーは、もしかすると、そうしたノイズの存在すら認知する機会すらないかもしれない。
画調モードは「スタンダード」が一番バランスがよいようだ。
●PC(NVIDIA GeForce6800Ultra/DVI-D接続) PCと接続は、アナログRGB(D-Sub15ピン)端子のほか、市販のDVI-HDMI変換アダプタを用いたデジタル接続も可能となっている。
今回、相性の問題からか、アナログRGB接続での正常表示が行なえず、デジタルRGB接続も1,920×1,080ドット/60HzのフルHD解像度でしか正常に表示できなかった。もっとも、最良条件である「デジタルRGB接続で、デスクトップ解像度とパネル解像度を一致させての表示」が実現できたので、画質評価での実害はない。
HDMI端子経由でPCを接続する際に注意すべきポイントは2つ。
1つはオーバースキャンを切らないと映像が微妙に拡大表示されパネル解像度と一致させた表示ができなくなるという点。これをキャンセルしてアンダースキャンに切り換えるには「画面の設定」-「HDサイズ」を「2」とすればよい。ちなみに、HDMI入力やデジタル放送の映像についても、同様の操作をするとスケーリングロジックの影響を低減できるため解像感が向上する場合がある。試してみるといい。
2つ目は「NR(ノイズリダクション)」「MPEG NR」「モスキートNR」 といった各種ノイズリダクション機能を切らないと、文字や映像に滲みやボケが出ることがあるという点。PC接続では有効にしてても意味がないのでカットしてしまおう。
PC接続をHDMI経由で行なおうと考えている人はこの2点に気をつければTH-50PZ600を50インチワイドの1,920×1,080ドットのPCディスプレイとして活用できるようになるはずだ。
●ゲーム(Xbox360/コンポーネント接続) 「プラズマは応答速度が速いので動画に強い」というのが定説になってはいるが、実際には、時間積分方式で色を知覚するプラズマテレビでは、ゲームのような随時視線を画面内に移動させる用途では色割れが知覚されることがある。
ところが、駆動が高速化されたTH-50PZ600では、この色割れがほとんど起こらない。今回は3Dカーレーシングゲームをプレイしてみたが全く違和感がない。TH-50PZ600はゲームプレイにおいても問題なく活用できると言える。
Xbox 360は720p映像の表示品質も文句なしで、ジャギーやぼやけもほとんどなく、ネイティブ解像度並の品質で表示できていた。
(C) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.Developed by Bizarre Creations Limited. (C) Bizarre Creations Limited 2006. All rights reserved.
■ まとめ
~お買い得感の面ではライバルを圧倒するフルHDプラズマ
TH-50PZ600の競合はといえば、やはり50V型でフルHDプラズマという括りで、本連載で紹介したパイオニア「PDP-5000EX」ということになるだろう。両者を簡単にだが比較してみよう。
まず画質は、さすがプラズマの命運をかけて登場してきただけあって、両者、特徴的な画作りになっており、優劣をつけがたい。傾向に関して言えば、バランスの良いナチュラルな発色なのがPDP-5000EXで、記憶色再現に振っているのがTH-50PZ600という感じか。TH-50PZ600の鮮烈な色合いはハイビジョン色域再現やビビッド・カラークリエーションに因るところが大きい。
色深度と階調表現能力に関してはPDP-5000EXの方が僅差ではあるが優っているように思える。カラーグラデーションの見え方はPDP-5000EXの方がなだらかで、暗部階調も、TH-50PZ600と比べても最暗部が埋もれずに的確に描けている。TH-50PZ600はややハイコントラストに振った画作りで、見た目としてパリリとした目に映えるようにするためか、暗部階調にパワーを割いていない。モニター調のPDP-5000EXに対して、万人ウケしそうなTH-50PZ600、といえる。
お買い得度においては、これは圧倒的にTH-50PZ600に軍配が上がる。パイオニアのPDP-5000EXがチューナ無しで実売価格が100万円近く、格安の通販サイトでも80万円程度。対して、TH-50PZ600はダブルチューナ内蔵で60万円以下、店舗によっては50万円を切っている。実質、PDP-5000EXはテレビというよりもディスプレイモニタなので、テレビとしての使い勝手を考えるとどうしてもTH-50PZ600の方が有利だろう。
上位モデルには58V型、65V型、103V型が用意されており、画素開口率の関係で基本的には画面が大きいほど画面が明るい。TH-50PZ600の暗さが気になった人は、そうした弱点がカバーされている上位モデルを検討するのもいいだろう。58V型が約70~80万円以下、65V型が80万~100万円弱となっているようだが、この50型との価格差は8インチ差、15インチ差という画面の大きさの差異だけでなく、画面の明るさも差として表れていると考えると、価格バランスは妥当に思えてくるかも知れない。
□松下電器のホームページ
http://panasonic.co.jp/
□ニュースリリース
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn060719-1/jn060719-1.html
□製品情報
http://panasonic.jp/viera/products/pz600/
□VIERAホームページ
http://viera.jp/index.html
□関連記事
【7月19日】松下、50/58/65/103型のフルHDプラズマ「VIERA」を投入
-103型は600万円前後。1080pHDMI×3やWチューナ搭載
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060719/pana1.htm
【6月29日】【大マ】“プラズマ究極画質”のフルHDモニター
~ 最高画質を使いこなせるか? 「パイオニア PDP-5000EX」 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060629/dg68.htm
【4月19日】パイオニア、50型フルHDプラズマモニターを6月に発売
-105万円。1080p対応で“世界最高画質”を目指す
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060419/pioneer1.htm
(2006年9月28日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 西川善司 | 大画面映像機器評論家兼テクニカルライター。大画面マニアで映画マニア。本誌ではInternational CES他をレポート。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。渡米のたびに米国盤DVDを大量に買い込むことが習慣化しており、映画DVDのタイトル所持数は1000を超える。 |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.





