 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
| 本田雅一のAVTrends |
スペック競争からニーズに応えた製品作りへ
-薄型化競争、BD普及など、今年の業界への期待
年初の恒例行事であるInternational CESも終わり、いよいよ今年1年の各社の取り組みの全体像が見えてきた感がある。今回はまず、全体を俯瞰して各カテゴリごとの大まかな状況を見返し、次回以降でさらに各分野のトレンドを掘り下げて今年のトレンドを追いかけてみることにしたい。
■ ニーズの多様化が進むテレビ
 |
| 最薄部3.44cmを実現したシャープの「AQUOS Xシリーズ」 |
CESのニュースに注目していた読者なら、今年は薄型テレビが数多く出展されていたことをご存じのことだろう。この流れはCESで始まったわけではなく、遡ると昨年のCEATECの時点で始まっており、昨年末の日立、そしてCES後のシャープと、ひとつの大きな流れに発展しつつある。
薄型化はもちろん、見た目に“カッコいい!”というデザイン面での利点もあるが、各メーカーの話を聞いていると、単に薄型になるメリットよりも、壁掛けを重視したユーザーが北米で多いところから、より簡単に壁掛けできるテレビとして、薄型軽量の製品を提案しはじめたというのが、実際の経緯のようだ。
北米では90%以上、ほぼ100%のHDTV購買者が壁掛け設置を検討しつつテレビ選びを行ない、実際に50%のバイヤーが壁掛けで設置を行なうという。住宅リフォームに関するお国事情の違いもあって、壁掛けニーズが最大消費地の北米で高いことが、薄型・軽量テレビの開発に繋がっている。各社がほぼ同時期に同じ提案をしているのも、実際にそうした声が販売店や消費者の生の声として上がってきているからに他ならない。
ただ、日本では壁に穴を空けて設置することに対する抵抗感や、ケーブルの引き回しなどの問題もあって、どこまで受け入れられるか未知数。純正スタンドを使っての設置ならば、ラックの奥行きなどの関係もあり、見た目に薄く見えるデザインにしておけばいいという考え方もある。ひとまずは電源さえ確保できれば簡易的な壁掛け設置も可能になるWireless HDの普及とセットで、超薄型化を考える必要があるだろう。
一方で無限大コントラストのプラズマ、4K2Kデバイスの展示など、未来に向けてさらに高画質・高品質という方向の展示もある。また、CESではあまり顕在化していなかったが、設置環境に合わせて自動的に画質を調整するといった、実利用環境で製品の実力を可能な限り発揮させるような工夫なども、今後のトレンドになっていくはずだ。
機能面ではフルHD化や液晶の倍速化、コントラストの(ある程度までの)改善など、カタログスペック上での機能、性能が一巡し、各地域ごとのテレビの使われ方、ユーザー層ごとのニーズの違いに合わせて、多様な製品作りが今後は求められるだろうし、実際の製品もそれに沿ったものになってくると思う。
 |
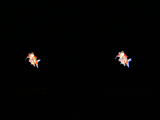 |
| ソニーの82型4K液晶ディスプレイ試作機 | パイオニアは超ハイコントラスト「KURO」をCESに出展 |
□関連記事
【1月24日】シャープ、業界最薄3.44cmの液晶テレビ「AQUOS X」
-フルHD倍速対応46/42/37型。チューナ外付け
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080124/sharp1.htm
【2008 International CESレポートリンク集】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/2008ces.htm
■ 北京オリンピック前にブレイクしそうなBDレコーダ
年始の「ワーナーブラザーズ、BD一本化」のニュース後、すっかり次世代光ディスクに纏わる論争も沈静化してきているが、日本市場で中心となっているレコーダ市場だけを見れば、昨年末からすでに決着は付いていた。これは以前にもこの連載で伝えたことだが、今後はBDレコーダが、DVDドライブ搭載ハードディスクレコーダに対して、どこまでシェアを伸ばせるかに、興味の対象が移ってきている。
 |
 |
| ソニー「BDZ-X90」 | 松下電器「DMR-BW900」 |
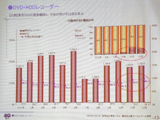 |
| BCNの年末商戦のレコーダ販売調査結果。約2割が次世代対応に |
昨年の年末商戦において、ハイビジョンレコーダ全体に対するBDレコーダの割合は、最終的に15%程度に落ち着いたようだ。個人的には20%程度と予測していたが、ソニーがかなり増産をかけたものの、松下電器は(年末ということもあり)部品調達で苦労して品切れが続き、かなり多くの生産を見込んでいたシャープの一部製品が発売延期したことなどでこの数字になった。
ただ、製品在庫と選択肢が多ければ、もっとたくさん売れたというのは、メーカーだけでなく流通も含めた業界全体の意見だと思う。今回の年末商戦を反省し、ソニー、松下などは、北京オリンピック前の“仕込み”で、ハイビジョンレコーダ全体の50%以上がBDドライブ搭載になると読んで部品調達と生産計画を練っているという。
また、現在発売されている3社以外にもBDレコーダに参入するメーカーがあることから、北京オリンピックの時期にはハイビジョンレコーダ全体の50%は言い過ぎとしても、40%以上はBDドライブ搭載になる可能性がある。
こうした情報は日本の映画ソフト会社にも伝わっており、これまでのんびりと構えていたディストリビュータの中には、「そろそろ始めないと乗り遅れる」との声を聞くようになってきた。HD DVD系を除くハリウッド直系のディストリビュータがBDソフトを充実させていくのは当然として、邦画や日本のディストリビュータが頒布権を持つ映画タイトルに関しても北京オリンピック前後には、明確な動きがあるだろう。
□関連記事
【1月17日】'07年末商戦は薄型TVで40~50型が大幅増
-BCN調べ。次世代レコーダのシェアはソニーがトップ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080117/bcn.htm
■ “つながる”ではなく、“つながる、つかえる”がキーワード
他、ここ数カ月で感じられるのが、“つながる”を超えて、“つながる、つかえる”を目指す製品が増えつつあること。まだ明確な解決策が見えているわけではないが、家電メーカーの考え方が少しづつ変化しているのではないか? という兆候が現れてきている。
非常にざっくりと言うと、従来のAV製品における“つながる”という言葉は、ある種、メーカー(あるいは特定メーカーグループ)による囲い込みの象徴のようなところがあった。たとえば、SDカードなどもそうで、“メモリカード方式+アプリケーションフォーマット”を組み合わせることで、機器の相互運用を高めるのだが、そこには“SDカード”というある種の利権が介在している。
最終的に消費者の利益になれば、どの企業の技術であってもかまわないわけで、SDカードほど普及してしまえば、それ自身に不満はないのだが、あまり利権に固執しすぎると規格の分裂という事態になってしまう。
メモリカード利権に関することを、ここで批判しようというのではなく、これまでの“つながる”には、ちょっとクセがあったということだ。
また、もう一つの視点として、デジタル化で製品がコンパクト化し、ソフトウェアで多様な機能を実現できるようになると、各製品が特定の目的、あるいは特定個人に使いやすいデバイスとして先鋭化が進むという状況も起こってきている。
こうした、ある種のパーソナル化が進み過ぎると、製品の先鋭化が行き過ぎてしまい、単体の製品は(その使い方に限って)とても素晴らしいのに、他分野の製品、他社の製品との連携、つながりが希薄になってくる。
もちろん、製品が進化する上で、ある程度、ユーザーの利用スタイルに合わせて先鋭化することは必要だし、そこでメーカー独自の技術が使われるのも致し方ないのだが、そこはオープンスタンダードで実現できる範囲とのバランスを取る必要もある。
 |
| 松下電器は、VIERAでYouTubeやPicasaなどに対応するネット接続機能「VIERA CAST」をCESで発表 |
“つながる、つかえる”がキーワードとしたのは、そうした混沌としたデジタル機器の状況に対して、やっと“実際に使い物になること”を真剣に考えて機能を実装しようという動きが出てきたと感じているからだ。
たとえば松下電器の発表したYouTubeやPicasa Webへの対応も、これまでのAV家電的な発想から言えば、“数社でコンソーシアムを設立して、そこでポータルを運営。各社製品がそのポータルを介してネットワークサービスを活用する”なんてことになっていたかもしれない。
そんなことをしても、インターネットならではのダイナミズムなど生まれない! と、この連載を読んでいる読者のみんなが思うだろうが、メーカー側に立つと“ビデオカメラやデジタルカメラが、独自サービスに対応して、パソコンを介さずにシームレスに利用できるようにすれば、大きなコミュニティを作れるはず”と考えがちだ。
今後、ハードウェアとネットワークサービス、ソフトウェアは三位一体での開発と提案が求められるようになるだろう。このあたり、各社がどのような戦略で市場を活性化させようとしているのか、まずは業界を注視していきたい。
□関連記事
【1月8日】【International CES基調講演レポート】
松下の坂本AVC社長が150型などプラズマ最新技術を紹介
-壁一面がテレビの“Life Wall”も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080108/ces11.htm
(2008年1月31日)
| = 本田雅一 = (ほんだ まさかず) |
PCハードウェアのトレンドから企業向けネットワーク製品、アプリケーションソフトウェア、Web関連サービスなど、テクノロジ関連の取材記事・コラムを執筆するほか、デジタルカメラ関連のコラムやインタビュー、経済誌への市場分析記事などを担当している。 AV関係では次世代光ディスク関連の動向や映像圧縮技術、製品評論をインターネット、専門誌で展開。日本で発売されているテレビ、プロジェクタ、AVアンプ、レコーダなどの主要製品は、そのほとんどを試聴している。 仕事がら映像機器やソフトを解析的に見る事が多いが、本人曰く「根っからのオーディオ機器好き」。ディスプレイは映像エンターテイメントは投写型、情報系は直視型と使い分け、SACDやDVD-Audioを愛しつつも、ポピュラー系は携帯型デジタルオーディオで楽しむなど、その場に応じて幅広くAVコンテンツを楽しんでいる。 |
[Reported by 本田雅一]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.