 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第112回:International CES特別編 CESに見た液晶関連最新技術 ~LEDバックライト、240Hz駆動、極薄モデルなど~ |
先にプラズマ編をお届けしたが、本稿では2009 International CESに見た液晶関連の最新技術にスポットライトを当てた。
■ LEDバックライトには4通りのシステムが存在する
ソニーが2008年秋、導光型白色LEDバックライト方式を採用したブラビア「ZX1」、直下型RGB-LEDバックライト方式を採用したブラビア「XR1」を発売して以降、LEDバックライト型液晶の実際の製品投入が加速している。もともとバックライトにLEDを採用する案は2000年代前半からあり、ソニーも直下型RGB-LEDバックライト採用の「QUALIA005」を発売したことがある。
当時のLEDバックライト型液晶は、色チューニングの不十分、色むら、輝度ムラなどなど、画質に若干の課題は抱えていたが、2008年後期から始まった第2世代のLEDバックライト採用液晶は画質面でも洗練されてきている。
CESにおいても、LEDバックライト関連の技術展示や採用新製品の発表や展示が相次いだ。今期の液晶から、ついにLEDバックライトの本格的な普及が始まるのではないかと予感させてくれる。
液晶は、バックライト種別に限らず、液晶パネルへのバックライトからの光の導き方で大別して2タイプがある。
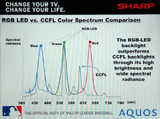
|
| RGB-LEDバックライトシステムの場合、RGB純色のパワーが強い |
1つは、液晶パネルの裏面にバックライトを敷くようにして配置して、バックライトの光をほぼ直接照射するような「直下型」だ。
2つ目は、バックライトをユニット化して、そこからの光を導光板、反射板、拡散板などを利用して液晶パネル全体に照射する「導光型」だ。
もちろん、これはLEDバックライトにおいても同様で、今期の液晶テレビ製品においても、直下型LEDバックライトと導光型LEDバックライトの両方が存在する。
そして、LEDバックライトにも、RGB(赤緑青)の3色LEDを用いるRGB-LED方式と、白色(WHITE)の1色LEDを用いるW-LED方式の2タイプが存在する。
つまり、「LEDバックライト液晶」と一口に言っても配置方法とLEDの種類とで、2×2=4通りの組み合わせが存在する。
| 配置 | 直下型 バックライト | 導光型 バックライト |
|---|---|---|
| 光源 | RGB(赤緑青) | W(白色) |
いずれ、4通りのバックライトシステムが、それぞれ適材適所の形で採用、あるいは淘汰されることだろうが、このLEDバックライト黎明期の今だからこそ、各社の取り組み方がバラバラで面白い。
・シャープ~RGB-LED直下型
LED直下型では、表示映像の内容にシンクロさせてLEDバックライトを局所的に暗くしたり明るくしたりすることでハイコントラストな映像を作り出すことができる。RGB-LED直下型では、さらにR、G、Bの各出力を調整することで特定色の色を強く出して色純度を高めた発色が行なえる。
これがLED直下型ならではの武器である「エリア駆動」(AREA DRIVE)または「ローカルディミング」(LOCAL DIMMING)だ。バックライトのエリア駆動は、本来は自発光ではない液晶パネルに対し、自発光に近い映像特性を与えられる技術としてかねてから注目されてきた。
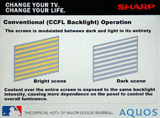 |
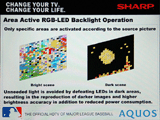 |
| 通常のCCFL(冷陰極蛍光管)を用いた直下型バックライト | RGB-LED直下型であればエリア駆動が可能 |
シャープはAQUOS XSシリーズで、RGB-LEDバックライトで直下型レイアウトを採用し、なおかつ、エリア駆動にも対応したことで話題を呼んだ。
今回のCESのシャープブースでは北米モデルが公開され、実際にこのバックライトシステムの駆動の様子をリアルタイムデモする展示を行なっていた。
RGB-LED直下型でさらにエリア駆動までやるとなると、色ムラと輝度ムラの回避の制御が困難だ。
シャープはLEDの配置や個数を公開していないが、RGB-LED直下型ではコストと消費電力的な観点から、適当な間隔を空けて配置されるのが一般的だ。バックライトが存在しない、その"間隔"のところに対応する液晶画素の駆動が難しいのだ。
例えば、最初期のLED直下型を採用したソニーのQUALIA 005では、特定映像表示時に色むらや輝度ムラが知覚されることがあった。
これを回避するには拡散板や反射板の配置の最適化はもちろん、エリア駆動にまで手を出すとなると、LEDバックライトの駆動と液晶パネルの駆動の完璧な連携が求められる。
その意味で、シャープのデモは非常に興味深い。下の2枚の画像を見比べてみよう。
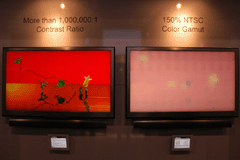 |
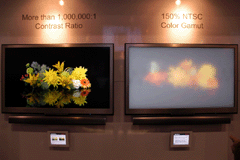 |
| シャープのLED部分駆動の制御例。左側テレビ画面出画時のLEDの発光状態を示す | |
左の赤背景の写真。全体的に赤い背景ではRGB-LEDのR成分を強めにするが、特定部分で緑色の描画領域があることから、バックライトに緑成分を乗せなければならない。緑描画領域のところだけ緑を乗せればいいように思えるが、そうなると緑を乗せたところと乗せてないところでの色むら/輝度ムラが発生しやすくなる。そこで、緑描画領域の周辺のかなり外郭にまで緑を乗せた発光をさせ、液晶画素駆動の方で、赤描画領域&近辺の不要な緑や、緑描画領域&近辺の不要な赤を取り除いていることがわかる。
同じように右の黒い背景の花束の写真。こちらも興味深い。表示映像の背景は真っ黒、花束は明るく輝いているが、机の鏡像は薄明るい。黄色く輝く花束の周辺は黄色成分を強くしたバックライト駆動だが、鏡像の描画領域に色むらや輝度ムラが出ないように、RGB全色成分を淡く乗せたグレー発光をさせていて、なおかつ、真っ黒な背景との輝度ムラが出てはいけないので、真っ黒な背景にもこのグレー発光を適用し、このグレー発光を消すのに液晶画素駆動で黒を描画している。
こうした、バックライト制御と液晶駆動の絶妙な連携は見事だ。AQUOS XSシリーズのRGB-LED直下型バックライトの制御は、非常によくできていて画質的にも素晴らしい。
ただ、公称スペックは、特定条件が揃ったとき、あるいは特定の映像表示時にしか実現できないと言うことは留意しておきたい。
シャープのAQUOS XSシリーズは公称スペックとしてコントラスト100万:1、NTSC色域カバー率150%を謳うが、これは最良ケースでの話。シャープのAQUOS XSシリーズに限ったことではなく、スペックはあくまで数値競争の産物なので、最終的には自分の目で画質を判断する必要があるのはLEDバックライトになっても変わらない。
・東芝~RGB-LED直下型
東芝も北米ではRGB-LED直下型を採用したREGZA SV670シリーズを、5月より販売開始する。なお、東芝のRGB-LED直下型には「FocaLight」という技術ブランド名が付けられている。
FocaLightでは横12×縦8=96エリアに分割してのエリア駆動に対応している。各エリアはRGB-LEDを1ユニット化したモジュールになっており、各LEDモジュールはRGB-LEDがそれぞれ1:2:1の比率で構成されているという。
 |
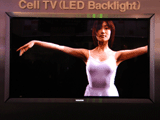 |
 |
| 2009年秋に登場予定の次世代REGZA「CELL TV」も、このFocaLightシステムを採用する | ||
・サムスン~W-LED直下型。超薄型はW-LED導光型(エッジライト)
サムスンはLEDバックライト採用の液晶テレビには「LEDTV」というブランド名をつけて、あたかも新しいテレビ方式のようにアピールするマーケティングを展開している。
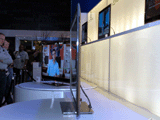
|
| 6000、7000、8000シリーズの厚みは3.0cm |
LEDTVは6000、7000、8000シリーズの3種類で展開され、特に6000シリーズはサムスンの液晶テレビ製品としては中堅製品に位置されるため、LEDバックライト採用製品の普及を狙った意欲的な戦略的製品となっている。価格は未定だが2009年前半に発売される予定だ。
6000、7000、8000シリーズのバックライト方式はW-LED直下型でエリア駆動に対応することで100万:1のコントラストを実現している。
最薄部の厚みは3.0cm。世界最薄は謳わずにコスト重視、コントラスト重視でW-LED直下型を採用した格好だ。
 |
 |
 |
| コントラスト感は良好。100万:1は伊達じゃない | ||
 |
 |
| 薄さと省電力性能を求めるならば導光型が優位 | 厚みはわずか6.5mm。ビクターの7mmを超えた薄さ |
6000、7000、8000シリーズでは世界最薄は狙わなかったサムスンだが、近未来における薄型の需要にも対応すべく、薄さ6.5mmの次世代「LEDTV」試作機も公開していた。こちらは、白色LED(W-LED)光源モジュールを液晶パネルの額縁部分に装着して光を導光板と拡散板で液晶パネルに導いて照射するW-LED導光型だ。特に最近では額縁側にLEDバックライトユニットを配することから「エッジライト」と呼ばれることが多い。ちなみに、ソニーのBRAVIA ZX1もW-LEDのエッジライト方式だ。
導光型はLED駆動基板などを液晶背面に内蔵しなくてよいため、厚みの面で有利だが、直下型のようなエリア駆動はできない。しかし、駆動するLEDの個数が減るので消費電力の面で有利になる。また、同じ導光型でもRGB-LEDよりもW-LEDの方がLEDの絶対個数をさらに少なくでき、駆動回路もシンプルにできるので消費電力とコストを抑えやすい。
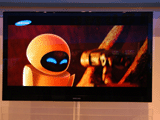 |
 |
 |
| 薄くても画質に見劣りする部分は無し | ||
・LG電子はW-LED直下型
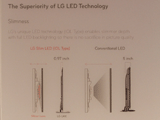 |
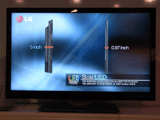 |
| LG電子はチューナを別体型とすることで、直下型バックライトながらも薄さ0.97インチ(約2.46cm)を実現 | |
LG電子は2009年内に北米市場向けにW-LED直下型を採用したLHXシリーズとLH90シリーズを発売する。
LHXシリーズは厚さ0.97インチ(0.98インチと記載されている資料もある)の薄さにこだわったモデルでチューナは別体型。LH90シリーズはLHXシリーズと同スペックのチューナ内蔵型で薄さにはこだわらないモデルになる。
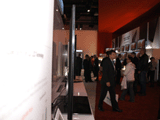 |
 |
| LHXシリーズはW-LED直下型を採用 | |
 |
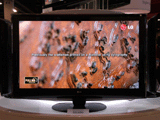 |
 |
| LH90シリーズもW-LED直下型を採用。チューナ一体型で薄さにはこだわらないモデル | ||
LG電子のW-LED直下型は、そのW-LEDの個数は2,880個と公開されており、その多さは業界随一だ。そしてもちろん直下型であるが故に、エリア駆動にも対応するが、そのエリア制御数が240エリアという破格の多さになっているのも特徴だ。
エリアの区分は横20×縦12。各エリアが1バックライトユニットとなっており、1ユニットあたり12個のW-LEDが実装される。
この圧倒的なLED数とエリア数を用いたエリア駆動は圧倒的なピーク輝度を実現できることから、公称コントラストは200万:1以上(測定不能)を実現できていると豪語している。
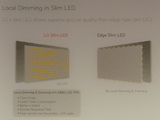 |
 |
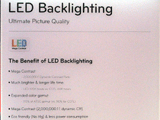 |
| LG電子のエリア駆動は業界トップレベルの240エリア駆動 | 解像度の高いエリア駆動と高輝度W-LED採用により、公称コントラストはなんと200万:1 | |
RGB-LEDではないので、その代わり広色域性能はうたっていない。スペック上は「NTSCカバー率110%、CCFLよりも20%以上広色域」というアピールに留まっている。
ただ、製品寿命の面でW-LEDは有利だという意見もある。RGB-LED直下型ではR、G、BのLEDごとに性能半減期、寿命が異なるため、経年劣化したとき、画質の落ち込みが急激だと予測されている。もちろん、R、G、Bの各色の発光輝度を寿命に合わせて変調する機構を持つ製品もあるが、W-LED直下型では全LEDがほぼ同時に劣化し、また、全同の白色であるためうちいくつかが急激に暗くなったり(場合によっては変色しても)画質に極端な影響を及ぼさない。
RGB-LEDの広色域か、W-LEDの長寿命か。ここは究極の選択と言ったところだ。なお、LG電子のW-LED直下型採用モデルの製品寿命は10万時間を設定している。
・パナソニック ~ W-LED直下型?

|
| NeoLCDの仕組み |
今回のCESで、パナソニックは、次世代液晶VIERAから、横電界駆動液晶の新世代のIPS-αパネルとLEDバックライトを組み合わせたNeoLCDパネルで実現されることがアナウンスされた。
このNeoLCDプラットフォームでは、特に公式発表はないが、CESで公開された図解や、色域カバー率がハイビジョン色域(ITU-R BT.709,sRGBと同等)120%程度であることを踏まえ、なおかつ後述のVIERAルールも踏まえるとると、W-LED直下型と推測される。
もちろんエリア駆動にも対応し、暗部と明部のはっきりした映像も鮮烈に描き出す。
ただ、パナソニックの場合、40V型以上の大画面モデルはプラズマでいくという自社ルールがあるため、必然的に液晶VIERAはエントリークラス的な位置づけとなる。他社のLEDバックライトシステム導入モデルは全て46V型以上だ。
価格激戦区の37V型以下クラスに、製造コストが高くつくLEDバックライトシステムをパナソニックがどれほど真剣に導入してくるのか。この点には興味が湧く。
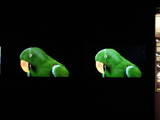 |
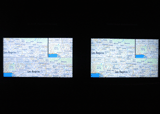 |
| パナソニックのNeoLCDのエリア駆動のデモ | |
□関連記事
【1月8日】パナソニック、消費電力1/3のプラズマ「NeoPDPeco」を開発
-8.8mm厚の50型。消費電力半減のNeoLCDecoも
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20090108/pana1.htm
ビクター ~RGB-LED直下型とW-LED導光型
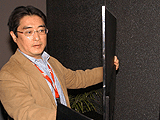 |
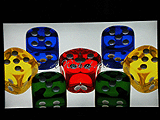 |
| 薄さ7mmの4辺エッジライト採用試作機 | |
ビクターは、まだLEDバックライト採用の具体的な製品計画は出てきていないが、LEDバックライトを採用した試作機を2モデル公開している。
1つはLED導光型(4辺エッジライト)の薄さ7mmを実現した32V型のフルHD対応プロトタイプだ。これは本連載108回で詳細にレポートしているのでそちらを参考にして欲しい。なお、特に言及はなかったが、広色域性能は訴えられていなかったことからLEDタイプは白色だと思われる。
RGB-LED直下型の試作機も展示。こちらはエリア駆動にも対応し、広色域、高コントラスト画質がアピールされている。いずれも、試作モデルであるため発売時期は未定。
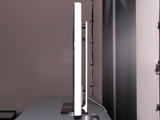 |
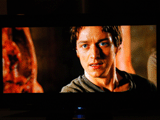 |
| RGB-LED直下型であることを強調するためか、発色の彩度が強め | |
日立製作所~RGB-LED導光型?
日立は37V型のRGB-LEDバックライトを採用した最薄部15mmのウルトラスリムな液晶テレビ試作機を公開。
解像度は1,920×1,080ドットのフルHD対応。液晶パネルは日立なので当然横電界方式のIPS方式だ。直下型か、導光型かの言及はなく非公開。
薄型液晶ブームの火付け役である日立のWooo UTシリーズは、EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp:外部電極蛍管)直下型でありながら、新開発の拡散板の実装によって薄さ35mmを実現し、直下型を薄く作る技術に長けている。厚さ15mmだと導光型と考えるのが普通だが、「Wooo UTの日立」と言うことで直下型であればホットトピックだ。早期製品化を期待したい。
 |
 |
| 超薄型液晶テレビの第一人者の日立。次期モデルからはLEDバックライト採用か? | |
Dolby~W-LED直下型でハイダイナミックレンジ!
Dolbyといえば、Dolby Digitalをはじめとした、サウンドフォーマットの会社というイメージだが、2007年2月にLEDバックライトシステムの基本特許を持つBRIGHT SIDEを買収してからは、音声だけでなく映像関連技術の開発にも乗りだしている。
Dolbyは直下型のLEDバックライトシステムに広く特許を押さえており、Dolbyスタッフによれば、実はRGB-LED、W-LEDの区別なく、直下型のLEDバックライトシステムを導入した液晶テレビメーカーは少なからずいくつかの特許使用のライセンスをDolbyと結んでいるという。
そんなDolbyも、自社ブースでW-LED直下型の46V型フルHDディスプレイ試作機を公開した。試作を担当したのはイタリアのハイエンドホームシアター関連機器製造メーカーのSIM2社。
公開された試作機のW-LEDの個数は2,200個。LGの2,880個は下回るが相当な個数になる。
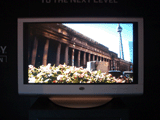 |
 |
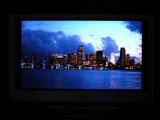 |
| Dolbyが所有する直下型のLEDバックライトに関連した技術、ここから生み出されるハイダイナミックレンジ映像技術に対して「Dolby Vision」という技術名が付けられた | ||
色再現性よりは輝度ダイミックレンジの再現性にこだわったものであるためか、コントラスト感は強烈だが、発色に関しては強く黄色にシフトしたような荒削りな印象を受ける。
なお、公称ピーク輝度や公称コントラスト比は非公開。
昨年公開の試作機が、LEDだけのピーク輝度が4,000cd/m2、最暗部輝度が0.01cd/m2なので、コントラスト比が40万:1で、液晶パネルと組み合わせたときの実効コントラストは30万:1と発表されていた。LED個数は昨年の1,380個から2倍近く増加しているので、スペックはさらに向上しているはずだ。
■ 4倍速240Hz駆動。疑似かリアルか、それが問題だ
液晶のような常時発光映像ディスプレイでは直前まで前フレームを見続けてしまうことから人間の知覚として残像が認識されてしまう。
これを低減する技術が倍速駆動技術で、前フレームと次フレームの間の中間フレームを算術的に合成して挿入することで、表示フレームレートを擬似的に増加させ、知覚上の残像を低減する。通常の表示フレームレートの60Hzの倍の映像フレームを表示することになるため「120Hz駆動」と呼ばれることもある。
初期の液晶における残像は液晶画素描画速度の遅さが原因だったため、その高速化が残像低減技術の中心だった。続いて、残像の起こりにくい短残光なブラウン管の表示システムを疑似的に再現して知覚上の残像を低減する疑似インパルス表示が台頭する。この疑似インパルス表示の実現方法としては、バックライトを液晶描画時に消し表示時に点灯する方法と、全黒映像を液晶描画する手法などがある。
現実世界の視界はフレームレート無限大でホールド型であるため、これを擬似的に再現しようとして登場してきたのが倍速駆動技術になる。
液晶関連技術でLEDバックライトに並んで2009年以降のトレンドになると思われるのが、2倍速の上を行く「4倍速240Hz駆動」だ。

|
| 東芝は疑似240Hz駆動にClearScan240と命名 |
4倍速240Hz駆動には2タイプが存在する。1つは、実際に算術合成の中間フレームをこれまでの1枚から2枚に増加させて表示するリアル240Hz駆動。
2つ目は合成する中間フレームは1枚のままだが、この中間フレームの表示と、実存フレームの表示を疑似インパルス表示して、擬似的な240Hz駆動を行なう方法だ。
ソニーが2008年冬モデルとして登場させた世界初の4倍速駆動対応のBRAVIA W1シリーズはリアル240Hz駆動方式を採用している。
では、他社はどうなのか。まず、東芝だが、2009年のREGZAから導入する予定の「ClearScan240」は疑似240Hz駆動になる。
LG電子も疑似240Hz駆動を採用し、LG電子はこれにTruMotion240Hzと命名している。
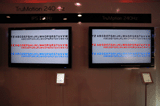 |
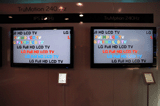 |
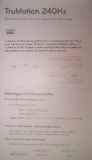 |
| LGは疑似240Hz駆動に対応 | 120Hz駆動で比較した場合でも、LG電子が採用する横電界液晶のIPS液晶の方が残像が少ないというデモ。これにはVA液晶陣営からの反論がありそうだ | 「リアル240Hz駆動よりも疑似240Hz駆動の方が消費電力の面でも優位」と主張 |
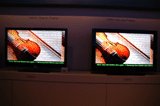
|
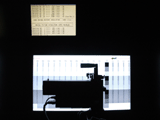
|
| サムスンは方式不明だが、同社ブース内では「240Hz Quarto Frame」と命名した4倍速駆動技術のデモが公開されていた | パナソニック NeoLCDの動画解像度測定の様子。1080ラインはNG結果だが、1000ラインでOKが出ている点に注目 |
パナソニックとサムスンは方式についての詳細説明は無しだが、240Hz駆動と思われる技術を次世代機より投入する。
特にパナソニックは、この新駆動技術によって動画性能が劇的に向上し、プラズマに肉迫する動画解像度が得られるとしている。
CESのパナソニックブースでは次世代液晶VIERA用のNeoLCDパネルにて、APDC測定方式の動画解像度の実測デモを公開。フルHDパネルで、プラズマにせまる動画解像度1000ラインを確実にマークできる様をアピールしていた。
どちらが優れているかの議論の決着はまだつかないが、今年のCESを見る限りでは、総じて疑似240駆動が多い。これは、倍速120Hz駆動でも補間フレームのエラーによる、残像とは違った不自然なピクセル振動が時々目に付く現状では、さらに架空の補間フレームを増やすのを嫌うためだと思われる。
ピクセル振動を軽減するために、元フレーム(実存フレーム)のブレンド率を上げる回避策もあるが、それでは240Hz化する意味が薄れる。
かけるコストと得られる効果のバランスの観点で、多くのメーカーが「疑似240Hzが現状の最適解」という判断を下したのだろう。
□2009 International CESのホームページ
http://www.cesweb.org/
【2009 International CESレポートリンク集】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/2009ces.htm
(2009年1月16日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 西川善司 | 大画面映像機器評論家兼テクニカルジャーナリスト。大画面マニアで映画マニア。本誌ではInternational CES他をレポート。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。映画DVDのタイトル所持数は1,000を超え、現在はBDのコレクションが増加中。ブログはこちら。近著には映像機器の仕組みや原理を解説した「図解 次世代ディスプレイがわかる」(技術評論社:ISBN:978-4774136769)がある。 | |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2009 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.