 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第82回:2007 International CES特別編 ~ レーザー光源SXRDリアプロ登場~ プラズマ対液晶の動画性能戦争 |
■ ソニー、レーザー光源の55V型リアプロ試作機
前回、フロント/リアプロジェクション用の新光源「LIFI」について紹介したが、今回のInternational CESではもう一つトピックとなる光源技術が紹介された。それが、レーザー光源だ。
ソニーブースではフルHD/1,920×1,080ドットの0.61型SXRDパネルを採用した55V型のリアプロテレビ試作機を展示。その光源としてRGB各色のレーザーを用いていることがアピールされた。
 |
| レーザー光源の優位性 |
レーザー光は位相が揃った光であり、そのスペクトラムはかなり理想に近い線スペクトラムが得られるのが特徴だ。
この理想的な純色が取り出せるRGB各色のレーザー光を光源にすることで、非常にダイナミックレンジが高く、なおかつ広い色域を再現しようというのが狙いだ。
RGB各色のレーザー光は、対応する3枚のソニー独自の反射型液晶パネル(LCOS:Liquid Crystal On Silicon)「SXRD」に照射され、各パネルの各画素ではRGB各色の階調が作り出され、その出力光はプリズムで合成されてフルカラー画素として出力される。
RGB-LED光源と同じように、RGBレーザー光源も白色光からRGB各色に分光する必要が無いので光源ブロックを小さくできるメリットがある。
1つ謎なのは、どのようにレーザー光を0.61型のSXRDパネル全体に照射しているかという部分。この部分は現在は非公開としているが、おそらくはすでに三菱電機が実用化している光ファイバーを組み合わせて多重反射を引き起こす仕組みを利用していると思われる。
 |
| 奥行きは55V型で約270mmとかなり薄い。リアプロテレビにも壁掛け設置時代がやってくるのか |
いずれにせよ、光学ブロックはかなりコンパクトに実現できたとのことで、55V型という画面サイズながら、奥行きわずか270mmというから、前回紹介したビクターのUltra Slim DesignのD-ILAリアプロTVに肉迫する薄さだ。
このレーザー光源の仕組みはNovaluxと協力して開発したもので、“NECSEL”という技術を用いたものである。
コントラスト比、最大輝度性能などのスペックについても非公開。ただし、表現色域はsRGBやNTSCを遙かに超え、RGB-LED光源よりも広いとのこと。「応答速度は5ms以下」としているが、これはSXRDそのものの応答速度なので、レーザー光源とは関係ない。LED光源と同様に電源オンからすぐに最大輝度照射が可能なので、起動時間も非常に高速だという。
「色表現はフィルムライク再現に努めた」とのこと。フィルムは光強度に応じて色域が変化する特性を持つが、おそらく、階調に応じて色域マップを変化させる3次元色域マップを持たせていると思われる。
実際に映像を見てみたが、フルHDの高精細感、画素間ギャップが少ないSXRDならでの粒状感の少ないしっとりとした画質とレーザー光源のワイドな色域とのマッチングは絶妙。純色の伸びもさることながら、階調の最暗部にも豊かな発色が感じられ、確かに従来の水銀系ランプによる映像からは一線を画したものになっている。リアプロテレビにありがちな中心と外周との輝度差もそれほど感じない。
課題はレーザー光源モジュールからの発熱をいかに冷却するか、そして製造コストの高さなどにあるという。
今回展示された製品はあくまでプロトタイプであり、発売時期や価格に関しては未定。発色はとても素晴らしいので、松下のLIFI光源のように、次世代のリアプロTVの光源として、早期の実用化を期待したい。
 |
 |
 |
| 赤の純色が鮮烈。また、暗い部分にも色味を感じられるのは色ダイナミックレンジが広い証 | ||
■ ソニー、70/82型の大画面トリルミナス液晶テレビを公開
~70V型は2月より発売開始
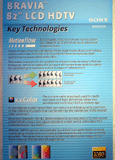 |
| 表現色域は現行の1.8倍も広いx.v.Color(xvYCC)に対応する。残像低減技術のMotionFlowにも対応 |
ソニーはRGB-LED光源をバックライトに採用した70V型と82V型のフルHD対応BRAVIA 2製品を展示。82V型は技術展示用の試作品で発売の予定はないが、70V型は「KDL-70XBR3」として2月より33,000ドルで発売される。
ソニーのRGB-LED採用液晶テレビといえばQUALIA005を思い出させるが、実際、今回のLEDバックライトシステムはQUALIA005と同じ「TRILUMINOS(トリルミナス)」の名称が使われている。
RGB-LED光源の仕組みには、複数LEDを1モジュールにまとめたLED光源ユニットから導光版を通じて液晶パネル全体に光を照射する「導光型」と、液晶パネルの背後に直接複数のLEDを意図する「直下型」の2タイプがあるが、トリルミナスは後者の直下型を採用する。なお、今回の70V型、82V型のLEDの個数は非公開としている。
直下型LEDバックライトシステムでは、そのエリアごとのLEDブロックの光量を調整してハイダイナミックレンジな色再現を行なう「ADDRESSABLE BACKLIGHT」タイプもあるが、トリルミナスではそうした制御までやっていない。ただし、画面全体に対するLED光源の動的光量制御は行なっているとのことで、70V型モデルでは動的コントラスト7,000:1を実現している。なお、ネイティブコントラストも1,300:1とのことで、液晶テレビとしてはなかなのハイコントラストぶりである。
 |
 |
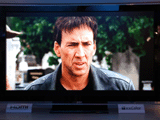 |
| 70V型のKDL-70XBR3。その大きさもさることながら、その表現色域の広さに感動。解像度は当然1,920×1,080ドット | ||
 |
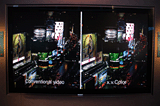 |
 |
| 82V型のトリルミナス液晶TV試作機。純色が鮮烈なのはもちろん、動的なバックライト制御で黒の沈み込みも良い。なにより暗部階調のリニア感と暗部発色の表現力が優秀 | ||
 |
| 82V型の側面。厚み自体は非公開だが10~15cm程度 |
液晶パネルは、その光源の位相を調光、制御するためにその裏と表に偏光フィルムを貼り合わせる。82V型は液晶パネル表示面に貼り合わせる偏光フィルム(ポラライザフィルム)が82V型サイズのものがなかったために、表示面に継ぎ目が見えてしまっている。これはあくまで試作機だからで、将来的に量産されるようなことがあればこの問題は解決されるとのこと。なお、発売される70V型にはこうした継ぎ目はもちろんない。
70V型量産製品、82V型試作品ともに、映像エンジン部はソニーの伝家の宝刀「DRC-MFv2.5」を内蔵した「BRAVIAエンジン・プロ」を採用。また、新開発のフルHD解像度までの120fps、倍速フレーム化技術を応用した液晶特有の残像を低減する「MotionFlow」もBRAVIAシリーズとしては初搭載する。
□関連記事
【1月12日】【CES】ソニー/パイオニア編
-70型「ブラビア」やAVアンプ、シアターシステムなど
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070110/ces12.htm
■ Optomaは120型の世界最大リアプロ
投射距離さえとればいくらでも大画面が実現可能な投写型の映像機器。特にリアプロTVは、投射距離を縦方向に投射距離を稼ぐことで、比較的コンパクトに大画面が得られるため、そのコストパフォーマンスの高さは液晶やプラズマを凌ぐ。とはいえ、大画面にすればするほどボディサイズが大きくなってしまうため、実際には本体の大きさが自ずと最大画面サイズを決定する。
しかし、アメリカでは、「設置スペースはいくらでもあるからとにかく大画面が欲しい」というニーズもあり、そうしたユーザー向けのリアプロ式の超大画面製品が時々発表される。普通のユーザーには縁遠いが、今回のInternational CESでもそうした製品がいくつか見受けられた。
1つはビクターのD-ILA(LCOS)ベースの110V型フルHD対応リアプロTVの試作機。
映像パネルはDLA-HD1などと同じ、第2世代0.7型フルHD解像度(1,920×1,080ドット)のD-ILAパネルを採用。消費電力が230Wとなっている。投写型で110V型という大画面にしても、中央部と外周部の輝度差はほとんど無く、D-ILAパネルのパルス駆動の甲斐もあって非常に明るい。
現時点では市販の予定は無いそうだが、完成度はかなり高い。EXEシリーズの最上位モデルとしての登場を期待したいものだ。
 |
 |
| ビクターのEXEシリーズの画質がそのまま110V型になったような画質。大画面リアプロは暗くなると言うのがセオリーだが、そんなマイナス面を感じさせないほど明るい | |
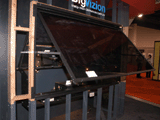 |
| BigVizion構造図。手前の開いている方が表示スクリーン部。奥側が反射ミラー |
もう一つ、注目を集めていたのはOptomaが「実際に市販されるリアプロシステムとして世界最大」とアピールしていた120V型 DLPリアプロシステム。こちらは、単板式のDLPリアプロ・ディスプレイという位置づけでチューナは非搭載。
パネル解像度は1,920×1,080ドット。公称コントラスト比は10,000:1。コンポジット、Sビデオ、コンポーネントのほか、HDMI入力をサポート。1080p入力も正式にサポートする。
奥行きは約1m(40インチ)。実際にBigBizionシリーズの最上位製品としてリリースされることが決まっており、価格は50,000ドルで2007年後半に発売を予定している。既に、80V型、90V型、100V型は、それぞれHDBV3080/3090/3100という型式番で発売中で、それぞれ22,999ドル、24,999ドル、29,999ドルという価格が設定されている。120V型が飛び抜けて高い気がするが、これは、「世界最大」というキーワードによるプレミアム効果なのかもしれない。
画質は、まずまずといったところ。外周の映り込みが強く、周囲の環境が明るいと輝度不足が否めない。価格、トータルな取り回し、画質などに配慮すると、無理してリアプロにせず、Optomaならば「HD81-LV」を使用した120インチのフロントプロジェクタのシステムを構築した方がコストパフォーマンス的に優れるのではないか、と感じた。
 |
 |
| 民生向け1080p対応リアプロとしては世界最大となるOptomaの120V型BigVizion。ただ、スクリーンの周囲の映り込みが強く、設置スペース以外にも設置環境を選びそうだ | |
■ APDC、テレビの解像度の新指標「動画解像度」の技術セミナーを開催
プラズマTVの優位性をアピール
 |
| 動画解像度測定システムの解説を行なったAPDC、画質評価プロジェクト委員川原功氏 |
株式会社次世代PDP開発センター(APDC:Advanced PDP Development Center)は、10月18日に発表した新しいテレビの解像度スペック表記方式「動画解像度」(MPR:Motion Picture Resolution)を解説するセミナーを、ラスベガス市内のホテルで開催した。
これまで、テレビやディスプレイ、プロジェクタなどの映像機器の解像度は、“1,920×1,080ドット”のような映像パネルの解像度で表され、動画の表示性能は、"4ms"というような、各画素の全黒→全白→全黒(逆順やグレイtoグレイの場合もあり)の応答速度(MPRT:Motion Picture Response Time)で表されてきた。
APDCでは、こうしたこれまでのスペック表記では、消費者がテレビを選ぶ際に重視する動画表示時の残像度合いを表し切れていないとし、新しい「動画解像度」というスペック表記を提唱した。
映像パネルは1,280×720ドットの720p、1,920×1,080ドットの1080pという解像度が当たり前となり、解像度性能的には画一的になってきている。応答速度も液晶でも一桁台の数ms以下のものも出てきている。しかし、APDCでは、ホールド型表示の液晶方式では、プラズマよりも動画を表示したときに解像感が劣化しやすいと主張する。
ホールド型表示とは常に発光し続ける画素表示を行なう方式のこと。プラズマやブラウン管、SEDなどは目的の色に光ってすぐに消えるインパルス型表示といわれる。より詳しくは本連載第73回を参照して欲しいが、動く被写体を視線で追い続けた場合はホールド型では残像を知覚しやすくなるという弱点がある。
毎秒60コマ表示の60fpsでは応答速度が16.66ms未満であれば応答速度としては足りていることになるが、ホールド型ではその応答速度の期間、本来表示すべきではない色を見てしまう。APDCでは、本当の意味での動画表示性能を示すことが急務であると考えたわけだ。
動画表示性能とは人間が視覚して体感するものなのでその定量的測定が難しいように思えるが、APDCではユニークな方法でその客観的かつ定量的な測定方法を考案した。
測定対象のディスプレイ装置に評価映像を水平方向に規定の速度で動かしながら表示し、これをカメラで追従しながら撮影し、取得した画像を数値解析して、その「動画解像度」を「TV本」という単位で算出する。
評価映像は垂直解像度基準の解像度で白線と黒線を交互に4本ずつ、合計8本を縦方向に描いたものを用いる。例えば1,920×1,080ドットの解像度では、1080TV本の評価映像は白黒4ドットずつ合計の8ドットの縦線に相当する。同じ1,920×1,080ドット解像度で500TV本の評価映像は白、黒がそれぞれ2ドットずつの合計16ドットの縦線に相当する。
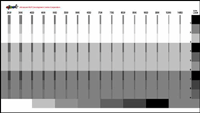 |
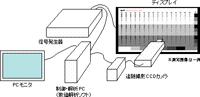 |
| 評価映像。3段階の背景色。左から300,350~1000,1080TV本の白黒縦線が描画されている | 測定模式図 |
この評価映像を横方向にスクロールさせるわけだが、その速度は、APDC調べの様々な種別の映像がスクロールアウトする時間の平均を測定し、5~6秒/画面が適切と判断している。
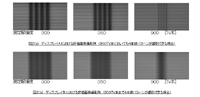 |
| 動画解像度の測定結果例 |
この横スクロールする評価映像をカメラで撮影するわけだが、撮影に用いるカメラは、APDCが事前に行なった人間の目視による測定と合致するように基準を設定している。
撮影した映像はフーリエ変換によってスペクトル解析し、正しく、交互の白黒線が白黒の線として認知できると判断できる最高解像度を結果の動画解像度「TV本」とする。
白と黒の交互線の見え方は、背景の輝度レベルによっても変化することを踏まえ、APDCの定めた多様な背景色の組み合わせで測定を実施。最終的な結果は全ての測定結果の加重平均を取って求めることになる。
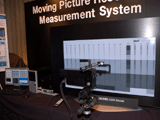 |
 |
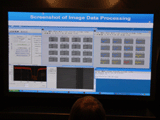 |
| セミナー会場に設置された測定システムの実機 | 測定結果をPCの専用ソフトで解析 | |
APDCによれば、結果はプラズマ方式の方が圧倒的に高く、最新の残像低減技術を適用した液晶テレビでもプラズマの優位性は変わらないとしている。
APDCとしては、この動画解像度は「当面のプラズマの優位性を証明することになった」としながらも、液晶陣営においてもこの測定システムを採用してもらい、「業界全体でより優れたフラットテレビ開発に臨むという姿勢を作っていきたい」と結んだ。実際にこのシステムの販売といった計画もあるようだ。
このシステムに対するいろいろな反論もある。
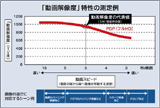 |
| プラズマは動画の移動速度が上がっても動画解像度の劣化が少ない |
例えば、今回の方法は、白黒による縦線のスクロールを撮影したものであり、様々な色の組み合わせでは違った結果が出るだろうという指摘が1つ。プラズマは明滅頻度を制御して階調を作り出すサブフィールド法を用い、時間積分的なフルカラーを実現しており、視線を移動させると色ズレが知覚されることがある。液晶ではこの色ズレの問題が原理上ない。今回の測定方法ではこの色ズレによる動画解像度の劣化が測定されにくく、プラズマが有利だという反論がある。
また、今回提案された手法は水平(横)スクロールに限定された測定方法であり、応答速度と同様、やはり動画性能の一部を測定しているに過ぎないという指摘もある。映像エンジンの中には映像の動きベクトル補間を行なって人工的に補間フレームを挿入するものがあるが、この動きベクトルの検出の方向が全方位か、それとも限定的か、そしてその補間されるベクトルや色の算出精度に依存した得意不得意もある。
この「動画解像度」という性能表記は、意義があり非常に価値のある情報だとは思うが、その採用を巡っては、液晶陣営とプラズマ陣営のせめぎ合いと、そして両方を手がける会社の微妙な立ち位置もあって一筋縄では行きそうにない。
 |
 |
| 壇上に立ったAPDCのメンバーの胸には「I LOVE PLASMA」のバッジ | セミナー参加者には「I LOVE PLASMA」のロゴ入りTシャツが配布された |
■ 2007年は映像エンジン120fps元年か?
液晶TVの残像低減技術は日進月歩で発展しているが、2007年は各メーカーで申し合わせでもしたかのように、「フレーム補間駆動」技術を自社の映像エンジンに組み込んでおり、これを強くアピールしている。
基本原理については第73回でも紹介しているので参照されたい。簡単にまとめると、映像エンジンが表示する複数フレームを参照し、どの画素がどこに動いたかを検出し、その加速度ベクトルを算出。これを元にフレームとフレームの間の中間フレームを算術合成する。
ホールド型表示の液晶では、各画素が指定する色に変化する段階の望ましくない途中の色を見てしまうことで残像が知覚されてしまう。だとすれば、その変化の途中の色を見せ、その望ましくない色を見せなければ残像は低減される。さらに副次的に動画そのものもスムーズに見えるはずだ。フレーム補間駆動技術はこうしたアイディアが元になっている。
存在しない映像をつくりだす、というとたいそうな感じに聞こえるが、画素や複数画素(2×2ドットなど)がどこに動いたかの検出はMPEG圧縮などにも用いられている技術であり、そのノウハウの蓄積はかなりある。
今回のCESでは、このフレーム補間駆動が軒並み「120fpsの倍速化」し、そしてフルHD(1080p)に対応したことが目立った。会場で見かけた各社のフレーム補間駆動技術を紹介していくことにしよう
松下電器が展示していたのは「Motion Picture Pro」と呼ばれるフレーム補間駆動技術。以前は「フレームクリエーション」と呼んでいた1.5倍速化90fps化したフレーム補間駆動を倍速化、120fps化してフルHDに対応した。
松下担当者によれば、他社の同種技術よりも全方位のベクトル検出精度が高いと自負しているそうで、補間フレームの信頼性が高いそうだ。
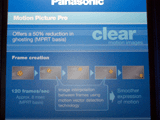 |
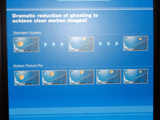 |
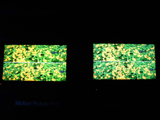 |
| 松下のフレーム補間駆動技術は「Motion Picture Pro」 | ||
液晶のシャープも、これまで「高速動画技術」という仮称で研究していた120fps化技術を「FineMotion Advanced Technology」として、フルHD対応で実用化している。
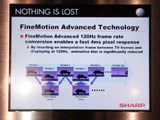 |
 |
| 右の写真の左側が現行の「LC-45D40U(北米モデル)」、右が2007年の120fps対応「LC-52D92U(北米モデル)」 | |
東芝も新映像エンジンのメタブレイン最新版には「CLEAR FRAME」技術と命名された120fps化技術を実装。REGZAの42/46/52/57LX177シリーズに登載している。もちろん1080pに対応している。東芝担当者によれば、映像プロセッサが従来の266MHzから333MHzにクロックアップしていることが1080p対応の鍵となったそうだ。
 |
 |
| 東芝の120fps化技術「CLEAR・FRAME」。写真でもその差が分かる | |
Samsungは、「120 Frame Rate」というそのものずばりの名前で120fps化のフレーム補間駆動を研究中だ。また、LEDバックライトの試作機ではその高速応答性を応用し、その表示に黒挿入をして高品位なインパルス駆動を実現する「LED BLU Scanning」技術も同時に展示していた。このスキャン式インパルス駆動は連載第47回で紹介したPhilipsのApturaによく似ている。斜め方向のベクトル補間の精度の良さをアピールしたいためか、デモンストレーションでは斜めスクロールの映像を表示していた。
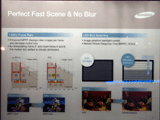 |
 |
| Samsungは120fps化技術とLEDバックライトによるインパルス駆動による2つの液晶残像低減技術をアピール | |
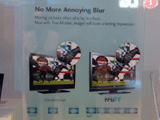 |
 |
| LG電子も「True Motion」という名称で120fps化、フレーム補間技術を、47LB4DFなど、型番末尾に「B4D」「LY3D」が付くモデルに搭載した。もちろんフルHDに対応 | |
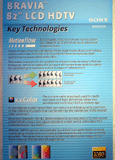 |
 |
| ソニーは、トリルミナス液晶TVの「KDL-70XBR3」に「Motion Flow」の技術名で120fps化、フレーム補間駆動技術を実用化 | |
ここまで各メーカーが120fps化を実用化、しかもフルHD解像度で実用化してきたのは、やはり映像プロセッサの高性能化、高クロック化によるところが大きい。
ただし、この120fps化等のフレーム補間駆動技術の問題点を指摘する声もある。
1つは、モーション補間ベクトルの検出や演算精度が不十分では、逆に映像にノイズを与えてしまうということ。ベクトル検出を何ピクセル単位で行なうか、どういう方向に対して、何フレーム分まで遡って、どういう演算精度で処理するかによっては、エッジ付近で変なノイズがでてしまったりするケースも想定されるという。
逆に、こうしたワーストケースを避けるために割り切ってしまい、あえて全方向にはベクトル補間を行なわない設計とする場合もある。この場合は、ベクトル補間を上下左右に限定してしまい、カメラのパンや文字テロップの動きによって発生する残像低減に特化するわけだ。「変なノイズを出すくらいならば、残像が目立つケースだけ低減すればいい」というトレードオフだ。こうしたエンジンでは、もちろん、画面内を縦横無尽に動く被写体に対して効果がない。
また、このフレーム補間により、表示フレームが表示されるまで、半フレーム分~1フレーム分の表示遅延を起こす可能性も指摘されている。テレビ放送や映画視聴などではほとんど気が付かれないが、表示映像を見ながらユーザーのインタラクティブ・リアルタイム操作が行なわれるアクションゲームをプレイする場合などでは大きな問題となる。
液晶の残像低減は、今回紹介したフレーム補間駆動技術のようなパネル駆動や映像エンジン処理が主流になっていくのか、それとも液晶パネル自身の改良によって極めていくのか、動向を注目していく必要がありそうだ。
□2007 International CESのホームページ(英文)
http://www.cesweb.org/
□関連記事
【2007 International CESレポートリンク集】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/2007ces.htm
(2007年1月18日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 西川善司 | 大画面映像機器評論家兼テクニカルライター。大画面マニアで映画マニア。本誌ではInternational CES他をレポート。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。渡米のたびに米国盤DVDを大量に買い込むことが習慣化しており、映画DVDのタイトル所持数は1000を超える。 |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.