 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
|
西田宗千佳の ― RandomTracking ― PS3システムソフトウエア開発者に聞く
|
 |
| PLAYSTATION 3 |
5月24日に公開されたアップデート「バージョン1.80」で、AV機器としてのPLAYSTATION 3(PS3)は、はっきりと「化け」た。Cellの能力を背景とした、クオリティの高いDVDビデオのアップコンバート、そして、DLNAやリモートプレイといった、ネットワークに関する機能を得るに至った。PSPという前例があるとはいえ、PS3がここまでソフトで機能アップすると思っていた人は、それほど多くないのではないだろうか。
今回は、PS3のシステムソフトウエアの可能性について、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE) CTOの川西泉ソフトウェア・プラットフォーム開発本部長と、AV関連機能の開発を統括する、ソフトウエアプラットフォーム開発本部の縣秀征課長に話を聞いた。
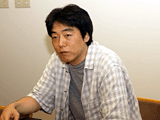 |
 |
| ソフトウェア・プラットフォーム開発本部 川西泉部長 | ソフトウェア・プラットフォーム開発本部 ソフトウェアプラットフォーム 開発部 2課 縣秀征課長 |
■ 半年かけて「アプコン」のクオリティを熟成
今後のカギは「NR」にあり
-発売から半年経って、ついにアップコンバートが実装されたわけですが、そこまでの流れを説明してください
縣:半年お待たせして、申し訳ありませんでした、というところです。
川西:これは、半年前のインタビューでもお話したと思いますが、普通にバイリニアでやったくらいでは、テレビやパソコンで実現されている程度の品質で終わってしまいます。それでは、Cellだからこその、PS3だからこそのレベルにもっていけない、という気持ちはあったんです。
じゃあ最初からやっとけよ、突っ込まれてしまいそうですが、アップコンバートの品質評価には主観も入りますし、評論家の先生にも見てもらい、検討する必要がありました。そのあたりを勘案すると、クオリティ的に間に合わなかった、ということです。
縣:ようやく、製品として出して恥ずかしくないレベルになったと思います。評論家の方からも、高い評価をいただけています。ただ、先生方はPS3が100台くらい買えてしまうような機材と比べていらっしゃいますから……。
いくつかのテストディスクの結果も見ていますが、まだ、個別の、特定のパターンでおかしい、というところがあるようです。ゴールに近いところまで来ているが、満足はできていない。理想の半分はクリアーしたけれど、あと3割、4割はやっていけると思っています。
川西:Cellのパワーも、まだ使い切っていませんからね。
-本田氏の記事の中に、アプコンの方向性を決める上で、アニメを強く意識していた、という話がありました。アニメを意識したのはなぜでしょうか?
縣:アニメに特化した、と理解されてしまうと、ちょっと違うのですが……。今回の機能というのは、アニメに特化したわけではないです。CGや実写、映画など、すべてで有効に働くものです。
アニメを使っていたのは、IP変換のバグを見つけるのに、非常に都合が良かったからなんです。IP変換をチューニングしないことには、アップコンバートの画質が上がりません。ただIP変換のバグは、自然画だとわかりにいんです。そこで、アニメを使おう、ということになりました。
記事に書かれているように、「AIR」というタイトルは、時間をかけて作られた、考えられる一番きれいなアップコンバート、と言われているので、比較ターゲットとしてわかりやすかった、という事実はあります。ただ、比較評価には、実写の建物や人物、CGなど、あらゆるソースを使った、といった方が正しいでしょう。
アップコンバートは元々、SN比の高い映像の方がきれいになるんです。アニメはその好例です。アニメといっても、ビットレートによって全然違います。そもそも、最近のデジタル制作のものなのか、昔のセルのものなのかによっても、全然違います。
ただ、現状のままでは限界もあります。これからはむしろ、アプコンの質よりも、ノイズリダクション(NR)系の問題になってきます。
-SN比の悪い映像といえば、DVDレコーダで記録したDVDが挙げられます。これについては、さほどきれいにアップコンバートされないようですが……
縣:そうですね。DVDレコーダで録った映像、4MbpsくらいのMPEG-2になると、前段のNRの部分でどこまできれいにできるか、ということが効いてきますね。
もちろん完全にはならない。そこのノイズを、どこまで取り去ってやるかが問題になってきます。現状でも、NRのパラメータは0から3まで用意していますが、あそこで少し強めにかけてやれば、少し良くなるのではないかな、と思います。
今回のアプコンでも、難しかったのは、ノイズなのか、背景なのでエッジをたてるべきなのか、ということを判断するルーチンのパラメータを決めることだったんです。
-そもそも、Cellを使ってNRをすることのメリットはなんですか?
縣:NRだけを単独でかけて、それを受けて……という流れに固定されないことが一番ですね。映像の種類により、NRをかけるレベルを変えることができます。
例えば、ここはノイズだ、とわかってしまっているところだけは、アップコンバートしない、というようなこともできます。画面全体に適応するのでなく、部分部分で最適化できるんです。これは、専用チップではなかなか難しい。
もうひとつ大きいのは、最終的に合成した映像でなく、DVDの映像をデコードしたソースに、直接NRをかけられる、ということです。端的にいえば、PS3なら字幕はあとからかぶせられます。一般的なDVDプレーヤーだと、合成映像全体にNRをかけることになりますが、当然、映像だけをNR処理した後、最後に字幕を合成したほうが、字幕の見え方はきれいになります。
もちろんPS3でも、専用チップとある程度分業はしていますが、作業の流れをフレキシブルに変えることで、高画質化を実現していけます。いままでの機械とまったく違う流れ、というわけではありませんが、柔軟に変更できることで、新しい高画質化の工夫ができる、ということです。
-これからの改善ポイントは?
縣:現在は、効果を体感しやすい、おいしいところにきている、という事情があります。今後は、努力のわりにはちょっとわかりにくい、という形ではありますけれど、地道に向上を続けていこうと思います。NRに関する改善も、その一環ですね。
川西:今はアプコンの話が注目されてきますけれど、今後HDの映像が中心になってくれば、またその中での画質向上があります。今度は、そこが問題になるでしょう。
-1080i収録のBDタイトルの、1080pへのアップコンバートはどうですか?
縣:もちろん、変換については内部で検討してはいるのですが、最終的にBlu-rayのスペックが見えてこないと実装が難しいんです。BDの規格も色々とアップデートがかかっていまして、それが行なわれた際に、処理能力がどのくらい余っているか、というところまで含めて検討している最中です。
今は処理できても、BDの規格があがったときに「処理負荷が大きくなったのでできませんでした」といって引っ込めるわけにはいきません。「残りのこのパワーで、ここまで演算しよう」というところがはっきりしないと、いつにどのような形で、というお話をするのは難しいんです。
-それは、ネットワーク機能などのためのメモリーや処理能力を残しておかねばならない、ということですか?
縣:そうですね。アップコンバートを実装するとしても、最終的な余力によっては、クオリティが多少変わってくることになるでしょう。
-処理能力に余裕があるなら、アップコンバートなどを、リアルタイムに処理せず、多少時間をかけて行なう、という可能性もありますよね。例えば、数フレーム分(0.016秒から0.1秒程度)の処理時間をかけて、じっくりアップコンバートをする、という形などはどうですか?
川西:それはほとんどリマスタリングの世界ですね。でも、リアルタイムが基本ですね、今は。
縣:もちろん、その可能性はあります。しかし、Cellの強みは、映像をリアルタイムで処理することだと思っているんです。
一晩かけて映像をきれいにする、というような形ならば、マシンが遅くてもなんとかできてしまうものです。なので、まずはリアルタイムにこだわっていきたいです。
ただ、リアルタイム処理にも限界はありますから、それを超えていくには、非リアルタイムでの処理が必要になるでしょう。ただその場合にも、結局、普通の人にはわかりにくい、究極のクオリティアップのレベルの世界になるんだと思うんです。
そこで、もう一回大きくジャンプアップするなら意味があると思います。ニーズを含め、色々考える必要は出てくるかと思います。
■ SACDに注力した理由は「Cellを極めたかった」から
DSDディスクの光出力やCDのアップサンプリングも検討中
-音について。PS3が発売されるまで、PS3でこんなにSACDの機能を充実させると思っていた人はいないはずです。なぜそうなったんでしょうか?
縣:いや、フィーチャーしたつもりはないんですけどね(笑)
なぜか、と言われれば、「極めたかったから」ですよ。それは、SACDを、というより、Cellを極めたかった、ということです。
初めは24bit/88.2kHzでしかデジメーションできませんでしたが、24bit/176.4kHzでもできるようになり、金井さん(ソニーで音質チューニングなどを担当する、シニアエンジニアの金井隆氏)とお話ししている中で、実はアンプはこういうことをやっているんだ、こういう音が出るんだ、という話がわかってきたんです。
SACDを鳴らしている時って、Cellはほとんどなにもしていないんですよ。半分以上寝ているんです。ならば、その余力を生かしてなにをするか、どう音を良くするのか、という意味合いにおいて、SACDは非常にいい題材でしたね。
そこで培ったノウハウは、いろんなことに生きてきます。研究開発的な意味合いも込めて、わかりやすいところから、ということでSACDを選んだ、という部分もあったんです。機能の中身としては、「プレイステーション」の世界から離れたところまで持って行ってしまっているかな、と思う部分もありますけれど。
-SACDへの対応などを見ていると、アナログのクオリティに凝るよりも、HDMIでPCMで、きちんとした出力ができる機器に素直に出す、という感じだと思っているわけですが、その理由は?
縣:それはすごく単純です。PS3に搭載されているアナログ出力も悪いものではなく、相応のいい音が出ます。しかし、何十万円のAVアンプと比較してしまうと、部品のクオリティの問題も含め、勝てない部分があるのが事実です。
じゃあ我々が勝負できるところはなにかというと、Cellを使った演算パワーがあるわけです。計算の結果でどこまでできるか、ということを考えて、そこを土俵にしてやっている、というところがありますね。
ただまあ、AVアンプの先、スピーカーまで、ある程度のものでないと品質がわからない、というところまでやってしまっているのは事実です。
我々もやっていてはじめて気づいたり、ソニーのエンジニアと話していてはじめて気づく部分ってたくさんあったんです。
アンプに乗っているチップよりも、PS3の方が性能が高いチップが載っているということを、やっている側は忘れていたんです。アンプがやった方がいいんじゃないか、と思っていたものが、実はそうじゃない。できるだけCellで処理して、PCMで渡してあげた方が音質がいい、ということになったんです。
ですがその結果、HDMIのアンプでないと性能が活かせない、ということになり、間口が狭くなってしまったのは事実なんですが。
-光アウトの活用はどう考えていますか?
縣:SACDの出力については、著作権保護の問題でどうしようもないですが、VAIOなどで作成できるDSDディスクは、そうではないです。あれを光で出せない理由はどこにもありませんので、対応を検討しています。DSDディスクをやったところで、SACDよりさらに小さなマーケットではありますけれど、そこは大切にしたいと思います。
-音楽CDのアップサンプリングはどうしますか?
縣:検討しています。そんなに遠くないうちに出せればな、と思います。こちらも、光アウトから出してはいけない、という話はないので、利用できるようにしようと思っています。
-そのほかの機能は? 例えば、PS3で2ch音声をバーチャルサラウンド化するとか、どうですか?
縣:おもしろいと思っていますよ。内部では色々研究と検討をすすめています。どういうものを出すと喜んでいただけるか、考えているところです。
極端にいえば、AVアンプでやっていたことはほとんど全部Cellでできます。アンプを持っている方にはそちらでやったほうがクオリティがいい、というものもあるでしょうが、テレビにつないで楽しんでいただいている方になら、という形で考えているものもあります。バランス含めて、AVプレーヤーとしてどこまでできるか、考えているところです。
-PS3をジュークボックスにしたい、という声も少なくありません。ロスレスでの取り込みとか、アルバム単位でのシャッフルだとか、そういった機能のサポートはどう考えていますか? また、ウォークマンなどのポータブルプレーヤーとの連動は?
川西:音楽専用のマシンとしての位置づけは、まだ決め切れていないんです。テレビの電源を入れないと聴けない、というものが、どこまで喜ばれるか、SACDのニーズもありますが、一般的なレベルで考えると、どのくらい喜ばれるんだろうか、という話もあります。
ただ、ソニー社内には、ウォークマンや携帯電話もありますし、それらの母艦となるような位置づけで、機能を拡張することはあり得るとは思いますし、そういう認識でいます。
そうなると、動画も考えないといけなくなります。さらには、配信も考えないといけない。一つだけでどうこうできる問題ではないです。
-ということは、配信やサーバー化まで含めた流れが出来た時に、そういった形を見せるということですか?
川西:そうですね。統合的なサービスとしてユーザーに見えないと、単機能に終わってしまうので。配信まで見えてこないと難しいですね。いまは、リッチなプレーヤーとして使っていただく、ということになるでしょう。もちろん、基本は「ゲームで遊んでいただく」ということなんですけど(笑)。
-ゲーム連携という意味では、「仮想サウンドトラック」への対応をやっていただきたいんですが……。Xbox 360では、ハードディスク内やLAN経由で繋がれたパソコン内にある音楽ファイルを、ゲーム中に、ゲームのBGM代わりに鳴らす機能があります。こういったものへの対応はいかがですか?
川西:現状のシステムソフトウエアには、その機能が組み込まれています。ゲームの側で対応してもらえれば、使えますよ。そのうち、そういう機能を持ったゲームも出てくるのではないでしょうか。
その辺は音楽だけでなく、静止画や動画についても同じですね。ゲーム内からの利用が可能です。
■ DLNAは「ビデオレコーダ」に期待
WMV/DivX/DCTP-IPは「検討中」
-現在のアップスケーリングは、BD/DVDと、映像ファイル、ゲームで、全部処理が違うわけですよね?
縣:はい、違います。
川西:ゲームについては、あまりアップコンバートに処理能力を割けないので、それなりのルーチンになっています。
-ゲームについて。現在は、GS(PS2グラフィックチップ。PS3にも内蔵)からの出力にアップコンバートをかけてますよね。GS内部でのレンダリング解像度そのものを上げる方向に変更することはできますか? より画質が向上するはずですが。
川西:いまは、画像出力の最終段でアップコンバートしています。PS2用のソフトの場合、内部でのレンダリング解像度を上げるのは難しいでしょう。ただ、PS1はすべてソフトでエミュレーションしていますから、そういう風にアップコンバートすることは可能ですね。
-DLNAについて。なぜクライアントだけなんでしょうか? PS3は、能力的にサーバーにも向いていると思います。実装しなかった理由は?
川西:PS3は、チューナを持っていませんからね。チューナを持っているデバイスであれば、サーバーになる価値が高いだろうな、と思います。そこが判断ポイントでした。
そもそも、「DLNA」という言葉を知らないお客様も多いので、サーバーとしての存在を強調してしまうと、「使いにくい」、「難しい」というイメージにとらわれそうだったので、今回はクライアントだけとしたんです。
DLNAも、個人的には限界があるかな、と思います。本当なら、ネットワーク経由でファイルがなんでも見えるのがいいのかな、と思うんです。そういう意味では、sambaでもなんでも良かったんですけれど、標準規格がありますから、それを採用した、ということです。
現状では、相手のDLNAサーバーのクオリティなどもわからないので、難しい点も多いんです。実際、DLNAでは、サーバーの能力は非常に高いものが要求されているんです。それは、演算能力だけでなく、ハードディスクやバスの転送速度を含めて、です。
-そういう意味では、ある程度均質なビデオレコーダなどが望ましい、ということですかね。
川西:そうですね。
-では、DTCP-IPは? デジタルチューナを持つDVDレコーダなどと連携するなら必要ですよね。
川西:うーん(笑)。今のところは、まだ検討段階です。
といいますのは、DTCPの暗号鍵をまだ内蔵していないので、それをソフトで解決する必要があります。ですが、できないことではないです。どちらにしろ、やらなければいけないことだとは認識しています。
-PCをサーバーにすることはどのくらい想定しているんですか?
川西:今使われている人の多くは、PCリテラシーの高い方だと思っていますから、PCで一般的に使われるDLNAサーバーとの相互接続性は、最初に注力しました。あと、NAS的な製品ですね。
-PS3にしてもPSPにしても、PCとの連携があると活かせる機器なのに、SCEからはPCソリューションに対する言及がほとんどありません。正直、一般のユーザーにはわかりにくい、伝わっていないという印象は否めません。解決策はありますか?
川西:そうですね。それは、PSP側の問題と認識してます。PS3を開発する上で、PS3がPCに変わる、PSPの母艦となることを想定していたので、PCでそれが出来てしまうと「PS3いらないじゃん」ということになるな、という意識があったのは事実です。立場的にそういう事情はありました。
ただ、PS3と同時にPlaystation Networkが始まっていて、ネットワークのサービスという観点でいうと、どんな端末もつながるので対象となる可能性があるわけです。ですから、当然PCの活用は視野に入れています。
-気になるのは、映像ファイル再生時のIP変換なんです。どうもクオリティが一定しておらず、画質が悪い時があります。PC側で作成したファイルの問題だろうとは思いますが……。
川西:正直、我々の中でも、PCで作成したファイルの再生品質をどこまで保証できるのか、という部分については、答えができていないんです。SCE側で、ファイルの形式に関して、現状がある程度把握できれば、解決できる部分もあるんでしょうけれど……。「MPEG-4だ」と謳っているにもかかわらず、全然トンチンカンなデータが送られてくることもありますからね。それを救うのも、けっこうな労力なんですよ。
縣:こちらとしては、規格で決められている範囲で、それに従って高画質化するアルゴリズムを組んでいるんです。そこに「規格外」のものがきますから、それをきちんと再生するには、当然追加の処理が必要になるだろうと思います。
川西:今は、できるだけいろんなファイルが再生できるようにしたい、という思いの方が強いです。
-いろんなファイルを再生できる様に、と考えるならば、WMVとDivXへの対応が必要ではないかと思うのですが。
川西:どちらも、特定の会社さんが利用しているファイルなので……。業界のスタンダードな規格というわけではないので、時期を見て対応を検討したい、というところでしょうか。
-でもWMAは対応していますよね?
川西:需要は重々承知しています。
-WMV対応アップデータをPLAYSTATION Storeで500円で売るとかは?
川西:そこまでえげつないマネはしませんよ(笑)。ただ、「相手がマイクロソフトだからやらない」とか、そういうお話ではないです。
■ リモートプレイで自宅のPS3起動も可能に?!
PSP以外で利用する可能性も示唆
-リモートプレイについて。狙うところは、できれば外からゲームをやってもらう、ということですか。
川西:そうですね。リモートプレイをゲームの中で活かせるようなSDKも、ゲームメーカーに公開しているので、そのうち使ったゲームが出てくるでしょう。
たださすがに、どんなゲームでもできるかというと、そういうわけではありません。遅延があるので、アクション性の低いゲームや、カジュアルゲームがメインでしょう。
-出力は、SDKで対応しないといけないんですか? 単純に、フレームバッファを横取りしてエンコードして出力する、という形ではだめなんでしょうか? そうすれば、どんなゲームでも対応可能ですけれど。
川西:実は、内部ではそういう形でも動いています。でも、ゲームの場合、ハードのリソースを全部使い切る場合もあるので、エンコードして出力するだけのパワーをさらに使うと、破綻する場合もあって、完全な動作保証が出来ません。ですから、やはりゲームメーカー側で配慮してもらった方がいいだろう、ということで、その機能は封印してます。
縣:それに、ボタンの数も違いますしね。
-現状のリモートプレイの、最大の問題としては、自宅を出る時にPS3を付けっぱなしにしないといけない、ということがあります。ちょっと現実的ではない。解決方法はありますか?
川西:まあ、楽しみにしててください(笑)。それができないと、やった意味ないですよ。
-PSP以外で使えるようになりますか?
川西:いい質問ですね。ノーコメントですけれど、色々想像してみてください。技術的には、どんな端末でやっても差はないでが、サービスとしてどこまで対応するか、ということです。
■ アップデートは「使っていただける限りやる」
トップが変わっても方向性は変わらず
-現在の、システムソフトウェア開発のスパンは?
川西:四半期に1回大きなものを、というイメージです。このくらいが、開発の体力的にはいいかな、と思います(笑)。
-いつまでもやるんですか?
川西:PS3の怖いところは、ハードディスクの容量があればどこまででも出来ちゃう、ということですね(笑)。
止めないですよ。使っていただける間は、手を変え品を変えてやります。というかですね、楽しいんですよ。お客さんの声を聞きながら、「じゃあ次はこれをやろうよ」といって開発を進めていくのが。PSPもそうです。いろんなユーザーさんの環境を見ながら、満足していただけるようなポイント、思っていなかったようなことを見つけ、改善していくのは楽しいですよ。
-でも、終わりが見えないのってつらくないですか?
川西:いや、それは、ネットワークビジネスである以上、宿命です。やり始めたら止められない、不退転の決意で。
縣:といっても、全然見えない方向に進んでいるわけではなくて、「とりあえずここまでできた」、「次はここまでやろう」というマイルストーンはありますからね。
-他の製品との兼ね合いとかを考えたことはありますか? 現時点でも、色味の違いこそあれ、クオリティや機能のレベル的には、他のBDプレーヤー/レコーダに並んでいます。今後アップデートを繰り返していけば、超えることもあるでしょう。クオリティ競争でいえば、一般的な家電用プロセッサを使う側に、かなり不利だと思うんです。
これが全部他メーカーならば、行け行けドンドン、というところでしょう。しかし、実際には、自グループ内にもライバルがいることになります。それを気にすることはありますか?
川西:とても立場が難しいところですけれど……。ただ、「ここから先は出来るけどやっちゃいけない」みたいなことは、ないです。それをやったら、もう、エンジニアとして終わりですから。そういう枠はかけません。
縣:ただ、2年後、3年後のハードとも戦っていかなければならないので、いつまでも有利、というわけではないですけどね。そう考えると、今のうちに差をつけておかないと、すぐに抜かれてしまいます。
川西:まあ、Cellもどこかで限界が来てしまうとは思うんですよ。1台でやれるパワーには限りがあります。その次に、つないで行く世界、みたいなところにいければな、と思うんですけれど。
-久夛良木さんがいなくなることで、方向性が変わることはあり得ますか?
川西:ないです。
-というのは、トップが久夛良木さんから平井さんに変わることで、「もう、AV的にスゴイアップデートは1.8で終わりじゃないか」みたいに言う人もいるわけですよ。久夛良木さんは生粋のAVマニアですから、その影響力が弱まると、AV機器としてのプライオリティは下がるのではないか、と。
縣:そういえば、すごいタイミングですね(笑)。完全に偶然なんですけど。
川西:そんなことはあり得ないですよ。AVのテクノロジーは、ソニーのお家芸・伝統芸ですから、それをないがしろにすることはあり得ないです。
ただ、ビジネスの主体がどこに置かれるか、という点については、また別ですが。
-PS3は非常にパワフルなハードウエアですが、性能を使えば使うほど、消費電力やファンノイズが大きくなります。AV機能では、ファンノイズなどが課題になることも考えられますが、どこまで負荷をかけますか?
縣:現時点のアプコンでは、まだまだピーク時でもパワーは余っているのは確認しています。その余力でなにしようか、と考えているところです。
一方で、ソフト作りのフェーズとして、とにかくきちんと動くようにするレベルと、それを最適化してCPU負荷を下げるレベルがあるわけですが、現状のものは、まだ最適化が行なわれているとは言い難い段階です。可能性として、最適化を追い込んでいく、という流れもあります。
しかし、負荷が下がった分だけ、画質を上げようとか、みなさんが望む機能を入れていこうか、という考えもあるので、現状から劇的に負荷が下がるか、というと……。せっかくのパワーを余らせて静かにするべきなのか、という点については、議論があるところだと思います。そもそも、機能を切れば負荷はかからないわけですし。
川西:といっても、Folding@Homeよりは、全然つかっていませんけどね。可能性を閉ざしてまで消費電力を下げる、というよりは、いいところで落ち着くんじゃないでしょうか。また今後、ハードウエア的な改善策が採られる可能性もあります。例えば、現行の薄型PS2はファンレスですが、将来的に、PS3もそうなる可能性はあるでしょう。
縣:もちろん、処理が一番重いところでも快適に使っていただける、という前提はありますが。
-PS3の可能性として、まだ機能的にのばせる部分はどの辺だと考えていますか?
川西:映像とか音声は今の延長線上で進化していくでしょう。ただ、入出力を考えると、色々できると思います。入力された映像などから演算して、それをなにかに活かす、という形の機能です。
縣:絵も音も、まだ仕込んでいる機能はありますので、お楽しみにお待ちください。
□SCEのホームページ
http://www.scei.co.jp/
□アップデート情報
http://www.jp.playstation.com/ps3/update/
□関連記事
【5月28日】【AVT】専用プレーヤーを超える「PS3」アプコンの秘密
「“Air”BD版と同レベルを目指した」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070528/avt007.htm
【5月24日】アップスケール対応のPS3「1.8」ファームを検証する
-DVD画質は大幅向上。強力なマルチプレーヤーに
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070524/sce2.htm
【5月24日】SCE、PS3のアップスケール対応ファームを日本公開
-BDビデオの1080/24p再生対応。ネットワーク再生も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070524/sce1.htm
(2007年6月14日)
| = 西田宗千佳 = | 1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に、取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、「ウルトラONE」(宝島社)、家電情報サイト「教えて!家電」(ALBELT社)などに寄稿する他、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。 |
[Reported by 西田宗千佳]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.