 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
|
西田宗千佳の ― RandomTracking ― パナソニック/PHL関係者が語る「3Dに行く理由」
|
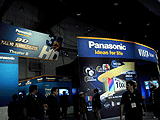 |
| CE会場に設置されたパナソニックフルHD 3Dプラズマシアター |
今年のCESでは、多くの家電メーカーが「家庭における3D映像」の着手を表明した。その先駆けとなったのが、昨年のCEATECにてパナソニックがアピールした、「プラズマとBDでの3D映像」にあることは間違いない。
では、なぜパナソニックは、急激に「3D」へと舵を切ったのだろうか? 「3Dシフト」の仕掛け人は、BDフォーマットの確立に大きな役割を果たした、同社蓄積デバイス戦略室と高画質高音質開発センター、そして、パナソニックハリウッド研究所(PHL)の人々である。CESで発表された「パナソニックハリウッド研究所アドバンスドオーサリングセンター」(PHL-AC)設立の話題を中心に、パナソニックが狙う3Dの世界について、蓄積デバイス事業戦略室室長・小塚雅之氏、AVCネットワークス社 技術統括センター 高画質高音質開発センター参事・末続圭介氏、そして、PHL所次長・柏木吉一郎氏に聞いた。
 |
 |
| パナソニック 蓄積デバイス事業戦略室室長 小塚室長とPHL柏木所次長 | 3Dシアターでデモを実施 |
■ 次は「4K」ではなく「3D」だ! 重要視するのは「WOWファクター」
-CESの3Dシアターのシステムは、CEATECのものと変わらないんですよね。
 |
| 蓄積デバイス事業戦略室室長 小塚室長 |
小塚:はい。一応CEATECの段階で、ビデオストリームとしてどうなるか、という話については見えたと思っています。
パナソニックの3Dシステムは、意外と特殊なことをしていない。プラズマディスプレイを120Hz駆動し、1フレーム単位で右目用の映像を左目用の映像を入れ替え、それに同期して、液晶シャッターで片方の目の前をふさぐ、というものだ。「フルHDの解像度」「60Hzのフレームレート」の2点を除けば、1980年代末から存在するテクニックである。末次氏も、「新方式ではなく、当たり前のことをやっただけ」と話す。
時期は明確にできないが、パナソニックが3D技術に取り組み始めたのも、そう昔の話ではない、という。
末次:一生懸命に、BDとプラズマの技術開発ををやっていたら、3Dができちゃった、というイメージです。でもやっぱり、フルHDと60Hzというクオリティが揃うと、いままでの3Dとはまったく違うものができるんですよ。
実はCEATECの後、来場者にアンケートをとったんですが、7割の人が「3Dに対する認識が変わった」と答えています。「seeing is believing」で、見なければ絶対にわからない。弊社幹部にも、3Dに懐疑的な人がいたんですが、つれてきて見せると「いいやん、どんどんやろう」と気持ちが変わる。いろんな技術開発をやってきましたけれど、これほど、見た後に反応が変わる技術というのはないですね。
-今年のCESは、すっかり「3D」一色。BDAの会見でも、2009年の方向性として、BD-Liveやデジタルコピーとともに、「3D」がフォーカスされました。
小塚:ぼくが驚いたのは、DEGのレセプションにて、DEGが2009年に目指す3つめのイニシアチブとしても、「3Dやるぞ」と宣言したことです。
CETATEC以降、みなさんが色々と活動されて、スタジオの側も、「これならいけるんじゃないか」という意識を持った、ということなんじゃないでしょうか。
DEGとは、映画会社や家電メーカーなどで構成される、映像コンテンツの業界団体。昨年設立されたDEGジャパンは、この日本版にあたる。BDAがあくまで「BD」のための団体であるのに対し、DEGは「コンテンツ供給の今後」を、コンテンツ・メーカー(すなわち映画会社)の側から考える団体、といえる。DEGが3Dに本腰になったということは、コンテンツ供給側が「3Dの導入」に本腰を入れた、ということだ。
-シンプルな疑問があります。ここでなぜ「3D」なのか、ということです。
小塚:重要なことは、いかに市場を伸ばしていけるか、ということです。
アメリカの場合、放送がHD化するといっても、画質はあまり良くないので、その面での牽引力には疑問があります。ロスレスは確かに重要だし、すごく魅力的だけれど、全員が全員、理解できるというものでもない。
だから、ハイデフの魅力の上に、ロスレスで上乗せして、Javaで上乗せして、BD-Liveで上乗せして……といった形で、少しずつでも魅力を上げよう、と考えてBDを作ったんですよ。
それは今も共通です。3Dというのも、そのワンフィーチャーなんですよ。BDのフォーマット戦争が終わったからじゃなく、BDのためにやってるんです。
-それは、すべてをハイデフの一言だけでひっぱるのは難しい、ということですか?
小塚:日本では、そうは言えないでしょう。でも少なくとも、アメリカ人はそう思ってますね。
 |
| パナソニックAVCネットワークス社 末次氏(2008年9月撮影) |
末次:確かに、ちゃんと作った4K2Kのコンテンツは、鳥肌が立ちます。ですがポストHDの姿として、4K2Kというのと、3Dというのとでは、得られる臨場感の違いと、技術的なハードルの高さを考えた場合、コンテンツのアベラビリティを考えた場合、どちらがいいか、といったら「まずはこちらの方が良さそうだね、こちらが先決なんじゃない?」という発想です。
-個人的にも、民生の「次」は単純な4Kではない、と思っているんです。リニアに伸ばすだけでは、体験は変わっていかないじゃないですか。
小塚:おっしゃるとおり。SDからHDだって、もちろん価値は大きいんですけれど、内部では「本当にすべての人に響くのかな」という議論はあったんです。3Dになると、WOWファクター(驚きの度合い)は全然違いますから。
 |
| PHL柏木副所長 |
柏木:2Kが4Kになるのと違って、2Dが3Dになるというのは、オーディオが2chから5.1chになるのと、同じような変化なのかな、と思っています。
だからですね、そのときに、2chからドルビーAC3(ドルビーデジタル)に行くんじゃなくて、2chからTrueHDに行くんだ、と。そういう考え方ですよ。中途半端なことはしないんだ、ってことです。
小塚:3Dはプラズマの拡販だ、と言われます。確かに、少しでもテレビ事業を持ち上げられるものを提案したい、とは思っています。ビデオ関連事業の規模は3,000億円くらいですが、テレビは2兆円。失敗はできないですし、(会社側から)かかってくる期待度・プレッシャーが明らかに違うんです。
ですが、だからといって、プラズマ事業があるからやるわけではない。うちはすごくわかりやすいんですよ。自分が見たいと思うものを作る。そうじゃないものは作らない。「まずはちゃんと3Dをやろうよ」という気持ちです。
映画館で3Dを見ると、やっぱり面白いんです。うちのメンバーも好きなんですよ。キャメロン監督も本気でやっていますしね。まじめに、3Dを出したいんですよ。
末次:デモでは、3D映像の撮影でトップクラスのノウハウを持つPACE Technologiesの協力を得て作成したクリップを使っています。彼らは、「3Dっていうのはエンターテインメントにレボリューションを起こすんだ」という意識で作っているんですよ。今回、同社が撮影に使っているカメラをかり出して展示しているのですが、その説明文に、社長のヴィンセント・ペイス氏自身が、「Revolutionalize Entertainment in 3D」という言葉を追加してきたくらいなんですよ。
■ 規格化は「骨太の方針」で可能性の高い「高画質」を貫く
-CESでも、様々な3D方式が提案されています。その中で、BDでの規格化に関し、パナソニックの提案が採用される自信は?
 |
| 65型PDPによるデモ機も |
柏木:我々が提案している内容は「ど真ん中」なんですよ。本当に技術として良い物にしよう、という意識で提案しているので、他社としても反対する理由がないというか、反対しづらいんです。
小塚:パテントをより取りやすいとか、そういうことじゃない。「うちとしてはこっちの方がビジネス的にはいいけれど、クオリティはこちらだよね」という選択をするんです。
例えばBDの中に、映像ストリームを両目分入れると帯域が足りない、という話があります。なので、720pに落としては、という議論があります。我々の中にも「3Dでは720と1080でそんなに違わない」という声もありました。
でもね、(2Dの世界で)もう720より1080の方がいい、ということを、みなさんご存じじゃないですか。そこで、1080でもできるのに720に落としちゃうというのは「違う」でしょう。
柏木:確かに多くの人には、Side by Side(BS11などでも使われる、3D表示方式。解像度は大きく落ちる)とフルHDの違いがわからないかも知れません。
だけど、コンテンツを作ってみたら、歴然とした差が生まれてくるかもしれない。
やってみなきゃわかんないんですよ。規格の段階で制限してしまっては、その可能性を閉ざしてしまうことになります。
規格としては、できるかぎり許容できるようにしておかないといけませんよね。我々としては、規格を決めるときにたいていそういう方向に持って行くので、反対する理由もあまりないと思います。
小塚:少なくとも骨太。基本路線はそうです。
柏木:逆に言えばね、別の理由で別の方向を選んでしまうようなら、独禁法に触れますよ。
-他方で、メガネゆえの「酔い」や「違和感」も問題ですが。
柏木:確かにメガネなしが望ましいのは事実。ですが現時点で3Dの良さを体験するためには、メガネをかけることが必要だろう、という判断をしています。
-裸眼で見られるレンチキュラーレンズなどを使った方式では、画質的に満足できないだろうと?
柏木:映画に集中できないだろう、ということですね。1時間半映画を見続けるには……。
小塚:解像度はぐっと落ちるし、ちょっと視野を動かしただけで映像がちらついてしまう。それでは、映画を集中して楽しむことはできないですよ。
■ 狙うは「エンターテインメントの革命」
細かなノウハウと調整が「高画質」の秘密?
 |
| 撮影に用いられたPACEの3Dビデオカメラ |
-3Dの撮影は、まだまだノウハウ構築も途上ですよね。
小塚:はい、非常に難しいものです。やっぱり、(デモで使っている)NHKが撮影したものや、キャメロン監督と組んでPACEが撮影した映像というのは、すごくしっかりしていますよね。わかっている人が撮影すればクオリティが高くなります。そこは、コンテンツを作る方々にお願いする部分です。
柏木:彼らは真剣に取り組んでいる。だからクオリティが高いんですよ。
小塚:我々はアニメを作るわけではないので、やっぱりそこもディズニーさんなどにお任せするしかない。
3D撮影用のカメラにしても、今は我々が作っているわけではないです。ひょっとすると我々も作るかもしれないので、ノウハウはきちんと吸収させていただきたい、とは思っていますが。だからこそ、トップランナーであるキャメロン監督やペイス監督と組ませていただいているわけですよ。
柏木:そもそも、映像の制作時期でも相当違いますよ。たとえば同じディズニーでも、「スパイキッズ」と最新CGアニメの「BOLT」ではかなり異なる。どんどんノウハウが高まっている成果だと思っています。驚きのためではなく、ストリーテリングの中で「立体感」が生かされ、臨場感を高めるために使われるようになってきているのです。
今回、何回か連続で、パナソニックの3D映像のデモを見ることができた。CEATECのデモをさらに洗練させ、PACEのクリップやディズニーの「BOLT」などを加えたものである。その出来はすばらしく、「パナソニックの3D技術の評判がいいのは、コンテンツが特に丁寧に作られているからだ」と語る技術者もいたほどだ。
特に、「BOLT」の映像を見ている時、ちょっと面白いことに気がついた。3D映像が立体に見える理由は、右目と左目の映像の「視差」にある。だから、メガネを外して映像を見ると、映像は左右にぶれたような感じになる。このぶれが、画面の「上部」と「下部」で違ったり、同じシーンなのに細かく変化したりしていたのだ。
通常この「視差によるぶれ」は、画面全体・シーン全体で一様である。例えば、視差が画面の上下で違うということは「画面の上と下でピントがあっている場所が違ったり、立体感が異なっていたりする」ということであり、普通にはあり得ない状況だ。
だがBOLTでは、同じシーンの中で、同じフレームの中で視差を細かく調整している。狙いは「どこがどのくらい立体的に見えるか」を調整し、視線を誘導するためだろう。
これにより、映像はあきらかに見やすくなり、臨場感が増している。「きちんと立体に見えない」「自分が見たい場所が飛び出して見えない」といった、3D映像につきものの違和感を減らす狙いがある、と見られる。単純に立体映像にするのではなく、「見せたい意図」が、視差の形で演出されているのである。
逆にいえば、映像を見やすくするには、そういった「意図」が重要になる。
柏木:放送はどうなるの? といったご質問をよく受けますけれど、放送は相当難しいだろうな、と思います。わからないことが、映画以上にたくさんあるんですよ。それを解決していて時間をかける、ということはしたくない。
小塚:ディレクターズ・インテンション(制作者の意図)を映像に反映しづらいですからね。違和感を感じる人や、「酔う」人が、映画よりもずっと出やすいでしょう。
だから僕たちは、まず「きちんとクオリティが維持できる映画からやろう」と考えているんです。
■ エンコードが悪いと「3D酔い」につながる?
-放送にも関わってきますが、エンコードには大きな問題がありませんか? 3Dになると情報量が増えるので、映像に割ける帯域が減る可能性があります。圧縮率が大きくなると、映像が平坦化して立体感が失われる可能性が高い。2Dでは気にならなかったものが、3Dでは気になってくる可能性もある。
柏木:すごく重要になるんじゃないか、と個人的には思っています。
もともと2Dの絵でも、立体感を感じる絵というのは、フォーカスがきっちりと合っている部分と、そうでない部分がしっかりと表現されていないと、制作した人が意図した形にならないんです。悪いコンプレッションだと、そういった意図が失われます。
それが3Dになると、人間の頭の中で感じる距離感と、(圧縮の段階で失われた立体感により)映像のフォーカスが違ったりすると、きっと混乱して気持ち悪くなるでしょう。
ですから、クオリティはすごく大事になってくると思いますね。
-ということは、3Dといっても、まずは2Dできちんとしたクオリティが維持されていないとダメ?
小塚:完全にそうでしょうね。
柏木:おそらく、そういう部分での差が、後々問題になってくるんじゃないかな、と思っています。そのほかにも、左目用の映像と右目用の映像の品質をどのように均質にするかは、悩ましいところです。
例えば、ボーナスコンテンツをばんばん入れたとします。そうすると、(メインの)ビデオの帯域はぎゅっと圧迫されることになります。すでに述べたように、圧縮で映像のディテールが失われると、立体感が失われて気持ち悪い絵になる可能性がある。そういった問題を解決するのは、重要な技術開発の要素になると思います。
-いまですら2層ディスクを使い切りがちなのに、3Dになって帯域が増えて、ほんとうに大丈夫なのですか? 2層でいいのか? という気にもなってくるんですが。
小塚:ビジネスとしては単純ですよ。2層から変えない。2層に入れる。
ディスク(の物理フォーマット)を変えたら、できないですよ。出来る範囲でやる、ってことです。ボーナスコンテンツは別にしちゃってもいいわけでしょう? ディスニーの大作などは、すでに2層を2枚、100GBですからね。それが増えていく、ということになるでしょう。
柏木:今のBlu-rayだと、1枚のディスクに最高の画質・音質のコンテンツとボーナスコンテンツ、という感じですよね。これがDVDだと、ディスクの中には映像コンテンツだけ、という感じです。3Dになったら、それと同じになるのかな、と。
-すなわち、3Dで最高の画質・音質のコンテンツのみが1枚のディスクに入る、と。
柏木:ええ。Blu-rayの規格を決める時に、かなりスペック面で上の方に決めましたから、そういう余裕がある、ということです。
だけどそれでも、我々が提案している符号化方式ならば、単純に2本のストリームをバラバラに入れるのに比べれば有利です。これが、単純に2ストリーム入れると、本当に50GBで本編しか入らない、という感じになります。そういう意味では余裕がある。ボーナスコンテンツを入れる余地がある。片側の50%くらいでも稼げれば、と思っています。
-ディスクは、2Dと3Dで別に必要になりますよね? ユーザー数を考えると、3Dのディスクだけを売りたい、っていうスタジオはないんじゃないかと思うんですが。
小塚:それは色々みたいですね。各社で、様々なマーケティング方針を持っているようです。
規格では、「3Dのディスクを普通のプレーヤーにかけた場合は、2Dで表示されねばならない」といったことを決める、とは言われています。そこで、2Dのディスクと3Dのディスクを完全にわけて、パッケージ内のディスク枚数を増やすかどうかはまた別の話で、判断次第でしょう。
■ ありとあらゆることが「わからない」。視聴距離も短縮?
-今回設立したPHL-ACでは、そういった部分のトライアルを続けることになるわけですね。
小塚:とりあえずエンコーダは変えないといけないですね。ここはノウハウの固まりになります。ですが、まだまだたくさんやらなければいけないことはあって……。
-例えばDVDやBDの時には、PHLではカラーコレクションのような行程を開発していますよね。劇場でかかる3D映像と、家庭で見る3D映像とでは、なにか変換などを行なうことになるんでしょうか?
小塚:結論からいえば、よくわかりません。
DVDの時は、フィルムからビデオテレシネしてビデオマスターを作る、という段階がありました。そのときには、もちろん監督さんに立ち会っていただいて、演出意図をくみ取って映像を作ります。ここで演出者の意図、ディレクターズ・インテンションが反映されているわけですから、それをそのままマスターにすればいい。
3Dに関してよくわからないのは、「HDテレシネ」にあたる変換作業があるのかないのか、ということなんです。なぜなら、現在(3D対応の)映画館でかけられている映像というのは、元々デジタルデータ。だったら、変換いらないじゃないですか。
でも、なにか「変換」しないといけないものがあるかも知れない。そこがわからないんですよ。
柏木:いらないかも知れないし、必要かもしれない。
キャメロン監督なんかがはっきりとおっしゃっているのは、「劇場でかかっているものをそのまま民生でも流す。モニターサイズが小さくなったからといって、なんらかのパラメータ変換を行なうようなことはありえない」ということです。
例えば、テレビの視聴距離に関しても「画面の高さの1.5倍から2倍」にまで近づいて、「かぶりつき」で見てください、という話になっています。
-現在は、SDのテレビだと、視聴距離は縦の6倍から7倍、HDだと3倍、という話になっていますよね。それが1.5倍になるということですか?
柏木:というのは、映画館の設定がそのくらいになっているからです。となると、我々の側で、現時点でそれを「変えよう」、とは言えない、ということです。
小塚:だから、その辺も本当にわからないんですよ。
キャメロン監督も、今は103インチの画面にかぶりつくように見てチェックされているんですが、ひょっとすると、明日には意見が変わるかも知れない(笑)。そういう検証も、これからやりたいんです。
-じゃあ、テレビのサイズはどのくらいを想定しているんでしょうか? 3Dでは、従来以上に大型であった方が効果的ですよね。
小塚:正直にいえば、わからないです。ですが、わかりやすい辺りで50インチかな、と思っています。
柏木:日本のご家庭には、55から58インチ、それ以上はなかなか置けないでしょうね。2Dの時以上にサイズが効いてきますから、できれば65インチ、あわよくば103インチ、可能なら壁全部、といいたいところですけれど。
小塚:42インチは小さいでしょうね。だいぶ印象が違うと思います。ゲームはまた別でしょうが。
■ 3Dで「字幕」はどこに入れるのか。勉強時間は「残り1年」?
-オーサリングというと、映像ストリームだけの話ではないですよね。
柏木:はい。そちらにも、ややこしいことになることがたくさんあります。
映像ソフトの場合、映画館で本編を流す時と違って、字幕やメニューが必要になります。その絡みがむずかしい。
例えば字幕。本編の上に乗っかってくるわけですから、それをいかに重畳するのか、という話があります。いかにも悩ましそうでしょう?
-それは、どの「深さ」に字幕を置くのか、という話ですよね。
柏木:そう。映画会社側も、全編に字幕が入った状態で確認した映像を送ってくるわけではないですからね。
小塚:特に日本語はたいへんですよ。横に出るだけじゃなくて、縦に出たり、重なったりしますし。
柏木:例えば、16:9のフルサイズで絵が出ているものだったらどうするの? ということもあります。
シネスコだったら下に出しておけば重ならないですけれど、フルフレームの絵が来たときに、映像に黒縁をつけるのか、映像に重ねてしまうのか……。絵に重なって白い字幕が出て、それが3Dになったときに読めるのか、みたいなことも試してみないといけません。
小塚:品質保証も問題ですね。
例えば、3Dの映像を2Dで見る場合には、左側のフレームだけを見ることになるんですが、そのとき映像に破綻がないかどうか? 画質確認のためのワークフローが、2Dの時とは全然違ってきます。それだって作らねばならない。
柏木:その上で、色々映画会社に対してフィードバックし、そのノウハウを蓄積してタイトルに生かしていく、という形になりますね。これまで2Dで、DVDやBlu-rayなど色々やってきましたけれど、そのどれよりも、3Dはオーサリングステージでの確認作業が重要になるだろうな、と思います。今まで以上に、オーサリングのステージで得られるものの価値が高くなるでしょう。
小塚:CEATECの後なにをやっていたのかというと、実際にディズニーやワーナーなどを回って、作ってみたメニューなどを見せながら試して……と、いうことをやっていたんです。そんな中で、少なくとも我々はいけるんじゃないか、という感触を得ました。
柏木:まあ、(オーサリング用の)基本ツールとして、こんな機能はもっていなきゃいけないよね、という話は出していただいた、というところですかね。
だけど、繰り返しになりますが、ここから、実際に商品(映像ソフト)としてのソフトウエアを作っていく段階で決めなきゃいけないことには、きっとまだまだ悩ましいことがあるだろうな、とは思ってるんですよ。
小塚:規格を決めるステージで悩まなきゃいけない部分と、本当にクリエーションとして悩まなきゃいけない部分、両方があるわけです。BDでJavaを使う、という風に決めた場合を例にとれば、どのくらいのスペックで動くかとか、どのくらいの絵が動かせるか、という部分を決めることと、実際にコンテンツを作る上でなにが必要なのか、ということは、やってみないとわからない。
だから、早いうちに着手したい。やったことないんですから。
商品化が来年といっているから、もう1年くらいしかない。DVDの時も、規格化の1年くらい前からオーサリングについては色々やっていましたからね。
柏木:早く立ち上げなきゃ、という意味もありますが、「早く勉強しなきゃ」という気持ちもありますね。
小塚:まあ、「受験まで1年だからもう受験勉強始めるぞ」って宣言したようなものですよ(笑)。
■ 映画特化で「一番いいもの」を狙う
-撮影からオーサリングまで、まだまだ検討課題が多いようですが。
小塚:やってみないとわからないことだらけです。でもね、だから楽しいんじゃないですか(笑)。すでにできあがっている映画に対し、カラコレやエンコードなどの処理を作り上げていった経験はありますが、撮影監督や映画監督と一緒に最初から作っていける、というのは初めての経験です。これが楽しい。
-ここまで急ぐ理由は?
小塚:遅くなれば遅くなるほど、お客様に迷惑がかかるからです。
だって、日本では2011年にアナログ放送が停波するわけですよね。それまでには導入した方がいいでしょう? みなさんの買い換え需要が出る時には3Dの商品があるようにしたい。3Dに意味を感じていただけるかどうかはまだわかりませんが、「3Dがあるんなら買おうか」と思っていただけるとありがたいです。
でもですね、そういった目的のために変なものを提案するつもりはないんですよ。半端なものをだしてはダメだと思います。最初からきちんとしたクオリティのものを提供したい。先ほど、「放送より先にクオリティの高い映画を」とお話したのはそういった理由です。
柏木:いま、第3次3Dブームとか、第5次ブームだとかいわれているんですが、またこれまでの「ブーム」という並びではダメだな、と。下手すれば次はない。それを、市場が熱いうちに出したい。鉄は熱いうちに打て、じゃないですけどね。
小塚:3Dって生まれたての子供みたいなものです。そこに毛布もかけないでいたら死んじゃうんですよ。だからやっているんです。
-それは、「いろんな問題がすべて片付いて、すべてのコンテンツを3D化できるまで待ってスタートする」のではなく、まずは一番いいものをガン、と出して、そこから「3Dっていいな」と思ってもらおう、という戦略ですか。
小塚:その通り。意外と高い理想を掲げてやってます。まずはね、映像体験だけでも良くしたいじゃないですか。
□パナソニックのホームページ
http://panasonic.co.jp/index3.html
□ニュースリリース
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn090108-10/jn090108-10.html
□関連記事
【1月8日】【CES】パナソニック、8.8mmの薄型PDPや3D戦略を披露
-VIERA CASTでビデオ配信。世界初ポータブルBDも
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20090108/ces03.htm
【1月8日】パナソニック、3D版Blu-rayソフトの制作センターを開設
-ハリウッドのPHL内に設置。3D版BDの試作開始
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20090108/pana2.htm
【2008年9月24日】【AVT】3D実用化に本気で取り組む松下の新技術
プラズマの特性を生かし、BDプレーヤーの互換性も確保
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080924/avt032.htm
【2008年9月24日】松下、Blu-rayとPDPを使ったフルHD 3D
-劇場の3D対応にあわせ、規格化へ。CEATECに出展
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080924/pana.htm
(2009年1月22日)
| = 西田宗千佳 = | 1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に、取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、読売新聞、月刊宝島、週刊朝日、週刊東洋経済、PCfan(毎日コミュニケーションズ)、家電情報サイト「教えて!家電」(ALBELT社)などに寄稿する他、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。 |
[Reported by 西田宗千佳]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.