| 本田雅一のAVTrends |
音の匠が「理論と経験」の両面から突き詰めたBDレコーダ
「BZT9000」高音質化プロジェクトはこうして進められた
 |
| DMR-BZT9000 |
パナソニックのDMR-BZT9000は、同社のBlu-rayレコーダ開発チームにとって“悲願”とも言える製品だ。実売37万円のレコーダ最上位機のため、たくさん売れる製品とは言い難い。しかし、この製品は開発チームのメンバー自身が、自分たち自身で使いたい、作りたいと思ってきた製品企画を5年越しで実現したものだからだ。
本誌の読者の多くは新DIGAシリーズの注目点として、3チューナ+1スカパー! 外部チューナーによる4番組同時録画や、制限を大きく改善したレコーダとプレーヤー機能の同時動作、改善の進んだAVCエンコーダなど、レコーダとしての基本機能に目がいくだろう。当初は動作制限が多く不自由の多かったBDレコーダも、地デジ終了後のレコーダ買い換え需要を目指し、この世代における改良はパナソニックだけでなく、どのメーカーの製品もめざましい。
そんな中にあって、よりグレードの高い部品を用いることで、画質、音質ともに高めたプレミアムモデルは異分子に見えるかもしれない。本当に部品のグレードひとつで、そんなに製品の質が変わるものなの? そうした疑問を持っている読者は、決して少なくはないだろう。一方で、毎年プレミアムモデルが継続できていることを考えれば、頭の中だけで完結する理論よりも、結果としての目の前に見える映像と聞こえてくる音を評価しているAVファンも少なくないはずだ。
とはいえ、今年のモデルは今までよりも、さらに何歩も踏み込んだ豪華仕様だ。3mm厚のアルミ天板や側板、3種類の共振点が異なる異種材料を重ねたレイヤードシャシー構造が、デジタルの映像と音に、そんなに効くのか? といった疑問を持ってもおかしくはない。従来から電源部やアナログ出力部には、高グレードのオーディオ向け専用品がプレミアムモデルに採用されてきた。
これらは、画質・音質を担当者がひとつひとつ評価しながら良い部品を探し出し、採用しているものだ。しかし、今年はもう一歩、前へと踏み込んだ。同じプレミアムモデルでもBZT910が部品グレードを向上させているだけなのに対して、BZT9000ではコンデンサのリード線を標準よりも太いものに変更して特注した。
これだけでも音質は明らかに向上するそうだが、標準規格外の太さであるため、部品をプリント基板に挿入する自動機械が使えなくなる。このため、BZT9000だけは電源部やアナログ回路部の部品を製造ラインの工員が手で挿入しているという。デジタルの映像と音に、スイッチング電源のコンデンサ、それもリード線の太さを変えることに、ここまでの手間をかける意味はあるのだろうか?
 |  |
| BZT9000のカットモデル。トップパネルは3.5mm厚のアルミ | 3層ベースシャーシで共振を排除 |
 |
| Uniphier |
機能だけを見れば、コストをかけて少量生産するBZT9000と他モデルの違いは大きなものではない。チューナ数やメモリ容量、搭載するLSIの構成といったハードウェアによる制限を受ける部分を除けば、DIGAシリーズは機能を上下のモデルで使い分けるということをほとんどしてこなかった。
メインLSIとなるUniPhierの世代が上がり、基本性能が向上して高画質化処理がアップグレードすれば(協調動作するLSIの有無などを除き)、下位モデルもグレードアップする。“単に製品をたくさん売りたい”だけならば、高価なアルミ材料を使ったり、試作を繰り返してパネルを留める方法の違い、ネジに使う材料や留める位置による音の違いを評価するなどのプロセスを経るまでもなく、高機能な製品をHDD容量の違いによって、適切な(もっとも売上が大きくなる)価格差で販売すればいいだけだ。
では、なぜプレミアムモデル、それもBZT9000のような専用BDプレーヤーにも負けない品位の映像と音を実現しようと、オーディオ製品的手法を盛り込んだプレミアム製品が生まれてきたのか。最後には簡単に製品のインプレッションもお届けしたいと思うが、この製品が生まれてきた背景について、まずは記しておきたい。
■ “理屈に合わない”を解明するために始まった高音質化プロジェクト
DIGAシリーズの画質改善のアプローチが極めて理詰めで行なわれていることは、ご存知の読者も多いことだろう。BDに収める段階で省略されている色情報を復元するアルゴリズムや、I/P変換と色復元プロセスを抜本的に見直すなど、デジタル処理部の高度化を進めることで、映像のデジタルマスターに近いデータ復元を目指してきた。
一方、これとは別に音質についても理詰めの改善が続けられてきている。これは本機を紹介してもらう時に聞かされたのだが、きっかけはBDレコーダのビジネスが始まった初期、筆者と当時のBDレコーダ開発部門責任者だった楠見雄規氏との何気ない会話だったそうだ。
「BDの世代になって音声規格としてはDVD-Audio並になったが、HDMIのみでしかデジタル出力できない。HDMIは音が悪いから素直に喜べない。かといってサラウンド音声を6本のアナログケーブルというのも時代に合わないしね」そう話すと、楠見氏は「HDMIはウチ(パナソニック)も推進している規格。高級オーディオ製品を販売しているわけではないが、BDの音があまり良くない、なんて話では困る。本当にHDMIの音は悪いのか?」と話し、ステレオサウンド社 HiVi編集部に試聴室を提供いただき、実際の音を比べてみることにした。2006年4月のことだ。
このとき、楠見氏、DIGA開発の現場メンバーと様々なソフトを視聴し、BDの音に限らず、帯域の狭いCDの音であってもHDMIの音が、情報量に乏しくS/Nも悪い音であることを確認した。プレーヤーを変更したり、HDMIでデジタルデータを受け取るAVアンプを変更することで、音の変化の傾向も変わる。しかし、一貫してどんなケースでも、HDMIよりもアナログ接続、あるいはCD音声の場合はHDMIよりも同軸デジタル接続の方が良い結果となった。
そのときに楠見氏が繰り返していたのが「理屈に合わない。なんで時間軸に同期させず、レシーバ側(AVアンプ側)で音声信号を作り直すHDMIで音が変わるんや」という言葉だった。その後、AVアンプのHDMIレシーバ部も改良。電源やグラウンドを強化することで、HDMI信号の揺らぎを抑えたり、サンプリングコンバータを間に挟んでジッターのアライメントを取ったり、あるいは基板上の信号経路を見直すなどで、かなり改善はした。
HDMIではGbpsオーダーの高速シリアル通信を行ない、レシーバ側LSI内部の動作が不安定になりやすいため、それを電気設計で補おうという涙ぐましい努力だ。しかし、レシーバ側だけで対処できる対策は限られている。そこで当時、筆者から開発の方々にお願いしたのが、HDMI出力を二つに分けること(片側を音声専用として画面を黒にすることで、信号部の見かけ上の周波数を下げるため)だった。パナソニックにだけ“お願い”しているわけではない。メーカーごとに得手不得手はあるため、要求することは違う。だがこの頃は、HDMIによる音質低下が大きな懸念になっていたので、同じリクエストをBDプレーヤー、レコーダを作っていたほぼ全てのメーカーに出していた。その甲斐あってか、あるいは各々のメーカー毎に工夫した結果か、高級機メーカーはHDMIを2系統出力させるのが当たり前になっていった。
しかし、パナソニックは別のアプローチでHDMIの音質対策を行ない、その手法やアプローチは、その後のHDMI高音質化のトレンドを作ったと言っても過言ではない。「理屈に合わないと感じるのは、現象を把握し切れていないから」。ならば「音が悪くなる理屈を突き止め、改善すればいい」。そこでHDMIそのものの音声伝送の仕組みを、一番、元の部分から洗い直したのだ。
■HDMIの音質低下要因に理詰めで迫ったパナソニック
パナソニックがHDMIの2本出しを採用できなかったのは、第1にコストの問題があったからだ。出力を2系統にするためには、HDMI出力用のLSIを2系統備えなければならない。同じ映像を同期させて2つ出すための周辺LSIも揃っていなかった。第2に使用者からのクレームの問題を懸念する社内の品質管理部門の壁もあった。2本あるHDMI出力のうち、片方に映像が出ない真っ黒映像では、接続間違い、設定間違いがあった時、製品へのクレームになる可能性がある。
このような事情を鑑みて、短期間の開発という目標から選択されたのが、HDMI出力系統は1つだけ。しかし、高級オーディオが得意なメーカーによるHDMIの2本出しに負けない音を出すことだった。
そこで、テクニクス時代から残る、数少ない音質チューナーの山崎雅弘氏は、HDMIの音が悪くなる可能性を理詰めで追いかけ直すことにした。試験用の試作機で得た経験則で言えば、2本出しにすれば改善する部分は確かに認められた。しかし、山崎氏は2本出しにしてS/Nが良くなりダイナミックレンジが拡大しても、揺らぎのないしっかりした低域が再現できないと感じ、何か他にも原因があるのでは? と目星を付けた。ここで山崎氏が発見したのが、HDMIに音声を載せる際に付加情報として加えるパラメータ、それにHDMIそのもののクロック周波数の揺らぎ(ジッター)が音質に大きな影響を与えていることだった。
HDMIの前身はパソコン用のDVIで、映像を伝送することしかできなかった。これがHDMIという規格になる中で、テレビ用の映像タイミングに合わせて規格化され、音声も伝達できるよう、後から仕様が追加された。これは後からHDMI定義に関わったエンジニアに聞いた話だが、多ビット高サンプリングの音声はサポートしたものの、音質変化に対するケアは行なわれなかった。参加していたエンジニアの中に、オーディオの専門家がいなかったからだ。
HDMIでは映像送出のタイミングに合わせて伝送クロックやフレームのアライメントが決められ、オーディオデータは映像送出に合わせて送られる。映像フレームレートと音声のサンプリングレートは同期していないためオーディオデータの送出速度は、どうしても不均一になる。この不具合を補正するためのパラメータがあるのだが、そのデフォルト値が「低域にジッターが多く出てしまう値だった(山崎氏)」のだ。
そこで送出タイミングの最適化を図り、最後は耳で聴き分けながら最適値を探し、さらにHDMIに載せるクロックを生成する発振器精度を高めることで音質を改善。その年末(2007年11月)に発売されたDMR-BW900に盛り込まれ、HDMI出力は1系統で音声を別端子に分離できないにもかかわらず、贅沢な2本出し構成に迫ることに成功したのだった。
■理詰めの後を、さらに経験値で追い込んだBZT9000
 |
| BZT9000の背面には2系統のHDMIを装備し、金メッキ処理が施されている |
その後も山崎氏は、さらに音声伝送ジッターをコントロールするため、様々なアイディアを繰り出してきた。HDMIを使っている限り、音声送出タイミングの揺らぎは避けられない。しかし、揺らぎの周波数、揺らぎの均質性などは工夫次第でコントロールできる。テクニクス時代に培った経験から、耳で聴きながら最適制御の手法を見つけ出し、その成果はDIGAシリーズの全ユーザーが享受してきた(一部はHDMI送出LSIとの協調動作が必要なため、低価格モデルには採用されていないテクニックもある)。その間、時代は変化し、AVアンプ側もHDMI入力の音質改善が進み、パナソニックのBDレコーダは3D対応をきっかけにHDMIの2系統出力をサポートした(3D非対応AVアンプに対応する、という名目で対応した)。
しかし、山崎氏の追求はここでは終わらなかった。HDMIが2系統になる前、米国でDMP-BD80というBDプレーヤが発売されたとき、同氏に「音を聴いてもらえないか」と同機が送られてきた。決して高級プレーヤーではないが、前述の工夫が施されていたため、情報量は多く低域もしっかりとしている。しかし、やや描写が粗くノイズが耳につく印象だった。そこで中身を空け、制震用のスポンジ、テフロンテープ、アセテートテープ、異種素材のビスなどで共振が影響しやすそうな場所に対策を施し、シャシー下に薄手のフェルトを貼り付け、BD80に合うインシュレータと電源ケーブルをセットにして山崎氏に戻した。
こうした対策をBDプレーヤーに施すと、不思議なことにHDMI経由での音に大きな影響がある。下手をすると製品の買い換えより大きな違いが出るが、そろそろパナソニックのHDMI出力音声も、そうしたチューニングを考えなければならない時期に来た。送られてきたテスト用の製品を試し、そう感じたからである。すると、山崎氏は上記の送り返した製品の、電源仕様に変更を加えたもの送ってきた。こうしたキャッチボールがその後、DIGAシリーズにはプレミアムシリーズが生んだのだという(もちろん、私はまったく知らなかったのだが)。
電源に使っている部品やインシュレータ、電源ケーブルなどを、パナソニックが扱えるコストの範囲内で山崎氏が吟味し、最上位モデルのみに対策するようになる。理詰めで高めたHDMIの音質を、さらに経験値で追い込んでいったわけだ。一方で画質向上対策も成熟が進んだこともあり、この経験を活かし、DVD時代におけるH1000/H2000のような、後世に語り、自慢できるような高品質プレーヤーを作りたいという機運が、開発チーム全体に満ちてきた。しかし、国内はレコーダに需要が偏り、プレーヤー需要が伸びないこともあって、なかなかゴーサインが出なかった。
 |  |
| BZT9000のインシュレータ | BZT9000の電源ケーブル |
■ レコーダ需要最大の年に、プレーヤーに負けないレコーダを
パナソニックのHDMI音質改善に絞って話を進めたが、もちろん、この間に業界は各社それぞれの方法で音質改善を続けてきた。パナソニックの場合、国内で好調を続けたレコーダにはコストをかけられるが、プレーヤーにはかけられない。そこで、レコーダをプレーヤー化するというアイディアを盛り込むようになる。これがシアターモード。レコーダとしての機能を一時的に捨て、チューナやHDDなどプレーヤーに不要な部分への電源供給を止めてしまう。予約録画は実行できないが、動作状態はプレーヤに極めて近くなるため、音質は良くなる。またアナログ映像出力用のDACが音声回路に輻射ノイズを出していたため、これを止めるハイクラリティサウンドという機能も考え出した。
だが、”高級プレーヤに負けない”音にするには、どうしても越えられない壁はあった。大多数のユーザーに提供する際のコストを重視したDIGAの設計を踏襲しつつ、高級機並の物量を投入するというのは難しい。しかし今年、地デジへの移行でBDレコーダの売上げが過去最高を記録することは確実だった。このタイミングだったからこそ、BZT9000の企画も通ったのだろう(少しでも品質の良いものパナソニックブランドで出したいという杉田氏が、事業部長になったタイミングだったことも企画が通った一因だと思う)。
電源インレットから内部シャシーの強度や共振制御のアルミパネル、下面の振動コントロール、それに各パネルの噛み合わせやネジ留めの方法など、あらゆる部分に、それまで山崎氏がやりたくてもできなかった構造が施された。見えない部分、たとえばBDドライブ本体の隔離といったところにもコストがかけられている。
また見えない部分としては、従来のプレミアムシリーズを、レコーダとしてではなくプレーヤ専用機として使う(シアターモードで確実に使うため)人たちのために、予約が一件も入っていない場合は、シアターモードへの遷移確認なくプレーヤーとして動作するロジックが組み込まれている。
さらに、HDMIの音質改善を行ないながら、アナログ2chの音にもこだわった山崎氏らしく、BZT9000はCDの音質もこだわっている。搭載する32bitDACやライン出力回路にもこだわったが、アナログ音声出力でCD再生時には、CDプレーヤーとして必要な機能以外はすべてオフにできるようにした。
 |  | 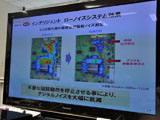 |
| アナログ回路は強化されている | 音楽のみの再生時は、回路やメモリなどの動作をストップする「ハイクラリティサウンド2」 | インテリジェントローノイズシステムの使用前(左)と使用後(右)の基板近傍ノイズ比較 |
シアターモード、ハイクラリティサウンドをそれぞれ有効にした上で、CD再生時に画面に現れる「青」ボタンをクリック。メニューでHDMI出力をオフにするとHDMIのLSIがオフになってノイズ輻射がなくなる(自動的にこの状態になる設定は、映像機器である以上はNGということで品質管理部門のオーケーが取れなかったようだ)。さらに前面FL表示を「暗」、SDカードインジケータを「切」、HDMIセパレート出力表示ランプを「切」、B-CASカードを挿入していない状態が山崎氏のお薦め。
標準添付の無酸素銅電源ケーブルで聴いてみると、力強い音くフワッと漂う空気感も再現してくれる。ただし、音像はやや太書きで曖昧な部分もあり、奥行き感や音場の広さ、開放感がもう少し欲しい。そこで手持ちのオーディオ用電源ケーブルを取り付けてみると、素直に反応してハイファイ機器らしい音になってきた。さらにセラミックインシュレータを採用した足の下に、様々なインシュレータを入れてみると、これがまたかなり良い感じで反応してくれる。
CD再生音を良くするための儀式(青ボタンとメニュー選択)は、正直とても面倒だ。しかし、こんな遊びがCD再生でできるBDレコーダなんてこれまでになかったことを考えれば、これはこれでユーザーも楽しめるのではないだろうか。
■完成された”HDMIの音”を様々なフォーマットで
さて、肝心のHDMI出力の音だが、これまでのパナソニックのプレミアムモデルとは、少しばかりキャラクターが異なると感じた。従来はとにかく情報量が多く、音像もシャープで、あらゆるところがハッキリと見える音。あらゆる情報が頭の中に入ってくる反面、音の情景、佇まいといったものは逆に希薄に感じた。簡単に言えば、スゴイ音だとは思うが、ゆったりとリラックスできる音か? と言えば、そこまでは至っていない。
しかし、今回は山崎氏が徹底してメカニカルな部分までチューニングし、電源部もこれまで以上に思い通りの設計へと力を振るった結果、圧倒的な情報量にふんわりとした空気感が加わった。低域は従来にも増してしっかりと揺るぎない風合いとなった。理詰めで追い込んだだけでは、こういった肌感覚の音造りはできなかったはずだ。
BZT9000の音が良くなってくると、せっかく高価なレコーダを購入してくれるユーザーに、もっと他種類の音源に触れてほしいと感じる。たとえばFLACなどロスレス音声のDLNA再生に対応してくれれば、ちょっとしたネットワークオーディオプレーヤとして活躍してくれるだろう。マルチチャンネル対応のFLAC対応なんてことも面白いんじゃないかな?
製品担当者はちらりと「SACD再生って必要でしょうかね?」と話していたが、SACDのマルチチャンネル再生手段が限られてきている現状を考えると、既存のソフトを含めて是非、聴きたいという人はいるんじゃないだろうか。今や強力な統合型デジタルメディアプロセッサの様相を呈している本機は、BDレコーダという枠を越えて、ネットワーク、光ディスク、あらゆるメディアの高品質再生に挑戦してほしいものだ。
大変に残念なことだが、BZT9000は、DIGAの音を育て、HDMIの音質改善手法に知恵を絞ってきた山崎氏が同社で最後に手掛ける製品となる。BZT9000は近年にない、手間とコストのかかった”作品”と言うにふさわしい製品に仕上がっている。大量に生産される製品ではないが、手にすることができたなら、そこに込められた魂がどのようなものか、是非とも奥深くまで楽しんでほしい。