 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

第9回:カジュアル路線のCinezaながら本格派
~ 高解像度ワイドパネルの「ソニー VPL-HS10」 ~
|
第9回:カジュアル路線のCinezaながら本格派 ~ 高解像度ワイドパネルの「ソニー VPL-HS10」 ~ |
昨年、「斜め投影が可能な低価格プロジェクタ」としてその名を馳せたCinezaシリーズに、上位モデルVPL-HS10が登場した。1,386×788ドットという高解像度液晶パネルを採用し、輝度1,000ANSIルーメン、コントラスト比700:1というスペックを誇りながら、標準価格は35万円という設定。「プロジェクタ市場のキラー製品」という表現がふさわしいだろう。
■ 設置性チェック~HS1とは異なり、常設が基本
 |
| VPL-HS10。標準価格は35万円 |
台置き専用のVPL-HS1は、「使いたいときに使う」という活用スタイルを前提としていたが、VPL-HS10では台置きのほか、天吊り、リア投影にも対応し、本格派ユーザーの要求にも応える製品となった。
もちろん、VPL-HS10もCINEZAシリーズらしく、水平方向の台形補正(Hキーストーン補正)に対応しており、斜め投影が可能だ。しかしVPL-HS1と比べて奥行きが7cmほど大きく、本体重量も約5.4kgと1.5kg重くなった。VPL-HS1に比べるとそれほど気軽に動かせないため、やはり常設が基本となるだろう。なお、天吊り金具は同じソニー製プロジェクタ、VPL-VW12HT用の「PSS-610」(標準価格5万円)が利用できる。一方、VPL-HS1とは異なり専用設置台のオプション設定はなくなっている。
また、VPL-HS1には専用のチルトスタンドが付属したが、VPL-HS10ではなくなっている。ただし、本体前面下部に引き出し開閉式のアジャスタースタンドが装着されているので、上下方向の調整はある程度は行なえる。
投射角度はアジャスター収納時の台置き時で若干上向きな程度で、一般的なプロジェクタと同程度の投射角度といえる。レンズシフト機能は無いので、天吊り設置を行なう際は、天吊り金具を取り付けた本体のレンズ位置、スクリーンの位置をよく考えて行なう必要があるだろう。
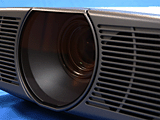 |
 |
 |
| レンズ前にはプロテクタを装備する | ホームシアター向けで横にスイッチ類を配置するのは珍しい | 後方から見たところ。天面のSONYロゴは紫色に光る |
投射距離は100インチ(16:9)で約4.0m。最近のホームシアター向け製品としては長めだ。しかし、この価格帯の製品としては珍しく、コンバージョンレンズが装着できる。オプションとして用意されている短焦点レンズと長焦点レンズを利用することで、ある程度まで環境にあわせた設置が可能だ。
100インチ(16:9)の場合、短焦点レンズ「VPLL-CW10」(標準価格170,000円)装着時は約3.0mに投射距離を縮めることができ、長焦点レンズ「VPLL-CT10」(標準価格170,000円)装着時は約6mにまで伸ばすことかできる。こうしたオプションはユーザーとしては喜ばしいことだが、ホームユース向けという製品コンセプトを考えれば、短焦点レンズの方を標準搭載レンズとして採用して欲しかった。
特殊機能として面白いのが、垂直方向の台形補正を自動で行なう機能。VPL-HS10自身の傾きを自動検知し、台形補正のパラメータを自動設定してくれるのだ。自動補正できるのは垂直方向のみで、水平方向は手動で設定を行わなければならない。常設が基本の場合、使いどころはあまりないと思われるが、ビジネス用途など、設置環境が変化しやすいシーンでは便利だろう。
なお、本機の台形補正処理は水平、垂直いずれの場合もデジタル処理であり、補正角度が大きければ大きいほど画素情報の欠落は多くなる。画質重視の用途では、自動補正機能はOFFにして、水平、垂直方向とも補正ゼロで使用したいところだ。
ファンノイズはプレイステーション 2よりも大きめで、やや高周波ノイズ音が強めに出ている。筐体前面にはスリットがあり、ここから排熱が行なわれている。ファンノイズが大きめなのは、このスリット部の開口が大きいからだと思われるが、ここからの目立った光漏れはない。
■ 操作性チェック~フォーカス合わせをリモコンでできる幸せ
 |
| 自発光ボタンを備えたリモコン。一部は蓄光式だ |
電源オンからCinezaのロゴが出てくるまでは13秒(実測)、入力映像が実際に表示されるのはその60秒後(実測)だった。これは最近の製品としてはやや遅い。
リモコンの電源ボタン、INPUTボタン、LIGHTボタンは蓄光式だが、それ以外のボタンはリモコン上部のLIGHTボタンを押すことで自照を開始する。自発光式は歓迎したいフィーチャーだが、そのトリガとなるLIGHTボタンは、暗闇でも直感的に押せるようにリモコン側面に付けるべきだと思う。また、押す頻度の高いINPUTボタン、電源ボタンも自照式にすべきだったのではないかと思う。
入力切り換えは順送り形式で、ターゲットとなるソースをダイレクトで切り換えることができない。ちなみに、入力切り換えボタンを押して実際にその映像が画面に表示されるまで実測で約3秒かかる。操作性を最優先にすれば、入力切り換え操作は各入力系統に対応した独立ボタンを用意すべきだったと思う。なお、アスペクト比切り換え操作、色調セット切り換え操作用の各ボタンは独立ボタンとなっており、使いやすい。
実際に操作してみて一番便利だったのは、このクラスでは珍しくフォーカス合わせをリモコンで行なえるという点。本体側のフォーカスリングを回しながらフォーカス合わせを行なう場合、「リングを動かしてはスクリーンに近寄り、合焦度を確認してまたリングを回すためにスクリーンから離れる」といった行為を繰り返さなければならない。しかしリモコンでフォーカスを調整できるVPL-HS10では、スクリーンの間近でクロスハッチを見ながらフォーカシングができるのだ。
■ 接続性チェック~待望のコンポーネントビデオ端子とDVI端子を実装
VPL-HS1の本体にはコンポジットビデオ端子とSビデオ端子のみで、PC入力はおろか、コンポーネントビデオ端子も実装されていなかった。これに対し、VPL-HS10はコンポジットビデオ端子、Sビデオ端子はもちろん、DVI-D端子とコンポーネントビデオ端子を標準で備えている。
しかし、アナログRGB入力が別に設けられていないことを考えると、汎用性を考えるなら、ここはアナログRGB入力も可能なDVI-I端子にすべきだったと思う。
このほか、PJ MULTI INPUT端子という特殊な形状の端子が実装されている。これはVPL-HS1にも搭載されており、シグナル・インターフェイスユニット「IFU-HS1」(オープンプライス)、アナログRGBケーブル「SIC-HS30」(標準価格9,000円)などが接続できる。VPL-HS10にアナログRGB専用端子がないことはすでに述べたが、PJ MULTI INPUT端子にSIC-HS30を接続すれば、アナログRGBによるパソコンとの接続が可能になる。
また、VPL-HS10には、コンポジットビデオ端子、Sビデオ端子、コンポーネントビデオ端子を各1系統ずつ増設することができるPJ MULTI INPUT端子用ケーブルが付属する。パソコン重視ユーザーはSIC-HS30を、AV重視ユーザーは付属のこのケーブルを接続すればいい。
 |
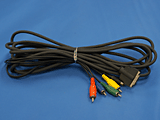 |
| 入力端子パネル。映像入力はコンポーネント、DVI-D、S映像、コンポジットを搭載 | 付属するPJ MULTI用のケーブル。コンポーネント、S映像、コンポジットを増設できる |
このほか、本体前面パネルにはVPL-HS1同様にメモリースティックスロットが搭載されている。ここにデジタルカメラなどで撮影したメモリースティックを挿入すれば、パソコンを利用せずともVPL-HS10単体で投影することができるのだ。再生に対応しているのはJPEGとMPEG-1。JPEG画像は90度単位の回転が可能なので縦位置で撮影した写真も正しい天地で鑑賞が可能。MPEG-1はちゃんと動画として再生できるが、音声はVPL-HS10内蔵の直径3cm程度のモノラルスピーカーから再生されるので、簡易再生といった感じになる。
そもそも、天吊り設置をはじめとした常設を前提とした製品なので、メモリースティックスロットの使用頻度はあまり高くないと思われる。個人的にはメモリースティックスロットの搭載よりも価格を安くするか、D端子、もしくはアナログRGB端子を標準実装した方が、訴求力が強まったと思うのだがどうだろうか。
結局,本機はPJ MULTI INPUT端子とメモリースティックスロットを含めると全部で8系統もの入力端子がある。これを整理すると以下のようになる。
- ビデオ1…本体側のコンポジットビデオ端子
- Sビデオ1…本体側のSビデオ端子
- 入力A…PJ MULTI INPUT経由で接続したアナログRGB端子、またはコンポーネントビデオ端子
- ビデオ2…PJ MULTI INPUT経由で接続したコンポジットビデオ端子
- Sビデオ2…PJ MULTI INPUT経由で接続したSビデオ端子
- コンポーネント…本体側のコンポーネントビデオ端子
- デジタル…本体側のDVI-D端子
- MS…メモリースティックスロット
■画質チェック(1)~1,000ANSIルーメンの最大輝度か、画質優先のシネマブラックか
光出力は公称1,000ANSIルーメン。ただし「シネマブラックモード」と呼ばれる黒浮きを抑えるモード時には830ANSIルーメン相当に下がる。輝度スペック的には低くなるが、シネマブラックモードの方が映像が引き締まって、見栄えはよくなる。
シネマブラックモードオフ時は、スクリーンの周りがかなり明るくても映像が見えるほど明るい。とはいえ、やはり映像の再現性はシネマブラックモード・オン時のほうが優秀。好みにもよるとは思うが、周りが明るいときの使用以外はシネマブラックモードで常用した方がよさそうだ。
液晶パネルは解像度1,386×788ドットという、見慣れない数値の組み合わせのものを採用する。上位機とも言えるVPL-VW12HTのパネル解像度は1,366×768ドットなので、縦方向にも横方向にも若干解像度が上がっていることになるのだが、それを実感できるほどではない。
画素形状は、各画素の右上と左下に影があり、完全な正方形で光が透過されているわけではない。しかし、解像度が高いこともあり、100インチ前後の投影サイズでは全く気にならない。
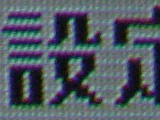 |
 |
| VPL-HS10のメニュー画面(左)とWindowsのダイアログの一部。各画素の周辺の回路の影が映ってしまっている、いわゆる液晶画素の典型的な形状。しかし、解像度が高いうえ、輝度も高いので実際の映像で粒状感はあまり感じない | |
プリセットの色調モードはダイナミック、スタンダード、シネマの3つを持ち、これらはリモコンから独立キーによりダイレクトに切り替えが可能となっている。加えて、各入力系統ごとに3つまでユーザー自身がカスタマイズした色調モードを登録することができる。プリセット色調モードの簡単なインプレッションは以下の通り。
●ダイナミック全体として原色の色合いが鮮烈。花畑のようなカラフルなシーンは本機の得意とするところで、実に華やかに表現する。コントラスト700:1は伊達ではなく、ハイコントラストかつ粒立ちのよい映像には一種独特の迫力がある。明暗をドラスティックに強調した、コントラスト重視の色調モード。明るい色を必要以上に強調した感があり、明るい階調は若干飛び気味に見える。PCやゲーム、文字図版コンテンツ向き。
●スタンダード
色温度こそ高めにはなるが階調表現は正確で、バランスの取れた色合いの映像が出てくる。特に不満がなければこのモードを常用すればいいだろう。
●シネマ
色温度は低めで、暗い階調表現の再現に重きを置いた色調モード。暗いシーンの多い映画ソフトなどで利用するといい。
しかし、暗部の階調表現は、シネマモードにおいてもあまり得意ではない。マッハバンドとは言わないまでも、暗い色のグラデーションには若干のざわつき感がある。全体として発色こそ鮮烈だが、暗色階調表現は兄弟機VPL-VW12HTと比べると色深度が浅いという印象を受ける。
また、光学エンジンのデザイン特性から来るものだろうか、画面左上と右下に若干の色むらを感じる。これは映像未入力状態にし、その背景を黒にするとよくわかる。
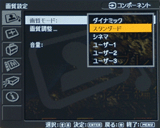 |
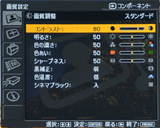 |
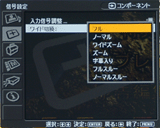 |
| メニュー画面。左から画質設定、画質調整、信号設定。 (c)Disney Enterprises,Inc. | ||
■ 画質チェック(2)~ハイビジョンも高密度に再現
 |
| 緑成分を低減するシネマフィルター |
実際に使用してみると、肌色が赤みを帯び「血の気」を感じさせる色合いになる。もちろんカラーフィルターなのでほかの色にも多少なりとも影響が出るのだが、それほど気にならないので常用しても問題はないと思う。
さて、ここからは、各映像ソースを投射したときのインプレッションを述べておく。
●DVDビデオ映画ソフトは、正しいアスペクト比を維持したままパネル解像度に拡大する「フル」を利用することになるだろうが、拡大表示処理自体は秀逸で、目立ったジャギーはない。リアル解像度で見ているような自然さがある。
映画ソフト視聴の際にお勧めの色調モードはスタンダードモードかシネマモードだ。両者ともシネマブラック機能が有効となり、階調表現のダイナミックレンジが広くなる。スタンダードとシネマの違いは、色温度とコントラスト強調(黒補正)が入るか否か。好みで使い分けるといい。「コントラスト重視でスタンダード」、「暗いシーンが多いならばシネマモード」というのが目安だろうか。
インターレース映像は、搭載されたプログレッシブ化エンジンで2-3プルダウン方式のプログレッシブ化が行なわれるはずなのだが、VPL-VW12HTと比べると解像感が落ちているような印象を受けた。動きの早いシーンでは若干コーミングも出ることがある。
一方、プログレッシブ映像を映した場合、こういった現象は全くなかった。VPL-HS10と組み合わせるDVDプレーヤーはプログレッシブ出力対応機種の方が良さそうだ。
●S-VHSビデオデッキ/地上波放送
S-VHSビデオデッキなどからのアスペクト比4:3の映像は、パネルの中央に縦横比を維持したまま最大表示してくれる、アスペクトモード「ノーマル」を利用するのがいい。
VPL-VW12HTが装備するDRC-MFのような高画質化ロジックが搭載されているわけではないが、ジャギーはほとんど気にならない。
●ハイビジョン
パネル解像度の制約から、1080iのハイビジョン映像は圧縮処理後に表示される。しかしハイビジョン特有の解像感は十分に維持されており、800×600ドット以下のパネルを使用した機種とは一線を画した高密度感を発揮している。
BSデジタル放送でハイビジョン(1080i)のバラエティ番組を視聴したときには、出演している女性タレントのアップシーンで、その髪の毛の質感のリアリティに驚かされた。本来ならば1,920×1,080ドットの解像度がなければリアル表示できないのだが、髪の毛一本一本の光沢感が自然に表現されていた。
●パソコン
サポートが明言されているDVI-Dの解像度は、640×350ドット、640×400ドット、640×480ドット、800×600ドット、832×624ドット(Macintosh)、1,024×768ドットまで。
アスペクト比4:3の画面モードはアスペクトモード「ノーマル」で表示すると、画面中央に縦横比を維持したまま最大表示を行なう。ただし、左右に表示されないスペースが出てくるので違和感は残る。パソコン映像の出力にはあまり適していないようだ。
なお、今回はアナログRGBケーブルSIC-HS30が使用できなかったこともあり、1,280×720ドットのようなアスペクト比16:9の映像入力のテストは行なっていない。
●ゲーム
プレイステーション 2をコンポーネントビデオ端子経由で接続してゲームを一通りプレイしてみたが、残像は一切なかった。
VPL-VW12HTでDRC-MFを利用したときにはプレイステーション 2の映像も解像感が高まった感じがしたが、VPL-HS10ではそういった見返りはない。ただ、CRTテレビでプレイしているときのようなちらつき感は一切ないのでプレイはしやすい。
また、バイオハザードのような色調の暗いゲームでなければ、色調モードは見た目がパリッとするダイナミックがお勧めだ。
|
||||
|
|
||||
| 視聴機材 ・スクリーン:オーロラ「VCE-100」 ・DVDプレーヤー:パイオニア「DV-S747A」 ・コンポーネントケーブル:カナレ「3VS05-5C-RCAP-SB」(5m) |
||||
■ まとめ~VW12HTとどっちを選ぶべきか
VPL-HS10の購入を考えているユーザーの多くは、同じソニー製でスペック的に拮抗するVPL-VW12HTと悩むところだろう。最後はこのあたりについてちょっと考えてみたい。
▼設置性整理すると以下のようになる。100インチ投射距離で比較するとVPL-VW12HTの方が若干だが短くて済む。本体重量はVPL-VW12HTの方がだいぶ重いが、両者共に常設が基本なのでそれぞれに有利不利はない。天吊り設置の場合は、いずれにせよ、天井補強は不可欠だからだ。
▼操作性
両者共に自発光式のリモコンを採用する部分では互角だが、微妙な違いは存在する。VPL-VW12HTでは入力切り換えが独立キーになっている。しかも、切り換えにかかる時間は、VPL-VW12HTの方が実測で1秒で、VPL-HS10の3倍も高速だ。しかし、アスペクト比の切り替えボタンがなく、メニュー操作をしないと変えられない煩わしさがある。
逆に、VPL-HS10はアスペクト比切り換えボタンを持つが、入力切り換えボタンは順送り式で希望する映像ソースに一発で切り換えられない。
フォーカス合わせは、リモコンで行なえるVPL-HS10の方が圧倒的にやりやすい。VPL-VW12HTは投射レンズに備え付けられたフォーカスリングを回さなければならず、投射距離が離れた環境ではかなり面倒になる。
▼接続性
付属品だけでコンポーネントビデオ端子を2系統利用できる点は両者同じだが、VPL-HS10はコンポジットビデオ端子とSビデオ端子を2系統ずつ持てるので、接続できるAV機器の数ではVPL-VW12HTを上回る。
PC入力に関してはVPL-VW12HTはアナログRGB入力にこそ対応しているが、コンポーネントビデオ端子を1系統潰し、なおかつ端子変換を行わなければならず一筋縄ではいかない。VPL-HS10はDVI-D端子を採用しており、「PCへの接続性」という意味では、VPL-HS10の方に軍配が上がる。
▼画質
両者、シネマブラックモード、Dピクチャー(黒補正)機能、シネマモーション(2-3プルダウン処理)に対応するなど、高画質化機能のフィーチャー数ではほとんど互角。
とはいえ、表示映像の品質面においては、やはり、VPL-VW12HTが価格差分、上を行っている。映像をパッと見たときのハイコントラスト性では「両者互角か」という印象を持つが、暗色の階調表現においてはVPL-VW12HTの方が優位に立つ。実際にDVDビデオなどの映画ソフトを再生してみた場合、「映像の再現性」という意味において差が出てくる部分だ。
ちなみに、パネル解像度ではVPL-HS10の方がVPL-VW12HTをわずかに上回るが、視覚的に解像感の差は無い。
- 設置性…互角
- 操作性…一長一短で互角
- 接続性…VPL-HS10の方が拡張性が高い
- 画質…VPL-VW12HTのほうが優秀
いずれにせよ、VPL-HS10は「お買い得感」という側面においては頭1つ分、抜きんでているといえる。この価格帯のプロジェクタ製品の性能底上げという側面から見てもVPL-HS10の存在意義は大きい。
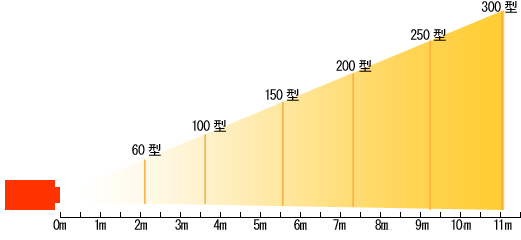 |
| ※台形補正機能は使用せず、ズーム最短の状態 |
| 投影デバイス | 0.87型TFTワイドXGAパネル(1,386×788ドット) |
| レンズ | 光学1.3倍電動ズーム |
| 明るさ | 1,000ANSIルーメン |
| 光源 | 180W UHP |
| コントラスト比 | 700:1 |
| 投影サイズ | ワイド40~300インチ |
| 映像入力 | コンポーネント、S映像、コンポジット、DVI-D、PJ MULTI×各1 |
| 対応ビデオ信号 | 480i/480p/1080i/720p |
| 消費電力 | 最大260W |
| 外形寸法 | 345×369×148mm(幅×奥行き×高さ) |
| 重量 | 5.4kg |
□ソニーのホームページ
http://www.sony.jp/
□ニュースリリース
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200208/02-0807/
□関連記事
【8月7日】ソニー、ワイドXGA液晶搭載ホームシアター用プロジェクタ
―Cinezaの上位モデル、天吊り対応、縦横同時に台形補正可能
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20020807/sony.htm
【6月13日】ソニー、ホーム向けワイドXGAプロジェクタ「VPL-VW12HT」
―MLAを採用し、クラス最高のコントラスト比1,000:1を実現
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20020613/sony.htm
(2002年10月10日)
| = 西川善司 = | ビクターの反射型液晶プロジェクタDLA-G10(1,000ANSIルーメン、1,365×1,024リアル)を中核にした10スピーカー、100インチシステムを4年前に構築。迫力の映像とサウンドに本人はご満悦のようだが、残された借金もサラウンド級(!?)らしい。 本誌では1月の2002 International CESをレポート。山のような米国盤DVDとともに帰国した。僚誌「GAME Watch」でもPCゲームや海外イベントを中心にレポートしている。 |
 |
[Reported by トライゼット西川善司]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|


