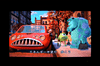|
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第32回:1インチ1万円以下で買えた! 37V型AQUOS ~ 大画面液晶テレビ「LC-37AD1」購入記 ~ |
 |
| 今回購入したLC-37AD1 |
この連載のタイトルの通り、筆者は無類の「大画面マニア」ではあるが、大富豪というわけでもないので、たくさん所持しているわけではない。
もちろん、情報収集は常に行なっているが、実際に所有しているものはそれほど多くはないのである。大画面機器を実際に購入することになれば、それは「一大事」なのである。
▼ 大画面マニアなのにテレビは15インチでした……
いきなりだが、つい最近まで筆者の自宅のリビングに大画面テレビはなかった。12畳のリビングはホームシアターを兼ねており、100インチスクリーンとビクターのD-ILAプロジェクタ「DLA-G10」、東芝のDLPプロジェクタ「TDP-MT8J」が設置してある。ところが、これらプロジェクタはテレビチューナを内蔵しておらず、いってみればDVDプレーヤーやLDプレーヤーといったAV機器のビデオモニター的な存在だ。もちろんビデオレコーダーなどに接続すればテレビ的な活用ができなくもないが、モニターの電源を入れて、ビデオレコーダーの電源を入れて、AVアンプの電源を入れて……という手順を踏まねばならず、少なくとも普通のテレビのような「お気軽さ」はない。
仕事部屋にはソニーのプロフィールプロ「KX-29HV3」があるが、これをリビングに持って行けばスクリーンの邪魔になるし、こいつもテレビではなくモニターなので、使い勝手の面ではフロントプロジェクタと大差はなく、状況の改善にはならない。
そんなわけで、うちは、昔懐かしのシャープのパソコン「X68000」シリーズ用の15インチテレビモニターを「テレビ」として活用していた。
このテレビモニターをスクリーン真下にあるAVラックの上に設置していたが、もともとホームシアターを前提とした設計のリビングであるため、視聴ポジションはテレビモニターから2~3m離れた位置になる。想像して頂くとわかると思うが、15インチの画面を離れて見ると携帯電話の液晶ディスプレイよりも小さく見える。大画面テレビをラックの上におきたいところだが、スクリーンが壁に接しているため、今度はスクリーンの一部が見えなくなってしまう。
▼ 失敗者から贈る言葉
ラックの上に大画面テレビを置けばスクリーンの邪魔になるし、かといって小型テレビだと寂しい。部屋の設計段階から「スクリーンと大画面テレビの両立」を考えていなかったために、このようなジレンマにさいなまれることになってしまった。
「天井からスクリーンを吊り下げるなら、あまり壁に寄せないこと」……これが失敗者からのアドバイスだ。将来、フラットテレビを壁掛け設置する場合、壁から20cm前後離れたところにスクリーンが吊り下がる設置にした方がいい。
こうすれば、スクリーンはフラットテレビの前に降ろすことができ、スクリーンを上げてしまえばフラットテレビを違和感なく楽しむことができる。もちろん、スピーカー類のオーディオ機器はフラットテレビとスクリーンの双方で共有できる。フラットテレビ自体の奥行きは10cm前後のはず。なぜ20cm前後もクリアランスを設ける必要があるのか。ここを疑問に思った読者もいるかもしれない。
これはフラットテレビの専用壁掛け設置金具と組み合わせると、金具自体の奥行きが加味されてトータルの奥行きが20cm前後になってしまう場合が多いからだ。特に排熱が重視されるプラズマテレビの場合、冷却機構の性能を十分発揮できるようにクリアランスを多めに取るものもある。そうしたケースに対応すべく余裕を見ておきたい。
▼ フラットテレビが欲しい~液晶かプラズマか
しかし、液晶テレビであれば重量はブラウン管と比べれば軽いはず。しかも、大画面フラットテレビは、チューナやインターフェイス類を別の筐体にまとめ、極力映像表示ユニット側を軽量化する傾向にある。ならば、スクリーンを使うときにはフラットテレビをラックから降ろせばいいではないか。「妥協案」と言うべきアイデアだが、この解に行き着くまでに、数年の時間を要した。この案を思いついてから以降、普段から漠然と大画面のフラットテレビが欲しいと思うようになったのであった。
となれば、次なる問題は「プラズマか液晶か」という二択。重さの点でいえば、圧倒的に液晶テレビの方が軽い。プラズマテレビはガラス板面が厚いのと、冷却機構の規模が大きいこともあり、同サイズの液晶テレビに比べて3~4割は重い。
最終的には好みの問題だといえるが、私個人としては最近は液晶テレビの画質の方が好きだ。そんなわけで液晶テレビで何かいいものはないか、と思うようになっていった。▼AQUOSに第一種接近遭遇!!
予算に余裕はなく、なるべく安い物をと思っていたので、最初はAEONが販売する激安大画面液晶テレビも候補に挙げていた。
そんな最中、1月某日、千載一遇の出会いを果たす。場所は地元のビックカメラ大宮西口そごう店だ。出会ったのは、シャープの液晶テレビ、AQUOS「LC-37AD1」。
AQUOSは1月初旬にGシリーズが発表されたために、旧モデルとなるAシリーズの展示品が格安で販売されていたのだ。価格は348,000円。1カ月間展示されたこともあるとのことだが、状態は良好で、むしろ画素欠けがチェックできた分だけお得といえる。ちなみに画素欠けはなかった。
LC-37AD1は、2003年夏に発売が開始されたAQUOS Aシリーズの最上位モデルで、BSデジタル、CS110度、そして地上デジタルチューナまでを搭載している。モニター用途としてのポテンシャルも高く、D4映像入力端子を2系統、PC入力もアナログRGB入力だが1系統を備えている。1世代前モデルとはいえ、機能自体は最新モデルと比較して遜色ない。
3月現在でもLC-37AD1は流通在庫としてまだ販売が続けられているが、いずれも最安値で46万円前後であり、1インチ1万円以下で購入できるチャンスはそう無い。そんなわけで、急遽預金通帳をかき集め、購入してしまった。
▼設置性チェック~重さは約25kgで、なんとか1人で移動可能なレベル
 |
| 我が家での設置状態。スクリーンの下部にLC-37AD1の頭が被るのでスクリーン使用時は下に降ろす必要がある |
AQUOSには私の購入したAシリーズに限らず、最新のGシリーズでも、ディスプレイ部の下部にスピーカーを取り付けたD1モデルと、左右に備え付けたD2モデルが存在する。購入したのは下部にスピーカーが搭載されている方だ。
D1モデルはスピーカーが下部に付いている関係で、画面の高さがD2モデルよりも若干高い位置に来る。
ディスプレイ部の奥行きは8cm強で画面サイズからすると非常に薄く見えるが、スタンドの奥行きが30cmほどある。設置スペースはブラウン管ほどではないにしろそれなりに必要になる。
表示される映像のサイズは約82×46cm。アスペクト比4:3の映像を表示させた場合は約61×46cmで、約30インチ相当になる。若干だが手持ちの29インチのプロフィールプロよりも大きい。なお、ディスプレイ部そのものの大きさは幅約95cmになる。ディスプレイ部 + スタンド + スピーカー取り付け状態の総重量は約25kg。25kgという重さ自体は軽いとはいえないが、これならばスクリーンを使う際にAVラックの上から降ろすのも1人でできる。約55kgの29インチのプロフィールプロではこうはいかない。
ディスプレイ部のスタンドの上下のチルト機構は前4度、後6度で、ほとんど傾かないが左右は10度だけ回転する。
このほか、チューナユニットがあり、これとディスプレイ部とは3つの接続端子が備え付けられた専用ケーブルで接続することになる。チューナユニットの重さは約6kg、43×25×10cm(幅×奥行き×高さ)ほどあり、イメージ的には据え置き型のDVDプレーヤーくらい。DVDプレーヤーなどと一緒にAVラックに入れてもいいし、同梱の縦置きスタンドを使い、ディスプレイ部背面などに設置することも可能だ。うちではAVラックに収納した。なお、チューナユニットとディスプレイ部を繋ぐ専用ケーブルは3mもある。電源はディスプレイとチューナでそれぞれ1系統を必要とするのでコンセントは2口必要になる。電源コードは4mあるのでコードが伸びることさえ気にしなければ、電源確保に困ることはないはずだ。
付属ケーブルは、さすがは高額商品だけあって、これ以外にもいろいろ付いてくる。電話線は10メートル、アンテナ線もCS/BS用と地上アナログ用がそれぞれ1本ずつ、4mのものが付属している。チューナには地上アナログと地上デジタル用のアンテナ端子が独立して実装されているが、地上デジタルのアンテナ出力端子から、地上アナログのアンテナ入力端子へ、付属の22cmのスルー接続ケーブルを用いて接続することもできる。
▼接続性チェック~コンポーネント、D4、PC入力と一通り装備
 |
| チューナユニットの外観 |
ビデオ入力は前面と背面の双方で合計4系統。D4端子はビデオ入力1と2に、コンポーネントビデオ端子はビデオ入力1に設定されている。
コンポーネントビデオ端子とD4端子は同じビデオ入力1になっているが、それぞれ独立した入力系統に設定することも可能だ。ただし、その場合メニュー操作は「入力切替」→「機能切替」の2段階手順を踏まなければならず、現実的にはビデオ入力1をコンポーネントビデオ入力、ビデオ入力2をD4入力として活用することになる。
「モニター出力端子」としてSビデオ、コンポジットビデオ、ステレオアナログ音声、デジタル音声の各出力端子が用意されているが、これはAQUOS側で表示中の映像と音声をこの端子から出力する。
「録画出力端子」というのもあり、こちらはSビデオ、コンポジットビデオ、ステレオアナログ音声の各出力端子が実装されている。こちらはAQUOS側のチューナで受信したデジタル放送の映像を480i変換して出力する端子だ。
モニター出力端子からの出力映像はAQUOS側のチャンネルを切替ると変わってしまうため、いわばクローン画面を表示するしか使いどころがない。これに対し、録画出力端子はデジタル放送の内容を出力しながらAQUOS側で地上アナログ放送を楽しむ、ということもできる(ただし480i出力)。
単体チューナと同じく、ビデオレコーダとの連動録画機能は持っている。あらかじめビデオレコーダのメーカーや機種コードを設定しておけば、付属の赤外線信号発信ケーブルでAQUOSチューナ側からビデオレコーダーの電源オン/オフ、録画開始/停止を制御できる。
 |
 |
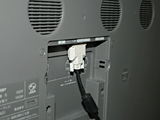 |
| チューナユニットの背面。スピーカー出力や、1ビットデジタルアンプも内蔵 | PC入力とビデオ入力4が並ぶチューナユニット部前面パネル。光デジタル出力も前面から狙える | ディスプレイ部のDVI端子でもPCとデジタル接続が可能だった |
デジタル音声出力端子は本体の前後にそれぞれ1系統ずつある。共にAACの5.1ch出力が可能になっている。音声周りとしてはこのほか、外部スピーカー端子を持つが、これは内蔵スピーカーとは排他仕様であり、内蔵スピーカーと外部スピーカーのどちらか一方しか駆動できない。
PC入力はアナログRGB入力に対応したD-Sub15ピン端子を前面パネルに1系統実装している。ディスプレイ部にもDVI-D入力があるが、これはチューナとディスプレイの接続に使う。念のため、ディスプレイ部のDVI-D端子とPCとを接続してみると、問題なくデジタル出力ができた。市販のDVI端子切替器などと組み合わせて、PCとチューナユニットを切替ながら活用するのも良いかもしれない。▼操作性チェック~起動は意外にも遅い
電源投入してから画面が表示されるまでは実測で8.3秒。意外にも時間が掛かるのに驚かされた。起動してしまえば、後は普通のテレビと変わらない。チャンネル切替、アスペクト比切替、画調モード切替などは瞬間的に実行される。
リモコンは薄いが全長は長め。1から12までの数字キーが2段でレイアウトされているのが特徴的だ。上段が地上アナログのチャンネル切替キーで、下段がデジタル放送のチャンネル切替キーに対応する。上段の数字キーのみ蓄光式で、暗がりでほのかに輝くようになっている。
入力切換はリモコンの最上部に独立キーとしてレイアウトされており、押すと入力切替メニューが開き、カーソルキーで切替る(順送り式操作も可能)。外部入力の使用中もテレビのチャンネル切替キーを選択すれば、ダイレクトにテレビ放送に切り替わる。
比較的使用頻度の高いと思われる「画面サイズ」(アスペクト比切替)キーや、「AVポジション」(画調モード切替)キーが、蓋を開けて使うサブパネル側にレイアウトされているのが個人的には少々不満。AQUOSをモニター的に使いたい人は少なくないはずなので、これは改善して欲しいポイントだ。
 |
 |
| 薄いが結構大きい付属リモコン | 下部の上蓋がスライド開閉する。中には使用頻度の高い操作も |
なお、上段の数字キーは、デフォルトでは地上アナログ放送のチャンネル切換キーだが、別途「お好み登録」することでユーザーキーとして再マッピングも可能。筆者は使用頻度の多い外部ビデオ入力やPC入力を数字キーの2、5、7、9、11などにマッピングして活用できるかと思って試してみたのだが、お好み登録で登録できるのは放送チャンネルのみとなっていた。これも制限の撤廃を臨みたいところだ。
▼画質チェック~アナログ感漂う滑らかな階調性と深みのある発色。IP変換は今一歩?
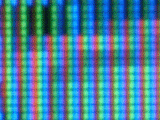 |
| Windows XPのデスクトップアイコンの一部。PCから1,360×768ドットでリアル出力した。画素を区切って縦に走る黒い縦縞が見えるが、実際の映像では線のように見えることはほとんど無い |
使用液晶パネルはASV(Advanced Super V)液晶パネル。以前よりASV液晶とは技術的な背景を元にしたカテゴライズではなく、シャープの液晶パネルの総合ブランド名のようなものとして扱われてきたが、最近ではCPA(Continuous Pinwheel Alignment)方式の液晶パネルを指すようになっているようだ。
CPA方式とは、原理的には富士通が開発したMVA(Multi-domain Vertical Alignment)をシャープが発展させたもの。1ピクセル内に複数のサブピクセル電極を形成し、画素全体としてみると液晶素子を放射状に連続的に傾斜配向させて制御させる。これにより、視線角度に依存しない光透過制御が行なえ、結果、CRT並の上下左右170度の視野角を達成できる。また、AQUOSに採用されているCPA液晶は、開口率や応答速度を向上させる工夫も施しており、モジュール輝度で450cd/m2、全黒白応答速度で15msを達成している。これまでの液晶テレビの弱点をかなり高いレベルで克服している。
パネル解像度は1,366×768ドット。ちなみにフラットテレビには1,280×768ドット解像度の製品もあるが、この場合、アスペクト比は15:9になる。こうした製品ではアスペクト比16:9の映像を表示時、下48ドット領域を非表示としたり、あるいは画素セルを7%ほど横長の長方形にして、表示領域を16:9とした製品もある。筆者は正方画素が好きなので、1,366×768ドットのLC-37AD1はまさに「願ったり叶ったり」だ。
実際の表示映像の品質だが、色深度はかなり深く、カラーグラデーションも美しく決まってくれる。純色の発色は良好。赤と緑の輝きはかなりシャープな印象を受ける。液晶テレビ特有の肌色の冷たさも、色温度を「中」にすれば人肌にも暖かみが生まれる。
階調性も文句なし。液晶テレビ特有の滑らかさが心地よい。最暗部階調はコントラストを稼ぐためにやや殺し気味になっており、これが気になるユーザーは黒レベルを若干引き上げるといいかもしれない。
液晶テレビに限らず、CRTやプラズマテレビもそうなのだが、各画素の発色は隣接したRGBの3原色サブピクセルが混合して見えることから成り立っている。このRGBサブピクセルの分離感の度合いが大型テレビの画質を語る上で避けることができない。この点については、LC-37AD1はまずまずといったところ。単色領域を多めに含んだアニメやゲームなどの映像を表示しても粒状感を感じることはなかった。
ただし、シャープな色境界付近で目を凝らすと偽色を感じることがある。画素の透過光の迷光が近接した画素のサブピクセルを鈍く発光させるためだと思われるが、いちいち目くじらを立てるほどはっきりしたものではない。
■ まとめ~新モデルとの違いは?
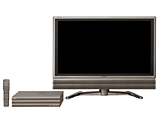 |
| ガンメタリックになり狭額縁化した新モデル「LC-37GD1」 |
私と同じように値崩れを始めたAシリーズを狙おうという人にとっても、やはり最新モデル、Gシリーズの存在は気にかかることだろう。
そんなわけで、東京・市ヶ谷にあるシャープのショールームにて最新モデルをチェックさせて頂いた。まず、特筆すべきは、最新AQUOSのGシリーズは37インチだけでなく、32インチ、26インチモデルにおいても解像度が1,366×768ドットのリアル16:9パネルになったこと。
とはいえ、パネル自体には大きな革新はなく、Gシリーズも同世代のASV液晶になる。シャープ側の説明によれば「カラーフィルターを変えている」(広報室東京広報グループ若松衛副参事)とのことだが、基本構造が先代Aシリーズのものと同じためか、表示映像の印象は大きくは変わっていない。ディスプレイのデザインは、Aシリーズよりも明らかに狭額縁化が進んでいる。ボディカラーもGシリーズはAシリーズに比べ濃い目の渋い色になった。
実はGシリーズの最大の進化ポイントはチューナユニット側にある。PCカードスロットが搭載され、各種メモリカードへの静止画記録(640×480ドット)、動画記録(MPEG-4、320×240ドット)までが行なえるようになった。そして正式に、DVI-I入力(HDCP対応)をサポートするようになった点もPCユーザーには歓迎されることだろう。
こうしたチューナユニットの機能強化に伴って、チューナユニットのデザインも一新、併せてリモコンの形状も変更されている。
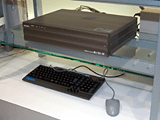 |
 |
| 一瞬「X68000PRO」と見間違えてしまった新AQUOS Gシリーズのチューナユニット(編注:キーボードとマウスは接続できません) | シャープの市ヶ谷ショールむに並べられたGDシリーズ(手前)。左からLC-37GD1、LC0-37GD2、LC-32GD2。右端は以前のラインナップにあったLC-22AD1 |
購入したLC-37AD1の後継は「LC-37GD1」になるが、実際に操作させて貰って感じたのは、起動が速いということ。電源投入後、LC-37AD1のおよそ半分以下の時間で画面表示が始まる。PCカードスロット機能はともかく、起動時間が早いのはちょっとうらやましかった。
しかし、今夏に登場する1,920×1,080ドットパネルの45V型新AQUOSを見てしまうと、さらにうらやましくなるのだろうが……。
□シャープのホームページ
http://www.sharp.co.jp/
□製品情報(LC-37AD1)
http://www.sharp.co.jp/products/lc37ad1/
□関連記事
【1月26日】シャープ、解像度1,366×768ドットの37/32/26V型「AQUOS」
-地上デジタルチューナ、DVI入力も装備
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040126/sharp.htm
【2003年6月17日】シャープ、地上デジタルチューナ搭載の37V/30V型AQUOS
-フラットパネルテレビで初搭載、アップグレードの必要なし
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20030617/sharp1.htm
(2004年3月4日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved.
|
|