 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第215回:シンプルさが光る小型写真DV機「IXY DV S1」
|
■ ビデオカメラの冒険
DVビデオカメラ市場のような安定微増のマーケットにおいて、冒険的なアプローチをするのはなかなか難しい。変なことをして外すよりも、今まで通りの姿形でちょっとずつ性能を上げていけば、それなりに売れる。そのほうがメーカーとしても、売り上げ計画が立てやすいのである。キヤノンはDVカメラに関して、割と保守的なイメージの製品が多い。もっとも冒険するときはXL1のようなとんでもないカメラが出てきたりするわけだが、ここ2~3年あまり大胆なデザインは見られなかった。
だが本日発表された「IXY DV S1」(以下DV S1)は、最初からコンセプト重視で設計された意欲作だ。そのコンセプトとは、Simple & Specialな「ミニマル デザイン」。形状のユニークさから、エントリーモデルだとナメてはいけない。機能面ではなんと昨年の縦型コンパクトフラッグシップ、「IXY DV M3」とほぼ同等だという。
キヤノンがこの秋に放つスタイリッシュコンパクトDVカメラ、DV S1を早速チェックしてみよう。
■ シンプルなモノフォルム
ここ最近のDVカメラというのは、光学部分とデッキ部という2ブロックが合体したデザインが主流となっていた。だがDV S1は、全体でほぼ立方体というモノフォルムを採用している。Hi-8時代からモノフォルムを採用したビデオカメラはいくつかあったが、そう言う意味ではちょっとレトロな雰囲気もあり、サイズ的にかわいいカメラに仕上がっている。光学部から順に見ていこう。レンズは高屈折非球面レンズ1枚を含む、9群11枚のキヤノンビデオレンズ。光学10倍ズームで、F値は1.8~2.8と、結構明るいほうだ。レンズ部には、スライドスイッチで開閉するレンズカバーを内蔵している。ぱっと見るとフィルタなど付きそうにないが、ちゃんとレンズ部内径にネジが切ってある。フィルタ経は27mm。

|

|

|
| 突起部が少ない四角形フォルム | 高屈折非球面レンズ採用のキヤノンビデオレンズ | スライドスイッチで開閉するレンズカバー |
NDフィルタは、キヤノン独自のグラデーションNDフィルタを採用。動画において、NDの半掛かり状態での回折現象を防ぐ働きがある。キヤノンのビデオカメラは、昨年のFV M20以降、エントリーモデルのFV500を除いた全機種で、このグラデーションNDフィルタを採用している。
画角は、動画が35mm換算で通常モード48.7~487mm、ワイドモード41.6~416mm。静止画は38.1~381mmとなっている。なお動画のワイドモードでは従来機どおり、手ブレ補正をOFFにすることでより広い画素で撮影する「高解像度ワイドモード」を備えている。
| 撮影モードと焦点距離(35mm判換算) | |||
| モード | ワイド端 | テレ端 | |
| 4:3 |
 48.7mm |
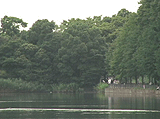 487mm |
|
| 16:9 手ぶれ補正・ON |
 43.3mm |
 433mm |
|
| 16:9 手ぶれ補正・OFF |
 41.6mm |
 416mm |
|
| 静止画 |
 38.1mm |
 381mm |
|
CCDは1/3.9型で、総画素数220万画素、フィルタは原色だ。有効画素数は、動画時123万画素、静止画時200万画素となっている。撮影可能な静止画画素数は、最大で1,632×1,224ピクセル。
そのほか前面には、お馴染みのLEDビデオライトと静止画用フラッシュがある。その脇の花模様の穴はスピーカーだ。Canonロゴの下にはステレオマイク、DC INとAV入出力端子がある。最近小型カメラは、だんだんマイクを付ける場所がなくなって、上面に付いているものが増えているが、ちゃんと前面に付いていると集音の面でも安心できる。
右側を見てみよう。液晶モニタは、背面のレバーをスライドするだけでパカッと開く、ワンタッチオープンLCDとなっている。これはなかなかいいアイデアだ。液晶モニタは2.5型TFTで、12.3万画素。

|

|

|
| 前面下部には電源とAV入出力端子 | シンプルな右側面 | ワンタッチで開く液晶モニタ |
液晶脇には、USBでプリンタやPCと接続できるイージーダイレクトボタン、液晶の輝度を上げるバックライトボタンがある。また液晶上部には、小型の録画ボタンも備えている。
液晶モニタを開けたところに、バッテリを装着するようになっている。かなり薄型だが、低消費電力設計を頑張ったおかげで、連続120分、実時間で70分という撮影時間となっている。ただし装着場所が場所なので、大型バッテリの装着はできない。

|

|
| 液晶内側にバッテリを装着する | バッテリはかなり薄型 |
側面には再生系ボタンが並ぶが、撮影時はビデオライトやフラッシュの切り替えボタンとして機能する。また上部にも3つのボタンがあり、主に静止画系の機能が割り当てられている。ここまで写真を見てお気付きかと思うが、ボタン類の名称はすべて英語表記になっている。このあたりもデザイン性を重視した結果だろう。
背面を見てみよう。DV S1のコンセプトをもっともよく表わしているのが、モードダイヤルだろう。キヤノンのビデオカメラはシーンモードが多く、前作のFV M30などはもうちょっとでダイヤル1回転全部がモードになりそうなイキオイだった。だがDV S1のモードダイヤルはシンプルで、フルオート、プログラムAE、シーンの3つしかない。だがこれが異様に使いやすいのである。詳しくは後で見ていこう。

|

|
| 上部にも3つのボタン。すべて英語表記 | シンプルなモードダイヤルが目を引く背面 |
そのほかメニューボタンとセットレバー、その下によく変更する機能を集めたファンクションボタンがある。マニュアルフォーカスへの切り替え、露出補正も別途ボタンが設けられている。
テープとメモリーカードの切り替えは、録画ボタン下のレバーになった。このスイッチは非常にタッチが良く、使いやすい。以前このスイッチはカメラの左側面や上部など、普通そんなとこに指届きませんケドみたいなところに付けられていたものだが、この場所は機能がイメージしやすい。
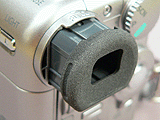
|
| 引っ張り出すと接眼になる2WAYビューファインダ |
ビューファインダ下にある穴のようなものは、リモコンの受光部だ。今までリモコン受光部は前面に付けられるケースが多いが、実際には液晶モニタは後ろを向いていることのほうが圧倒的に多いわけで、リモコンも背面から操作できた方がいいに決まっている。これは案外気がつかなかった部分だ。
ビューファインダは、引っ張り出すと接眼で、押し込んだ状態では離れた位置から覗き込んでピントが合うようになっている。この2WAY仕様はプロ機の大型ビューファインダでよくある機構。狭い場所に手を突っ込んで撮影する場合など、液晶モニタが広げられないときに便利だ。
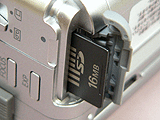
|
| miniSDカードは背面底部から差し込む |
メモリーカードは、後部底面から差し込むようになっている。対応カードがminiSDなのは、ビデオカメラとしては珍しい。カードスロットのフタがあるこの部分は、ホールドしたときに親指の付け根が当たるところで、硬い素材では手に負担がかかってしまう。従来製品ではここの部分だけ別途ゴムパーツをはめ込んだりしていたわけだが、今回はそのゴム素材をSDカードのフタとして兼用するというアイデアが秀逸だ。
テープドライブ開口部は、上向きに付けられており、三脚に乗せた状態でもテープ交換可能。ドライブ部下にはUSB、DV端子が並ぶ。
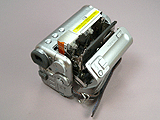
|

|
| テープ交換は上部から可能 | ドライブ下部にはUSB、DV端子が |
■ 曇天ながら十分発色が楽しめる
| 動画サンプル | ||
 ezsm01.mpg (34.3MB) |
||
では実際に撮影してみよう。週明けの東京は、台風7号の接近に伴って降ったり止んだりの不安定な天候で、残念ながら撮影条件としては最悪と言ってもいい。そのあたりを考慮に入れて、サンプルを評価していただきたい。
特徴的なモノフォルムだが、実際に構えてみると、非常に安定して持ちやすい。ビデオカメラは今までグリップを付けたりオーガニックな形にしてみたりと、持ちやすさを追求していろいろな試みが行なわれてきたが、結局はまっ四角でもサイズが妥当ならそれなりにしっかり持ててしまう、ということのようだ。
絵柄だが、曇天にもかかわらずキヤノンらしいはっきりとした発色が出ている。さすが記憶色へのこだわりで絵作りを行なっている成果とでも言おうか。ただ菖蒲の紫のような色は微妙で、青に丸め込まれる傾向がある。目視の色にこだわる場合は、ホワイトバランスの設定を変える必要があるだろう。

|

|
| あいにくの曇天ながら、発色のバランスがいい | 微妙な紫は青寄りになる傾向がある |
ぱっと見レンズ経が小さくショボそうに見えるのだが、レンズの質は良く、解像感も良好だ。解放でのボケ味も悪くない。ただ若干絞りの形である菱形が気になるケースもある。もっともこのクラスのカメラでは、そこまで構えて撮ることは少ないため、あまり問題にならないだろう。

|

|
| 水面に反射する木々の緑も色濃く捉えている | 細かいディテールに対する解像感も良好 |

|
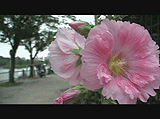
|
| スミアは以前から出やすい傾向にある | 被写体には10cmぐらいまで近づける |
撮影していて非常に使いやすかったのが、意外にも3モードしかないモードダイヤルだ。例えばプログラムAEは絞り優先に、シーンモードはナイトモードに設定しておくと、ダイヤルを回すだけでどんな明るさの違う場所に移動しても、瞬時に対応できる。そう言う意味では、ダイヤルに自分の好きな設定をプリセットできることと変わらない使い勝手だ。
最初は、シーンモードをいちいちダイヤル回して、さらにファンクションボタン押して切り替えなければならないのは面倒だと思っていたのだが、ある程度撮影場所に応じて決め打ちでセットしておけば、通常撮影から瞬時に切り替えられることになる。
ワンタッチで開く液晶モニタも、なかなか便利。撮影中には電源を落とさず、省電力のために液晶モニタを閉じた状態で移動することが多いのだが、撮影ポイントに来て一発で液晶が開くのは快感だ。
液晶上部にある録画ボタンは、存在が地味なためうっかりすると使えるシーンなのに、使うのを忘れてしまうことがある。またボタン周りの凹みが小さく、爪の先でなければ押すのが難しい。

|
| マニュアルで手前の花にフォーカスを合わせたつもりだったのだが、よく見えなかった |
このカメラの場合、もちろん女性のウケも狙っていることだろうが、爪を伸ばしている女性にはちょっと使いづらいのではないだろうか。もう少し周りの凹みを広く取れば、爪を使わず指の腹でも楽に押せるようになるだろう。
弱点と言えば、液晶モニタの解像度が粗く、マニュアルでフォーカスを合わせたいときによくわからないところか。またAFの精度は悪くないのだが、ちょっと頑固なところがある。絞り開放でテレ端の時に、被写体をちょっとずらしたところ、前のフォーカス位置から動いてくれないことがあった。
撮影条件は悪かったのだが、その分ナイトモードのテストができた。絞り開放でも暗くて撮れないシーンでも、色味も含めてしっかり撮れる。個人的にはあまり使う機能ではないのだが、ビデオライトを付けるほどでもない状況で、案外使い出があるモードのようだ。夜景用としては「打ち上げ花火モード」も備えており、これからの季節が楽しみだ。ただ発売が8月下旬なので、お楽しみは来年に持ち越されてしまうかも知れないが。
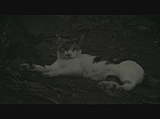
|

|
| 通常モードで撮影すると、絞り開放でも追いつけない | ナイトモードではコマ数は落ちるが、ここまで写る |
■ 相変わらずソツがない静止画機能
続いて静止画機能を見ていこう。デジカメの世界では、すでにコンパクト機でありながら6メガピクセルの世界に突入しようとしている。そんな中で2メガの静止画は、スペックとしては見劣りしてしまう点は否定できない。だがキヤノンのDVカメラは、以前から「写真DV」を名乗るだけあって、絵作りの上手さで画素の少なさをカバーしてきた感がある。今回はかなり暗い中での撮影だが、発色、S/Nともに良好で、絵としての満足感は高い。実際に印刷すればL版程度になるだろうが、そうそうでっかくプリントする機会もないだろう。そう考えれば、日常的な使い勝手としては十分だと言える。

|

|

|
| 画素数は少ないが、雰囲気のある写真が撮れるのが魅力 | 単調な背景部分でのノイズ感が少ないのも特徴 | グリーンの発色が綺麗だ |
静止画モードのAFでは9点で測距するので、フォーカスの追従はかなり柔軟に対応できる。ちょっと気取ったフレーミングでも、そこそこ思ったところにピントが来てくれるのはナイスだ。

|

|

|
| 静止画のAF機能は優れている | AFの追従も速く、シャッターチャンスを逃さない | 狙ったところに気持ちよくフォーカスが来る |
難点と言えば、採用しているメモリーカードがmini SDカードというところだろうか。ケータイなどでは採用が進んでいるものの、SDカードと違って既に持っている人は少ないだろう。新たにそこそこの容量のものを購入しなければならないわけだが、SDカードよりも割高になってしまう。
■ 晴天時に改めて撮影
後日、台風一過の晴天下で追加撮影してみた。やはり光量があると爽快感のある絵が撮れる。
|

|

| ||
| 光りの透明感がいい感じだ | 光量がある分だけコントラストの高い絵が撮れる |

|

|
| 画質効果「ソフト」で撮影。やわらかいトーンが綺麗 | 画質効果「切」で撮影。若干輪郭がキツ目だ |
■ 改善されたメニュー回り
DV S1ではメニューのGUIも改善されているので、そのあたりも見てみよう。まず通常メニューだが、各設定カテゴリを選んだだけで、そこにどんな設定があるのかが一覧でわかるようになった。以前はカテゴリを選んで中に入らなければ、どんな設定があるのかわからなかったため、ある程度メニューの内容を記憶しなければならなかったのだが、今回からかなりその辺が楽になっている。頻繁に変更するであろう機能を集めたファンクションボタンは、以前から搭載されている。ただ今回は、モードダイヤルが3モードと非常にシンプルになったため、その役目が大きくなっている。
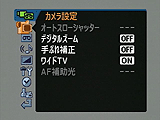
|
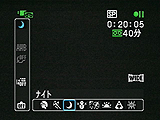
|
| カテゴリを選んだだけで、どんなパラメータがあるのかがわかる | ファンクションメニューも健在だが…… |
3つのモードそれぞれに対して使用可能な機能とそうでない機能があるのだが、このぐらいモードが少なければ、使えない機能はわざわざグレーアウトして残しておくのではなく、表示を隠してもいいのではないか。あるいは表示しても、選択がスキップされるようにすべきではないか。そのほうがシンプルさが際だって、より好感が持てるだろう。
ファンクションメニューにおける操作系の問題は、横移動が多いメニュー構成にもかかわらず、レバーが縦方向にしか動かないというところだ。感覚的には、メニューが左側から開いていくので、左が始点だと感じる。そういう観点からすると、メニューを右に移動する、つまり始点から離れる方向に移動するには、レバーを下に動かすのが妥当だと思うのだが、DV S1では逆に上に動かすと右に移動するようになっている。
左右の移動を上下レバーでどう操作するかは、人によって感覚が違うのかも知れないが、実際に撮影中にいつも逆に動かしてしまって、設定の変更に手間取った。ファンクションメニューの構造も、操作レバーの方向と合わせてくれれば、もっと使いやすかっただろう。
■ 総論
IXY DV S1は、ほぼまっ四角なボディの中に絶妙なレトロ感が配合されている、不思議なカメラである。なにかこう、最近リニューアルされた「鉄人28号」の世界観というか、古いクセに最新鋭、みたいな感覚なのだ。それがまた妙に手に馴染むというか、ずーっといじくり回していたい気にさせるのである。カタチは妙にかわいいのだが、ボタン類の配置や操作に関して良く練られていて、シーンごとに設定を瞬時に切り替えるマニアックな使い方から、フルオート一点勝負な使い方まで、柔軟に対応できる。店頭予想価格も9万円前後と、お手ごろな価格帯だ。
機能的にはM3とほぼ同等ということもあって、1CCD機ながらこの悪天候でもこれだけの絵が撮れるというのは驚きである。なにせ去年のミドルクラス最高機種と同等なのだから、機能的に悪いわけがない。光学ズームが10倍ということからも、いわゆる小学校の運動会カメラではなく、友人、恋人、ペットなど、身近な被写体を撮るといった使い方がいいだろう。
もちろん欲を言えば、もっと小さくてもっと高画素でほかの色が選べて、ときりがないわけだが、デザイン的にも機能的にも、いい落としどころだろう。これより高性能なカメラはいくらでもあるが、カタチとスペックだけでは、DV S1の良さはなかなかわからないかもしれない。実際に絵を撮ってみると、普通のカメラがつまらなく思えてしまうのである。
いや、これはいいカメラだよぉ。
□キヤノンのホームページ
http://canon.jp/
□ニュースリリース
http://cweb.canon.jp/newsrelease/2005-07/pr-ixydvm5.html
□「IXY DV S1」の製品情報
http://cweb.canon.jp/dv/lineup/ixydvs1/index.html
□関連記事
【7月28日】キヤノン、430万画素原色CCD搭載の「IXY DV M5」
-220万画素で世界最小・最軽量の「IXY DV S1」も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050728/canon2.htm
【2004年6月16日】【EZ】“ダブルOK”がよりコンパクトに「IXY DV M3」
~ 見かけは小粒だが絵はすごい! ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040616/zooma158.htm
(2005年7月28日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c) 2005 Impress Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
