 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|

|
第55回:デュアルアイリス機構でコントラスト7,000:1? ~ 正常進化の720pモデル 日立「PJ-TX200J」 ~ |
今秋続々と登場する720pフロントプロジェクタ。液晶系ではエプソンの新D5パネル搭載製品などが各メーカーから発売。一方DLPも新720pチップを搭載した低価格帯の製品が続々発売されている。
今秋の「大画面☆マニア」では、実売20~30万円台の売れ筋製品をピックアップ。毎週新製品のレビューを掲載する。(編集部)
■ 設置性チェック
~クラストップレベルの100インチ(16:9)を2.8mで投射可能
本体デザインは細部に相違点を見出せるものの基本デザインは先代「PJ-TX100J(2004年6月発売)」と共通。ただし本体色を「ミッドナイトチタン」と呼ぶ、青みを帯びたメタリックカラーに変更しており、見た目上の高級感を向上させている。
本体デザインは先代を踏襲しながらも、正面を絞ったスポーツカーライクな大胆なデザインには未だ斬新さを感じることができ、競合他社製品と並べても遜色ない。とは言ってもいつまでもこの手が使えることもないだろうが。
本体重量は約4.7kgとPJ-TX100Jから300g増加しているが、このクラスとしては標準的な重さであることに変わりはない。大人であれば一人での移動も問題なく行なえる。
 |
 |
| 本体サイズは340×299×113mm(幅×奥行き×高さ)で、だいたい大型のA4ファイルサイズノートPC程度 | 本体大きさ比較。上から日立PJ-TX200J、エプソンEMP-TW600、松下TH-AE900 |
天吊り設置用の金具も前モデルと共通の「HAS-TX101」(42,000円)が純正オプションとして設定されている。つまり、PJ-TX100Jを天吊り設置しているユーザーは、本体のみを買い換えるだけでPJ-TX200J環境にアップグレードできる。
投射レンズはPJ-TX100Jと同型の1.6倍、マニュアルズーム、マニュアルフォーカスタイプを採用する。100インチ(16:9)画面の投射距離はワイド端で約2.8m、テレ端で約4.6mとなっており、特に「最短投射距離2.8mで100インチ」という短焦点性能は、強い訴求ポイントとなることだろう。
競合、松下「TH-AE900」や三洋「LP-Z4」と比較してみると最短投射距離は約30cmほどPJ-TX200Jの方が短く、最長投射距離は1.6mもTH-AE900やLP-Z4の方が長い。つまり、小さい部屋での大画面投射はPJ-TX200Jの方が得意で、大きい部屋の最後部に設置して画面サイズを選びやすいのは、TH-AE900やLP-Z4ということになる。
 |
| 存在感のある投射レンズ。100インチ(16:9)の最短投射距離はクラス随一 |
本機は奥行きが30cm程度なので、本棚などの天板に載せての疑似天吊り設置を考えている人も少なくないだろう。こうした疑似天吊り設置の場合、本体を天地逆転させて設置するのがセオリーとなるわけだが、この上下±75%のレンズシフト機能を使えばその必要もない。普通に天板上に設置して投射画面を下にシフトすればいいだけだ。
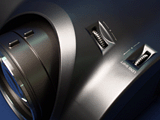 |
| フォーカスとズーム調整は行いやすいが、レンズシフト調整のダイヤルは堅く、微調整が難しい |
フォーカスとズームの調整はレンズ外郭のつまみをスライドして行なう方式。つまみの動きはスムーズで調整はやりやすい。レンズシフトはボディ上面に備え付けられた2つのダイヤルを回してX軸方向、Y軸方向に画面をずらしていく操作系なのだが、こちらのつまみは固めでやや扱いづらい。X軸を調整するとY軸がずれたり、フォーカスがずれたりしてしまう。実際の設置の際にはズーム調整とシフト調整を先に調整して、その後フォーカス調整をした方がいい。
騒音レベルは低輝度モードの静音モードで公称25dB、標準輝度モードの標準モードでも公称28dB。標準モードでもプレイステーション 2(SCPH-30000モデル、以下PS2)よりも静か。視聴を開始すれば、PJ-TX200Jの存在を意識することはほとんどなくなるはずだ。
光漏れは側面の排気スリットから若干ある程度で投射映像への影響は皆無だ。採用ランプはPJ-TX100Jと同じ150Wの超高圧水銀系のUHBランプ。交換ランプ自体もPJ-TX100Jと同じ「DT00661」(29,400円)が設定されている。
 |
 |
| 吸気は正面右側面スリットから、排気は正面のスリットと正面向かって左側の側面スリットから行なわれる。吸排気系が背面にないので、投射距離をめいっぱい稼ぐために壁に寄せて設置しても廃熱効率に影響が出ないわけだ。ただし、側面を塞いでしまうとエアーフローをかなり制限してしまうことになるので危険。本棚などに設置する際には注意したい。 | |
■ 接続性チェック
~PJ-TXシリーズとしては初めてHDMI入力をサポート
 |
| HDMI端子が実装されたほかは、PJ-TX100Jと同じ |
アナログビデオ入力としてはコンポジットビデオ入力、Sビデオ入力、コンポーネントビデオ入力が各1系統ずつというラインナップ。D入力は先代同様採用が見送られている。
デジタルビデオ入力としては、HDMI入力を1系統実装。そのかわりPJ-TX100Jに搭載されていたDVI-D端子はカットされた。
PC入力はその関係でD-Sub15ピン端子経由のアナログRGB接続のみを公式サポートする。実際には、市販のHDMI-DVI変換アダプタを用いることで、PCとのデジタルRGB接続は可能なのだが、それについては後述する。
外部機器連動用のトリガ端子、メンテナンス&リモート制御用のRS232C端子は、PJ-TX200Jでも引き続き実装されている。
■ 操作性チェック
~オリジナルガンマカーブとカラーバランス設定に対応
 |
| リモコンもPJ-TX100Jのものとほぼ共通。底面には窪みがあって人差し指をその窪みに添えると親指が十字キーに位置するようになっている |
リモコンはPJ-TX100Jのものと、ボタンのレイアウトに至るまでほぼ同一。この小型リモコンは外注品のようで2002年発売の松下電器の「TH-AE300」も採用しているもので、さすがに古くささが否めない。
前回取りあげたTH-AE900の大きくなったリモコンをしばらく使っていたせいか、PJ-TX200Jのリモコンは小型ボディに小さいボタンが高密度に並びすぎてて、どのボタンがどの機能かが瞬間にわかりにくいと感じた。
最上段右端の[LIGHT]ボタンを押すことで、リモコン上の全ボタンが自照式にオレンジ色に点灯するが、ボタン上の文字が小さいために読みにくい。たとえば[BLACK]ボタンの"B"の文字を計ってみたところ横幅はわずか1mm。これを暗闇の中で淡いオレンジ色のバックライトだけで短時間に読むのはさすが容易ではない。次期製品ではそろそろリモコンのデザインにも再考が必要かもしれない。
 |
| 十字キーと基本操作用のボタンは本体側の上面にもレイアウトされている |
[POWER]ボタンを押すことで電源が投入されるが、「LCD ENTERTAINMENT PROJECTOR」と書かれた起動画面が表示されるまでが約5.0秒(実測)、実際にHDMI接続された機器の映像が表示されるまでが約16.0秒(実測)かかった。PJ-TX100Jと比較するとだいぶ高速化されたことになるが、最近の機種の傾向と比較すると標準的か、やや早めといったところ。
[BLACK]ボタンと[IRIS]ボタン、これがおそらくPJ-TX200Jユーザーを最初に悩ませるものになるはずだ。
PJ-TX200Jでは、投射系において、絞り(アイリス)機構が2つ組み込まれいる。
 |
| PJ-TX200Jのデュアルアイリス機構。ランプ直後にあるのが「アクティブアイリス」、投射レンズ内にあるのが「レンズアイリス」 |
両方に「アイリス」の名前が付けられているので、リモコン上の機能名が略記されたボタンのどっちがどっちの機能を制御するものなのかわかりにくい。
結論としては[BLACK]ボタンがアクティブアイリスを制御するもので、[IRIS]ボタンがレンズアイリスの方を制御する。これは技術名優先で機能を名付けた結果、ユーザーに対してなにができるのかを伝わりにくくしてしまった典型パターンだといえる。
ボタンの[BLACK]を活かすならば、アクティブアイリスは「アクティブブラック」と命名すべきだったし、機能名の方を活かすならばボタンの方を[A.IRIS]と[L.IRIS]というふうに記述すべきだった。この2つのボタンの扱いをマニュアル無しに理解するのは難しいだろう。
[BLACK]ボタンは、押すことでこのアクティブアイリスの効き具合を「オフ」「オート1(効き小)」「オート2(効き大)」の3段階に順送り式に切り替えて設定できる。[IRIS]ボタンの方は押すことで、レンズアイリスの開度を10段階設定する調整バーを呼び出すことができる。調整バーは十字キーの上下ボタンで動かすことができ、0が最小絞り(最小輝度)、10が絞り開放(最大輝度)の設定に対応する。
さらに、ややこしい話になってくるのが、このデュアルアイリス機構と後述のプリセット画調モードとの関係性。レンズアイリスの設定はプリセット画調モードの切り替えによって上書き制御されてしまうのだが、アクティブアイリスの設定はプリセット画調モードの切り替えの影響を全く受けずに設定が生き続ける。
たとえば、ユーザーが任意のレンズアイリスを設定したとしても、プリセット画調モードを切り替えた時点でその画調モードに設定されているデフォルトのレンズアイリス値に上書きされてしまう。どうしてもその設定状態を維持したければユーザーメモリを利用する必要がある(後述)。 ところが、アクティブアイリスの設定はPJ-TX200Jのグローバルな設定値として管理され、画調モードの切り替えの影響は受けない。
投射環境に応じたアイリス設定がレンズアイリスで、投射映像種別に連動したアイリス設定がアクティブアイリス、という機能説明がなされているにもかかわらず、実際には画調モードに連動しているのはレンズアイリスの方で、ユーザーとしては何がなんだかわからなくなってしまう。
とにかく一度、機能と実機での動作を把握してしまえば、ユーザーメモリを活用することでやりたいことはできるので実害はない。しかし、理想としては、レンズアイリスの設定もアクティブアイリス同様に、画調モードの切り替えの影響を受けないようにして欲しかったと思う。
[ASPECT]ボタンはアスペクトモードを順送り式に切り替えるもので、切り替え所要時間はゼロ秒。操作した瞬間に切り替わる。用意されているアスペクトモードは「4:3」、「16:9」、「ワイド」、「映画1」、「映画2」、「14:9」の6個、PJ-TX100Jに14:9モードが追加された格好だ。
「ワイド」は、映像中央部のアスペクト比をなるべく維持したまま4:3の映像を左右端を引き延ばす疑似16:9モード、「映画1」は4:3映像にレターボックス記録された16:9映像をパネル全域に表示するモード、「映画2」は映画1で字幕がかけてしまうケースに対処するために用意されたモードで映画1よりもズーム率を抑えて表示するモードとなっている。新設された「14:9」は、欧州向けのモードとのこと。
[MODE]ボタンはプリセット画調モードを順送り式に切り替えるもので、切り替え所要時間はゼロ秒。PJ-TX100Jからモード名が一新されて、「ノーマル」、「シネマファンタジー」、「シネマリアリティ」、「ミュージック」、「スポーツ」というラインナップになった。
使用頻度の高くなる入力切り替え操作は、その入力へダイレクトへ切り替えられるように個別に独立ボタンを用意した操作系となっていて使いやすい。切り替え所要時間はSビデオ→HDMIで約2.5秒(実測)、HDMI→コンポーネントビデオで2.3秒(実測)。ややもたつく感じで、PJ-TX100Jよりも遅くなっている。
メニュー操作は[MENU]ボタンを押して十字キーでカーソル移動、[ENTER]ボタンでメニューアイテムを選択して、その後上下カーソルで値を変更する操作系。設定値の変更は必ず上下ボタンで行ない、右ボタンでメニュー階層を下がり、左キーでメニュー階層を上がれる。操作系は直観的でわかりやすく、反応も良好、誤操作が起こりにくい。設定値をデフォルト値に瞬時に戻す[RESET]ボタンがあるおかげで大胆に設定値を変えて効果を楽しむことも気兼ねなくできる。
画調の調整はメニューからもできるがリモコン上のBRIGHT(明るさ),CONTRAST(コントラスト),COLOR(色の濃さ)の項目に個別に設けられた[+][-]ボタンを押すことで直接調整モードに入れるのも、調整マニアにはうれしい。この場合ももちろん[RESET]ボタンを使って基準値に戻すことが可能となっている。
 |
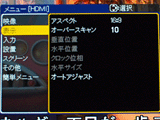 |
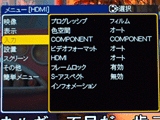 |
| 「映像」メニュー。画質の調整が行なえる | 「表示」メニュー。オーバースキャン(後述)の設定などが可能 | 「入力」メニュー。プログレッシブ化ロジックの動作モードの設定はここで行なう |
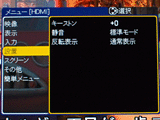 |
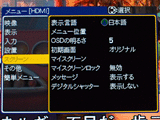 |
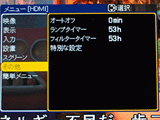 |
| 「設置」メニュー。「静音」の設定は実質的にはランプの輝度モードに相当 | 「スクリーン」メニュー。メニュー位置などの調整が可能 | 「その他」メニュー。工場出荷状態への初期化等はここで行なえる |
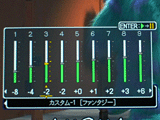 |
| 「ガンマイコライジング機能」。9個に分けた階調ブロックそれぞれに対して出力レベルを設定し、独自のガンマカーブを作り込むことができる |
PJ-TX100Jに搭載されていた投射映像を見ながらGUIベースで好みのガンマ補正が行なえる「ガンマ・イコライジング」機能はPJ-TX200Jにも継承された。
このガンマ・イコライジング機能では、完全黒から最大輝度の白までを9ブロックに分割し、各ブロックの出力レベルに対応した9個のスライダーの上げ下げで各ブロックの出力レベルを変更して任意のガンマカーブを作り込むことができる。
色温度のきめ細かなカスタマイズができる「カラーバランス設定」機能もPJ-TX100Jから引き続き搭載されているが、インターフェイスが格段にわかりやすいものに変更された。PJ-TX200Jでは暗部(低)、中明色(中)、明部(高)の三段階の出色に対して個別のRGB出力特性を設定できる。たとえば「暗部の青の階調が弱く、緑や赤のパワーに負けている」と感じた場合、暗部の青の出力レベルだけを上げることが可能。これは調整マニアにはたまらない機能だろう。
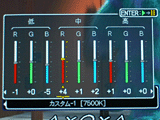 |
| 進化した「カラーバランス設定」。RGBを個別かつ同時に調整できるので、たとえば肌色の陰影の出方を高中低のそれぞれの階調ごとに個別に作り込むことができる |
調整結果を保存するユーザーメモリの機能はPJ-TX100Jよりも制約がゆるやかになって自由度が増した。
ガンマ・イコライジング機能で作り込んだオリジナルガンマカーブは、プリセットのガンマカーブとは別の4個のユーザーメモリに保存可能で、同様にカラーバランス設定で作り込んだ「色温度」モードも4個のユーザーメモリに保存できる。
この「ガンマ」と「色温度」のユーザメモリは、それぞれが個別に管理されるので、例えば「ガンマ」設定をユーザーメモリ2に保存したものを用い、「色温度」設定をユーザーメモリ1に保存したものを使う、といったユーザーが作り込んだ設定の自在な組み合わせが可能となった。
そして、「明るさ」、「コントラスト」、「ガンマ(ユーザーメモリ選択可)」、「色温度(ユーザーメモリ選択可)」、「色の濃さ」、「色あい」、「画質(シャープネス)」、「レンズアイリス設定値」、「アクティブアイリス設定値」、「ランプ駆動モード」といった基本画調パラメータの設定値は、これまた別管理の4個のユーザーメモリに保存できる。やや複雑な管理体制だが、カスタマイズの自由度は非常に高い。
なお、このような多段ユーザーメモリ管理体制のため、ユーザーメモリは入力切り替えごとには管理されず、全入力系統にて共有される格好になっている。これで各入力系統ごとに管理されていたら、とても使いこなせないので、これは妥当な設計だろう。
■ 画質チェック
~クラス最高の1,200ANSIルーメンがテレビ的な活用を可能に
なお、1,200ANSIルーメンの最大輝度はレンズアイリスを最大開放し、色温度モードを「ハイブライト」にしたときに実現される値となっている。実際、この最大輝度モードで使うと部屋の中がパッと明るくなるほどで、蛍光灯照明下でもバラエティ番組やスポーツ中継ならば普通に見ることができる。PJ-TX200Jには「照明下で食事をしながら見る」というテレビ的な活用すら可能な輝度ポテンシャルがある。
ちなみに、レンズアイリス、アクティブアイリスの2つのアイリス機構を最大限に絞った時には400ANSIルーメンにまで輝度は下がる。
最大コントラスト性能は公称7,000:1という、ずいぶんと大きく出た数値を出しているが、これはレンズアイリスを最大絞りにし、アクティブアイリスを最大制御する「オート2」とし、色温度モードを「ハイブライト」に設定したときの値。7,000:1というと平均的なDLPプロジェクタやLCOSプロジェクタをも遙かに凌駕する値だが、これは2つのアイリス機構を最大限絞った400ANSIルーメン時の黒色と、デュアルアイリスをともに開放した1,200ANSIルーメン時の白色との対比であるので、1フレームの中で7,000:1のコントラスト表現ができるわけではない。
PJ-TX200JのネイティヴコントラストはD5パネル自身の公称コントラスト性能である750:1に準じた値になっていると思われる。実際の体感上もそのくらいであった。
なおPJ-TX200Jは、日立のホームシアター機としては初の動的アイリス制御機構(アクティブアイリス)を組み込んだモデルになる。一世代分、この機能に取りかかるタイミングが他社より遅れたわけだが、果たしてその実力はどうか?
実際に「オフ」、「オート1」、「オート2」の3段階設定でどのような効果が現れるのかをじっくりと検証してみたが、使い物になると感じたのは「オフ」と「オート1」のみ。
「オート2」は映像の輝度レベルに応じてドラスティックに絞りを切り替えるため、非常に明暗の変化が激しい。激しいのはともかくとして、シーンの明暗の変化が大きいとき、このメカニカルな絞り制御がシーンの切り替えに極端に遅れる。たとえば、極端に暗い洞穴のシーンから、全く別の同時進行する屋外の明るいシーンに切り替わったりすると、0.5秒くらいかかってやっと適正輝度になって明るいシーンが描画される、といった具合。この動作には映像を見ていて違和感を感じる。もう少しアイリス制御を高速化しないと「オート2」のアクティブアイリスは7,000:1のカタログのスペック表記のためにあるモード、という印象を持たざるを得ない。
制御幅が幾分緩くなる「オート1」は、動作速度がなんとか間に合っているようで、「オート2」のような不自然さはなく、ちゃんと使える。
気になる黒浮きだが、PJ-TX200Jは最大輝度が高いこともあって、その明るさに黒が持ち上げられてしまう。スクリーン上の投射映像としての黒と、部屋の暗さの黒との輝度格差があるため、映像に黒領域が多いと、本来は黒のはずのところから鈍く光る灰色を感じてしまうのだ。
しかし、レンズアイリスを5程度にまで落とし、アクティブアイリスをオート1に設定すれば、これも大部気にならなくなる。もちろん絶対輝度として1,200ANSIルーメンの明るさはなくなる。
階調表現は非常にバランス良くまとめられている(オートアイリス=1までは、以下同)。前述の黒浮きがあるということを踏まえた上での潔いチューニングがなされており、出てくる映像には自然かつリニアな階調表現を感じることができる。デュアルアイリス機構を活用して黒浮きを低減させたときも、この階調性のバランスの良さは維持されている。
発色の傾向はナチュラルで、過度な原色強調も感じない。純色系の輝きにも適度な鋭さがある。赤にはもうちょっと深みは欲しいが、光源が超高圧水銀系ランプであることを考えればがんばっていると思う。肌色の発色にも黄緑感はなく、みずみずしさと血の気をほどよく感じられる。色深度も深く、混合色のグラデーションもなだらかに決まってくれていた。
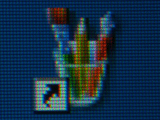 |
| HDMI接続のPC画面の中央付近を撮影。大口径レンズの恩恵か、画面中央でのフォーカス性能と色収差の少なさは特筆に値する |
視線の集まる映像の中央付近では色収差が非常に良く抑えられており、フォーカスもくっきりと決まり、画素1つ1つがぼやけることなく美しく描画されている。しかし、映像外周になればなるほど(フォーカスは合っているものの)色収差が強く出る傾向にあり、最外周では約1ドット分、緑が右に赤が左にズレているようだ。実写映像だほとんど気にならないが、PC映像で文字情報を映したときには気になるかもしれない。
【映像タイプ別のインプレッション】
●DVDビデオ(DENON DVD-2910、HDMI接続) HDMI接続の際、デジタルYCbCr、デジタルRGBのいずれのケースにおいても、TH-AE900のような階調レベルの相違はなし。フレーム相関型のノイズリダクションが甘いのか、モスキートノイズが目に付くことがある。気になる場合は画質(シャープネス)」を3程度に下げた方がいい。 画調モードは、臨場感重視ならば、クセのないホワイトバランスと純色が美しい「ノーマル」がお勧め。素のままだと黒浮きがあるのでレンズアイリスを4~5程度に下げた方がいい。
暗部階調を重視するならば、しとやかな色あいの「シネマファンタジー」がいい。この画調モードではピーク輝度が下がる分、相対的に黒浮きが見えやすくなるので、暗いシーンの多い映画ではレンズアイリス開度は3くらいまで下げたほうがいい。
アクティブアイリスは、「オート2」の使い心地がよくないので「オート1」がお勧めだ。
●Sビデオ(NEC PK-AX20/Sビデオ接続) PJ-TX100Jではインタレース映像のプログレッシブ化ロジックに難点があったためか、コーミングを知覚することが多かった。PJ-TX200Jではこの問題は改善を見ている。 ただ、PJ-TX200Jになっても、映像の自動判別機能を持っておらず、プログレッシブ化ロジックの動作モードは、ユーザが「TV」(2-2プルダウン)とするか、「フィルム」(3-2プルダウン)トするかを適宜選択しなければならない。なお、モードの選択を誤るとちらつきが出てしまう。
実写だと気が付きにくいが、アニメなどだと輪郭線のブレが知覚され、違和感を覚える。次世代機では、マニュアルモードの他、競合他機種のような賢いオートモードの実装を希望したい。
●ハイビジョン(東芝T-D2000/コンポーネントビデオ接続) 1,920×1,090ドットの200万画素映像が1,280×1,720ドットの100万画素画素への圧縮表示となるが、解像度変換品質が高いせいか、非常にシャープな映り具合になっており、HD映像の解像感の高さは十分に伝わってくる。 アップとなった人物の髪の毛の一本一本がぼやけず、なおかつジャギーも出ないで描画されている様はなかなか感動的。このクラスの解像度変換としてはよくできていると思う。
ハイビジョン放送の映像は、コントラスト重視に振って撮影されているものが多いためか、画調モードはバランスの良い発色とハイダイナミックレンジ表現に長けた「ノーマル」がしっくり来る。レンズアイリスを5程度に下げて黒浮きを抑え、アクティブアイリスをオート1設定とすれば完璧だ。
●PC(NVIDIA GeForce6800Ultra/デジタルRGB/アナログRGB接続
入力解像度 アナログRGB HDMI 640×480ドット ○ ○ 720×480ドット △ ○ 720×576ドット ○ ○ 848×480ドット ○ ○ 856×480ドット △ ○ 800×600ドット ○ ○ 1,024×576ドット △ ○ 1,024×768ドット ○ △*1 1,152×864ドット ○ △*1 1,280×720ドット ◎ ◎ 1,280×768ドット △ △*1 1,360×768ドット △ △*1 1,280×960ドット ○ △*1 1,280×1,024ドット ○ △*1 1,600×1,200ドット ○ △*1 1,920×1,080ドット ○ △*1 アナログRGB接続はD-Sub15ピンケーブルにて、デジタルRGB接続はHDMI-DVI変換アダプタ「MONSTER400 FOR HDMI」を用いた。
PJ-TX200JのHDMI入力はビデオ接続向けの調整になっているため、デフォルト状態でPC画面を映すとスタートメニューなどが欠けて表示されてしまうオーバースキャン表示となってしまう。これは「表示」メニューの「オーバースキャン」を最大値の10設定とすることで回避できる。
この状態で接続できれば、いうまでもなく、HDMI接続が最も高品位な表示となり、なかでも画面解像度とパネル解像度とが一致する1,280×720ドットモードが一番美しい。常用はこのモードになるだろう。
※パネル画素に一対一に対応した表示……◎、正常表示……○、表示はされるが一部に違和感あり……△、表示不可能……×
*1 1,920×1,080のインタレースモードと誤認されちらつく●ゲーム(プレイステーション 2/コンポーネントビデオ接続) PJ-TX100Jではコーミングが出ていたプレイステーション2の映像も、PJ-TX200Jではちゃんとプログレッシブ化されるようになった。 動きが激しい3Dゲームやスクロールゲームでも残像もなく違和感なくプレイできる。
■ まとめ
基本性能が高く、それだけに息の長かったPJ-TX100Jも、満を持してのモデルチェンジとなった。PJ-TX100Jで好評を博した迷光低減用のレンズアイリスを強化しつつ、さらに競合達が先行して実装していた動的制御型のアイリス機構までも実装。この「デュアルアイリス機構」によって、「カタログスペック」であるコントラスト比7,000:1を実現したわけだが、これを達成するアクティブアイリス「オート2」設定は実際の映像投射ではあまり使えないモードであった。
前回のTH-AE900の時にも触れたことだが、コントラスト性能においては、ダイナミック制御を行わない1フレーム内で表現されるネイティヴ・コントラスト性能の方を知りたいと思っている。コントラスト数値競争をメーカー間で争うことは確かに面白いのだが、ユーザーにわかりやすい製品選びが行なえるように、今後、各メーカーは、スペック表記にネイティヴ・コントラスト値の方も同時記載する必要があると思う。
実際には、PJ-TX200Jのデュアルアイリス機構はかなり使える機能であり、黒浮きは透過型液晶の原理上、避けられない問題だが、レンズアイリスによりかなり低減できる。さらに同時にアクティブアイリスを「オート1」設定とすれば、明色対黒の比率をほぼ一定に保ちながら見られるので、意識しない限りは黒浮きが気にならない。
このアイリス機構を2つ搭載するアイディアは、LP-Z4も「ツインアイリス機構」として採用しており、透過型液晶プロジェクタの投射系のトレンドとなってきそうな予感がある。
 |
 |
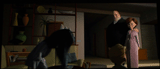 |
| 画調モード=シネマファンタジー。レンズアイリス=10(絞り開放)、アクティブアイリス=オフ/黒浮きが激しい | 画調モード=シネマファンタジー。レンズアイリス=5(デフォルト)、アクティブアイリス=オフ/黒浮きが減る。透過型液晶プロジェクタならばこれで実用レベル | 画調モード=シネマファンタジー。レンズアイリス=5(デフォルト)、アクティブアイリス=1/黒浮きはかなり低減される。暗部階調との整合性も良好 |
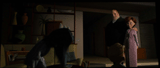 |
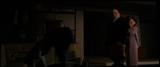 |
|
| 画調モード=シネマファンタジー。レンズアイリス=5(デフォルト)、アクティブアイリス=2/黒浮きはさらに低減されるが陰影が甘くなる | 画調モード=シネマファンタジー。レンズアイリス=0(最小絞り)、アクティブアイリス=2/これがコントラスト7,000:1を実現するための黒。黒は真っ黒だが暗部階調も死ぬ | |
| DVDビデオ「Mr.インクレディブル(国内盤) (C)2005Disney/Pixar |
||
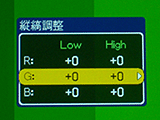 |
| 透過型液晶パネルを使用した液晶プロジェクタで問題となる縦縞ノイズ問題。PJ-TX200Jでは、この縦縞ノイズを低減する調整機能が搭載された |
上下シフト量±75%という、クラス最大級のレンズシフト機能。100インチ(16:9)の投射距離2.8mもクラス最短。この価格帯の720p透過型液晶プロジェクタ製品は多数あるが「とにかく、できる限りの大画面が欲しい」というユーザーにはPJ-TX200Jが候補の筆頭となるだろう。
□日立のホームページ
http://av.hitachi.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2005/09/0914.html
□製品情報
http://av.hitachi.co.jp/homeproj/lineup/tx200j/index.html
□関連記事
【9月14日】日立、720p/デュアルアイリス採用液晶プロジェクタ
-HDMI搭載、D5パネル採用。コントラスト比は7,000:1に
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050914/hitachi.htm
【2004年6月10日】【大マ】大口径レンズ搭載の720p対応モデル
~画質と設置性を両立した 日立「PJ-TX100J」~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040610/dg35.htm
【2004年5月12日】日立、720pパネル/レンズシフト機能搭載の液晶プロジェクタ
-F1.7/1.6倍ズームの「Woooハイビジョンレンズ」を搭載
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040512/hitachi.htm
(2005年10月20日)
[Reported by トライゼット西川善司]
| = 西川善司 = | 遊びに行った先の友人宅のテレビですら調整し始めるほどの真性の大画面マニア。映画DVDのタイトル所持数は500を超えるほどの映画マニアでもある。 本誌ではInternational CES 2005をレポート。渡米のたびに米国盤DVDを大量に買い込むことが習慣化している。僚誌「GAME Watch」でもPCゲーム、3Dグラフィックス、海外イベントを中心にレポートしている。 |
 |
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部
Copyright (c)2005 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.




