 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
|
西田宗千佳の ― RandomTracking ― 開発陣が語る「新DIGA」の能力
|
10月末以降、ビデオレコーダの市場が大きく動いている。10月末から11月初旬にかけて、各社が新製品を投入した結果だ。
10月29日の週のGfK Japanの集計結果では、BD搭載モデルの台数シェアが、DVDレコーダ全体に対して15%近くを占めるに至った。市場の移行がこのままの勢いを持続するとすれば、今冬は、各社が狙った通り、「国内BD市場離陸」が実現されることになりそうだ。
松下電器の新「ブルーレイDIGA」では、今年のハイビジョンレコーダのトレンドともいえる、MPEG-4 AVC/H.264エンコーダを搭載し、BD、DVD、HDDへのハイビジョン長時間録画を実現。さらに、DIGAシリーズでは、BD非搭載のハイビジョンDIGAでもAVC録画と、DVDへのAVCREC機能を搭載。特にハイビジョンDIGA「DMR-XW100」は、価格設定の安さもあり、人気を集めているようだ。
今回、「新DIGA」について、技術開発の責任者に話を聞いた。話題は、DVDへのハイビジョン記録から、PHL(パナソニックハリウッド研究所)譲りのチューニングにまで及んだ。
 |
 |
| ブルーレイDIGA「DMR-BW900」 | ハイビジョンDIGA「DMR-XW100」 |
■ ハイビジョン感にこだわってAVCで残す
AVCエンコードは新オリジナルチップで
DIGAの技術開発の責任者である、AVCネットワークス社・ビデオビジネスユニット・商品技術グループの楠見雄規グループマネージャーは、「今回の製品は、特に時間とリソースをかけた自信作」と語る。
 |
| 左からビデオビジネスユニット 商品技術グループの山崎雅弘主幹技師、楠見雄規グループマネージャー、甲野和彦主幹技師 |
ビデオレコーダで大切なのは、画質・音質・使い勝手の3点。デジタル放送の時代となり、画質・音質の2点は大きく進歩したが、最後の「使い勝手」については、退化した部分も多い。
「アナログの時間は“100時間、200時間録画!”と謳っていたのに、デジタルでは短くなってしまった。それでは、お客様になかなか納得していただけない」(楠見氏)。
そこで導入したのが、AVCによる長時間録画であることは言うまでもない。当然、長時間記録のメリットを生かして、ブルーレイ1枚に「ドラマ1クールまる録り」も可能となった。だが、松下が考えていたのは、「長時間」だけではなかった。
「いかにハイビジョン感を残したまま残せるか、できる限り最高の画質を維持できるか、バランスのとれたところで実現する、というところがポイントです」と楠見氏は話す。
今回のDIGAに採用されたエンコーダは、「パイレーツ・オブ・カリビアン」などのBDタイトルのオーサリングを担当した、PHLのMPEG-4 AVC High Profile対応エンコード技術を元にしている。リアルタイムという特質から、ハイビジョン対応カムコーダで培われたノウハウも生かされてはいるが、「出発点はあくまでPHLエンコーダ」(楠見氏)。
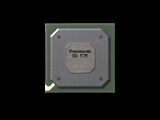 |
| 新UniPhier |
使われているのは、45nm世代プロセスで作られた、松下の家電向け統合プロセッサ「Uniphier(ユニフィエ)」。このプロセッサは、メインCPUにマルチメディア演算用の高性能演算器を組み込んだもので、AVCエンコードの他、DIGA向けのグラフィック処理、BD-Java、通信など、DIGAに必要とされる処理のほとんどを1つでこなす。テレビやビデオレコーダなど、様々な機器のために開発されたLSIだが、搭載例はこの新DIGAがはじめてとなる。すなわち、新DIGAのAVCエンコーダは、この製品ではじめて使われた「オリジナルチップ」である。
機能の多くが1つのチップに集約されているため、新DIGAのメイン基板はおそろしく小さい。昨年のDMR-BR100/BW200に比べ、大幅に薄型化されているが、その秘密の一つが、このUniPhierにある。中を見ると、これだけ薄型化されていても、まだかなり空洞があるくらいなのだから驚かされる。
DIGAの画質面に関する技術開発を担当する、ビデオビジネスユニット・商品企画グループ の甲野和彦主幹技師は、新DIGAのAVCエンコードの「勘所」を次のように説明する。
「AVCのエンコーダは、普通に使うと“画像がぼやける”と言われます。いかにハイビジョン感を残してやるかが重要です。“ボケやすさ”に対して、一つ壁を破ったのがPHLの技術提案を主体に作られたHigh Profileという技術なんですが、High Profileはあくまで規格なので、使いようによってどうにでもなります。うまく使いこなせれば良いのですが、下手をするとボケボケになる。我々がやってきたのは、PHLの生み出したノウハウを生かし、ハイビジョンの良さを残すことなんです」。
とはいえ、PHLのパラメータをそのまま設定しても「ビデオレコーダではうまくいかない」と甲野氏は話す。「PHLのエンコードは、非常にハイレートで、しかも24pという、映画に特化したものです。それに対しビデオレコーダは、インターレースの60フレームを扱う必要がありますし、長時間録画を考えるとレートも非常に低いところで勝負しないといけない。そこには新たな技術開発が必要でした。これまでやってきたムービーやDIGAのノウハウも加えて作り上げたんです」。
High ProfileはMain Profileに比べ、映像を作り上げるために必要なチューニングの幅が広い。それだけ画質向上の余地がある、ということだが、逆にいえば、ノウハウの差が出やすいものでもある。「何を使って何を捨てるか、リアルタイムエンコーダで実現するための“すりあわせ”が、非常に大切。きわめてアナログ的な要素ですね」と楠見氏は説明する。
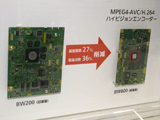 |
 |
| 新Uniphierの導入で部品点数や基板面積を大幅に削減 | 上が「DMR-BW900」。下のDMR-BW200に比べると大幅に薄型化されている |
■ 「BD一枚にハイビジョンドラマ1クール」
できるかぎり「精細感」を残したい
| 【新DIGAのAVC録画モード】 | |||
|---|---|---|---|
| 録画モード | 解像度 | コーデック | ビットレート |
| HG | 1,920×1,080ドット (1,440×1,080ドット 放送は1,440で記録) | AVC | 12.9Mbps |
| HX | 8.6Mbps | ||
| HE | 5.7Mbps | ||
今回の製品では、AVCによる長時間記録とDVD記録が、製品のウリとなっている。それはすなわち、「低ビットレートでのエンコード」を、いかにアピールするか、ということにつながっている。
「そこで大切にしたのは精細感。ハイビジョンらしさ、といってもいいでしょう」と楠見氏は話す。
「DVDのアップコンバード画質もあがってきています。そこで、(ハイビジョンとはいえ)あんまり精細感のない絵を出してしまっては、“SDでもHDでも変わらないんじゃないの”と言われてしまいます。誰がみてもハイビジョンである、ということがわかる絵で、しかも破綻がない、というレベルを目指しました。エンコーダの性能によっては、横1,920ドットだとぼけてしまい、むしろ1,440にした方がいい、という話になるんですが、幸い我々にはHigh Profileのノウハウがありますので、BSデジタルなどの1,920の映像は1,920のままにしています。今回だと、5.7Mbpsくらい(HE設定)ならば、かなりハイビジョン感の残った映像をお楽しみいただけるのではないでしょうか」。
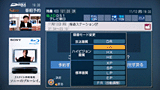 |
| HG、HX、HEの3つのAVC録画モードを用意する |
甲野氏も次のように補足する。「とにかくボケないエンコーダを作ろう、というコンセプトを持っていましたので、フルハイビジョンの精細感やディテールをできる限り忠実に再現する事にこだわって開発しました。厳密には、ビットレートが低くなるにつれて、ジワジワと精細感が失われるのはある意味やむをえない部分はあります。しかし、あるところから、いきなり精細感が失われるようなことになるのは避けたかった。記録時間だけ長くなっても、“絵はSDのアップコンみたいや”と言われては、本末転倒ですから」。
とはいえ、松下も魔法を持っているわけではないから、同じビットレート、それも5Mbps前後という低レートで圧縮した場合、横1,920ドットと横1,440ドットでは、前者の方がより厳しい事実に違いはない。
このあたりのさじ加減を、甲野氏は次のように説明する。「ビットレートに余裕があるHGモードやHXモードは迷わず横解像度1,920ドットを選びましたが、(AVC記録の)最低ビットレートであるHEモードで、1,920にするか、1,440にするかは、慎重に検討しました。一般に、ビットレートが低くなると符号化ノイズが増えるため、解像度を落とした方がトータルの画質が良くなるケースがあるからです。ただし、やみくもに解像度を落とせば画質が上がるというわけではありません。解像度を下げれば、その分、本来の映像が持つ大切な高域信号が確実に失われるわけですから。大切なのは、高域の映像信号と符号化ノイズのバランスです。ビットレートを下げた時に、高域の映像信号を残す効果より、符号化ノイズの増加が支配的になった場合は、解像度を下げた方が良いという判断になります。どのくらいのビットレートまで1,920でいけるかは、エンコーダが発生する符号化ノイズ量によりますので、つまりエンコーダの実力次第という事になります。我々のエンコーダでは、HEのビットレート(5.7Mbps)でもトータルの画質は1,920の方が良いと判断しました」。
この辺りのノウハウは、アナログ放送向けレコーダ時代の経験が生かされているという。アナログ放送用のレコーダでは、MPEG-2で圧縮する際、ある程度のビットレートを下回ると、映像の水平解像度をD1(約500本)から、ハーフD1(約250本)へと引き下げる手法が使われていた。当時、松下を含めた多くのレコーダは、設定が切り替わる「境目」が「LPモード(約2Mbps)」の時だった。
「お客様から、“LPモードになると画質が極端に悪くなる”という声が多かったんです。我々は、新しいアルゴリズムを開発する事により、他社に先駆けてLPモードでフルD1化を実現しました。その頃から、解像度とビットレートの関係は常に気を使って設計しています」。
楠見氏は、また別の視点を指摘する。「(1,920で収録された)BDの映画タイトルを見慣れると、地デジとの解像度の差がわかってきます。ならば、元々解像度を持っているものは残してあげた方が、“目が慣れてきたあと”の満足感は高いんじゃないだろうか、ということです」。
HEモードでも1,920ドットを選んだ理由には、「長時間記録が望まれる番組は、ドラマが多い」という分析もあるようだ。「ドラマはさほど激しい動きは多くありませんから符号化ノイズもほどんど気になりません。ハイビジョンドラマの1クールを“HEモードでBD1枚に”という使い方をしていただくなら全く問題ありませんね」と楠見氏も説明する。
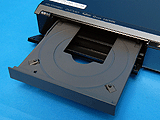 |
| BDドライブはカートリッジ式DVD-RAMも使用可能 |
現在のエンコーダ技術では、5~6Mbps程度でフルHDの映像を残すのは、かなり難しいことだ。それだけに、録画設定の調整は困難を極めた。今回のDIGAの場合、ビットレートを含めた録画設定の調整が完了したのは、9月に入ってからのこと。10月初めのCEATECで発表、11月には売り出す、というスケジュールを考えると、「まさにギリギリ」(楠見氏)というタイミングだったという。
また、BD-Rメディアへの4倍速記録に対応。AVC録画した番組であれば、さらに高速なダビングが可能となったことも、ユーザーにとっては大きな機能向上といえる。なお、今年末より登場予定のLtH(有機系色素ディスク)タイプのBD-Rメディアについては、「搭載しているドライブはLtH規格に準拠して設計しているが、現在では各社のメディア試作品で検証中。間もなくお知らせできると思うので期待していてください」(楠見氏)と前向きな対応を伺わせた。
■ 「なぜ記録できないの?」の声に応える「AVCREC」
AVCという点で気になるのは、やはりDVDへのハイビジョン記録規格「AVCREC」。DMR-XW100が売れているのは、新製品の中で手頃である、ということに加え、ようやく「ハイビジョン放送をハイビジョンのままディスクに残す」ということが、手に入る価格で実現できたから、ということになるだろう。
ソニーがすべてのラインナップをBDでそろえてきたのに対し、松下がDVDを残した理由は、「ハイビジョンをより身近に楽しんでいただく為に、ハイビジョンコンテンツをディスクに保存する際の、選択肢を増やしたい、という判断」(楠見氏)だ。
| ||||||||||
| ※太字が新DIGAで対応 |
そこで、DVDへの記録にAVCRECを採用した理由は、「HD記録=Blu-rayという基本路線の中で、如何にDVDメディアへのHD録画を実現するかで検討したのが、今回BDAで新規に策定したAVCREC規格。従ってAVCRECのストリーム構成が、BDと同じだから」(楠見氏)だという。松下のレコーダは、元々BDへの記録を前提に開発されている。そのため、内部でのデータ保存形式はBDに準拠した形である。そこで高速ダビングを実現するなら、BDの枠の中にある規格でやりたい、ということのようである。
「そもそも、話はもう少し単純なんです。我々の元には、お客様から、“DVDにはなぜハイビジョンで記録できないの?”という疑問が多数寄せられています。じゃあ、それをなんとかしましょう、というのが基本。フォーマット戦争が云々、という話ではないんです。もちろん、新フォーマットですから過去の機器で再生できるわけではありませんが、私どもから今後出させていただくハイビジョンレコーダでは対応をしていきます。ただし、AVCRECはBDAの規格ですが、新規格のため、昨年のBR100/BW200では再生できないことは申し訳ないのですが……」。
なお、前々回の東芝のインタビュー記事で、AVCRECにはMPEG-2 TSのストリーム映像が記録できないと書いたが、これは正確ではない。AVCRECの規格上は、AVCでの記録の他、MPEG-2 TSでの記録にも対応している。また、その範囲はHD映像だけではなく、MPEG-2 TSのSD映像、AVCで圧縮されたSD映像も扱える。また、AACやドルビーデジタルでのマルチチャンネル音声、リニアPCM音声なども使えるという。
ただし、新DIGAに実装されたAVCRECでは、AVCの録画のみに対応。わかりやすさを重視してSD映像記録を採用せず、音声についても、ドルビーデジタルに変換して記録しているという。SD映像のDVD記録は「従来のVR規格の方が互換性がとれるためユーザーにとっては混乱が少ない」と考え、こうした実装になっているという。
■ PHL柏木氏の認めたチューニング
ヴェールを剥いだような「瑞々しさ」が魅力
次に気になるのが「アウトプットクオリティ」だ。前モデルである「DMR-BW200」も、BDの再生品質では評価が高かった。私自身も、数種のプレーヤーでBDを観ているが、こと色合いではBW200が一番好みに近かった。
だが、このBW200の画質に、「クレームをつけた人物」がいた、という。その人物とは、PHLの副所長を務める柏木吉一郎氏。AVCのHigh Profileの開発を手がけ、「パイレーツ・オブ・カリビアン」のAVCエンコーディングを担当した、松下屈指の「画質の専門家」である。
DIGA開発メンバーが、完成したBW200をもってPHLを訪れた時、柏木氏は一言つぶやいたという。「良いことは良いんだけど、ちょっと違う」と。
PHLでは、映画BDタイトルをエンコードする場合に、業務用プロジェクタと380インチ巨大スクリーンを用いて、エンコードしたBDビデオの画像を、エンコード前の原画と1画素単位で比較しながら画質チューニングを行なっている。その時にPHLの標準再生機で見るBDビデオの画質と、BW200で見るBDビデオの画質が違うというのだ。
「柏木に指摘されたのは、映画フィルムが持つグレインノイズの再現性の違いです。本来のフィルムが持っているグレインノイズとは、例えて言うなら乾いた砂がさらさらと流れるような自然なものであり、これをきちんと再現する事によって、フィルムの持つ質感や豊かな階調を正しく再現できるのですが、BW200ではこの表現が不充分だというのです。この指摘を受けて、我々も検討を始めたのですが、このような画質の違いが出る原因はなかなかわからず、突き止めるのにはかなり苦労しました」と甲野氏は言う。
原因は「クロマ(色)処理」だった。PHLでは、色情報を各画素ごとに予測補完するクロマアップサンプリングの処理に、独自の高精度な演算を行なっており、これが画質の違いの原因であった。この解析結果に基づき、今回、45nmプロセスを用いた新世代Uniphierを用いて、このアルゴリズムをBDレコーダに導入している。
「実際に商品に搭載してみると、我々の想像以上の効果でした」と甲野氏は笑う。「今年の夏には、DIGAの映像担当者が試作機をPHLに持込み、柏木氏と一緒に何日も徹夜をしながら最終的な画質を仕上げました」
画質の仕上がりには柏木氏も納得しているという。その差は、おそらくみなさんが思うより大きい。今回、取材時に使ったのは、松下の65型VIERA「TH-65PZ750SK」。サイズこそ大きいが、一般的な「高画質テレビ」である。先ほど、「BW200は他のプレーヤーより色味が好みだった」と書いたが、それは、一般的な液晶テレビなどではわかりづらい小さな差だった。
だが、今回の新DIGA(テストに使ったのはBW900)の画質は、「ハイエンド環境」でなくても体感できる。色合いがすっきりし、一枚ヴェールを剥いだような精細感、瑞々しさがある。
□関連記事
【11月6日】映像の質を“元から”改善するPHLのクロマ処理技術
-新DIGAでBDビデオ高画質化。レコーダ世界展開も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071106/bd3.htm
■ 「リ.マスター」でBDも高音質化
HDMI音質改善は「オリジナルLSI」で実現
改良点は音質にもある。元々、昨年の上位機種であるBW200は、アナログでのアウトプット品質にこだわった機種。ノイズ除去のためにオリジナルのコンデンサーを開発するなど、さまざまな音質強化への取り組みが行なわれていた。
音質関連の技術開発を担当した山崎雅弘主幹技師は、「アナログでのアウトプットのブラッシュアップも丹念に行なって、より締まった音になっているのですが、他にも追加した機能があります」と語る。
その一つ目は、信号補間処理の「マルチチャンネルデジタル リ.マスター」だ。 主にデジタル放送のAAC音声のクオリティアップや、AAC/リニアPCMによるCDリッピング機能でHDDに蓄積した楽曲再生時の高音質化を図るために用意したものだ。機能的には、圧縮時に切り捨てられた高音域を補間し、より自然な音として再生するものである。
「BW200の時も採用していたのですが、残念ながら、BDビデオでは働かなかったんです。今回は、音楽・映像、すべてのアウトプットで有効になりました」(山崎氏)
大容量のBDではあるが、現在は音声がロスレスコーデックでないソフトもある。また、新DIGAで記録したAVCRECのディスクは、音声をドルビーデジタルに「圧縮」してしまう。これらのディスクでも音質補間が効くようになったため、トータルでの音質はあがった、といえるだろう。
 |
| DMR-BW900の背面 |
二つ目が、「HDMI音声出力」の強化だ。新ブルーレイDIGAでは、リニアPCMはもちろん、ドルビーTrue HDやDTS-HDなどのビットストリーム音声を出力可能となるなど、機能面での進歩を果たしている。
たが、HDMI音声出力については、昨年までは、ほとんどの次世代ディスクプレーヤーで、「HDMI接続は音が悪い」との評判があった。ロスレス・マルチチャンネル系コーデックへの対応が不十分であったこと、そして、HDMI出力時、音声出力に重なるジッタ信号が、AVアンプからの出力に悪影響を与えていたこと、などが原因という。
「以前のHDMI出力は、“低音が軽い”、“押し出しが弱い”と言われました。そこで、アナログと同軸での出力にこだわったところはあったのですが……」と、山崎氏は当時の状況を語る。
今回の新機種では、最上位機のDMR-BW900からも、アナログでのマルチチャンネル出力が廃止されることが決まっていた。「ならば、HDMIでいい音を出さねばいけない」、そう考え、山崎氏たち音響関連開発メンバーは、1年から1年半かけて、HDMIのトランスミッター側での音質改善検討を開始したという。ちょうど、松下の半導体部門でLSI開発の動きがあり、そのチームと共同で、「なにが原因で音が悪くなるのか」を突き止めるところから始めた。
「HDMIは、映像クロックしか送らないんです。そこから音声クロックを合成するんですが、ここで発生するジッターがAVアンプに影響を与え、音質を悪くしていました。そこで、本質的な課題であるジッターの発生について、解決策を用意することで音質劣化を防ぐことに成功しました」。
山崎氏が採ったのは、ジッター発生を抑え、相手がどんなアンプであっても、ノイズの影響が極力でないようにする仕組みだった。結果、HDMI出力の音質は大きく改善されることとなった。「各社のアンプを買ってチェックしましたが、音の押し出しはかなり良くなったと思います」と、改善結果に自信を見せる。
さらにDMR-BW900だけの強化ポイントとして、ピュアオーディオ用コンデンサの搭載や銅フレームオペアンプの採用、超低インピーダンス電解コンデンサの搭載なども行なわれている。
■ 半導体の力で実現した「全機種高音質・高画質化」
今秋のビデオレコーダは、各社非常に気合いが入っており、製品性がきわめて高く、お買い得感がある。BDレコーダのシェアが上がり始めているのは、その証明といえそうだ。
今回のDIGAは、BDの再生品質でいえば、他社を凌駕する存在となった。各社の最上位機では、様々な味付けの違いはあるが、大切なのは、「下位機種でも、普通のテレビでも差がわかりやすい改善が多い」というところではないだろうか。
BDビデオの再生品質向上も、音質に関する向上も、新機種すべてで楽しめる。以前は「クオリティを採るなら最上位機種の一択」であったが、今回は、「録画時間よりコストを重視したい」という方にとっては、BW900ではなくBW800を選ぶ、という選択もあり、ということになるだろうか。その背景になっているのが、松下の自社LSIである、ということを思うと、今後のソフトウエア開発の可能性が、また楽しみになってくる。
□松下電器産業のホームページ
http://panasonic.co.jp/index3.html
□ニュースリリース
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn071002-2/jn071002-2.html
□DIGAのホームページ
http://diga.jp/
□製品情報
http://panasonic.jp/blu-ray/index.html
□関連記事
【10月19日】【RT】松下の“ミスターBD”小塚氏が語る「Blu-rayの現状」
-AVCRECなど新採用も「映画のため」は揺るがず
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071019/rt043.htm
【10月2日】松下、フルHD/AVC圧縮録画対応の「ブルーレイDIGA」
-DVDへのハイビジョン記録対応。1TB HDDモデルも
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071002/pana1.htm
【9月12日】ソニー、MPEG-4 AVC録画対応の新BDレコーダ4モデル
-320GBに800GB分録画可能。レコーダは全てBDへ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070912/sony1.htm
【11月2日】【RT】東芝・片岡氏が語る「HD Rec」の真意
- 分裂した「ハイビジョンDVD」の行方
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071102/rt045.htm
(2007年11月16日)
| = 西田宗千佳 = | 1971年福井県生まれ。フリージャーナリスト。得意ジャンルは、パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」。主に、取材記事と個人向け解説記事を担当。朝日新聞、読売新聞、月刊宝島、週刊朝日、週刊東洋経済、PCfan(毎日コミュニケーションズ)、家電情報サイト「教えて!家電」(ALBELT社)などに寄稿する他、テレビ番組・雑誌などの監修も手がける。 |
[Reported by 西田宗千佳]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp
Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.