 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第374回:究極のおっさんホイホイ「KORG DS-10」
|
■ 楽器業界に訪れた第2のデジタル革命
最近、楽器メーカーの新しいトライアルが注目を集めている。KORGの「KAOSS PAD」や「KAOSSILATOR」、YAMAHAの「TENORI-ON」など、ギターや鍵盤ではない、新しい演奏の形が生まれてきている。
まず弾き方を練習しないと曲にもならないという従来の楽器のあり方から、デジタル技術を使って誰でもとりあえず曲になる、というところまできた。ギターヒーローには憧れるが、格好だけならエアギターで充分。そうなればあとは、楽器が弾けなくても音楽的素養があれば実際に音楽が作り出せるようにならなければ、この業界に発展はない。
しかしそれらの動きと、近年始まったアナログシンセ的なものの復刻とは、まったく別物だと思っている。アナログシンセが素晴らしいのは、その音質だけでなく、発想や操作性が人間にとってわかりやすいからである。ちゃんと弾ける人にとって使いやすい、ということなのだ。
 |
| ニンテンドーDSソフト 「KORG DS-10」 |
ニンテンドーDSをシンセサイザーに変えるソフト、「KORG DS-10」(以下DS-10)は、初心者でも簡単に、などと紹介するつもりはない。これはもうガッツリ、アナログシンセの基本を理解した人間じゃないと、その楽しさは10%程度も理解できないだろう。
ここで注目したいのは、シンセサイザーをマスターすることと、ピアノやオルガンが弾けることとはまったく別物であるということである。もちろん両方できた方がいいに決まっているが、演奏が上手くなくても、理解していればいいものが作れる、そこがDS-10のポイントである。
今回はそんなDS-10の魅力について語ってみたい。
■ モデルとなったKORG MS-10の立ち位置
DS-10のモデルとなったシンセサイザーは、KORGの「MS-10」というモノフォニック・シンセサイザーだ。まずはそのあたりから話していこう。
そもそもシンセサイザーとは、音を合成によって作り出す機械である。原理的になどんな音でも作り出せるはずだが、まだ本物の音を拝借するデジタルサンプリング技術が登場していないアナログ時代では、発振器の音だけを元に生楽器そっくりの音を作るのは困難であった。
もちろん大掛かりなシステムモジュールを使って多面的に合成していけば、不可能ではない。かつてはウォルター・カルロスの「スウィッチト・オン・バッハ」、富田勳の一連の作品群では、その可能性が示唆されている。また「メロトロン」という楽器は、鍵盤一つ一つに磁気テープが割り付けられており、本物の音を録音するという力業でシミュレーションが行なわれた。
しかしそれと平行して、これまでの楽器にはない「シンセサイザー」としか言いようのない音もまた、シンセサイザー自身の発展を促した。「MiniMoog」や「Prophet 5」、「Overheim 4Voice」が未だに名器として語り継がれているのは、他のシンセサイザーでそれらの音を真似しようにも、同じ音にならなかったからである。これはシンセサイザーというものの意味を考えると大変におかしなことなのだが、それだけ個性が強烈であり、この個性がのちの電子楽器の発展につながっていった。
日本のシンセサイザーは、YAMAHA、Roland、KORGの三大メーカーが牽引した。各社ともプロ用のハイエンドモデルは早くから開発してきたが、YMOの登場とほぼ時を同じくして、10万円以下で買える入門機をリリースして以降、日本でも急速にシンセサイザーブームが訪れた。
YAMAHA CS-10、Roland SH-09、KORG MS-10が、当時の入門機である。筆者はどれも使ったことがあるが、中でもMS-10はハイエンドのモジュラーシンセでしか実装していなかったパッチモジュレーションを備えており、一番マニアックだった。
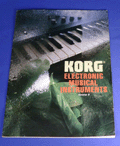 |
 |
| 筆者所有のMS-10現行モデル時のカタログ | MS-10の扱いはやや小さめ |
いやマニアックと言うより、扱いが難しかったマシンだ。全部パッチを抜いた状態で音が出るような設計にはなっていたが、変な風にパッチしてしまうと全然音が出なかったし、何よりもジャックがいっぱいある分だけ、接点不良も起きやすかった。
いくら楽器とはいえ、よくこんな面倒くさいものをコンシューマ機として出したものである。おそらく入門三強の中では一番売れなかったと思うが、値段は一番安かった。当時のカタログには、53,500円とある。しかしギターやマイクを突っ込んで変調させたりといった変なことができるのは、入門機ではこれだけであり、それだけに大変なインパクトを残した。
MS-10を名器と呼ぶ意見も散見されるが、リアルタイムでこの時代を経験したものの視点で言わせてもらえば、当時の入門機を名器と呼ぶのは、いささか買いかぶりすぎだ。KORGであればもう一つ上のMS-20やボコーダVC-10あたりは準名器と呼んでもいいだろうが、本当に名器として過去現在に名を残すのは、のちに発売されるMONO/POLYとPOLYSIXである。
■ 豊富な音源と使えるシーケンス機能
MS-10などのモノシンセが悲しいのは、和音が出ないことである。したがってなんらかの曲を演奏するには、バンドをやるか、自分で多重録音するしかない。つまり、本当にMS-10をそのままエミュレーションしたら、鍵盤がない分さらに悲しさがますばかりであったろう。
DS-10は、MS-10的なメソッドを取り入れつつ、普通に音楽が制作できるよう、シーケンス機能も装備している。シーケンス構成としては、MS-10型シンセサイザー2系統+ドラムモジュールということになる。しかしドラムモジュールが4音で、音の作り方はMS-10と同じなので、実質モノシンセ×6あると言っていい。これだけで十分なアンサンブルが可能だ。
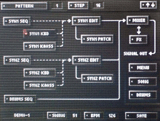 |
| DS-10のメインパネル |
DS-10のメインパネルが、その構成を示している。 DS-10の基本的な操作は、この画面から各設定画面をタッチパネル側に呼び出し、操作が終わればまたこの画面に戻るという作業の繰り返しだ。もっともこのメインパネルから機能を選ぶという操作自体もタッチパネル側で行なわなければならないので、頻繁に上下の画面をスワップする必要がある。画面スワップは右上隅のボタンか、Rボタンで行なう。
まずメイン画面でSYN1のほうを追ってみる。SYN2はこれと全く同じで、DRUMSはもっと単純なので、まずはSYN1から理解するのが近道だ。
最初に音を鳴らす方法として、ステップ入力によるシーケンス、ソフトウェアキーボードを使う方法、タッチパッドを利用したKAOSS方式で入力する方法の3つがある。キーボードとKAOSS方式はシーケンスに対してレコーディングすることも可能だ。
シーケンスでの入力は、縦方向に配置された鍵盤を見ながら、横方向16ステップで音を置いていくスタイルだ。長音を使いたい場合は、連続で音を置いていく。
注目はKAOSS方式で、単にでたらめな音階を入力するのではなく、スケールが指定できる。BluesペンタトニックやDiminish、俗に四七抜きと言われる日本音階、琉球音階など数多くのスケールから選択することができる。
これにより、でたらめにタッチペンをうごかしても、それなりに聞けるメロディを奏でることができる。これで荒削りに音階を入力したあと、シーケンスに戻って修正、という使い方ができるため、アイデアを練るのに便利だ。
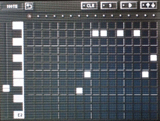
|
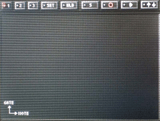
|
| シーケンス画面。16ステップで音を置いていく | DS画面上で操作するKAOSS PAD |
| 【シーケンスで入力したフレーズの例】 syn1.mp3 (248KB) |
【日本音階でKAOSS PADを操作】 scale.mp3 (223KB) |
■ MS-10を現代風にアレンジ
 |
| DS-10の音色エディット画面 |
DS-10のメインともいえる部分が、音色作りである。煩雑になるので、ここでは音作りの仕組みの細かい部分は解説しない。本を読めば、中学生ぐらいでも十分理解できる程度である。実際に筆者もシンセサイザーの音作りを独学したのは、中学生の頃だった。
SYN1 EDITをタッチすると、かつてのMS-10似の画面が出てくる。MS-10似というのは、厳密にはMS-10と構成が同じではないからだ。
実際のMS-10はシングルオシレータしかないため、もっと音が細かった。しかしDS-10のシンセモジュールは、2オシレータ仕様になっており、2つをデチューンしたりモジュレートすることで、太い音にできる。2オシレータという意味では上位モデルだったMS-20に近いが、以下のような違いがある。
- リングモジュレータがない代わりにVCO SYNCがある
- パルスワイズが変えられない
- VCO2でノイズが選べる
- ローパスとハイパスのフィルタが分離しておらず、セレクト式になっている
- エンベローブジェネレータ(EG)が1系統しかない
- VCAにDRIVE(Over Drive)が追加されている
 |
| MS-20はVCOなどがデュアル仕様だった |
元々MSシリーズにはVCA操作部がなく、エンベロープが直接突っ込まれる格好になっていた。それ以上のモジュレーションは、パッチでアサインするという構造である。だからでたらめにパッチすると、すぐ音が出なくなるのであった。そういう意味ではDS-10のシンセ部は、MS-10とMS-20の間ぐらいの機能で、しかも後年スタンダードになった構成を取り入れた、改良型になっている。
操作はまさにつまみを回すという操作をタッチペンで実現しており、シーケンスを走らせておいて音作りを行なう。アナログシンセの音作りは、オシレータに含まれる倍音の豊富さと、CUTOFFフィルタの切れの良さ、そしてカットオフ周波数付近を持ち上げるPEAK(レゾナンス)の特性で決まる。フィルタに関しては、もうオリジナルの切れがどんな感じだったか忘れてしまったが、今改めて触るとなかなかいい感じだ。
もう一つ、タッチパネルを生かしたインターフェースが、パッチパネル部である。下一列にあるLFO出力を、その上の列にあるモジュレーション入力に繋いでいく。間が黄色いケーブルでうにょーんと繋がる姿は、まさにパッチそのものである。
 |
| DS-10のパッチパネル。ペンでドラッグして結線する |
このパッチパネルは、オリジナルよりもずいぶん整理されてわかりやすい。またモジュレーションの度合いもつまみで決められるようになっており、より柔軟性が高くなっている。もちろん、あり得ないパッチングはきちんとできないようになっており、無茶をして壊すこともない。
今となっては当たり前だが、作った音色はセーブすることができる。昔はパネルの配置そのものをメモして覚えるか、またいちいち考えて作るかしかなかったので、いろんな意味で現実的になっている。
■ まじめに曲が作れる

|
| DRUMSのシーケンス画面。発音タイミングを設定していく |
| 【パターン入力したドラムの例】 drums.mp3 (327KB) |
気に入った音色とフレーズができたら、それをパターンとして記憶できる。DRUMSを4音全部使うのではなく、2音を楽音にしてコード弾きさせるなど、いろいろな使い方が可能だ。
またパターン全体に対して、エフェクトをかけることができる。エフェクトはDELAY、FLANGER、CHORUSの3種類で、DRUMSだけ、SYNだけにかけることもできる。このエフェクトとMIXERの値はパターン単位では記憶されず、全パターン共通となる。
1ソング中にアクセスできるのは16パターンで、まめにフィルインを入れていると数が足りなくなってしまう。そのあたりはミニマル的なアプローチを取りつつ、ランダムな発音のモジュレーションを掛けることでバリエーションを出していくといった工夫が必要になる。
 |
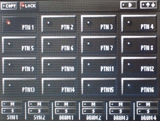 |
| エフェクトセッティング画面 | 1ソングにつき16パターンが作成可能 |
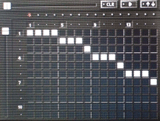
|
| ソング制作画面 |
| 【起承転結を持った曲の作成が可能】 song.mp3 (3.33MB) |
ソングの作成は、1小節づつ、どのパターンを鳴らすかといった方法で作成していく。任意のところから再生しながら組み立てていくことが可能なので、昔のステップ型シーケンサーとは違って使いやすい。ただし任意の範囲を選んでコピー、ペーストするといった編集機能はないので、曲の構成を変えたり、途中にパターンを追加したりという後作業が発生すると、結構大変だ。
しかし、きちんと計画を立てて入力していけば、ちゃんとした楽曲としての構成を作ることができる点で、成り行き任せのデジタル楽器モドキとは根本的に違っている。「ここまでやれればまあ遊びとしては十分でしょ」という限度を超えて、大まじめな勝負が可能なところに、DS-10の恐ろしさがある。
ソング、パターンをまとめたものが「セッション」で、このセッション単位でロード、セーブを行なう。セッションは最大18個保存することができる。すなわち18曲がDS-10内に仕込めるわけだ。
あいにくソングをプレイしながらマニュアルでの演奏はできないが、同時発音数や処理速度を考えれば、さすがに限界だろう。バッキングをこれで、生演奏はソフトシンセを仕込んだPCで、というのもおもしろそうだ。
■ 総論
DSの内蔵スピーカーで鳴らしている分にはそのすごさはわからないが、ヘッドホンやスピーカーに繋ぐとものすごい音がする。DSの内蔵音源ではなく、CPUで演算している結果なのだという。
PCでソフトシンセという世界は早くから存在したが、ポケットサイズで音楽が作れるマシンをゲーム機で実現したアイデアは、見事である。さらにタッチセンサーを使って古いシンセを操作する感覚までもシミュレートした。専用機を作ったら結構な値段になっただろうが、シーケンサまで付いてDSとソフトウェアだけで完結するのだから。
シンセサイザーの魅力は、ただプリセットから選んで弾くだけではわからない。じっくり音を練り込み、こつこつと打ち込みで作り上げる職人的要素があるからこそ、日本でTechno文化が生まれた。
「テクノは忍耐」とは、YMOのマニピュレータとして活躍した松武秀樹氏の名言である。ただ楽なだけではない、本物の楽器と音楽制作環境がDSの中に収まってしまうというのは、驚くべきことである。
□AQインタラクティブのホームページ
http://www.aqi.co.jp/
□ニュースリリース(PDF)
http://www.aqi.co.jp/company/info/ir_info080312.pdf
□製品情報
http://www.aqi.co.jp/product/ds10
□関連記事
【AV製品発売日一覧】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/hardship/
【3月12日】パッチシンセ「MS10」風ニンテンドーDS用音楽ソフト
-「KORG DS-10」でスタイラス・ミュージックを提唱
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080312/aqi.htm
【4月21日】【DAL】ニンテンドーDS用ソフトシンセ「KORG DS-10」開発者に聞く
~ パッチングなどに対応。オリジナルに匹敵するほどの出音を実現 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080421/dal323.htm
(2008年8月27日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.