 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第375回:すべてのテレビを綺麗にする、ソニー「BDZ-X100」
|
■ レコーダ飛躍の年?
レコーダにとって、今年は大きなターニングポイントを迎える年である。今年2月にはHD DVDの撤退、7月にはダビング10開始と、経済、技術両面で大きな環境の変化が起こった。いやまだ今年は残り4カ月あるので、これからまた何が起こるかわからないわけだが。
Blu-rayレコーダの製造各社には、この両方の事情は大きな追い風となるはずである。先日発表されたJEITAの国内出荷実績によれば、2008年7月の実績は前年比1,805.6%を記録するという、大きな伸びになっている。ただこれはオリンピック特需だろうから、全体の成長率はもう少し慎重に見ていく必要があるだろう。
レコーダ各メーカーの中でも、ソニーは早くからDVDモデルを終息させ、Blu-ray一本に絞ってきた。以前のソニーなら、何かブランド名を立てて訴求するところだが、今回は単に「ソニーのブルーレイ」と呼ぶだけという、これまでとはちょっと違った戦略を取っている。またモデルを価格の上中下で分けるのではなく、機能・用途別に4モデルに分けた点も新しい。
そしていよいよこの秋に向けての新製品だが、今年発売のAシリーズは継続、それ以外のX、L、Tに新モデルが登場する。今回は中でも1TBのHDDを搭載した「BDZ-X100」(以下X100)を取り上げる。シリーズ共通、またXシリーズ独自の高画質回路と、画質にこだわった新Xを、早速試してみよう。
■ 見えないところが贅沢
ではいつものようにデザインから見ていこう。ソニーのブルーレイは上中下で分けていないとは言いつつも、X100は一番値の張るモデルである。デザインも高級感を意識したものとなっている。 前面は電源とメディアのイジェクトボタンが左右にあるだけで、あとはパネル内に隠れたすっきりしたデザインになっている。天板は、肉厚のアルミをヘアラインで仕上げており、AVラックにしまうのが勿体ない感じだ。
 |
 |
| 外側からは機能を感じさせないデザイン | 肉厚のアルミ天板を使用 |
上部パネルを開けると、BDドライブと再生操作などのボタンがある。HDMI出力切り替え、録画停止など、すぐに動いて欲しい機能のボタンを装備しているのは好感が持てる。 下部パネルは二分割されており、左側はB-CASカードへのアクセス、右側は外部入力端子へのアクセスとなっている。端子側が小さく開くのは、テンポラリ的に機器を接続する際に、全体がガバッと開いて汚く見えないようにという配慮だろう。
 |
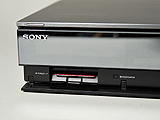 |
 |
| 上部パネルを開けるとドライブと操作ボタンが | 左側はB-CASスロット | 右側は外部入力端子 |
BDドライブはBD-R DLにも対応し、二層メディアを使えば最長のLRモードで約24時間の録画が可能になった。ドラマ2クールが1枚に、というのがウリだ。内蔵HDDは1TBと、他モデルの2倍となっているのも、X100のポイントである。
画質モードと記録時間は以下のようになっている。今回AVC録画はハイプロファイルに対応し、4MbpsのLRモードまでハイビジョン対応とした。また1,920画素での記録にも対応している。ただソースが1,440×1,080の場合は、そのままの解像度での記録となる。
| 録画形式 | 録画モード | 解像度 | ビットレート | HDD(1TB) | BD(2層50GB) | サンプル | ||
| DR | BS | 1,920×1,080 | - | 約88時間 | 約4時間20分 |
 |
 |
HDV 元データ dr.m2t (137MB) |
| 地デジ | 1,440×1,080 | 約125時間 | 約6時間 | |||||
| MPEG-4 AVC |
XR | 1,920×1,080 | 15Mbps | 約130時間 | 約6時間20分 |
 |
 |
xr.mpg (77.3MB) |
| XSR | 12Mbps | 約166時間 | 約8時間 |
 |
 |
xsr.mpg (60.6MB) |
||
| SR | 8Mbps | 約249時間 | 約12時間10分 |
 |
 |
sr.mpg (40.5MB) |
||
| LSR | 1440×1080 | 5Mbps | 約374時間 | 約18時間20分 |
 |
 |
lsr.mpg (26.8MB) |
|
| LR | 4Mbps | 約499時間 | 約24時間20分 |
 |
 |
lr.mpg (20.3MB) |
||
| ER | SD | 2Mbps | 約999時間 | 約48時間50分 |
 |
 |
er.mpg (10.1MB) |
|
| 編集部注:再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。なお、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい | ||||||||
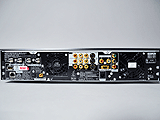 |
| HDMIが2系統あるのもポイント |
背面に回ってみよう。アンテナ入力は、地上波はデジ・アナ供用で、衛星放送はBSデジ、CS110度デジ供用となっている。アナログ外部入力は、前面に1、背面に2系統。アナログ出力は、コンポジット1、コンポーネント1、D端子1。本機で特徴的なのは、HDMI出力が2系統ある点だ。普段の番組はテレビで、映画はプロジェクタで、と使い分けたいユーザーにはいい機能だろう。
■ 新高画質回路の威力
次にハードウェア的な進化点を見ていこう。この秋モデル全機種に搭載されているのが、新高画質回路「CREAS(クリアス)」である。その内訳は、階調をなめらかにする機能+ディテールの再現機能のHD Reality Enhancerと、ビット数を擬似的に向上させるSuper Bit Mapping for Videoの2つだ。
HD Reality Enhancerは、放送などオリジナルソースの8bit(各RGB)の映像を14bitにまで拡張し、いわゆる階調を細かく刻む処理を行なう。またMPEG圧縮によりオリジナル映像内に埋もれてしまった画素をエンハンスして、ディテールを復活させる。14ビット処理というのは、つい数年前までは非圧縮映像を扱う放送用スイッチャーなどの演算回路ぐらいしかなかったものだが、最近コンシューマでも使用可能なレンジになってきた。
スムージングとエンハンスは、方向性としては逆の機能である。したがって画面全体にかけると、後処理くさい映像になってしまうが、一つの画面内で細かく処理部分を分けて、必要な部分に必要な処理を行なうようになっている。この機能は、コンテンツ視聴中に「オプション」ボタンを押して、画質設定を選ぶ。エンハンスは-3から3までの7段階、スムージングは切、標準、強の3段階で切り替え可能だ。
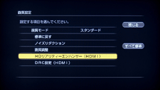 |
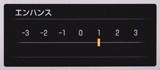 |
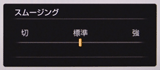 |
| 画質設定内に「HDリアリティエンハンサー」として項目がある | エンハンスの設定は7段階 | スムージング設定は3段階 |
しかし内部処理が14bitでも、テレビのパネル自体は8bitや10bitである。これをそのまま突っ込んだら、今度はビットの足切りが行なわれることで、せっかく処理した効果が失われてしまう。そこで2番目のSuper Bit Mapping for Videoの出番である。
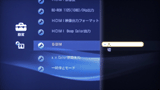 |
| SBMの設定。デフォルトでは「入」 |
SBMは、これの映像版と考えていい。データとしては8または10bitだが、独自の信号処理により14bit相当の階調をキープする。これはHDMIでテレビと接続する必要があるが、メーカーを選ばずどんなテレビでも映像を1ランクアップさせるのが特徴だ。この設定は、「ホーム」メニューの「映像設定」の中にある。入と切どちらかを選択する。
 |
| DRCの設定パネル |
Xシリーズのみの特徴としては、最新の画像処理エンジン「DRC-MFv3」を搭載した。従来の「DRC-MFv2.5」では1080/24Pのソースが処理できなかったが、今回のv3から可能になっている。市販のBlu-rayコンテンツも、ハイエンドな画像処理が可能になった。DRCの機能は、「HD Reality Enhancer」と同じところにある。効果は「くっきり」と「すっきり」のグラフから、好みの画質ポイントを選ぶという方式だ。標準では2×2の設定になっている。
全体をデフォルト値に設定して東芝REGZA「37Z3500」に接続してみたところ、確かに効果は高い。Z3500自体もそう古いモデルではないが、パネル性能が1ランク上がってなんだか画素1ピクセルずつが非常に細かくなったという印象の絵だ。精細感も上がるが、ぼけたところは甘く、精細感が欲しいところは集中的に細かくなるので、絵の立体感がより強調される。録画だけでなく、普通にテレビ視聴の時にも常時活用したくなる画質だ。
■ 「公共性」を意識させる新機能
続いてソフトウェア面の新機能を見てみよう。この秋モデル全部に搭載された新機能が、「x-みどころマガジン」である。まだレコーダのEPG受信が一般的ではなかった頃、テレビ雑誌が趨勢を極めていた。
テレビ雑誌の良さは、2週間分の番組表が載っているということだけではなく、特集記事やコラムなど、テレビをネタとした読み物としての魅力もあった。だがご存じのようにデジタル放送以降、番組表はEPGで見るというのが主流となり、テレビ雑誌は昔ほどの部数もなく、休刊したものもある。
EPGは検索性が高いため、いつも見る番組やジャンルが決まっている場合には便利だが、新しい番組に出会うきっかけにはあまりならない。また今何が流行ってるかといった話題性の指針にもならない。しかしテレビというのは元々、流行のネタに対して過敏に反応するメディアであり、ネットに縁のない世間一般のトレンドを知るには役に立つ。
「x-みどころマガジン」は、これまでのレコーダで弱かったこのような面を補強してくれる。具体的には、1週間分の蓄積されたEPGデータから頻出するテーマを探し出し、特集として記事風にまとめてくれる。テーマの変更は1日1回だが、時間が進むにつれて放送してしまった番組が出てくるので、内容は適宜変わっていく。また季節特有のテーマ、4月、10月の番組改編時には最終回、新番組を特集するなどのアルゴリズムも搭載している。見出しやサブタイトルは、EPG内に含まれる番組説明の文章から抽出する。
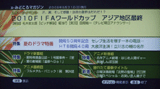 |
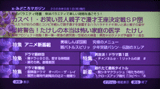 |
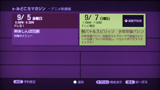 |
| 8月31日と9月1日の画面。毎日テーマが変わる | 予約したかどうかもわかる | |
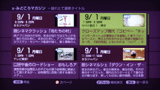 |
| 録画済みの番組も特集の一つとなる |
これまでの録画機能、例えばx-おまかせ・まる録などの機能は、個人の趣味や嗜好をベースに番組を集めて、サジェスチョンしてくれる機能が中心だった。この機能は、その反対側、社会性や公共性に注視する機能と言えるだろう。誰でも、「一般になにが問題になっているのか」ということには、少なからず興味があるものだ。例えば電車の中吊りをつい見てしまうようなことは、多くの人が経験していることだろう。
「x-みどころマガジン」は、そういった興味に対する回答を、アルゴリズムで実現する試みと言える。また、x-おまかせ・まる録で自動録画された番組も、特集としてまとめてくれる。録画一覧から選ぶよりも詳細なメタデータが表示されるため、見てみようかなという気にさせる。
■ 総論
今回発売の全シリーズを俯瞰すると、XはLシリーズに搭載されているメモリーカードスロットとワンタッチダビングボタンを除けば、他のモデルの機能をすべて網羅している。例えばAシリーズのおでかけ転送も搭載しているし、LシリーズのAVCHDカムのBDダイレクトダビングも搭載する。ホームシアター向けではあるが、オールインワンでもある。
レコーダ的な進化としては、「x-みどころマガジン」は面白い試みだと言える。というのも、これまではいかに自分の好みの番組を見逃さないかに注力してきたレコーダが、興味はないかもしれないのを承知で、データとして流行ってるはずというのを抽出してくるわけである。実際に見る、見ないを別にして、テレビ局の編成や番組構成などを客観的に見る一つの指針になるように思う。
欲を言えば、メインで取り上げられた番組ぐらいは、自動録画されてもいいのではないか。また昨日の特集をもう一度表示させて、録画された番組をこの特集ページから見られるようになったり、PSPなどへも特集画面が書き出せて、そこから番組が見られるようになるというのも面白い。「録画して見る」という導線が変わるような、イノベーティブな機能に発展させて欲しいと思う。ただ名前がちょっとベタ過ぎるのが難点だが。
ハードウェア的な進化としては、「CREAS」の威力はなかなか凄い。繋いだだけでテレビの画力を上げることができるという点では、AVプロセッサ的な機能でもある。少し前のテレビで不満を感じているものの、なかなか買い換えるわけにも行かないという人にもグッと来る製品だろう。Xシリーズだけでなく、この秋発売の全モデルに搭載されている。一番安いモデルでもこのプロセッシングが手に入るわけだから、お買い得感が高いシリーズと言えそうだ。
□ソニーのホームページ
http://www.sony.co.jp/
□関連記事
【2007年12月19日】【EZ】AVC録画のBDレコーダ、ソニー「BDZ-X90」
~ ホームシアターに注力した冬商戦のフラッグシップ ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071219/zooma335.htm
【2007年10月25日】開発陣に聞く、ソニーBDレコーダの「ここが新しい」
~ 「AVC録画」、「4倍速記録」だけではない魅力とは? ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071025/rt044.htm
【2007年9月12日】ソニー、MPEG-4 AVC録画対応の新BDレコーダ4モデル
-320GBに800GB分録画可能。レコーダは全てBDへ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070912/sony1.htm
(2008年9月3日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.