 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第96回:トップシェアを走り続ける東芝RDシリーズ
|
■ なぜX3なのか
 |
| ヘアライン入りのアルミ素材を採用したフロントパネル |
その中でも矢継ぎ早の製品ラッシュで市場を席巻しつつあるのが、東芝のRDシリーズである。エントリーモデルRD-XS30が昨年11月に発売になったと思ったら、翌月にはRD-XS40、そして年明け1月には早くもRD-X3が発売された。
RDシリーズのフラッグシップモデルに位置づけられるX3だが、デザイン的にはXSシリーズとほとんど変わりない。従来の感覚で言えば、フラッグシップと名の付く限りは筐体デザインもそれなりに高級感のあるもの、というのが相場だが、X3の場合はいったいどういう点がフラッグシップなのかわかりにくいというのが本音だ。
わかりにくいなら直接関係者に話を聞いた方が早いんじゃないか、と考えた我々一同(といっても2人だが)、早速東芝さんにご連絡したところ、OKということになった。そんなこんなで今回のElectric Zooma!はちょっと趣向を変えて、東京は芝浦にある東芝本社にお邪魔し、開発者のお話を交えながら、X3の秘密に迫っていきたい。
■ ホントはXS50だった!?
ここでいつもならボディチェックが入るところだが、X3のボディはXS30、40とほとんど変わりがない。強いてあげればフロントパネルがミラーではなく、アルミになったことぐらいである。XシリーズとXSシリーズでデザインが同じになっちゃったが、我々ユーザーはこれをどういう風に考えていけばいいんだろう。
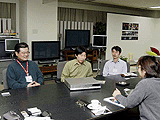 |
| 左から高品位部分のエンジニア桑原氏、商品企画担当の片岡氏、「ネットdeナビ」開発者の須田氏 |
「XSのSはStandardのSです。価格的にもファンクション的にも普及を優先したラインナップ、ということですね」と広報担当主務の勝俣健太氏(以下敬称略)。「ただし機能においても手抜きはありません。ソフトウェアは同じですし、ベーシックな動き方も同じです」
「もともとX3は、そこまで差別化するつもりはなかったんです。XS30、40ときて、その次にプログレ(プログレッシブ出力)だけをつけるというスタンスだったんですが、それだけじゃ物足りないと」と語るのは、X3の映像回路とオーディオ部のグレードアップを担当した桑原光孝氏(以下敬称略)。氏は東芝のハイエンドDVDプレーヤー「SD-9000シリーズ」開発スタッフでもある。X3開発のためにハイエンド部門から抜擢されたエンジニアだ。
「作ってるうちにあれもやりたいこれもといった意見が出てきまして、そろそろ再生にもこだわって高画質機として使えるようなモデルがあっていいんじゃないか。それだったらもういっそのことXというブランドを貰ってX3で行こう、ということになったんです」
■ 恐るべき再生能力
画質面では、X3にはXSシリーズにはない多くのハードウェアを搭載している。その1つが、待望のゴーストリダクション機能の搭載だ。RDシリーズとしては、実にX1以来の搭載となる。
ゴーストリダクションの機能は、単にゴーストが取れるというだけではない。ゴーストとして画面に現われなくても、映像のコントラストなどに影響が現われる場合がある。映像信号を正確に受信することは、効率よくAD変換するためにも重要だ。X3の場合は、各チャンネルごとにゴーストリダクションの入/切が設定できるという、こだわった設計となっている。
さらにX3では再生機能強化の一環として、再生時にも3次元DNRが搭載された。入力ラインにも3次元DNRが付いているので、入り口と出口にDNRがあることになる。このあたりの使いこなしを桑原氏に伺ってみた。
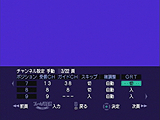 |
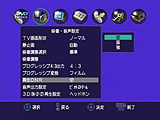 |
| X3に搭載されたGRTの設定設定画面 | 再生にもDNRが装備された。デフォルトでは「切」になっている |
桑原:「テレビ番組をスルーで見ているときは、再生と録画のDNRは両方効かせることができます。しかし基本的には録画のほうは『弱』で、再生のほうは『切』で使ってください、というのが私の心づもりです。この効き具合は我々“絶妙”という言い方をさせて貰ってますが(一同笑)、この担当者が毎日相撲放送を見ながらですね……」
小寺:なんで相撲なんですか(笑)
桑原:「いや相撲が彼には一番よく見えるらしんですね、いろんなものが(笑)。ほかにもディスクとかいろいろなものを見ながら、この設定値を決めていったんです」 再生DNRの効き具合は読者にお目にかけることはできないが、編集部が録画DNRのサンプルを作ってくれたので、その「絶妙」と言われるDNRの効き具合ををご覧いただこう。
| モード | 解像度 | 映像レート | 音声 | DNR | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|
| LP | 352×480ドット | 2.2Mbps | DD1 (192kbps) |
切 |  |
| 弱 |  |
||||
| 強 |  |
||||
| SP | 720×480ドット | 4.6Mbps | DD1 (192kbps) |
切 |  |
| 弱 |  |
||||
| 強 |  |
||||
| MN | 720×480ドット | 【最高画質】 9.2Mbps |
DD1 (192kbps) |
切 |  |
| 弱 |  |
||||
| 強 |  |
||||
| 編集部注:DVデッキ「WV-DR5」で再生したCREATVECAST Professionalの映像をRF経由でRD-X3に入力、各モードで録画した後、RD-X3でDVD-Rに書き出した。各モードの記録解像度が異なるため、掲載した静止画は800×600ドットで表示したものをキャプチャしている。 | |||||
| MPEG-2の再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載したMPEG-2画像の再生の保証はいたしかねます。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |
さらにDVD商品企画担当の片岡秀夫氏からは、「エアチェック系のソースは録画系のNRはかけたほうがいいでしょうね。エッジが立ったノイズが出たままだと、ビットレート配分がばかばかしいことになってしまうので」とアドバイスをいただいた。元々オーサリングをやっていたという片岡氏らしい意見だ。録画系の3次元DNRは、XSシリーズにも搭載されているので、ユーザーはチェックしてみるといいだろう。
それに加えてXシリーズとしての進化ポイントは、やはりプログレッシブ出力(D2)を装備したことだろう。筆者宅でもX3をお借りしてしばらく使ってみたが、プラズマや液晶などプログレッシブ表示が基本のモニタを持っているならば、その威力は簡単に確認できる。単にテレビ放送をX3経由で見ただけなのだが、テレビのチューナ部を経由して見るよりも大幅に解像度がアップしているのが体感できた。
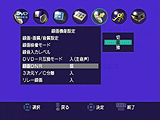 |
 |
| 録画のDNR設定。デフォルトでは「弱」 | 背面にあるD1/D2出力端子がX3のキモ |
特に画面中に挿入される文字にその威力が顕著だ。我々放送人がいつも気にしている、細い横線が綺麗に表示される。多くのプログレッシブ表示ではフリッカーは起きないまでも、横線が段差で表示されたり、一部凹んでいたりといった表示になってしまうが、X3ではそのようなエラーは確認できなかった。
さらに桑原氏にプログレッシブ出力の面白いデモを見せていただいた。DVDプレーヤーの最高機「SD-9500」とX3で同じDVDを再生してみるというものだ。
X3の再生性能の実力が発揮しやすく、同社で調整にも使ったという特定のDVDタイトルを再生しただけだが、そのディスクでは明らかにX3の方がプログレッシブ補間に起因する画面のちらつきが少ない。もちろん、すべてのDVD再生でSD-9500を上回るということはないだろうが、プログレッシブ出力プレーヤーとしての能力は、かなり高い。
そのほかにもDAC後のアナログ処理に関して、桑原氏自ら図を書いてで解説していただいたのだが、そのあたりは社外秘ということで、筆者と担当のみが知る秘密である。だがSD-9500のベースになった技術がかなり組み込まれているということは言っても差し支えないだろう。
■ レコーダ市場の特異点
 |
| リモコンもXS30、XS40と同じデザイン |
「品質の高いものを求めるマーケットは確かにあります。再生主力の人は、質を重要視しますよね。しかし記録となると、求める質と価格が合わなくなってきます。ハイエンドな録画機というのはある程度は売れるんでしょうけど、それが市場を支えるわけではない。反対に例えばVHSなんかそうなんですが、外側は形成が悪くてスイッチなんかは斜めに凹むんだけど、中身は3次元YCですごいのが入っているという製品も珍しくない。結局コストを抑えるためにデザインが落ちるわけです。ただこういう現象は、健全ではないと思っています。要はバランスなんじゃないかと」
XSシリーズやX3が市場で支持されるということは、それだけユーザーが中身をよく勉強していて、指名買いしているという現状がある。これに対して片岡氏は、マニアのためだけに作っているわけではないと苦笑しながらも、「Macintoshやある意味バイオなんかもそうだと思いますが、こだわりを持った人間が作っている、というところが支持されているとしたら、うれしいですね」
実際のシェアでは、DVD単体のレコーダとDVD+HDDレコーダを合わせても、RDシリーズは37~38%でトップだと言う。現在DVDのみのレコーダというのは主力製品ではないということを考えると、具体的には東芝とパナソニックとパイオニアの三つ巴の戦いと見ていいだろう。従って3割強のシェアを取ればトップ、ということになる。
■ 総論
普及クラスのXSシリーズに対し、Xシリーズは上位ラインナップに位置するわけだが、ボディデザインが変わらないことに対して不満を持つ人もいることだろう。もちろん東芝開発陣もこれで満足しているわけではなく、さらにカッコいいモデルの投入も十分あり得るわけだが、ここで片岡氏の言う「バランス」が意味を持ってくるのではないだろうか。
X3の潜在能力を検証した限り、ボディデザインを新規に起こさなかったからこそ実現できた、かなりのお買い得モデルである。ハイエンドプレーヤーであるSD-9500は、どんなところへ行ったってまず20万は下らないという値段だ。しかしX3なら、録画系は従来のRDシリーズで培われたノウハウが入り、再生系ではハイエンドDVDプレーヤーに匹敵するクオリティを持つ。
普段液晶テレビで番組を見ている筆者などは、録画しなくて単にX3をスルーして見るだけで、手軽に1ランク上の映像が楽しめるというという点が気に入った。今までのテレビ録画機は、録画したものを見るときだけしかその能力を発揮しなかったわけだが、X3ならハイクオリティTVチューナ、プログレッシブコンバータとしても役に立ちそうだ。
さらにインタビューでは、デジタル放送や次世代DVDは、どうなるといった方向にまで発展したのであるが、それはまた別の機会に譲ることにしよう。少なくとも東芝では、レコーダに対するユーザーのニーズをがっちり把握しているといった印象を持った。今後も痒いところに手の届くレコーダをリリースしてくれるものと期待していいだろう。
□東芝のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/
□製品情報
http://www.rd-style.com/products/rdx3/index_j.htm
□関連記事
【リンク集】ディスクビデオレコーダ関連記事リンク集
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/recorder.htm
【2002年12月18日】【EZ】この冬の目玉、東芝「RD-XS40」
~ ネットワークで変わった機能とは ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20021218/zooma88.htm
【2002年12月4日】東芝、HDD/DVDレコーダのフラッグシップモデル「RD-X3」
-160GB HDD/GRT/D1入力搭載、プログレッシブ再生対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20021204/toshiba.htm
【2002年11月6日】【EZ】レコーダの王座が獲れるか? 東芝「RD-XS30」
~ 妥協なしでここまでコストダウン!! ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20021106/zooma82.htm
【2001年11月16日】東芝、DVDビデオ/オーディオプレーヤーのフラッグシップ機
―108MHz/14bit映像DAC、192kHzへのDDコンバータ搭載
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20011116/toshiba.htm
(2003年2月12日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
|