 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第372回:新GUI搭載のHDDモデル、キヤノン「iVIS HG21」 |
■ 同スペックのHDDモデル?
キヤノンの秋商戦用モデルは、先日レビューした「iVIS HF11」が事実上の目玉だろう。内蔵メモリで32GBという容量は、一昔前のHDDモデルに匹敵する。またビットレートにしても、規格上の上限である24Mbpsに到達した。潤沢なリソースを使った映像は、「AVCHDだから」ということを理由に我慢しなくていい領域になってきたように思う。
しかし、同時に発売されたHDDモデル「iVIS HG21」も興味深い。最高ビットレートなど目玉機能は同スペックだが、GUIが全く新しくなっているほか、再生操作としてHDMI-CECにも対応するなど、操作性が結構変わっているからである。もしかしたら今後のモデルは、こちらのGUIになっていく可能性もあるわけだから、見ておいて損はない。
また前回は時間の都合でテストできなかった、付属ソフトの新バージョン「ImageMixer 3 SE Ver.3」も、今回はトライできた。光学部分やエンジンなどはHF11と同じなので、スペックなどはそちらのレビューを参考にしていただくとして、今回は補助的な情報をお届けしよう。
■ HVっぽいデザイン
 |
| グリップ部が突出しているあたり、HG10とはずいぶんイメージが違う |
HG21は、事実上昨年発売されたHDDモデル「HG10」の後継機となるわけだが、デザインはかなり違う。グリップ部が突出しているようなあたりは、HDDモデルでありながらむしろHDV機の「HVシリーズ」に近い。
では細部を見ていこう。レンズなど光学系はHF11と同スペックである。マイクはレンズ下にあり、正面を向いている点は評価できる。
 |
| 静止画用フラッシュはあるが、ビデオライトはない |
前面にはAF用外測センサーを設けるほか、静止画用フラッシュがある。しかしHF11にあったLEDビデオライトは装備していない。必要な場合は、前回テストした外付けビデオライト「VL-5」を利用することになる。
内蔵HDDは120GBで24Mbpsの最高画質モードでは、約11時間5分の撮影が可能。ただしこのモードでは、9時間以上の連続録画はできない。画質モードと録画時間の関係は、以下のようになっている。
| 撮影モードと記録時間 | ||||
| モード | ビットレート | 解像度 | 内蔵HDD 記録時間(120GB) |
|
| MXP | 約24Mbps | 1,920×1,080ドット | 約11時間5分 | |
| FXP | 約17Mbps | 約15時間45分 | ||
| XP+ | 約12Mbps | 1,440×1,080ドット | 約21時間40分 | |
| SP | 約7Mbps | 約36時間 | ||
| LP | 約5Mbps | 約45時間55分 | ||
液晶回りのボタン、コントローラ類はHF11と同じで、操作体系も統一されている。HG10に搭載されていた十字キーと「クイックセレクトリング」は廃止された。
別途電源ボタンがあり、液晶の開閉でスタンバイと起動が行なえるところも、HF11と同じだ。ただしHG21は、ビューファインダも装備している。これには別途「ファインダー」ボタンを設けて、点灯できるようになっている。液晶の開閉動作に相当するアクションを、ビューファインダで実現するためだ。
 |
 |
| 操作体系はHFシリーズと共通 | ビューファインダ用の「ファインダー」ボタンが新設 |
例えば液晶モニタを閉じたスタンバイ中でもファインダーボタンを押すと、ファインダが点灯して電源が入る。もう一度押せばスタンバイに戻る。また独立したファインダON/OFFボタンにもなっている。液晶モニタで使用中にファインダーボタンを押すと、ビューファインダも両方見ることができる。
通常ファインダ付きのカメラは、ファインダのみで撮影する可能性があるため、液晶を閉じてもスタンバイにはならない。それを両立させるためのボタンというわけである。ただしファインダが点灯中は、液晶モニタを閉じてもスタンバイにはならない。液晶の開閉だけで使っていた人には、ファインダの状態にも注意を払う必要がある。
ズームレバーは、HG10のシーソー式から普通のレバー式になったのは残念だ。グリップ部は、後方にミニHDMI端子、前方にアナログ出力とマイク入力がある。電源はボディ背面、USBは液晶内側と、端子類の配置は結構ばらばらである。このあたりの設計も、HG10の頃より悪くなった。
 |
 |
| HDMIは単独で後方にある | 電源も単独で下に |
 |
 |
| 前方にアナログ系端子類 | アクセサリーシューのカバーは、半回転して使用する感じ |
■ 撮影時の操作感も変更
HF11と光学系は同じとは言え、前回は曇天だったこともあってあまりぱっとした絵柄が撮れなかった。今回の撮影は晴天で、60iでプログラムモードを中心に撮影している。普通に撮ったらどんな感じかというのもわかるだろう。
| 動画サンプル | |
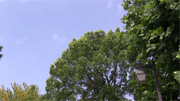 ezsm.mpg (375MB) |
 ezroom.mpg (124MB) |
| 60i、シネマモードOFFで撮影 | 室内サンプル。ワイコン「WD-H37II」を併用 | 編集部注::Canopus HQ Codecで編集後、MPEG-2 50Mbpsで出力しました。再生環境はビデオカードや、ドライバ、OS、再生ソフトによって異なるため、掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、編集部では再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |
晴天時にあらためて人物を撮ってみると、露出オートでは顔が飛びすぎる傾向が見られた。画面全体を測光するとこうなっちゃうのだろうが、おそらく明るい方のラティチュードが足りないので飛んでしまうのだろう。シネマモードを使えばもう少し救えるとは思うが、ポートレートモードでももう少し救えるようになって欲しい。
 |
 |
| 人肌は若干飛び気味の傾向 | 3段階マイナスの露出補正 |
一方他社は顔認識があるので、その辺が自動でカバーできるということである。ただ現状HG21は人に限らず同様の傾向があるので、ちょっとコントラストを付けすぎなのかもしれない。例えばビデオカメラには日付時刻や地理的位置を設定する機能があるので、だいたいの光量を予測してラティチュードを自動調整するような機能があっても面白いかもしれない。
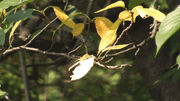 |
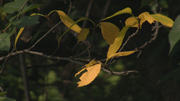 |
| 自然画も同様の傾向が見られる | 6段階マイナスの露出補正 |
新GUIは、撮影時にも多少の変化をもたらした。絞り優先、シャッター優先の時に、設定値が単なる数値のみだけではなく、バー上にグラフィカルな表示が加わった。一眼レフレンズのダイヤルのような感じで、設定値が感覚的にイメージできる。
撮影時に表示されるファンクションメニューは、多少配色が違う以外は同じだが、メインメニューはかなり感じが変わっている。前作のように縦方向の切り替えではなく、ブラウザなどでおなじみのタブ式となった。液晶が横長なので、以前よりも細かいカテゴライズ分けになっている。
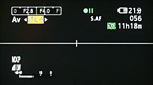 |
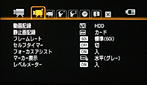 |
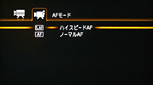 |
| 絞りやシャッタースピードをグラフィカルに表示 | 設定値が一度に把握できる新GUI | 光るバーで設定値を選択 |
一番大きいのは、フォントサイズが大小選べるようになったことだ。フォントサイズを小にすると、カテゴリ内の設定がスクロールなしで見られるため、一覧性がいい。また現在の設定値も、アイコンだけでなく説明が横に表示されるので、わかりやすくなった。要するにスクロールではなく、面で見せるようになっただけだが、メニューの全体像が初めて掴めたように思う。
ただメニュー操作時はジョイスティックの上下と決定だけが有効で、左右に倒す動作は使われていない。どうせ使わないのなら、メニュー操作中に別のタブへ移動するアクションを割り当てた方が便利だったろう。
■ HDMI-CECに対応
再生機能も、メニューの変更に伴っていくつかの新機能がある。まず画像のサムネイルだが、従来の6つから15個へ切り替えできるようになった。液晶画面でみると15分割は小さすぎるように思えるかもしれないが、これは大画面テレビに繋いだときに威力を発揮する。
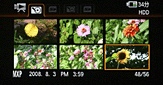 |
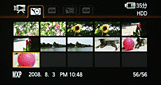 |
| 従来の6画面表示 | 新しい15画面表示 |
 |
| クリップの分割機能も搭載 |
またキヤノンのHDD機として初めて、クリップの分割機能を搭載した。単に任意の場所でクリップを分けるだけだが、本体操作でメモリーへ動画をコピーできるので、必要になったということだろう。
動画のコピーは、本体HDDからSDカードへは可能だが、逆はできない。必要ないという判断なのかもしれないが、逆にSDカードに動画を撮るほうをメインにして、HDDはバックアップ、という運用もあり得るのではないだろうか。撮影後に自動でSDカードからHDDのほうにアーカイブしてくれるような機能があったら、それなりに意味があるように思う。
再生のもう一つの目玉は、HDMI-CEC対応である。現在テレビは各メーカーとも、HDMI経由で機器をコントロールする機能を持っているものが増えた。Panasonicはビエラリンク、ソニーはブラビアリンク、東芝はレグザリンクと言った具合に名前を付けている機能だ。
これらは各メーカーごとに独自の拡張を行なっている部分も多くあるが、規定された基本的な動作であれば、ある程度は動く。HG21も特に動作保証はしていないが、テレビからのコントロールを受け付けるようになっている。
 |
| 東芝REGZAでHDMI-CEC操作中 |
試しに東芝REGZA Z3500に接続してみたところ、HDMIケーブルを接続した時点で自動的に入力が切り替わった。再生画面のGUIは、テレビのリモコンの十字キーとセンターボタンで操作できる。映像の再生中に決定ボタンを押すと、再生用のメニューが表示される。次のクリップへのスキップなどは、ここで操作する。
REGZAのリモコンには、再生系のボタン類があるが、再生、停止、早送り、などは使える。ただスキップボタンだけは反応しなかった。また機器コントロールでは、HG21の電源OFFは可能だ。しかし電源ONはリモコンからはできない。
たったこれだけではあるが、離れた場所から鑑賞するには、カメラを接続するだけで済むので便利だ。別途何かにアーカイブするのではなく、カメラ自身が家族の思い出を保存するストレージであるという使い方も、HDDモデルならあり得るかもしれない。
PC用管理ソフト「ImageMixer 3 SE Ver.3」は、新たにBlu-ray書き込み機能が追加された。これはまあAVCHDフォーマットのDVDを作成する手順と大差ないので、ドライブさえあればすぐに使える。現状24Mbpsの映像を、そのまま再生できる形で保存できるのは、Blu-rayだけだ。
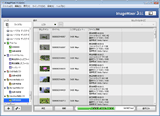 |
| 単体での再生はできないが、24MbpsをそのままDVDメディアに保存できる「データ記録モード」を搭載 |
もう一つの機能は、DVDメディアを用いたデータ記録機能だ。これはDVDメディアに動画データを書き込むだけなので、このメディア単体では、Blu-rayプレーヤーやレコーダで再生はできない。しかしDVDメディアに24Mbpsのままで保存できるという点で、メリットがある。
またこのフォーマットで書き込んだ映像は、PCのライブラリを経由してカメラに書き戻すことができる。カメラ本体を思い出再生機として考えれば、バックアップはデータとして書いておき、普段はカメラを使って再生するという使い方と合致するだろう。
■ 総論
今ハイビジョンカメラのHDDモデルは、難しい岐路に立たされている。メモリカードの大容量化が進み、日常的に撮影するには十分となった今、単に「何十時間撮れます」だけでいいのか。容量が重要なPCでさえ、モバイルに強いという理由でSSD化が進んできている。そういう意味では、モバイルデバイスにHDDを使うということに対して、もっと積極的な意味が求められている。
なぜ大量に撮れるだけではいけないかというと、容量に甘んじていつまでもバックアップしないからである。もし何かのトラブルでHDDのデータが読み出せなくなった時に、大容量であればそれだけ失われる映像の量も多い。記録メディアはある程度容量が限られて、別のものへ待避する必要があったほうが、リスク分散できるという考え方もあるということだ。
カメラ内のHDDに全部入っているというのは、利便性は高まるが、安全とは言えない。光メディアへのバックアップが面倒というのであれば、カメラのHDDの映像を、無線LAN経由で別のHDDに自動でミラーリングできたりする機能もあっていい。今後HDDモデルで、「なるほど」と思わせるメーカーはどこだろうか。
ビデオカメラは、撮る趣味であっていいのだが、積極的に見るソリューションが足りていないのも問題である。いろんなリソースが潤沢になった今、問われるべきはいかに映像をハンドリングして、テレビに流し込んでいくかということである。そのあたりはHDMI接続とSDカードを使って、Panasonicが積極的にトライしてきた分野であったが、他メーカーも徐々にそこに気づきつつある。
テレビ事業を持たないキヤノンが、持たないからこそできることは何かを探すのは、なかなか難しい作業になるだろう。
□キヤノンのホームページ
http://canon.jp/
□ニュースリリース
http://cweb.canon.jp/newsrelease/2008-07/pr-hf11.html
□製品情報
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hg21/index.html
□関連記事
【7月22日】キヤノン、AVCHD規格上限24Mbps対応ハイビジョンカメラ
-内蔵32GB+SD/SDHCモデルと、120GB+SD/SDHCモデル
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080722/canon.htm
【7月23日】【EZ】ついにAVCHDの限界まで到達、キヤノン「HF11」
~ コーデック戦争終結その先は…… ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080723/zooma370.htm
【1月29日】キヤノン、同社初のフルHD/フラッシュメモリ型AVCHDカム
-内蔵16GBメモリとSDカード併用など。HDV後継機も
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080129/canon1.htm
(2008年8月6日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.