 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第315回:コンテンツ保存に命を賭ける東芝VARDIA「RD-A600」
|
■ HD DVD普及モデル登場
昨年7月にHD DVDレコーダ初号機「RD-A1」が登場、その年の11月には松下がBDの「DMR-BW200」を、そして12月にソニーが「BDZ-V9」を発売したわけだが、どうもそのあとがとんと続かない。全盛期の2004年頃は、毎月レコーダのレビューをやらない月はないというぐらい新製品が発表されたことを考えると、気味が悪いぐらいの沈静化である。
日本にとっては寂しい状況が続いてきたわけだが、昨年から今年前半ぐらいまで、次世代DVDの戦いは主に米国のプレーヤー市場が戦場であった。そろそろ日本のレコーダもなんとかしないと、ということなのだろうか、ここでもまずは東芝が仕掛けてきた。
HD DVD/HDDレコーダ「RD-A600」(以下A600)の登場は、6月12日に大きな発表会があったので、ご存じの方も多いだろう。6月末からすでに発売が開始されており、店頭予想価格は20万円以下となっていたが、現在ネットでは16万円台まで下がってきている。
最近ではコピーワンスを廻る動きも活発化しており、あきらかにレコーダの動作を複雑怪奇なものにしてしまった最大要因が変わろうとしている。その中での発売というのは、よほど腹が据わっていないとできない話だろう。
では次世代DVDレコーダ第2弾を、さっそくテストしてみよう。
■ 基本に忠実な落ち着いた外観
まずは外観だが、初代機「RD-A1」が値段度外視の重厚路線であったので、あれは比較対象にはできないだろう。そういう意味ではA600の外観は、A1ほどコストをかけている感じはないものの、久しぶりにレコーダが高級品だった頃を思い出させてくれる、落ち着いた中にも品のあるデザインとなっている。
 |
 |
| 黒を基調とした、シックなデザイン | ボディ両脇の吸気口。背面のファン排気はそれほど熱くない |
ボディ全体が黒で統一され、上から見ると柔らかいアールの中にフロントパネルが埋め込まれているような格好だ。左から電源、W録切り替え、HDD/HD DVDのメディア切り替えスイッチ。中央部のドライブを挟んで、右側はトレイ開閉、停止、再生、録画とシンプルにまとめている。一番右は下部フロントカバーの開閉スイッチだ。
ドライブは、DVD-RAM/R/RWとHD DVD-R対応で、HD DVD-RWはまだサポートされていない。またDVD-RAMのカートリッジに対応していない。このカートリッジへのこだわりは、DVD-RAM推進の中核である松下電器への配慮とは関係なく、コンセプチュアルな意味で採用を続けてきたわけだが、この点は意外である。
カバー内部にはボタン類はなく、B-CASカードスロットと外部AVアナログ入力、DV入力、そしてEXTENSIONという名称のUSB端子がある。正式にUSBを謳っていないのは、USBの仕様をフルでサポートしないからであろう。ここはもっぱらタイトル入力などの便宜のために、外部キーボードなどを接続するポートとして利用することになる。
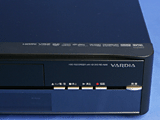 |
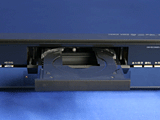 |
 |
| パネル面のやわらかなアールがアクセントとなっている | ドライブはカートリッジ使用不可のトレイを採用 | フロントカバーを開けたところ。ボタン類はない |
 |
| ややすっきりした背面パネル |
背面に回ってみよう。まずRFはBS/CSデジタルで共用、地上波はアナログ/デジタル共用となっており、アンテナ配線がシンプルになった。入力端子としてはアナログAVが背面に2系統、前面に1系統。そのうち1つはD1端子が付いている。D1入力をサポートし続けているのは、東芝だけではないだろうか。
出力は、アナログAVが2系統、うちD4端子が1である。D端子用のアナログ音声出力はなく、出力2と共用だ。デジタル系では、HDMIが1、角型光デジタル音声が1となっている。通信系端子としては、モデムとEthernet、i.LINK端子とスカパー! 連動端子が付いている。
考えてみれば、まだアナログ入力3、出力が2系統あることになる。このあたりはデジタル機器の普及具合を見ながら、いつかは整理されていくことになるだろう。
 |
| 大幅に改善されたリモコン |
次にある意味レコーダの顔とも言えるリモコンも見ていこう。基本的なテイストは以前からのリモコンを継承しているが、実は改良点は多い。一つはボタンに様々なアクセントを付けて、わかりやすくしているところだろう。
例えば以前は「簡単メニュー」だったボタンは「スタートメニュー」となり、大きなオレンジ色の丸ボタンになった。その下には「編集ナビ」「番組ナビ」「見るナビ」が並び、このエリアで機能別操作をひとまとまりで押さえている。
また従来は「HDD」、「タイムスリップ」、「HD DVD」と3つが個別に並んでいた部分は、「ドライブ切り替え」ボタンに集約された。タイムスリップは、下部の隠しボタンエリアへと移動した。最近はテレビにHDDを搭載してタイムスリップする製品が主流となっており、レコーダでのタイムスリップ機能は、そろそろ役目を終えるのかもしれない。
レコーダで最も使用頻度が高い番組表表示ボタンを表に出したのは、妥当な判断だ。円形ボタンの右が番組表をダイレクトに全面表示する「番組表ボタン」、左が放送中の番組下部に表示する「見ながら」ボタンである。また左下には、どんな階層の深いメニューに入っても一撃で抜けられる「終了」ボタンが付いた点も大きい。
 |
| フタ内部に移動したボタン類も、現実的な判断がなされている |
また再生まわりのボタンも、かなり改良された。以前はチャンネルボタンを強く意識したためか、間の空いた丸ボタンだったが、今回は四角いボタンになった。もちろんそれだけではなく、再生、ポーズなどよく使用するボタンはマークが立体的に出っ張っており、手触りだけでなんとなくわかる。ボタン配置は以前と変わらないが、機能のプライオリティに応じてボタンサイズが違っているため、操作性は格段に良くなっている。
デジタル放送用の4色ボタンは、以前REGZAで採用したような半透明の細いボタンになっており、このあたりもセンスの共通化が行なわれている。なお今回フタ内部にリストラされたボタンに、「録画」ボタンがある。レコーダで録画ボタンが隠れていることに違和感を感じるかもしれないが、今どきレコーダを手動で録画するというニーズは少ない。というかそういう原始的なことをするぐらいだったら、タイムスリップを使うべきだし、さらに言えばそういうことをしょっちゅうやる人はREGZAをよろしく、ということなのだろう。
レコーダも時代に合わせて、過去の常識を見直す時期に入ってきているということなのである。
■ 新機能とうまく融合したGUI
ではメニュー周りを見てみよう。さすがに前作から丸々1年の準備期間があったこともあり、以前のような取って付けたようなギクシャクした感じはなくなっている。またA1はTSのW録ができなかったが、A600は可能だ。このあたりも、ようやくこれまでのDVDレコーダと同じ水準まで来たわけである。
メニューで面白いのは、「スタートメニュー」を表示したときに現われる「ぷちまど」だ。これはおすすめサービスをダイジェストで表示してくれる機能だが、すっかり忘れがちな機能を教えてくれる。例えば以前からVARDIAではクリップ映像ダウンロード機能が装備されているが、よほど積極的に使おうという意志がないかぎり、使わない人は全然使わない機能である。
だが「ぷちまど」で定期的にサジェスチョンしてくれるので、ちょっと使ってみようという気にさせる。ダウンロードした映像は、録画番組と同じように「見るナビ」から再生することができる。映画の予告編などが手軽に手に入るため、今度の休みには映画でも行ってみようかなぁ、というコンテンツビジネス全体の底上げが期待できる機能だ。
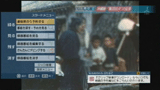 |
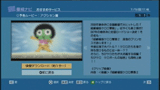 |
| スタートメニューの表示中に現われる「ぷちまど」 | 映画の予告ムービーなどがダウンロードできる |
番組表はこれまで通りHD解像度を生かした高精細表示だが、全体的にレスポンスが上がっている。特に「Myジャンル」で特定ジャンルを検索した場合のページ送りなど、以前であれば局のアイコン表示が遅れて付いてくるようなところがあったが、そういったいかにも奥で巨大戦艦が動いてます感もなく、軽快だ。
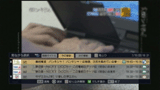 |
| 「見ながら」番組表は、選択すればすぐに録画予約となる |
「見ながら」の番組表は、現在放送中の番組をチャンネル並列で表示してくれるため、地デジ対応テレビのような挙動となる。また「次の番組」表示では、見たい番組を選択するだけで、なんのダイアログも出ずに録画予約となる。もう一度選択すれば、予約解除だ。このようにシンプルな予約形態を備えたことも、「録画ボタン」などなくてもいいということと繋がっているのかもしれない。
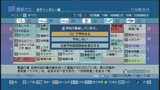 |
| 重複予約は、TS2に誘導してくれる |
W録も軽快で、基本的にTS1ベースで予約、重複したときにはTS2で予約するようガイダンスが出る。基本的にはそのまま「登録」をクリックすれば、問題なく録れる。
またW録中にも再生や編集が可能になった点は大きい。これら録画予約と関係なくパラレルに再生・編集ができることは、ヘヴィユーザーには必須の機能だ。ただW録時には市販HD DVDソフトが再生できないという制限はあるが、これは市販HD DVDの状況を考えれば、現在のところあまり問題になることはないだろう。
■ 強力なダビング・ムーブ機能
新レコーダでもっとも気になるのが、ダビング機能である。以前のA1は試作機であったため、結果的には単にメディア2枚を破壊しただけに終わるという惨憺たるレビューに終わったわけで、まだ一度もHD DVDのライティングをやったことがないというのが正直なところである。
だが今回はもちろん既に発売中のもので、さらにファームウェアのアップデートも1度行なわれている。録画した番組を普通にメディアに焼くなどということは、もちろん普通にできる。問題はそれ以上のダビングである。
次世代DVDに誰もが期待するのが、従来のレコーダからのメディアチェンジである。例えばDVDメディアのコンテンツをまとめたり、あるいは録り溜めたRec-POTのコンテンツをいつかは何らかのメディアに書き出せる日が来ると思ってきたわけである。
ではまず、DVD-RAMからのメディアチェンジを試してみよう。DVD-RAMと言えば、繰り返し録画の利便性が高いため、メディアを使い回す、いわゆるメディアキャリー的な使われ方が多いと思われているが、実はそのままライトワンスメディアとして映像保存に使われる例も多い。
このようなコンテンツを新メディアへ移行させようとした場合、まず旧メディアから一旦HDDへダビング、その後HDDから新メディアへダビング、という作業になる。ドライブが1台しかないので、高速ダビングできるかどうかがキモになってくるわけだ。
この点、BDでは、コンテンツの記録はMPEG-2 TSでなければならないという縛りがある。このため、DVDに記録したコンテンツをBDに記録するときには、等倍で変換ダビングを行なわなければならない。だがHD DVDの場合は、コピー保護のかかっていないVRモードのDVDであれば、高速ダビングが可能となっている。このあたりは、そもそもの規格に違いがあるわけだ。
試しに9Mbpsで記録した30分番組をダビングしてみた。まずDVDからHDDへの高速ダビングが13分。ドライブ自体は5倍速メディアまで対応しているが、高速ダビング時は一律2倍速になるようだ。メディアの初期化は30秒弱なので、ほとんど考えなくていいだろう。一方HDDから同じコンテンツをHD DVDにダビングするのに、約9分10秒。
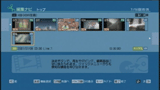 |
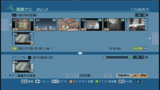 |
| DVD-RAMからの高速ダビングが可能 | アナログ放送録画であれば、当然コピーもできる |
結果的に、HDD経由で行って来いしても実時間より速いことになる。今すぐDVDをまとめなくちゃいけないというニーズはないとは思うが、あと2~3年後にはどうなるかわからない。それを考えると、旧メディアからのダビング保存については、HD DVDのほうがフォーマットとしては有利かもしれない。
ではもう一つの互換ソース、Rec-POTからのムーブを試してみよう。Rec-POTはご存じのようにアイ・オー・データ機器の録画用HDDである。レコーダというよりもデータストレージに近い作りで、テレビと連動して簡単に予約録画はできるが、リムーバブル記録メディアを持たないため、保存がきかなかった。これまで録画したはいいが、消すに消せないコンテンツが貯まっているユーザーも多いことだろう。
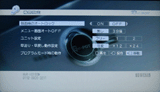 |
| Rec-POTの設定を変更する |
BDでも松下の「DMR-BW200」では、後にRec-POTからのムーブに対応した。一方A600は、公式にはサポートしておらず、機能としてはi.LINK装備のRDからのムーブには対応している。だが実際に手元にあったRec-POTの「HVR-HD160M」でテストしてみたところ、ムーブすることができた。
コツとしては、まずRec-POTをD-VHSモードで起動すること。i.LINKの接続は、1つはテレビに、もう一つはA600に接続しておく。Rec-POTをD-VHSモードで使っている人は少ないだろうと思われるが、このモードだと設定メニューが出てくる。プログラムモード時の動作を「移動」に設定しておく。
なお接続機器設定のところで、A600のステータスにも注意しておこう。電源が入っていても、予約録画中や、予約録画が実行予定になっていると、状態が「OFF」と表示されてしまう。この状態ではムーブに失敗する。A600側の録画予約一覧のところで、一時的に「実行」のチェックを外しておくと、ステータスが「ON」に変わるはずだ。またマニュアルには、W録モードを「RE」に設定するよう記述がある。TSのラインがなんらかの形で占有されていると、i.LINK入力にならないということかもしれない。
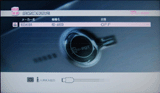 |
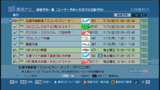 |
| 接続機器でA600側のステータスを確認しておく | A600の予約一覧で「実行」を外すと、うまくいった |
あとはプログラムモードの番組一覧で、ムーブしたいコンテンツマークを付け、決定ボタンを押すだけでムーブが始まる。D-VHSモードでの動作なのでムーブはリアルタイムだが、HDDを経由してHD DVDへ高速ムーブも可能だ。
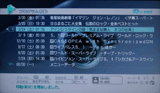 |
| プログラムモードで移動開始 |
ただHD DVD書き込み時には結構制限があり、番組表の表示を始め、ほとんどの機能が動かない。このあたりは、運用で逃げる必要がありそうだ。
■ 総論
次世代DVDメディアというものがどうなるのか、正直言ってまだ現時点ではなんとも言えないところである。どちらかが勝つのかもしれないし、そのまま2陣営のままで行くのかもしれない。だが過去のコンテンツの継承という点では、HD DVDは良くできている。
一つは、DVDメディアからの高速転送、高速書き込みが可能なこと。もう一つはRec-POTからメディアチェンジ可能なことである。もちろんすべてのRec-POT、あるいはD-VHSに対して動作保証を行なうというのは無理だろうが、少なくともベストエフォートで対応できる余地はあるということである。
先日はBD陣営もPC用として4倍速ドライブを開発するなど、動きがようやく出てきた。これまでのコンテンツ販売メディアとしての戦いから、今年は記録メディアとしての戦いにシフトするのではないかと思われる。
記録/保存と言うことになれば、舞台は日本である。元々DVD時代から日本は欧米とは別トレンドであったわけだが、その状況というか資産を継承できるかというのは、大きな問題だ。
その点でHD DVDの戦略は、DVDの継承者としてのメリットを最大限利用していくということに集約されそうだ。
□東芝のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2007_06/pr_j1202.htm
□製品情報
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-a600_a300/index.html
□関連記事
【6月12日】東芝、低価格化したHD DVDレコーダ「RD-A300/A600」
-VARDIAエンジンで高速動作。i.LINKムーブ/DLNA対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070612/toshiba1.htm
【6月12日】東芝、新HD DVDレコーダを発表。国内シェア7割へ
-実売15万円から。「BDに勝ったとは言わないが、圧勝」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070612/toshiba2.htm
【2006年7月19日】【EZ】次世代初めの一歩、東芝「RD-A1」
~ 史上初、HD DVDレコーダ登場 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060719/zooma266.htm
【2006年6月22日】東芝、世界初のHD DVDレコーダ「RD-A1」を7月14日発売
-2層HD DVD-R対応。1TB HDD搭載で398,000円
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060622/toshiba1.htm
(2007年7月18日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.