 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第225回:AVパソコンここに極まる? ソニー「type X Living」
|
■ type Xのもう半分?
先々週に取り上げた、「Xビデオステーション」で述べたように、初代type Xの半分がアレであったわけである。ではもう半分はどこに行ったのか。それが今回取り上げる、「type X Living」(以下 X Living)というわけである。レコーダのように、リビングに置くものとしてまったく新しいアプローチで設計されたこのPCは、もちろん普通のPCとして一通りの機能を持つ上に、テレビとの親和性を高めたマシンだ。
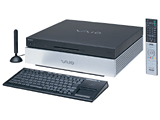
|
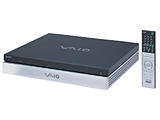
|
| VAIO type X Living | Xビデオステーション |
これまでテレビに対してWYSIWYGをやってのけたパソコンは、個人的には「AMIGA」ぐらいしかないと思っているのだが、当時テレビ放送はアナログしかなかった。時代は変わってデジタルエイジとなった今世紀、テレビとパソコンを両方やれるメーカーの真価は、X Livingで生かされるのだろうか。さっそくチェックしてみよう。
なお今回お借りしているのは試作機であるため、最終的な仕様とは異なる点があるかもしれないことをお断わりしておく。
■ レコーダライクな接続
X Livingの外観は、でっかいDVDレコーダといった感じだ。横幅は43cmで、多くのAV機器と同じ寸法になっている。重量は10kg強あり、おそらくラックの中では一番下に置いた方がいいだろう。サイドには大きく吸気スリットが設けてあるが、その内部は金属シャーシで囲まれており、両サイド全体で吸気するわけでもないようだ。

|
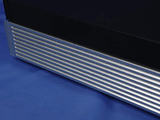
|
| 見た目はまさしくでっかいレコーダ | サイドには吸気用のスリットが |
正面上部のアクリルパネルには、電源ボタンとスロットインのDVDドライブがあるのみ。下部のアルミパネルを開けると、端子類が現われる。左側には各種メモリーカードスロット、右にはB-CASカードスロットがある。USBやi.LINK端子はパソコンっぽいとも言えるが、最近はレコーダでも珍しくはなくなってきている。

|

|
| ドライブはスロットインタイプ | アルミパネルを開けると端子類が現れる |
逆にパソコンっぽくないのは、標準プラグ採用のヘッドホン端子である。これはVAIOチームが新規開発した「Sound Reality」チップを搭載し、ヘッドホンアンプ部も独立設計したという気合いの入れようだ。Sound Realityに関しては、Digital Audio Laboratoryの記事が詳しいので、参考にしていただきたい。
外部AV入力端子も金メッキ処理されている。一番右のボタンは、ワイヤレスキーボードと本体をリンクするときに使うCONNECTボタンだ。キーボードはワイヤレスとなっており、10キーがない代わりにタッチパッドとFeliCaポートが付けられている。

|
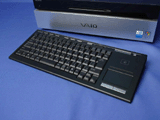
|
| AV端子類は金メッキ処理されている | 付属のワイヤレスキーボード |
今回のX Livingは、VAIOオーナーメードというシステムで販売されることになっており、HDDやメモリの容量などはユーザーが自由に指定できる。メモリは最小で512MB、最大で2GB。HDDは最小で500GB、最大1TBとなっている。なおHDDは自分で拡張すれば、最大で1.5TBまで増設可能だ。
背面に回ってみよう。まず目に付くのが、巨大なデュアルファンである。電源部には別途ファンがあるだろうから、ここは内部機構の放熱用だろう。以前からVAIOは、水冷などやらず空冷で静音化に取り組んできたこともあって、音は大してうるさくない。また手を当ててみても、熱風が勢いよく吹き出してくる感じもなく、静音のために大型ファンを2つにした、ということかもしれない。

|

|
| 背面のデュアルファンが目に付く | 普通のパソコンモニタに接続する端子類はない |
端子類は狭い範囲に集まっている。中でも特徴的なのは、パソコン画面出力用のVGA端子やDVI端子類がないことである。その代わりに、テレビ接続用のD4端子とHDMI端子が1つずつ設けられている。つまりX Livingは、パソコン用モニタには繋がらず、テレビにしか繋がらないのである。ここまで思い切ったPCは、なかなかない。強制的にリビングに置くこと決定なのである。

|
| 付属のワイヤレスLAN用アンテナ |
テレビアンテナ入力端子は、地上デジタル/BS/110度CSデジタルで1ボード、地上アナログと外部入力で1ボードとなっている。このうち地上アナログは内部的に2チューナに分配されており、ダブル録画が可能だ。
そのほかデジタル音声出力は光と同軸の両方を備え、無線LAN用のアンテナ端子もある。無線LAN用のアンテナも付属しており、既存の無線LANのアクセスポイントに接続するためにも使えるし、逆にX Living自体をアクセスポイントにすることもできる。

|
| 「VAIO」ボタンがフィーチャーされたリモコン |
リモコンも見てみよう。大筋は従来のVAIO付属リモコンをベースにしているが、デジタル放送対応ということで4色のカラーボタンが付けられている。またセンター上部には、リモコン操作向けのアプリケーションをラウンチする「VAIO」というボタンが設けられている。このリモコンからテレビも操作できるように、テレビ用のボタンも付けられているのはよく練られている。
■ テレビ直結型PC
おそらく多くの人が興味があるのは、パソコンをテレビに繋いだらどんなになっちゃうのか、ということだろう。早速HDMI端子を使って、26インチの液晶テレビに繋いでみた。テレビ側は26インチであるから当然フルHDパネルではなく1,366×768ドットだが、X Livingの出力は最大の1,920×1,080を選択すればいいようだ。ただこの出力では1080i、つまりインターレース出力になってしまう。
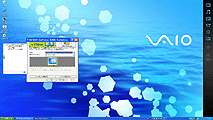
|

|
| 1,920×1,080でデスクトップを出力 | 「Sharp HDMI」としてAQUOSを認識 |
それをテレビ側でIP変換してプログレッシブ表示にするわけだが、フルHDパネルじゃないせいか、デスクトップ上の細い文字や横線がちらついて、非常に見づらい。文字のフォントなどをアンチエイリアシングするか、テレビ用の太めのフォントを組み合わせて新たなデスクトップテーマなどが用意されていればいいのだろうが、そういうことでもないようだ。一応自力でボールドなどに変更してみたのだが、根本的な解決にはならなかった。
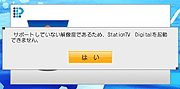
|
| 720p設定ではデジタル放送が視聴できず |
ではいっそのこと、1,280×720ドットの720pで出力したらどうか、という考え方もある。確かにその出力では、出力がプログレッシブになるので画面のちらつきもなくなるのだが、今度はデジタル放送用アプリケーション、Station TV Digitalが「解像度が合わない」として起動できない。痛し痒しである。
もっとも完全な解決法は、フルHDパネルを搭載したテレビを買うことだ。だが現状フルHDパネルを搭載した テレビは最小でも40インチぐらいになってしまうわけで、日常的に使うにはデカすぎないか? あと数年で老眼の域に突入するかもしれない筆者にとっては、大画面で思う存分仕事ができるかもと期待したのだが、それを実現するには結構な出費が必要そうだ。
また、テレビに対してはアンダースキャンとオーバースキャンの問題もある。元々ブラウン管テレビでは、入力される画面の全域を表示しないオーバースキャンが当然であったのだが、PCのデスクトップはそういった見えない部分ののりしろみたいなものはまったく考えられていないので、そのままではタスクバーなどが見えなくなってしまう。
X Living搭載のグラフィックスカードではそのあたりを自動調整する機能があるが、テレビ側にも画面全域を表示する、アンダースキャン表示機能が備わっている必要がある。多くのフラットディスプレイはアンダースキャンモードがあると思うが、テレビの事情もPCの事情を両方把握しておく必要がある。
HDMIは映像だけでなく、音声も伝送できるのがポイントだ。X Livingの音声出力はSound Realityチップが握っていることもあって、ここもHDMI出力するように設定を変更する必要がある。元々Windowsがテレビに接続するなどまったく考慮していない設計であるため、ユーザー側がいろいろと配慮する部分も多いようだ。
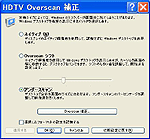
|
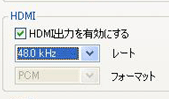
|
| テレビとPCのスキャンモードの違いを理解しておく必要がある | Sound Realityの設定でHDMI出力設定を行なわないと、音が出ない |
■ 強力なダブルチューナ
では順にテレビ録画関係を試してみよう。まずはアナログ放送だが、これは従来と同じようにDoVAIOで操作を行なう。予約録画では、リモコンの「番組表」ボタンを押すことでテレビ王国の番組表が表示される。番組表の移動や予約もすべてリモコンだけで操作可能だ。2チューナあるわけだが、機能的にはまったく差がないので、よくあるレコーダのように予約時からどちらのチューナであるかを意識する必要はない。同時間帯で3つ目の番組を予約しようとしたときに初めて、どの番組がどちらのチューナで録画されるのかを意識する程度で、なかなかスマートにできている。
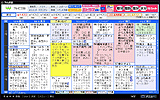
|
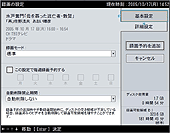
|
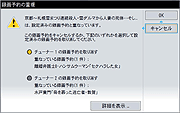
|
| テレビ王国の番組表をリモコンだけで操作できる | 予約設定画面。同時間帯の2番組までは、チューナ数を意識する必要はない | 同時間帯の3番組目を予約しようとしたところで、初めて2チューナに気付く |
自動予約録画を行なってくれる、テレビ王国のおまかせまる録機能だが、ダブルチューナにも対応できるようになっている。新番組の多い今どきのシーズンには、強力に機能する。
またアナログ外部入力端子には、著作権保護機能が設定できるようになった。例えばCATVのSTBからのアナログ出力には、コピープロテクションのためにマクロビジョン信号が含まれており、通常のレコーダには録画ができない。だが著作権保護機能が備わった入力では、録画が可能になるわけだ。
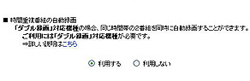
|
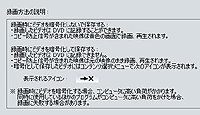
|
| おまかせまる録もダブル録画対応 | 暗号化機能を装備して、マクロビジョン出力も録画可能 |
DoVAIOは、全画面表示だけではなく、アスペクトを保ったまま縮小表示することができる。こうすれば通常のWindowsアプリケーションを使用しながら、テレビを見ることもできる。さらに2チューナを生かして、通常テレビ画面内に、さらに別チャンネルを小画面表示できる。あらゆる情報をデスクトップ上で展開することが可能だ。
次にデジタル放送録画を見てみよう。デジタル放送の試聴や録画は、DoVAIOではなく、まったく別の「Station TV Digital for VAIO」を使用する。DoVAIOと連携しないだけではなく、使用するためにはDo VAIOを終了させなければならないのが、しんどいところだ。
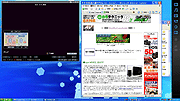
|

|
| Do VAIOで2番組を視聴、さらにWindowsアプリケーションも平行して使用できる | デジタル放送の試聴や録画は、いったんDo VAIOを終了しなければならない |
要するにこれはなんなのかというと、ピクセラ製のデジタル放送キャプチャカードを使っているということなのである。現時点ではARIB(社団法人 電波産業会)の標準規格に準拠しているPC用のチューナカードはこれぐらいしかないので、多くのPCメーカーもデジタル放送の録画ではこのカードを使用している。ゆくゆくはソニー自力の開発チューナが搭載されると思われるが、それまではDo VAIOとの統合もお預けとなるだろう。
番組表の表示には、リモコンの番組表ボタンがそのまま使えるなど、VAIOなりのインテグレートがなされている感じだ。ただ番組表の表示枠が狭く、BSデジタルのように3波1番組表示では、同時に2局ぶんしか確認できないのは辛い。また録画予約に関しても、番組表を使っての毎週予約が設定できないなど、細かい部分の使い勝手は、for VAIOと言いつつもまだVAIOらしい手が入っていない感じがある。
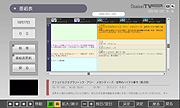
|
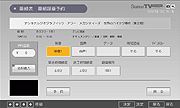
|
| 番組表もリモコンで起動できるが、画面が狭い | 番組表予約からは毎週予約などの設定ができない |
録画自体はアナログ放送録画とは別に動作するので、番組予約が重なっても問題なく録画ができる。ただ録画した番組は、DVDなどのメディアに焼くことはできず、X Living上で見るだけに留まる。
| モード | 地上デジタル | BS/110度CS | 高画質 | 標準 | 長時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500GB | 43時間 | 38.5時間 | 121時間 | 231.5時間 | 386時間 |
| 1TB | 87.5時間 | 78.5時間 | 244.5時間 | 467時間 | 742.5時間 |
■ テレビ画面向けにカスタマイズされた機能
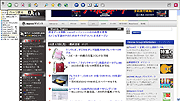
|
| リモコン操作用に特化した専用IEを装備 |
接続するディスプレイがテレビになるということで、いくつかのアプリケーションもリモコン対応になっている。PC機能で最も使われる機能として、Internet Explorerにも手を入れたバージョンが搭載されている。
これもVAIOボタンから起動でき、全画面表示される。上部にはツールバーが表示されるほか、リモコンの数字キーにはよく使う機能がショートカットとして登録されており、表示を拡大することで文字も読みやすくなる。
| 1 | お気に入り | 2 | ホーム | 3 | オートフィット |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ページ戻る | 5 | 検索 | 6 | 拡大 |
| 7 | ページ進む | 8 | リロード | 9 | 縮小 |
| 10 | ウィンドウ切替 | 11 | URL入力 | 12 | ウィンドウ閉じる |
またリモコンのチャンネルボタンを押すと、十字キーの操作がスクロール、ナビゲーション、マウスポインタの3モードにローテーションする。スクロールは縦横のスクロール、ナビゲーションはリンクごとに選択ポイントがジャンプ、マウスポインタは自由にマウスポインタが動く。
一応リモコンでもURLの入力などをサポートしているが、さすがにそれはあらかじめキーボードとマウスでブックマークでも作っておいた方が早い。
もう一つ、スクリーンセーバー代わりに起動する、「LifeFlow」というソフトがある。写真のスライドショーや世界時計、カレンダーなどを表示してくれるソフトだ。VAIOでは以前から、キーボードの閉じた上の方に時計や音楽を再生するためのソフトが起動する機能などを搭載してきたが、それの機能強化版といった感じのものである。
面白いのは、設定でRSSを指定しておけば、ニュースフィードを流してくれる機能だ。音楽再生機能と組み合わせれば、音楽をBGMにしながら、ニュースのヘッドラインをチェックできる。ニュースの詳しい内容は、そこからIEに移らなければならないが、LifeFlow画面を壊さずに各サイトを表示するのは難しいし、問題もあるということだろう。
また、この時に起動してくるのが、この時に起動してくるのが、先ほどのリモコン対応のIEではなく、普通のWindowsのIEだ。こうなると、もうリモコンでは操作できなくなるので、これはなんとかして欲しいところである。
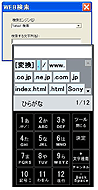
|

|
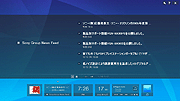
|
| リモコンでURLの入力や検索も可能 | 待機状態を無駄なく使える「LifeFlow」 | RSSを指定すれば、ヘッドラインを自動的に表示する |
■ 総論
米国のPCメーカーというのは、HPにしろDellにしろ、ある意味パソコン専業とも言えるメーカーである。一方日本のパソコンメーカーは、家電メーカーの一部門であるケースが多い。そう言う意味では、家電の殿堂とも言えるリビングにPCを持ち込もう、すなわちテレビにパソコンを繋ごうという試みは、日本では早くから行なわれてきた。しかしこれの本当の意味は、単にモニタ1つで済みますよね、って話ではないはずだ。パソコン使うときはテレビ切り替えてくださいって、じゃあテレビ見ながらパソコン使いたいときはどーするんスか、という答がなかったのである。
文化も流儀も違うテレビとパソコンは、これまでパソコンの中にテレビを入れてしまうという発想でやってきた。パソコンの流儀の中にテレビを合わせてしまったわけである。
テレビをパソコンに入れて、それをまたテレビに戻してやる。その最初の試みが、type X Livingなのではないかという気がする。AVラックに収まる平形、リモコン操作、そしてテレビに対しての出力の装備など、これまでVAIOが取り組んできた方向性をベースに、各所に新しいトライアルが行なわれている。
デジタル放送録画では、まだまだPCの利便性を享受できる状態にまではなっていないが、技術的にここまでできたのであれば、これから先やれることは沢山ある。デジタル放送を本格的に飲み込んだとき、VAIOがどうなっていくのか非常に楽しみである。
□ソニーのホームページ
http://www.sony.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.vaio.sony.co.jp/Info/2005/products_1004.html
□製品情報
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGX-XL70S/
□関連記事
【10月5日】【EZ】地アナを録り尽くせ! ソニー「Xビデオステーション」
~ あのtype Xが分割、リーズナブルに ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051005/zooma223.htm
【10月4日】ソニー、8ch同時録画が可能な2TB HDDビデオレコーダ
-約3週間の番組格納。DLNAサーバーから2番組を同時配信
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051004/sony1.htm
【10月4日】ソニー、DTCP IP/ハイビジョン録画対応のAVパソコン
-コピーワンス番組のIP伝送に対応。HDMI/D4出力装備
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20051004/sony2.htm
【9月5日】【DAL】ついに登場したDSD対応の新「VAIO」【ハード編】
~ 自社開発チップ「Sound Reality」で高音質化 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20050905/dal204.htm
【2004年10月5日】ソニー、7ch同時録画対応レコーダ「VAIO type X」
-HDD容量1TB。デジタル放送録画ユニットも発売
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20041005/sony1.htm
(2005年10月19日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2005 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.