 |
 【バックナンバーインデックス】
【バックナンバーインデックス】

|
 |
| “Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語” |

|
第356回:NAB 2008レポート その2 |
■ 既存メディアを水平、垂直に展開するSONY
放送機器の展示会として長年開催しつつけてきたNABショーだが、近年はカメラ以外の機材がほとんどIT化、IP化、ソフトウェア化してきている。IPは元々非同期転送であるため、ある意味リアルタイムを超えられるメリットがあるわけだが、人間が鑑賞する場合は時間軸に対して同期、つまりリアルタイムでしかあり得ない。効率化のために非同期は欠かせないが、放送がすべて非同期になることは、今後もないだろう。
 |
| いつも大混雑のSONYブース |
こうした中、同期型記録メディアをIP化する際に求められているのは、どんなビジョンなのか。そのあたりの答をSONYが見つけつつある。
XDCAMシリーズは、元々業務ユースや報道などの低価格でスピーディな足回りが要求される現場用として開発がスタートしたが、顧客のニーズに合わせて上下に幅広く展開し、今ではSONYのメインコンセプトとなっている。
XDCAM HDのハイエンドの方は、昨年のInterBEEでXDCAM HD422シリーズ第一弾となる「PDW-700」を発表しており、今回のNABのタイミングでいよいよ発売される。
これに対してXDCAM HDをコンパクトにまとめたEXシリーズに新ラインナップ「PMW-EX3」が加わったのは、すでにお伝えした通りだ。小型ながらGenLockやTC IN/OUT、リモート端子などがあり、スタジオカメラとしても使えるようになっているのも特徴である。
ブースではレンズ交換可能なEX3に、フジノンの2/3インチシネレンズを装着して実写デモを行なっていた。カメラ付属の1/2マウントアダプタを付け、さらにフジノンの2/3インチ(レンズ側)to1/2インチ(カメラ側)マウントアダプタを付けることで、2/3インチのシネレンズが装着できる。ビデオレンズは2/3インチマウントアダプタで直接マウントできる。画角は若干テレ側寄りになるという。
1/2インチレンズはXDCAMからXDCAM HD(XDCAM HD422を除く)にかけて採用されてきたこともあって、種類もかなり揃いつつある。しかし既に2/3インチレンズの資産を沢山持っている撮影会社も、新しいワークフローについて行けるという点で、このマウントアダプタは重要だ。またヨーロッパでは1/2インチレンズはあまり普及しておらず、設備投資としても敬遠されることもあって、2/3インチマウントアダプタの需要は大きいと思われる。
さらに、今回XDCAM EXシリーズとして、コンパクトデッキ「PMW-EX30」も登場した。SxSカードが2枚差せるハーフラックサイズのレコーダで、32GBのカード2枚を使えば約140分の収録が可能。入出力としてHD SDIとHDVを備え、出力としてHDMIを備える。SxSカードは別売だが、HD SDIによる収録が可能なスタジオデッキとしてはおそらく最安になるのではないかと思われる。日本での価格は未定だが、米国ではだいたい6,000ドル程度で考えているという。発売は今年夏を予定している。
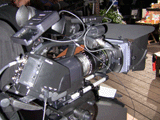 |
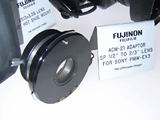 |
 |
| シネレンズを装着したPMW-EX3 | FUJINONブースに展示してあったEX3用2/3インチマウントアダプタ | SxSに記録するコンパクトデッキ「PMW-EX30」 |
 |
| 参考出展されていたHDDバックアップデバイス |
型番はまだないが、フィールドでのメモリ記録に対して、HDDにバックアップするデバイスも参考出展されていた。SxSスロットとCFカードスロットを備えており、ボタン一つで簡単にバックアップできる。CFカードスロットがあるのは、既に発売されているHDVの業務用機「HVR-S270J」と「HVR-Z7J」に、CFカードを使用するメモリーレコーディングユニットが標準付属しているからである。これは日本のSONYの企画ではなく、SONY Americaの企画商品だ。
PanasonicのP2に対してSONYのXDCAMのアドバンテージは、メモリも光ディスクも両方あるということだ。だがディスクベースのXDCAM HDはMXF、EXシリーズではMP4とファイルのラッパーが違うため、EXで撮影した映像をそのままXDCAMに記録することができなかった。
この問題を解決する試みとして、XDCAMのデッキに新しく「データモード」を追加した。PCを経由する必要はあるものの、EXで撮影した映像をデータとしてXDCAM用ディスクに記録できる。
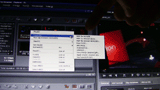 |
| コンシューマメディアへの変換出力を備えた「XDCAM EX Clip Browser Ver2.0」 |
もう一つ新たな試みとして、EXの映像をブラウジングするための無料ソフトウェア「XDCAM EX Clip Browser Ver2.0」にファイル変換機能を持たせた。XDCAM HDの記録に合わせて解像度やビットレート、ラッパーを変換できるほか、PSPやYouTube用にも変換できる。カット編集まではできないが、クリップの範囲を決めて変換することができるので、ちょこっと撮って映像をWEBでシェアするという使い方も、専用ブラウザだけでできるようになる。ただし再エンコードが必要なフォーマットに関しては、有料のプラグインを追加する形になるようだ。
■ 1080pへのトライアル
ルーティングスイッチャの世界では、今やデュアルリンクを越えて“シングルワイヤーで3Gbps伝送”が今回のNABのトレンドのようだ。伝送距離は若干短くなるが、それでも3Gbpsにこだわるのは、1080pでの映像制作が次第に見えてきたからである。
日本ではHDと言えば1080iしかないが、世界的に見れば1080iと720pに分かれている。映像制作の立場からすれば、今後マルチユースを考えた際に、どちらのフォーマットで作ればいいのか、ということが悩みとなる。それに対する答えが、両フォーマットをオーバーレイする形となる1080pでの制作だ。
SONYブースでは、1080pのワークフローと、それをそのままコンシューマ機で再生、表示するデモを行なっている。HDCAM SRで撮影した1080pの映像編集は、ノンリニアソフトでも徐々に対応が始まっているが、リニア編集およびライブ制作は、同社のスイッチャー「MVS-8000G」シリーズで可能。5月にリリースされるにオプションのソフトウェアをインストールするだけで、1080pの映像制作が可能になる。
ただし1080iに比べて帯域が2倍になるため、スイッチャーのクロスポイントやME列、DMEチャンネルなどは、半分になるという。つまり2MEのスイッチャーは1ME仕様に、DME4chは2chとして使うことになる。ハードウェアのリソースは大量に必要だが、ソフトウェアだけで1080p対応になるというのは面白い。
 |
| ノーマルのPS3で1080pの出力が可能 |
コンテンツの再生に使用していたのは、ノーマルのPS3だ。元々PS3は1080pの出力が可能なので、AVCにエンコードした1080/60pのコンテンツをUSBメモリに入れてCellプロセッサでソフトウェアデコードし、有機ELモニタで表示していた。テレビ側のI/P変換に依存しないためI/P変換エラーは皆無で、特にスポーツコンテンツには強い。
放送はいまさら1080pにするのは無理だが、家庭用フラットテレビは元々プログレッシブ表示である。Blu-rayビデオやネット配信ならば今すぐにでもできる体制は整っている。
テレビも年々性能が上がり、I/P変換のエラーも少なくなっているが、すでに買ってしまったフラットテレビは、これまでは買い換えるしか動画品質を上げる手段がなかった。だがテレビに食わせるフォーマットを変えるだけで、もっと綺麗に映ることになる。1080pは、ネット配信のキラーフォーマットとなるかもしれない。
■ データストレージの道を開いたHDCAM SR
プレスカンファレンスの記事内でも少し触れたが、HDCAM SRのレコーダをネットワークストレージ化するオプションボードのデモも見ることができた。元々HDCAM SRは昨年から日本の民放でも番組納品フォーマットとして認められたわけだが、今番組送出はほとんどビデオサーバになりつつある。テープ納品しても結局はサーバに実時間かけてインジェストしなければならないわけだが、このオプションボードを使えば、HDCAM SRフォーマットの映像を2倍速で転送することができる。テープが2倍速で回るわけである。
さらにデモでは、2Kや4Kの非圧縮データの転送の実際も見ることができた。元々VTRは、リアルタイムでしか書き込むことができないわけだが、IP転送は非同期である。そこでオプションボードにメモリバッファを大量に積み、IP転送されたデータがある程度溜まったところで、テープにおもむろに書き始める。バッファを全部書き出したら停止し、次のバッファが一杯になるまで待機、続きをAssembleモードで繋ぎ録りしていくという仕組みになっている。
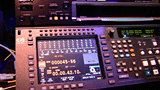 |
| オプションボードを入れたHDCAM SRのディスプレイ |
もちろんHDCAM SRのデータと違って巨大データなので、1枚の映像を書くのに、4Kならば50数フィールドを使うことになる。VTRのディスプレイにはオリジナルデータのコマ数と共に、1枚を書き込むのに何フィールドを使っているかもカウントされる。
普通のデータストレージとの最大の違いは、再生ボタンを押せば、2Kでも4Kでも映像が再生できる点だ。4Kの場合は2fpsぐらいで、出力はHDサイズにリサイズするか、一部分を拡大表示することになるが、どのポイントでも中身が簡単に確認できるというのは、普通のデータストレージではあり得ない大きなアドバンテージである。
ラージテープを使用した場合、4Kでは約6分程度しか録れないが、2Kであれば20分、ちょうどフィルムの1000フィートに相当するので、1リールが1本のテープに収まることになる。テープ自体には、様々なアスペクトやピクセルのフォーマットが混在可能。
現時点での課題は、シャトルした時に映像が壊れることと、テープを入れただけでは全体のインデックスがわからないところである。ある意味それはテープストレージの宿命ではあるが、データを全部ロードしないと絵にならない従来のテープストレージにはない検索性は、2K・4Kデータの素材搬入・搬出メディアとしても大きな可能性がある。
従来の同期型記録メディアを非同期のネットワークに合わせていくというやり方は、これから数年の大きなトレンドとなっていくだろう。
□NAB 2008のホームページ
http://www.nabshow.com/
□関連記事
【4月15日】【EZ】NAB 2008レポート その1
~ 進化するフィールドレコーダほか ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080415/zooma355.htm
【4月14日】【EZ】NAB 2008プレスカンファレンスレポート
~ カムコーダで世界を席巻する二大日本企業 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080414/zooma354.htm
【2007年4月17日】【EZ】熱狂のApple、クールなSONY
~ 対照的な両社のプレスカンファレンス ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070417/zooma302.htm
【2007年4月17日】【EZ】時代はいよいよシリコン記録?
~ AVC-Iで気を吐く松下、池上は東芝と協業 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070417/zooma303.htm
【2007年4月25日】【EZ】NAB2007 レポート その2
~ 急速に様変わりする映像産業 ~
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070425/zooma304.htm
(2008年4月17日)
| = 小寺信良 = | テレビ番組、CM、プロモーションビデオのテクニカルディレクターとして10数年のキャリアを持ち、「ややこしい話を簡単に、簡単な話をそのままに」をモットーに、ビデオ・オーディオとコンピュータのフィールドで幅広く執筆を行なう。性格は温厚かつ粘着質で、日常会話では主にボケ役。 |
 |
[Reported by 小寺信良]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
AV Watch編集部av-watch@impress.co.jp Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.