
|
||
|
◇ 最新ニュース ◇
|
||
|
【11月30日】 【11月29日】 【11月28日】 |
||
|
|
DEGジャパン設立。Blu-ray立ち上げに各社が連携 -「日本ならではのデジタルコンテンツビジネスを」 |
|
6月10日設立 |
国内のハードウェアメーカーやコンテンツメーカーなど27社は10日、デジタルエンターテインメントに関する意見交換や情報発信を共同で行なうための団体「デジタル・エンターテインメント・グループ・ジャパン」(DEGジャパン)の設立総会を開催。活動を開始した。
 |
| 左から松下電器小塚氏、ウオルト ディズニー スタジオ塚越氏、20世紀フォックス内藤氏、ソニー島津氏 |
活動開始当初は、Blu-ray Discを中心とした次世代デジタルエンターテインメントの普及活動や宣伝、市場調査、情報交換などを行なう予定。DEGは、1997年に米国でThe DVD Video GroupとしてDVDの普及を目的に設立。その後、名称をDEGに改めて活動を続けている。
映像コンテンツ会員が20社、機器メーカー会員として7社が参加。今後も、関連業界の参加企業を募っていくという。
会長にはウオルト ディズニー スタジオ ホームエンターテイメント日本代表の塚越隆行氏が就任。事務局もディズニースタジオ内に設置される。
6月10日現在の参加企業は以下のとおり。
-
【映像コンテンツ会員】(20社)
- ウォルト・ディズニー・ジャパン
- エイベックス・エンタテインメント
- エスピーオー
- 角川エンタテインメント
- ジェネオン エンタテインメント
- 松竹
- ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
- ソニー・ミュージック ディストリビューション
- 東映
- 東宝
- 20世紀 フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン
- 日活
- バップ
- ハピネット
- パラマウント ジャパン
- バンダイビジュアル
- ビクターエンタテインメント
- ポニーキャニオン
- ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
- ワーナー エンターテイメント ジャパン
-
【機器メーカー会員】(7社)
- シャープ
- ソニー
- 日本ビクター
- パイオニア
- 日立製作所
- 松下電器産業
- 三菱電機
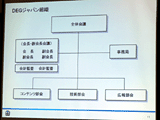 |
| 3つの作業部会を設けて、コンテンツや技術について検討を進める |
DEGジャパンでは、コンテンツ部会、技術部会、広報部会の3つの部会を設置。コンテンツ部会の部会長には、20世紀 フォックス ホーム エンターテイメント 代表取締役社長の内藤友樹氏が就任。技術部会の部会長は、松下電器産業 理事 蓄積デバイス事業戦略室 室長の小塚雅之氏が、広報部会の部会長にはソニー BD戦略室 室長の島津彰氏が就任。各部会長は、DEGジャパンの副会長も兼任する。
コンテンツ部会では、ユーザー調査や、次世代デジタルエンターテインメントの普及に対する企画立案などを行なう。技術部会では、技術の紹介や意見交換のほか、日本独自の技術を活用したデジタルエンターテイメントの可能性などを検討していく。
また、広報部会では、活動内容の対外発信や市場データの公表、CEATECなどのイベント参加のほか、表彰イベントなども実施する予定。
■ BD推進と日本ならではのデジタルエンターテイメントを
 |
| ウオルト ディズニー スタジオ ホームエンターテイメント日本代表の塚越隆行氏 |
DEGジャパンの会長に就任した、ウオルト ディズニー スタジオの塚越氏は、薄型テレビやBDレコーダ、ワンセグ機器などの市場拡大を例に引き、「より多くの人に最高の映像体験をしていただける状況になってきた」と現状を分析。
DEGの設立の目的については、「デジタルエンターテイメントにおける協力の可能性について、映像コンテンツ、機器メーカーの双方から議論する場を提供する。当初はBlu-rayが中心となるが、DEGでは、BDに限らず次世代デジタルエンターテインメント全般の発展のためのパブリシティや普及活動、協議などを行なっていく」と説明。米国や欧州のDEGとも協力し、情報を交換するという。
現在の参加社は27社だが、コンテンツ関連ビジネスを展開している各社に参加を呼びかけていく方針。「志を同じくする会社と一緒になって、この産業を盛り上げていきたい」とした。
また、「BDのためだけに集まったわけではない。一番大事なのはハードとソフトが一緒に勉強する場ができたということ。その次は、日本ならではの特別な環境があり、日本ならではの可能性がある。この可能性についてここで話し合いができたらいい。ソフトとハードが一緒にいる。それがコンセプト」とDEGジャパン設立の意義を強調した。
20世紀フォックスの内藤社長は、コンテンツ部会の活動について説明。同部会では、次世代フォーマットの普及促進活動や消費者調査などを担当する。普及活動の例としては、「Blu-ray Discがどういうもので、何ができるのか。消費者に正しく理解してもらうためのパンフレットなどを共同で作成する」という。
さらに、技術部会と連携した情報提供や勉強会などを開催。「BD-JavaやBD-Liveといった新しい規格、機能が提案されている。それがどうやって消費者に認知していけるのか、また、コンテンツやメーカーの各社における情報共有なども必要となる。こうした活動を続けていく」とした。
 |
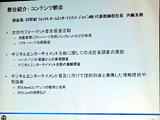 |
| 20世紀フォックス内藤社長 | コンテンツ部会の活動目標 |
技術部会の部会長を務める松下電器小塚氏は、「今夏にはレコーダ市場の半分がBlu-rayになるだろう。DEGではBDの立ち上げはもちろん、携帯電話なども含めてデジタル機器、技術のコンバージェンスを日本のコンテンツプロバイダと一緒にやっていきたい」と活動目標を説明。
「蓄積メディア、ネットワーク、携帯で持ち出すなど、さまざまなデジタルコンテンツの展開が考えられるが、チャンスもリスクもある。新しいビジネスチャンスを作りたい」とし、「パッケージは世界で統一できるが、ネットワークの領域でははそうは行かない。日本の独自性を考えた上で、コンテンツ部会と協力し、新しいことに取り組む」と語った。
また、DEGジャパンの活動の意義については、「例えば音楽配信。日本ではハードもコンテンツもうまくできなかった。パッケージだけでなく、ブロードバンド、モバイルなど様々な流れがあり、3年ぐらいで状況が大きく変わる。インフラ、携帯電話、テレビなど日本の事情に合わせた議論をメーカーとコンテンツの双方からできる場ができた。そこで成果が出せればいい」と説明した。
 |
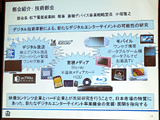 |
| 松下電器 蓄積デバイス事業戦略室 小塚室長 | 技術部会の活動目標 |
ソニーの島津氏は、広報部会の活動を紹介。Webサイトを立ち上げて、Blu-ray Discの発売リストや月間ランキングなどの情報を提供していくほか、高品質なタイトルなどを表彰する「DEGジャパンアワード」の立ち上げも検討しているという。また、CEATECにも、BDAと共同で出展するなどの情報発信に努めていくという。
 |
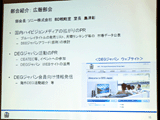 |
| ソニー BD戦略室 島津室長 | 広報部会の活動目標 |
■ 問題意識を共有し、市場を立ち上げる
コンテンツとハードウェアの連携をテーマに活動開始したDEGジャパン。発表会同日に、役員に就任した4氏に設立の経緯を伺った。
塚本氏によれば、DEGジャパンの設立を決めたのは、2007年の年末だったという。「当初は1年以上かかると思っていた」というが、実際には1月に設立発表、そして6月の活動開始と、かなり早い段階で設立まで至っている。その背景には「多くの人が必要性を認識してくれたため」という。
例えば、BDの新機能や特徴、市場性などについて、Blu-ray Disc Associationにボードメンバーとして参加しているメーカーや大手スタジオの間においては、ある程度の情報共有が図られている。しかし、国内のコンテンツホルダなどと、最新情報を共有し、連携できるような体制はできていなかった。こうした、主要スタジオ/メーカー以外のニーズが反映されづらい状態を解消する場が求められていたともいえる。
塚越氏が語るように、コンテンツ/メーカー間の議論の場を設けることで、「新しい可能性を探る」。これがDEGジャパンの最大の狙いという。
ただし、Blu-ray Discを推進してきた4社ということもあり、BD推進のための団体のようにも見えてしまう。
この点について、塚越氏は「それは違います。米国ではHD DVDがあるときから、活動はしています。やるべきことはデジタルエンターテインメントの普及活動で、消費者のメリットを最大化すること。ただ、現在、一番力を入れていくのはBDの理解がまだ行き届いていないので、BDに力を入れている。将来的にはコンテンツを届けるため、どういう方法、技術があるのか、それを検討していくための場所になりたいと考えています」と語る。
DEGジャパンへの加入にあたっては、一定の基準を設けてはいるが、デジタルコンテンツに関わる各社には積極的に参加を呼びかけていく方針で、(HD DVDを推進していた)東芝とも連絡を取っているという。
また、BDやデジタルコンテンツのビジネス展開についての協議も、DEGジャパンで進めていく。「BDの場合、BDAは規格化以上の作業には関われません。それをどうやって使っていくかという、実際のビジネスに近い領域での話し合いができる場所になります」(島津氏)。また、こうした話し合いから規格化の必然性が生じれば、BDAなどでの規格化にも生かされていくという。
例えば、BD-LiveやBD-JAVAなどの開発はアメリカが中心となっている。そのため、ハリウッド大手と、国内企業では情報の差などが生じてしまう。こうした情報や、「なにに使えるか」という意識を共有し、関連各社が「同じ言語がしゃべれる」環境を作る。その上で、消費者にも統一したメッセージを発していくことで、「業界として市場をちゃんと作る。まずはそれが重要(塚越氏)」という。
DEGジャパンは、7月2日に各部会を開催。実際の活動がスタートする。
□DEGのホームページ(英文)
http://www.dvdinformation.com/
□関連記事
【1月9日】The Digital Entertainment Group、日本支部を2008年に設立
-次世代DVDなどの国内普及の加速化目指す
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080109/deg.htm
( 2008年6月10日 )
[AV Watch編集部/usuda@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
Copyright (c)2008 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
