| 本田雅一のAVTrends |
「安全で疲れずに楽しめる3D」とは?
新時代の3D映像制作ノウハウ共有を目指す国際3D協会
 |
| パナソニック研究開発部門メディアアライアンス戦略室の小塚室長(左)と、国際3D協会 日本部会の河合会長(右) |
一昨年末公開の「アバター」以来、3D映画がたくさん公開されてきた。しかし、映画館に頻繁に足を運び、3D映画も多く見ている読者なら、3Dで見て良かったと思える作品もあれば、3Dじゃないほうが良かったと感じるものまで、実に様々。玉石混交の状態にあると感じているのではないだろうか。
2Dでの撮影や映像演出にも巧拙があるように、3Dにも等しく、いやそれ以上に作品ごとの良し悪しがある。既にノウハウが蓄積されており、映画人を目指すものなら誰もが若い頃から勉強する2Dの演出でさえ差があるわけだが、3Dに関しての撮影、演出に関するノウハウは、まだまだ十分に蓄積されておらず、また基本的な知識も含めて広く映像制作者に知られているとは言いがたい。
冒頭で挙げた「アバター」は、ジェームズ・キャメロン監督が10年近い時間をかけて準備と撮影、編集を行なってきたため、3D作品としての演出に優れていた。しかし3Dが流行したからといって付け焼刃で作ったものに、3D作品としての良さを感じられない人がいるのは、ある意味当然のことと言える。
では、どんな映像が良い3Dで、どんな映像が悪い3Dなのか。このテーマには以前、ソニー・イメージワークス出身のステレオグラファー(3D演出を行なう専門エンジニア)のバズ・ヘイズ氏に話を伺ったことがあったが、実は日本にも同様の研究をしている人物がいた。
国際3D協会の日本部会・会長を務める早稲田大学基幹理工学部 表現工学科教授・河合隆史氏は、定量的に映像の分析を行ない、より良い3D映像とは何なのかを評価、研究している。その取り組みについて、レポートすることにしたい。話を聞いてみると、そこには楽しく楽に見ることができる3D映像を作るために、まだまだ多くの技術、ノウハウが開拓される可能性が残っていると強く感じた。
■ まだ熟成していない3D映像制作ノウハウ
まず国際3D協会と河合氏について簡単に紹介しておこう。
国際3D協会(International 3D Society)とは米国で設立された、3D映像制作のノウハウを共有し、発展させるための組織だ。米国ではハリウッドの映画製作会社が中心メンバーだが、日本ではテレビ局、テレビ局系映像製作会社、家電メーカー、3Dポストプロダクションベンダーなどが参加している。
こうした業界団体の場合、有名無実で活動実績が少ない場合もあるが、米国における国際3D協会ではエミー賞運営スタッフなども運営に関わり、積極的な情報交換や優秀な3D映像に対する表彰活動などを行なっており、早くもハリウッド界隈ではその名前が定着し始めているという。
前述したように3D映像の制作、演出ノウハウは蓄積が浅いため、自分たちでノウハウを囲い込むのではなく、あらゆる企業が知見を集めることで、業界全体のレベルを底上げしようという機運が強い。良い3D映像と悪い3D映像の差はかなり大きく、悪い3Dを減らしていかなければ、そもそも3D映像技術そのものが危機にさらされるからだ。
たとえば「アバター」は3Dによる映像の可能性を見せてくれたが、それ以降、「アバター」に匹敵するほどすごいと思わせる出来の3D映画は少なかったと筆者は感じている。「トイ・ストーリー3」は快適な3Dだったが、必ずしも3Dである必要性を感じなかった。「アリス・イン・ワンダーランド」は2D撮影の限界を感じたし、「パイレーツ・オブ・カリビアン」の最新作は3Dよりも2Dで見たほうが楽しめた。
しかし、その一方で「トランスフォーマー3」のアトラクティブな3D効果は、長時間派手な3Dを見せられたにもかかわらず、さほど目の疲れや3D酔いを感じなかった。また「塔の上のラプンツェル」は心地良い上に効果的な3Dの演出効果がもたらされており、「アバター」以来、もっとも優れた3D映像だったと感じ入った。
ここで作品名を挙げて比較するのは適切ではないかもしれない。上記は筆者の個人的な感想だ。しかし、その映像に歴然とした差を感じるのは、実際に多くの3D映像を見比べた人の正直な感想ではないかと思う。
3D映画製作では、こうした3D映像の設計を脚本の中に書きこんでいくという。奥行きがどの程度、被写体の位置はこのあたり、手前に出っ張る部分はここまで、と空間の設計を映画の頭から最後まで、通しでの演出をステレオグラファーという3D空間設計のエンジニアが行なっていく。
ステレオグラファーの仕事は今のところ、“経験によるカン”が重要で、その方法論はステレオグラファーごとにまちまちだ。こうした曖昧な方法論を「言語化する(河合氏)」のが、国際3D協会の目的だ。
■“より優れた3D映像”の演出とは?
パナソニック本社・理事で研究開発部門メディアアライアンス戦略室の室長を務める小塚雅之氏は、国際3D協会の目的が3つあると話した。憶えている方もいるだろうが、小塚氏はブルーレイディスク規格策定におけるパナソニックの代表を務めていた人物だ。国際3D協会の日本部会設立における実務は、小塚氏のチームが担当している。
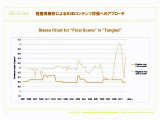 |
| 視差角によるS3Dコンテンツ評価へのアプローチ |
まずは正しい3D映像の知識を啓蒙する教育プログラムを確立させること。なぜ書割のような映像に見えることがあるのか。被写界深度はどう設定すべきなのか。カットをつなぐ際、被写体の奥行きをどのように設定すべきか。目が外に向いてしまうなど、不自然な視差の映像を作らないためには何に気を付けなければならないか。そうした3Dにおける撮影手法や演出手法などをテキスト化して教育プログラムとして確立させる。
もうひとつは表彰。クリエイターが目標を持てるようにするため、エミー賞やアカデミー賞などのように、優秀な表現を行なったクリエイターを表彰する。公平な基準で表彰を行なえるようにするため、3D作品の評価基準も確立させる。
そして最後が、より優れた3D表現を行なう手法について研究することだ。国際3D協会には、映像制作に関わる多くの企業が参加している。それぞれの持つ知見、作品制作を通して得た経験を集め、それを共通認識としてまとめる。よりよい3D映像を作るための方法論としてまとまった段階でテキスト化し、それを教育プログラムへとフィードバックする。
こうしたサイクルを続けることで、業界を挙げて3D映像品位改善を目指していく。とはいえ、これだけでは漠然として、どのような3Dがより優れたものになるのかわからない。
河合氏は、3D映像の質を決定づける演出手法は大きく分けて3つあるという。「メトリック深度」、「コグニティブ深度」、それに「エモーショナル深度」だ。すなわち被写体や背景などの深度(奥行き)表現の演出方法である。
【奥行き感の演出に必要な3段階のスキル試案】
| メトリック深度 | 視差角を定量的に把握して、コンテンツを制作するスキル | 例:建築シュミレーション |
| コグニティブ深度 | 視差角の大小ではなくカット間の変化など、 認知的特性を踏まえて奥行き感を表現するスキル | 例:eラーニング用教材 |
| エモーショナル深度 | 視聴者の情感に訴える奥行き感を演出するスキル | 例:映画の感動的シーン |
メトリック深度とは、視差角(左右の目から見た像のズレ)を定量的に把握し、視聴者に大きな負担をかけたり、誤った見え方となる3D映像にならないように配慮した演出方法だ。メトリック深度のルールを守ることで、気持ち悪くなりにくい安全な3D映像を作ることができる。これが第一段階。
次にコグニティブ深度とは、知覚認識特性を生かした演出手法のことだ。人間の脳が感じる奥行き感を、ある意味騙すことで効果的な3D映像とする手法である。たとえば、被写体の深度を徐々に変えて奥のほうに注目をさせておき、カットのつなぎで手前に唐突に被写体を登場させると、さほど深度を手前に取らなくとも飛び出しを強く感じる(実際にはあまり飛び出していない)など、定量的なパラメータにとらわれない演出方法である。
これが現在、河合教授の研究テーマになっている第二段階だ。
これらを研究することで、最終的には、奥行き表現によってより感動的なシーンを演出するには、どのような方法があるのか。再現性のある方法で、感情に訴えかける奥行きの演出を研究するのがエモーショナル深度で、これをクリアすれば第三段階となり、3D映像として優れたものになる。
■ 高評価の3D映像作品が採った手法
では、どうすればそのような奥行き表現を行なうことができるのか。
その答えを見つけるために、河合氏は各種の試験映像を用いて、被験者の反応を観察、数値化しており、既存の3D作品(たとえば3D映画)を用いた試験も行なっているという。実験用の映像はストーリー性がなく作品としての感動がない。しかし、実際に見て感動する3D映像を見ている場合は、同様の3D演出でも疲れ方が後者のほうが軽減されるとの実験結果もあるそうだ。
評価は被験者の反応を見るだけではない。映像分析ツールを開発し、既存の優れた3D映像作品の分析も行なっている。分析結果の多くは著作権者に配慮して外部には非公開になっているが、「塔の上のラプンツェル」に関しては公開できるデータがある。
河合氏の分析によると、たとえばクライマックスで強い3D効果を出したい場面では、その直前に奥行が3秒前後ゼロになり、その直後に背景が奥に沈み込みながら、被写体が前に迫り出している。映像を見ると、思わずのけぞるような3D感だが、付いている視差を計測すると1度しか付いていなかったそうだ。実際の視差が小さくとも、時間軸方向での表現を工夫した映像を作ることで、より強い立体感や迫力を演出できるということだ。
これは前述したコグニティブ深度のテクニックを使っているのだが、「塔の上のラプンツェル」で3D演出を行ったステレオグラファーのロバート・ニューマン氏は、コグニティブ深度の理論を知らずに「塔の上のラプンツェル」を作っている。「チキン・リトル」以来、長年ディズニーの3Dアニメでステレオグラファーを努めてきた経験から、自然により良い3Dを作ったのだ。
河合氏は他にも、背景の深度や一番手前の被写体の深度、その中間にある被写体の深度など、これらの位置が作品の中でどのように変化したかを積算し、作品ごとに比較するなど多角的な検証を行なって来た。その結果、「アバター」と「塔の上のラプンツェル」の3D空間の使い方や深度の演出には、非常によく似た特徴があることがわかってきたという。
「3D映像に関して業界団体で、安全な3D映像の規則を作っている場合があります。こうした規則の範囲内では、3Dの演出が限られてしまい、海外の作品などに比べると、どうしても保守的な、あまり3Dでなくてもいいのでは? という3D映像になってしまう。そんな話をする方もいます。しかし、優れた作品は大きな視差で驚かすのではなく、最小限の疲れにくい視差や奥行きの設定で、深度を操るテクニックで人が感じる立体感を変化させています。安全基準見直しなどの議論も将来は必要かもしれませんが、何より現行の基準のままで、より効果的な3D演出を行なえる可能性は、まだまだたくさんあります(河合氏)」
具体的には、立体視できる範囲内の空間を、どのように使ってキャラクターを動かしたり、風景などを描くかといった基本的な部分の設計が、評判の良い3Dに共通の特徴を示すことが多い。まったく別の人が、別の映画会社で制作しているにもかかわらず、あらゆる統計が一定の範囲内に収まる。ならば、あとはそれをまとめるだけだ。
このように得られた3D映像制作に関する知識をより多くのクリエイターに知ってもらうため、国際3D協会は10月20日から3日間かけて「3DUniversity Japan」を開催する。
河合氏は「今はとにかく、良い3D映像とは何かを少しでも多くの映像制作者に知ってもらい、優れた3D映像を制作してもらうこと。これが目標です。良い3Dとは何かという認識を、現在の2D撮影ノウハウと同じように常識的な知識にしていきたい。また、名作3Dは様々な角度から分析すると、たくさんのノウハウが見えてくる宝の山です。これらを皆さんに知ってもらい、日本でもステレオグラファーという職業が生まれてくれるといいですね。第一歩としてセミナーを10月に開催するので、是非、興味のある方には参加していただきたいと思っています」と結んだ。