
液晶テレビのバックライトが「LED」になった理由
~利点や、CCFLとの違いを解説~
現在、液晶テレビのバックライトは、かなり早いスピードで冷陰極管(CCFL)からLEDへの置き換えが進んでいる。
特に最近、各社が積極的なのが白色LEDへの置き換えである。「同じ白色光を発するCCFLを白色LEDに置き換えただけ」と思われるかもしれないが、デバイスとして全く異なるものであるため、実際にはそこまで単純な話ではないはずだ。
今回の大画面☆マニアでは、液晶テレビの光源デバイスとしての白色LEDがどういうものなのか、をまとめてみることにした。この記事作成にあたっては、三重県亀山市のシャープ AVシステム開発本部を訪れて取材を行なった。
 |  |  |
| LEDバックライトの開発を行なうシャープ亀山工場 | ||
■ 液晶パネルのバックライトはCCFLからLEDへ ~白色LEDは青色LEDがベース
液晶テレビなど、ドットマトリクス構造の液晶パネルを採用した液晶ディスプレイ採用製品には、ほぼ間違いなくバックライトがあしらわれる。一部の屋外向け商品などでは外光を取り入れた反射型液晶パネルの製品もあるが、いずれにせよ、液晶パネルはそれ自身が発光しないため、パネルとして情報を表示するためには光源が欠かせない。
バックライトの実装法の主流は、現状、2タイプがある。それが「直下型」と「導光型」(エッジライト方式)だ。
直下型は液晶パネルの背面側にバックライトを並べたり敷いたりする方式で、バックライト(Backlight)の名にふさわしく、液晶パネルの背面から直接照らす方式だ。
導光型は液晶パネルの外周四辺や、左右端二辺、上下端二辺、一辺端のみといったバリエーションがある。いずれにせよ、端に配置した光源からの光を導光板を用いて液晶パネルに導いて照射させる方式だ。光源を液晶パネルの端に配置することから「エッジライト方式」と呼ぶこともある。一般的には導光型の方が液晶ディスプレイ機器として構成したときには薄型になりやすい。
さて、これまで、直下型にせよ、導光型にせよ、一般的なテレビ製品やモニタ製品では、この光源、すなわちバックライトとして、冷陰極管(CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamp)が採用されてきた。CCFLは、その構造は、ほとんど蛍光灯に近く、水銀や希ガスなどを封入した管に放電させ、その際に発生した紫外線を蛍光体にぶつけて発光させている。
一方、「LED」(Light Emitting Diode:発光ダイオード)というデバイスは、CCFLとは全く異なる原理で発光する。簡潔に説明すると、LEDは、正孔が多いP型半導体と、電子が多いN型半導体がPN接合された形態をしていて、ここに電圧を掛けるとLED内の正孔と電子が衝突して再結合を起こし、この際に発光現象を生じる。これがLEDの発光原理となっており、この半導体化合物のレシピが変わると生じる光の色も変わる。
初期の広色域液晶テレビに採用されたバックライトは、赤、緑、青のそれぞれの原色発光する3種類のLEDを用いていた。
液晶パネルのバックライトとして長らくメインストリーム的立場だったのはCCFLの方だ。しかし、CCFLは水銀を使うために「環境に優しくない」と指摘されるようになったこと、発光効率の良い白色LEDの高性能化が進んだことで、数年前からノートPC用の液晶パネルのバックライトでの採用が加速した。
ノートPCの液晶パネルから先行して採用が始まった白色のLEDは、実は青色LEDがベースとなっている。白色を発光させるために、この青色LEDに黄色の蛍光体を組み合わせたり、あるいは赤と緑のRG蛍光体を組み合わせたりしている。例外的に近紫外線光を発光するLEDに対して赤、緑、青のRGB蛍光体で白色光を図らせる白色LEDもあるにはあるが、液晶パネルのバックライトとしてはよく用いられるのは前出の2タイプの方になる。
白色LEDは、水銀フリー、発光効率が良いために省電力性能に優れており、経年に対する輝度低下がCCFLよりも白色LEDの方が優れていたことから、「LEDはエコで長寿命」というイメージも確立された。
ここまでが(LED)バックライトにまつわる基本情報といったところになる。
■ RGB-LEDよりも白色LEDを各メーカーが推進する理由
シャープは、2008年にRGB-LEDバックライトシステムを採用したAQUOS XS1シリーズを発売した。このタイミングで、ソニーもRGB-LEDバックライトシステム採用機としてBRAVIA XR1シリーズを発表している。
 |  |  |
| 2008年発売のシャープ「AQUOS XS1」。直下型RGB-LEDバックライトを採用していた | ソニーのBRAVIA XR1「KDL-46XR1」。2008年発売 | ソニーのBRAVIA XR1世代の直下型RGB-LEDバックライトシステム「トリルミナス」では、1LEDモジュールあたり赤×1、緑×2、青×1という構成となっていた |
2008年にも、白色LEDバックライトモデルは存在したが、当時はRGB-LEDバックライトがLEDバックライトの本命だった。しかし、2009年以降、各メーカーは、液晶テレビのLEDバックライトとして、白色LEDの方をメインに活用している。
ユーザーとして気になるのは、こうした各メーカーの積極的な白色LED推進への変化だろう。
これにはいくつかの理由がある。まず、RGB-LEDバックライトの採用はテレビ製品として構成した際にコストが高くなることが避けられない。直下型で考えると、ある画面サイズにおいて、輝度ムラが出ないように適当な間隔を開けてLEDを敷き詰めるとして、単純計算でRGB-LEDは白色LEDの3倍の個数が必要になる。しかも、各RGB-LEDを個別に駆動しなければならず、制御基板も複雑になる。コストが高ければ高額商品にせざるをえなくなり、一般ユーザーには手の届かない高嶺の商品となってしまう。そして、このLED個数に大きく関係することだが、RGB-LEDでは消費電力が高くなってしまう問題を生む。
筆者の個人的な推察だが、RGB-LEDの超広色域性能があまり活かせるコンテンツがなかったというのも、RGB-LEDバックライトシステムの割高感を強めてしまった気がする。現状、広色域コンテンツといえばx.v.Color採用のビデオカメラで撮影したムービーくらいで、テレビ放送やブルーレイなどの商業コンテンツで広色域対応のものはほとんど無い。RGB-LEDがウリとしていた広色域は、それほと使いどころのない贅沢機能となってしまい、一般ユーザーにとって、高額な追加投資をしてまで欲しい性能ではなくなってしまった。
ただ、今回、取材したシャープによれば「RGB-LEDがダメと言っているわけではない」とのことで、「現状、LEDの良さを多くのお客さんに知ってもらうのには白色LEDのほうが都合がよい」ために、現状は白色LEDバックライトを強力に推進しているのだという。筆者が、他メーカーを取材したときにも、ほぼ同じ回答が得られている。
LEDバックライトシステムの普及には、「まずは白色LEDの方が適している」という判断が働いたということなのだ。
■ 同じ白色光源、LEDとCCFLの違いはどこにある?
RGB-LEDから白色LEDへのムーブメントの移り変わりの経緯についてはだいたい分かった。
ただ、白色LEDはノートPCの液晶パネルのバックライトとして早期から採用例があったが、液晶テレビのバックライトとして採用されはじめたのは近年になってからだ。液晶テレビには長らくCCFLが標準的に活用されて来たので、そう単純に白色LEDに置き換えてしまっていいものなのか、ここに疑問を抱く人も少なくないかもしれない。白色LEDは、CCFLに対して大きなアドバンテージがあるのだろうか。
まず気になるのは発色について、だ。色域の広さはRGB-LEDに及ばないとしても、CCFLに対してはどうなのか。
この点については、「CCFLバックライトであっても、カラーフィルターを工夫しCCFLも高性能なものを使えば、広色域の表現は出来る」(高倉氏)とのことであった。「ただし、色の純度という点においては白色LEDの方が優れている。これはCCFLとLEDのそれぞれの発光原理の違いから来る特性だ」(横田氏)という。
 |  |
| AVシステム開発本部 商品開発センター 第一開発室 副参事 高倉英一氏 | AVシステム開発本部 要素技術開発センター第四開発部 副参事 横田匡史一氏 |
これには補足説明が必要だろう。
CCFLでは、放電によって発生した高周波でピーキーな紫外線を蛍光体にぶつけて可視光に変換しているため、RGBの各原色の周波数帯におけるピーク以外にもランダムなノイズのようなピークが立ってしまう。白色LEDの場合は、周波数の低い青色を蛍光体によって白色にしているため、RGBの各原色帯でピークが立つ特性となる。つまり励起している元々のスペクトルの違いが、取り出せる原色の違いに現れるのである。
よくいわれる「同じ白色でも、CCFLよりも、白色LEDでの発色の方が透明感を感じる」という白色LEDバックライト採用液晶テレビのインプレッションは、この違いが視覚されているのではないか、と筆者は考えている。なお、現状の白色LEDバックライトシステムではハイビジョン色域(BT.709、sRGB相当)をほぼ100%カバーできているとのこと。
この他、「白色LEDは、調光の安定範囲が広く、応答速度がCCFLよりも圧倒的に高速というメリットがある」(高倉氏)という。
これも説明を補足しよう。調光範囲というのは、実質的には輝度ダイナミックレンジと置き換えてもいい。液晶テレビでは、表示する映像の平均輝度などをキーにしてバックライト輝度を上げ下げして動的なコントラスト制御を行なったり、暗いシーンにおける暗部表現の階調特性を最適化したり、黒浮きを抑えたりするが、こうした制御はCCFLよりも圧倒的に白色LEDの方が優位だ、というのだ。
最大輝度を100%として、CCFLの場合は、基本原理が蛍光管なので輝度を10%程度に落とすとチラチラしだして出力光が安定しなくなってしまう。つまり、CCFLでは最低輝度を10%以下に下げられない。
一方、白色LEDは完全にオフにするところまで安定してリニアに出力光を暗くしていくことが出来る。
つまり、同一の液晶パネルを用いて比較した場合、白色LEDの方が、より黒浮きが少なく、そして暗部表現が美しい(暗部階調が的確、暗部の色ダイナミックレンジも広い)と言うことになる。
また、白色LEDの高速応答速度のメリットはバックライトスキャンの実現に効果的に効く。バックライトスキャンとは液晶パネルの内容を書き換えている箇所(ブロック、エリア)に対してバックライトを消してしまう制御のことで、疑似的にブラウン管のような短残光表示(インパルス表示)を実現して、残像を低減させる技術のことだ。白色LEDでは消灯から瞬間的に最大輝度に光らせることができるので、これを理想的に実現させることができるのだ。
「複数のCCFLを映像パネルの各エリアで個別駆動するようにした、CCFLベースのバックライトスキャンを行なったとしても、コスト的にもスペース的にも難しいだろう」(高倉氏)という。
なお、温度特性もLEDの方が圧倒的に優れている。
電源オンした直後の蛍光灯が若干暗いと感じた経験はあると思うが、これは冷感スタート直後は内部の水銀が蒸発しきっておらず、なおかつ希ガスも十分に活性化していないため。原理を同じくするCCFLはこの特性を受け継いでいて電源オン直後は、色度も安定しない。LEDは電源オン時直後からほぼ最大輝度で発光し、色度もより早く安定する。これもLED(白色LED)の優位性と言うことが出来るだろう。
コスト的にCCFLと比較して白色LEDはどうなのか。
「まだ、若干、CCFLを採用するよりは白色LEDを採用する方が高くつくが、いずれ差はなくなるはず。また、シャープとしては全社的にそれを目指している」(高倉氏)とのこと。
現状、バックライト専用の特製白色LED素子そのものにかかるコストはもちろんのこと、駆動回路などは白色LED専用のものとなり、また、液晶パネルに貼り合わせるカラーフィルターなども白色LEDに合わせたものを採用しており、そうした部分がコストを若干押し上げている。
ただ、白色LEDからの光を一様に液晶パネルに照射するための拡散板などはCCFLモデルに用いていたものと同じものであるため、何から何まで特別というわけではない。だからこそ、白色LEDがCCFL機に対してそれほど高くない価格でリリースされているのだ。
■ 白色LEDバックライト、直下型か導光型か
前述したようにバックライトシステムには直下型と導光型がある。
白色LEDには、どちらが向いているというのはあるのだろうか。これまでノートPCの液晶パネルのバックライトとして白色LEDを導光型で実装するのが定型パターンだったために、最近増えてきている白色LEDの直下型タイプに違和感を覚えている人もいるかも知れない。
結論を言えば、白色LEDは、直下型、導光型、どちらとの相性も悪くはない。ただ、RGB-LEDバックライトは、意外なことに直下型実装は技術的に難しい困難を乗り越えての実現だったという。それは、色ムラの問題への対策だ。何も考えずに液晶パネルの直下にRGB-LEDバックライトシステムを配してしまうと、RGB-LEDからの赤緑青の光がうまく混じりきらずに液晶パネルに照射されてしまい、白っぽい映像を表示したときに赤緑青の色味が不自然に出てしまうのだ。これはLEDの光が直進しやすい特性を持っているためで、実際、シャープも、RGB-LEDバックライトシステムを採用したAQUOS XS1では、RGB-LEDからの3原色光がうまく混じり合うように、特別な拡散技術を導入していた。
「導光型よりも直下型の方が光の利用効率が高い。これは導光板での光のロスが避けられないため」(高倉氏)
ノートPCの液晶パネルに対して導光型の採用が多かったのは、薄型化することが重視されたためで、さらにいえば、テレビほど高輝度でなくもよかったため、というのが理由として考えられる。
なお、エリア駆動を行なう際には、絶対的に直下型の方が向いている。導光型でエリア駆動実現させるユニークな技術を発表しているメーカーもあるが、ピーク輝度の明るさやエリア駆動を行なう単位の細やかさの点で、直下型の方が原理的に優位となる。また、同様の理由で、バックライトスキャンによるインパルス駆動についても直下型で実現した方が優位となる。
そして、現状、バックライトシステムの実現コスト的には、直下型と導光型とでは、大きく変わらないと言う。これは、光源の数を減らせば直下型でも安くできるし、導光板の利用コストやその枚数、全長などによっては導光型が高くつく場合もあるため。ただ、20インチ前後の製品を初めとする小型画面サイズについては、コスト的な面において導光型の方が圧倒的に優位だ。
■ シャープ、AQUOS LX1、SE1開発秘話
白色LEDバックライトの優秀性は大体理解できたが、一般ユーザーの視点では「CCFLを白色LEDに置き換えただけの製品」として見えてしまうかも知れない。
 |
| AQUOS LX1 |
ところが実際の製品開発の現場では、さまざまな「白色LEDならでは」の工夫を迫られたようだ。この辺りについて、白色LEDバックライトシステムを採用したシャープのAQUOS LX1やSE1シリーズの開発ケースを例に見ていくことにしよう。
まず、一口に「白色LED」とはいうが、製造された白色LEDはそれぞれ性能に個体差があり、輝度、色度のばらつきを生じてしまう。これは意外に知られていないことかも知れない。
照明用のLED電球の場合は、この輝度、色度のばらつきは多少許されるようだが、液晶パネルのバックライトとして用いる場合、映像の位置ごとに輝度や色の違いが出てしまってはまずいので、対処が必要になる。
そこで、シャープの場合は(恐らく他社も同様だろうが)、製造された白色LEDを特性によってランク分けして、性能がばらついた白色LED同士を複数組み合わせて、輝度ムラ、色度ムラがでないようしている。
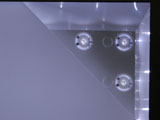 |
| AQUOS LX1シリーズに採用されている白色LED。透明な飴玉のように見えるのが光を放射状に拡散させるための光学系の役割を果たす |
ちなみに、この白色LEDの性能のばらつきへの対処は、導光型でも必要不可欠だという。性能のばらつきのある白色LEDを、いかに平均化してバックライトモジュールを構成するか、については各社が一家言あるということなのだろう。
シャープの白色LEDチップは独自開発のもので、発光部分が飴玉のような外観をしているのが特徴だ。これは直進性の強いLED光を放射状に拡散して発光させるための構造であり、光をうまく混ぜ合わす役割も果たしている。
液晶パネルもそうだが、この白色LEDもシャープ自身で開発しており、青色LEDから白色光を取り出すための蛍光体については、色純度を上げられる新しい蛍光体を開発したとのこと。なお、現状のAQUOS用の白色LEDは青色LEDに赤と緑の蛍光体を組み合わせたタイプになっている。
 |
| 実際にこの白色LEDモジュールを発光させた状態 |
この白色LEDの仕様が決定したとほぼ同時に、専用のカラーフィルターの設計を行なった。これは材質レベルで、白色LEDへの最適化を図ったものだという。
開発時に苦労したのは、白色LEDの数を減らしながら、いかに均一の光を液晶パネルに照射するかといった工夫の部分だそうで、飴玉型の白色LEDは、その工夫の1つ、ということになる。
2008年のAQUOS XS1では、RGB-LEDでただでさえLEDの個数が多く、LED間の距離が近かったことで、互いに暖めあってしまい、熱対策で相当苦労したとのことだが、AQUOS LX1、SE1では、輝度ムラ、色ムラが起きない範囲でLED間を離したことで、放熱に対しても有利な構造となっている。
 |  |
| 東芝のCELLレグザ「55X1」。右側の製品で映像を表示している時に、左側の液晶パネルを取り外したデモ機で白色LEDがどのように光っているかを示したデモ | 55X1は、生の白色チップをかなり高密度に配置させての直下型白色LEDバックライトシステム |
驚くべきは、その開発スピードで、2009年の1月に直下型モデルの企画が立ち上がってから、同年4月には試作機を完成させ、7月には海外モデルの製品化までを行なっている。これはLED開発、新カラーフィルター開発、UV2A液晶パネル開発の全てを自社で行なっていることが効果的に機能したからであろう。
■ LEDの今後への期待
ところで、今回のシャープの技術者との取材でも、「どうして直下型の白色LEDバックライトを採用していながら、AQUOS LX1、SE1シリーズがエリア駆動に対応していないか」というテーマが議題に上った。購入検討者でも、この点を気にする人は多いだろう。
直下型のLEDバックライトでは、映像内の明暗分布に応じて、LEDバックライトの輝度を局所的に上げたり下げたりさせるエリア駆動とセットで考えられることが多い。自発光画素ではない液晶パネルにとって、鋭い高輝度と漆黒の暗部が同居できる映像表現は「憧れ」であり、これを実現する方策としてエリア駆動が有効だからだ。ただし、シャープでは、UV2A技術によるコントラスト性能の向上などを理由に、エリア駆動の搭載を見送ったとする。
ただし、コントラスト向上など画質アップに寄与するという点で、エリア駆動の利点は明確。さらに、ソニーのBRAVIA「HX800」のように、エッジライト方式でエリア駆動を実現したものも登場するなど、今後のさまざまな進化が見込まれる。
また、「エリア駆動」にも深く関連したことだが、液晶テレビのスペック表記において、コントラスト値も意味を持たなくなりつつある。この点もユーザー側としては、数値だけに惑わされないように心がけたい。
例えば、液晶テレビのスペック表記で、「コントラスト比」というと全黒と全白の比較になるが、LEDバックライトの場合、エリア駆動の有無にかかわらず、全黒フレームではLEDを完全にオフできるので輝度値ゼロとなり、全白:全黒の輝度比は「∞:1」となってしまう。つまり、コントラスト比「∞:1」が謳える。とはいえ、エリア駆動がないと、1フレーム内に最大輝度の画素と漆黒画素が同居していた場合、漆黒画素に若干の光が乗り、コントラスト比は「∞:1」にはならない。ただし、カタログ値には「∞:1」の方が記載されることだろう。
一方、エリア駆動採用機にも事情がある。例えば、東芝のCELLレグザは最大輝度1,250cd/m2を謳うが、この輝度で液晶パネル全体が光ることはない。というか、最大輝度で発光を続けると発熱しすぎて実用に耐えない。この1,250cd/m2という圧倒的な輝度は、あくまでエリア駆動時に局所的に光らせられる最大輝度で、これとフレーム内の最も暗い黒画素との対比をコントラスト比が500万:1としている。
つまり、カタログ表記のコントラスト値だけで比較すると、エリア駆動ありの500万:1のCELLレグザは、前出の∞:1のエリア駆動なしの製品よりもコントラスト性能が劣ることになってしまう。しかし、実際はそうではないのは想像に難くない。今までは切り口が違う測定方式で出した値でもそれなりの参考にはなったが、「無限大」やら「何百万」という数字が出てきてしまうと、大小比較した際の差が多すぎて、実態を表すものではなくなっている。
こうした問題も、液晶テレビ、LEDの進化の過程の最中であるからこそのもの。今回の大画面☆マニアで、業界が液晶のバックライトとして白色LEDをメインに据えてきた経緯というものが整理できたと思う。画質、省エネ、薄型化などのLEDの利点は明らか。それを活かしながら、ユーザーにとって分かりやすい情報の提供にも期待したい。
(2010年 4月 8日)
