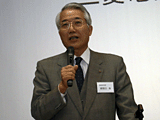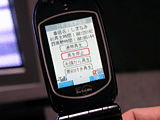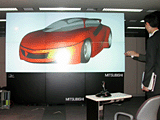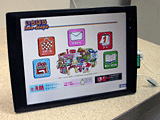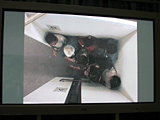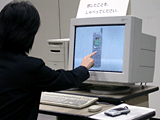| ||
|
◇ 最新ニュース ◇
|
||
|
【11月30日】 【11月29日】 【11月28日】 |
||
|
三菱電機株式会社は13日、神奈川県鎌倉市の東部研究地域において、マスコミやアナリスト向けに研究開発成果の披露を行なった。
また、今後の展望としては「2001年度は大赤字だったが、2002年度は半導体、携帯電話などを中心に再生へと取り組んできた。収益力増加の方向性がだいたい見え始めたので、2003年度は成長に力を置きたい。その一翼を担うのが技術力。本日紹介する技術が、何年後かに三菱を支えるものとして、皆さんの前に登場するだろう」と述べた。
MPEG関連では、MPEG-2とMPEG-4の両方の符号化に対応した「リアルタイム電子透かし技術」をデモンストレーションした。NHKとの共同開発によるもので、コンテンツをほかの方式に変換後、2次利用するケースを想定しており、変換後も著作権保護が有効となるのが特徴。実用化は未定としている。
またMPEG-21標準化技術を使い、動画コンテンツを端末ごとに最適化して自動配信するデモを行なった。現在MPEG-21では、コンテンツの効率的な配信に必要となるフレームワークを検討しており、「Digital Item Adaptation」として7月に最終ドラフトをまとめるという。今回の展示はこれに即したもの。
会場では、携帯電話を使ってテレビ、PC、PDAで同じ動画コンテンツを視聴するデモが行なわれた。携帯電話でコンテンツの視聴キーを取得し、赤外線経由でPCやテレビなどにキーを転送すると、ビデオサーバーからMPEG-4化されたコンテンツがストリーム再生される仕組み。さらに再生停止後、続きをテレビなどほかの端末で視聴することもできる。今回のデモの場合、フォーマットはテレビがMPEG-2、PCや携帯端末がMPEG-4を採用していた。 さらに、HD映像のネットワーク配信技術も紹介された。埼玉県川口市の「NHKアーカイブス」で採用された技術で、最大20MbpsのHD映像(1080i)をオンデマンドで配信できる。配信パケットの最適化と新開発の配信制御技術によりIPネットワーク上で実現したとし、大型フラットパネルと組み合わせて、公共施設などへの導入を図るという。
■ DLPプロジェクタ リアプロジェクタコーナーでは、非球面ミラーを応用した「鋭角投射型シームレスマルチ大画面」を参考出品した。これは、2002年12月発売の「LVP-60XT20」と同じく、非球面ミラー搭載の超広角光学系を採用したシステム。光学系とDMD素子をスクリーン前方上下に2基ずつ設置し、フロント投写で4画面マルチシステムを構築したもの。特徴は、投影画面を一部重ねあわせ、重なった部位を「目地補正回路」で補正すること。また、超広角の非球面ミラーを採用することで、DMDおよび光学系を配置した張り出し部分を業界最短の55cmに収めている。 会場では100型相当のマルチシステムを展示していた。解像度はDMD1基あたり1,024×768ドット。重ね合わせ部位はほとんど判別不能だった。ただし、今回は静止画でのデモで、動画の場合は「同期の関係などで多少重ねあわせが難しい」(三菱電機)としている。
また、リアプロジェクタのマルチ画面による3Dグラフィックス表示システムの展示された。クライアントPC1台と、画面分の描画サーバーを必要とするシステムで、同社が開発したのはクライアント側の3Dグラフィックスミドルウェア。3Dグラフィックスのライブラリをエミュレートし、データを描画サーバーにマルチキャストできる。OpenGLにも対応し、将来的にはアミューズメント向けなどへの展開を図るという。 ■ そのほか 15型液晶ディスプレイを利用した家庭内ネットワーク端末も参考出品された。これは、NMビジュアルのWindows CE 3.0端末「ヴィシム」をベースにしたもので、インターネットや家庭内サーバーへの接続のほか、家庭内のAV機器や家電の制御をコンセプトに掲げている。AV機器との接続にはHAVIを想定している。単体でもWindows CE端末として動作するほか、PCのディスプレイとしても作動。無線LANは内蔵していないが、PCカードスロットで対応する。 主婦やお年寄りがターゲットのため、「画面は15型、バッテリ持続時間は2週間以上」という設計思想に近かったのが、ヴィシムだったという。将来的には、自社販売のほか、システム構築の得意な企業とNMビジュアルとのコラボレーションといった展開を視野に入れている。
「車載情報機器の新しい操作インターフェイス」という展示では、車の走行、または停止の状態に合わせて表示を変化させるカーマルチメディア用のインターフェイスが紹介された。走行中にはメニュー項目を最低限にまで減らし、文字も大きくするなど、運転のさまたげにならないよう変化させるという。また、HDDなどの車載ストレージを持ち、音楽などのデータベースを構築できる。
また、デザイン研究所管轄の「ユーザビリティ評価室」も公開された。これは、開発品のモックアップなどをモニタに体験してもらい、インターフェイスデザインを第三者的見地から評価検証するためのもの。近年ではカーナビゲーションシステム、携帯電話などで利用され、成果を上げたという。 なお、モニタは基本的に同社社員から選抜する。もちろん評価を適切なものにするため、被験者には開発の意図は伝えないそうだ。
□三菱電機のホームページ (2003年2月13日) [AV Watch編集部/orimoto@impress.co.jp]
Copyright (c) 2003 Impress Corporation All rights reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|