
|
||
|
◇ 最新ニュース ◇
|
||
|
【11月30日】 【11月29日】 【11月28日】 |
||
|
|
世界最小HDDプレーヤー、ケンウッド「HD10GB7」を試す -小さくても「Media Keg」音質。メモリ型とも比較 |
|
12月上旬発売 標準価格:オープンプライス
|
「Media Keg」(メディアケグ)ブランドを掲げ、ポータブルプレーヤーの高音質化を進めるケンウッド。HDDプレーヤーの初代モデル「HD20GA7」(当時実売45,000円)をリリース後、マイスター・チューニング版として2005年11月に「HD30GA9」(当時実売5万円)を発売。2006年9月にはさらなる高音質化とHDDの大容量化を果たした「HD30GB9」を実売5万円でリリースした。
価格競争や多機能化がキーワードになっているポータブルプレーヤー市場において、真逆とも言える戦略を取り、音質を重視するユーザーから支持を獲得。独自の市場を形成し、「Media Keg = 高音質」というブランドイメージの確立に成功している。
だが、マニア向けの路線をとっていたため、価格が高価だったり、サイズやデザインが初代「HD20GA7」からほとんど変化していないなど、音質以外の要素が弱く、一般ユーザーへの普及は難しいのが現状。そこで、デザインやサイズにも注力したモデルを拡充することになった。
その第1弾としてフラッシュメモリタイプの「M2GC7」(2GB/実売約27,000円)と「M1GC7」(1GB/実売約2万円)を11月にリリース。さらに、HDD搭載型としては世界最小となる1インチの10GB HDD内蔵「HD10GB7」(実売約4万円)が12月上旬にリリースされた。
今回は、世界最小HDDプレーヤー「HD10GB7」をレポートする。サイズが変更されたことで、操作性や音質にどのような変化があるのか気になるところ。また、同モデルはMedia Kegシリーズで初めてWM DRM 10に対応し、定額制音楽配信サービス「Napster to Go」に対応しているところも注目だ。
■ HDD搭載プレーヤーで世界最小を実現
外形寸法は62×44×17mm(縦×横×厚み)で、1.8インチHDDを搭載した「HD20GA7」の104×61×17mmと比べると格段に小さい。厚さは同じだが、縦はほぼ半分のサイズだ。重量も「HD20GA7」は140gだが、「HD10GB7」は78gと半分程度に抑えられている。

|

|

|
| 側面には光沢のある金属パーツが使われ、高級感が高い | 左がHD10GB7、中央がフラッシュメモリ型のM1GC7、右が1.8インチHDD採用のHD20GA7 | 厚さはほぼ同じ |
本体上部にイヤフォン端子とホールドスイッチを装備。下部にUSB端子を備える。背面パネルは取り外すと内蔵のリチウムイオン充電池が現れる。充電はUSB端子経由で行ない、充電所要時間は約3時間。連続再生時間はWMAファイルを再生した場合で約20時間。HD20GA7は同条件で約24時間なので若干短め。しかし、本体サイズを考えると健闘していると言えるだろう。
搭載するHDDはSeagate製の1インチ「ST1.3シリーズ」の10GBモデル。全体のデザインは小型化されているものの、HD20GA7から続く縦型スタイルを採用。フロントパネル上部にディスプレイを備え、下部に操作部を配置した基本レイアウトに変更はない。

|

|

|
| 中央のスイッチは電源ON/OFFではなく、バッテリとの接続をON/OFFするもの。長期間使用しない場合などはOFFにする | 下部にUSB端子を装備。充電はUSB経由で行なう | |

|

|

|
| 背面パネルを外すとバッテリが現れる | シャーシ | 背面パネル。Supremeのロゴマークが大きく描かれている |

|
| トップメニュー。文字は大きめだ |
ディスプレイサイズは「HD20GA7」の2.2型から、1.5型へと縮小。さらに液晶ではなく、有機ELを採用している。コントラストは高く、文字の視認性は高い。表示性能に問題はないのだが、フォントサイズに疑問が残る。画面が小さいので文字は大きいほうが見やすいが、あまりに大き過ぎるのだ。年配向けの携帯電話の「デカ文字モード」を利用しているみたいで個人的には違和感を感じた。
実質表示可能な文字数は、全角の場合縦が5文字、横が6文字。解像度的にはもう少し表示できそうなのだが、項目の先頭にアイコンがあったりするので少なめ。デザインは「ベーシック」、「ゴージャス」、「リラックス」、「ポップ」の4種類から選べるのだが、フォントサイズは変更できない。画面が小さいからこそ文字のサイズ指定を設け、情報量の多い表示モードも用意して欲しかった。

|

|

|
| デザインは「ベーシック」に加え、「ゴージャス」、「リラックス」、「ポップ」から選択可能 | ||
各機能にはトップメニューからアクセスする。メニューには「アーティスト」、「アルバムトラック」、「お気に入り」、「新着トラック」、「ジャンル」、「リリース年」、「プレイリスト」、「ピクチャ」、「フォルダ」、「設定」を用意。各項目をカーソルキーの上下で選択。右ボタン、もしくは再生ボタンで階層を降りていく。楽曲に辿り着いたら再生ボタンで再生スタート。右ボタンの長押しでも再生できるので、基本操作をカーソルキーのみで行なうことも可能だ。
こうした基本操作は「HD20GA7」などの1.8インチHDDモデルと共通で、ユーザーならば戸惑うことなく利用できるだろう。左ボタンを長押しすることでトップメニューへショートカットも可能だ。しかし、一点気になったのは、再生中に左ボタンを押してトップメニューまで戻った際、再度左ボタンを押しても再生中の画面に戻れないこと。
1.8インチモデルでは左ボタンを押すだけで、表示が再生画面にループして戻ったのだが、「HD10GB7」では右ボタンの長押しでなければ戻れない。1.8インチモデルでは頻繁に利用する機能だったので、新モデルではどうやれば元の画面に戻れるのかわからず、戸惑ってしまった。1.8インチモデルの操作の方が直感的に理解でき、指への負荷も少ないため、できれば操作方法は統一して欲しかった。

|

|
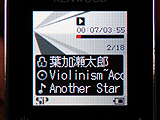
|
| トップメニュー | アーティストモードで楽曲を選択したところ | 再生中の画面 |
再生中に電源ボタンを押すと、クイックメニューが表示される。お気に入りへの登録と、再生モードの切り替え、SupremeのON/OFF、サウンドモードの変更、タイマー設定、楽曲のプロパティ表示が可能だ。お気に入りに指定しておくと、トップメニューにある「お気に入り」欄に登録され、登録した曲のみを再生できる簡易プレイリストのような機能。通常のプレイリストにも対応しており、Windows Media Playerから転送可能だ。
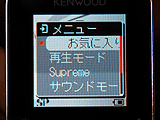
|

|
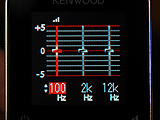
|
| 再生中に電源ボタンを押すとクイックメニューを表示。イコライザモードやSupremeのON/OFFなどが選択できる | グラフィックイコライザは調節する周波数も指定可能。このあたりのこだわりはMedia Kegらしいポイントだ | |
ジャケット画像も一緒に転送すると、再生画面に縮小表示される。画像ファイルのみの全画面表示にも対応しており、トップメニューから「ピクチャ」を選択することで、HDD内に保存した静止画(JPEG)ファイルがリストアップされ、楽曲再生中でも画像の閲覧が可能。また、フォルダモードで再生している際は楽曲とともに、同一フォルダ内にあるジャケット画像も表示できる。

|

|
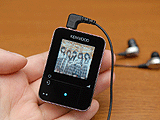
|
| 再生中にジャケット画像の表示も可能。フォルダモードで各アルバムフォルダにアクセスする場合、ジャケット画像が入っていれば楽曲ファイルと同列に表示される | 全画面表示したところ | |
表示文字数が少ないので一覧性はイマイチだが、操作方法はわかりやすく、4、5曲選択しているうちに慣れるだろう。本体を手のひらにのせて親指だけで操作が可能。リモコンなどは用意されていないが、本体サイズがこれだけ小さいのでポケットなどからの出し入れも苦にならないはずだ。ただ、本体がツルツルとした素材なので落下防止のストラップは常用したい。

|
| 起動中の画面 |
気になったのは全体的な動作スピードだ。特に起動に時間がかかる。楽曲数960曲/6.1GBを書き込んだ状態で起動させてみる。電源ボタンを長押しすると、ライブラリインデックスを構築しているようなプログレスバーが表示される。この間が約20秒。これが終了すると再生がスタートすると思いきや、あらためて「Media Keg」というロゴマークが約10秒間表示される。よって起動時間は計約30秒だ。
最近のプレーヤーにしてはかなり遅い部類で、すぐに音楽を聴きたい時などにはイライラしてしまう。1.8インチHDDモデルの起動は2秒程度なので大きな違いだ。もっとも、1.8インチモデルはデフォルトでレジュームのような動作になっており、バッテリ接続をOFFにして再起動するとライブラリの読み込みに約15秒ほどかかる。
「HD10GB7」ではこのレジューム機能が備わっていないようで、起動のたびにライブラリインデックスを構築しているように思える。また、楽曲を選択してから再生されるまでのレスポンスも、1.8インチモデルよりも1秒ほど遅い印象。1インチHDDの読み込み速度も関係しているのだろうか。
【12月15日追記】
12月15日、「HD10GB7」のファームウェア・バージョン1.01.04が公開されました。同ファームを適用することで起動時間が短縮されます。また、そのほかの不具合修正も行なわれています。
□関連記事
【12月15日】ケンウッド、HDDプレーヤー「HD10GB7」の起動時間短縮ファーム
-特定のMP3でノイズが発生する問題も修正
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20061215/kenwood2.htm
■ サブスクリプション配信楽曲にも対応
Media Kegシリーズはこれまで、楽曲の転送には専用ソフト「Kenwood Media Application」を使用し、専用形式に暗号化して転送するものが多かった。しかし、「HD10GB7」はこれを撤廃。著作権保護がかけられていないファイルであれば、基本的にストレージクラスでドライブとして認識させ、エクスプローラからドラッグ&ドロップで転送できる。転送速度は197曲/約1GBのデータを転送した場合で12分30秒。
保護された楽曲の転送にはWindows Media Player10を使用する。また、同モデルではMedia Kegシリーズとして初めてWM DRM 10に対応しており、サブスクリプション(月額固定)サービスのNapsterで取得した音楽ファイルの転送にも対応している。
これを行なうためには、設定メニューからUSB接続時の接続方法を変更する必要がある。通常はマスストレージクラスモード(MSC)となるが、設定を「自動検出」に変更。Napsterなどの対応ソフトを起動させた状態でPCと接続すると、DRM 10ファイルの転送が可能な「MTP接続モード」での動作に切り替わる。
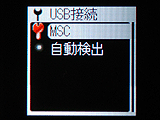
|

|

|
| MTPモードを利用するためにはUSB接続設定を「自動検出」にしておく必要がある | Napsterでダウンロードした楽曲をストレージクラスモードで転送しても再生できない | |
同モードで接続すると、Napsterのソフトウェア上で「Napster To Go」に対応したプレーヤーとして認識。ダウンロードした楽曲をNapster上でドラッグ&ドロップするだけで転送できる。また、Napsterでダウンロードした楽曲はデフォルト設定ではマイドキュメントフォルダ内の「My Music」に保存されており、このファイルを直接Windows Media Player10で転送することもできる。
なお、MTPモードとストレージクラスモードはまったくの別物で、MTP接続時にストレージ領域にアクセスすることや、もしくはその逆は行なえない。もちろんストレージクラスモードでNapsterでダウンロードした楽曲をコピーしても再生は不可能だ。

|

|

|
| Napster To Goに対応したデバイスとして認識される | WMPでNapsterのファイルを転送することも可能だ | |
なお、PC以外にも同社のミニコンポ「UD-A77/UD-A55/RD-UDA55」と、USB経由で連携が可能。マスストレージモードで接続すると、プレーヤー内の楽曲をコンポで高音質再生できるほか、コンポのCDからプレーヤーへ、WMAフォーマットで4倍速録音が行なえる。
従来のMedia Kegシリーズは、好みのエンコーダを探してCDから自分でリッピングするようなマニア向けのイメージが多かったが、PCレスでCDからプレーヤーへのリッピングができるソリューションを提案することで、敷居を下げる狙いだ。

|

|

|
| USB/SD/CD/MD装備のミニコンポ「UD-A77」。前面にUSB端子を備え、プレーヤーと連携可能 | USB接続したプレーヤー内のファイルも再生できる | |

|
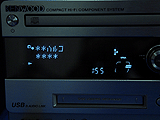
|

|
| プレーヤー内にアクセスしたところ。ひらがなと漢字表示には対応していないようだ | CDからプレーヤーへ/SDメモリーカードへの録音はボタン1つで行なえる | |
■ 期待に応える再生音
比較対象として1.8インチHDD採用の「HD20GA7」を用意。イコライジングはノーマルで試聴してみた。分解能や音場はどちらも非常に優秀で、音質はほぼ互角と言って良い。わずかにHG20の方が低域の音圧が高く、山下達郎「アトムの子」冒頭のドラム乱打の迫力が増しているようだが、ボディが大きいことからくるプラシーボ効果かもしれない。それくらい違いは微小だ。
決定的に違うのはノイズ量。HD20GA7は、再生中に聞こえるホワイトノイズが大きいことが欠点で、後に発売された「HD30GB9」ではこのノイズを大幅に低減したことが特徴だった。「HD10GB7」では「HD30GB9」クラスまでノイズが少ない。クラシックの再生中などに、かすかに残っていることがわかるが、音楽が始まってしまえば気にならないレベルだ。
また、「HD10GB7」ではSupreme機能も搭載している。これらの要素を加味すれば、HD20よりも音質は上と言えるかもしれない。気軽に持ち運べるサイズでここまでの音質が得られるという点は非常に魅力的だ。
■ フラッシュメモリ型の「M1G7」とも比較
同じく「Media Keg」ブランドのフラッシュメモリタイプ「M1GC7」(容量1GB)とも比較してみよう。サイズは「HD10GB7」の方が縦に長いものの、横幅はスリム。厚さはどちらも同じ程度で、比べて持つとどちらが大きいとは一概に言えない。ただ、「M1GC7」のフロントパネルは光沢仕上げで高級感があるものの、筐体のベースはプラスチックで、手にするとチープな印象は拭えない。

|

|

|
| M1GC7。フロントパネルのレイアウトは、1.8インチモデルとよく似ている | ボリュームや録音ボタンは側面に用意 | |
上部にディスプレイ、その下に操作パネルという基本レイアウトは共通。十字キーも備えているが、「HD10GB7」の再生/一時停止ボタンが十字キーの左側に出ているのに対し、「M1GC7」は十時の中心に配置されている。指の移動が少なくて済むので操作感としては「M1GC7」の方が上。HDDシリーズのユーザーにも「M1GC7」の方が操作方法が近くてやりやすいだろう。
FMラジオを搭載し、ライン入力やラジオ録音機能を備えること以外、GUIの主な操作方法は同じ。十字キーの上下で項目を選択し、右ボタンで階層を降りていく。階層を上がった際に、トップメニューから左ボタンで再生画面に戻れないのも「HD10GB7」と同じで、右ボタンの長押しで再生画面に戻れる。

|

|
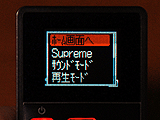
|
| トップメニュー | 再生画面 | クイックメニューも用意する |
再生音を比べてみよう。「M1GC7」の音質は極めてニュートラルだが無味乾燥ではなく、低音に芯があり、音楽にドッシリとした安定感がある。同社プレーヤー共通の傾向だ。シリコンタイプのプレーヤーとしては非常にハイレベルな音質だが、「HD20GA7」や「HD10GB7」と比較すると音場が若干狭い。
女性ボーカルの中高域から高音にかけて音が荒れ気味で、低音の分解能や輪郭も雑だ。音色の傾向が3機種で同じなため、一聴しただけでは違いがわかりにくいのだが、ボリュームを目一杯あげていくと違いが良く出る。「HD20GA7」や「HD10GB7」では個々の楽器やボーカルが形を保ったまま音圧が増していくのに対し、「M1GC7」では個々の音の境界があやふやになり、くっついたまま音量だけが上がっていく。
耳が痛いような、うるさく感じてしまう「M1GC7」に対し、「HD20GA7」と「HD10GB7」ではかなりボリュームをあげても音楽が破綻しないため、聴き続けられる。売り場で比較する際には試してみて欲しい。無音時のホワイトノイズは「HD10GB7」ほど抑えられておらず、「HD20GA7」と同程度だ。
ただし、こうした音質の差はあくまで「Media Keg」の上位モデルと比較した比較したものであり、「M1GC7」はフラッシュメモリプレーヤーとしてはトップレベルの音質だ。良い意味で「相手が悪い勝負」であり、価格やサイズ、重量を考えるとと善戦していると言えるだろう。ただし、HDDのような回転機構を持たないフラッシュメモリでは音質で有利な面もある。上位モデル並みのデジタルアンプや電源回路を備えた「超高音質フラッシュメモリプレーヤー」が登場しても面白いだろう。
■ 小型/大容量で高音質なプレーヤーを求めるなら
音質はポータブルプレーヤーのトップクラスであり、ほとんどの人が満足するクオリティを確保している。その上で、1.8インチでは弱かった小型化、女性ユーザーにも訴求できるデザイン性の向上を果たし、DRM 10もサポート。動作速度に難ありだが、全体としては非常に完成度が高い。小型/大容量のプレーヤーを探しているなら第1候補に挙げていい製品だ。
最大の問題は実売4万円という価格。相応の高級感は持っているが、8GBフラッシュメモリ搭載のiPod nanoが29,800円、30GB HDDのiPodも29,800円ということを考えると割高感はいなめない。
「Media Keg」は価格よりも音質重視のシリーズであり、最上位モデルの「HD30GB9」が実売5万円前後、価格がこなれた「HD20GA7」が35,000円程度で販売されていることを考えると妥当な価格ではある。しかし、新機軸である「HD10GB7」の価格だけが“従来通り”というのも残念な話。この音質をより多くの人に触れてもらうためには3万円台前半が望ましい。やはりMedia Kegシリーズは「音質にどのくらいの価値を見出せるか」が鍵になるのだろう。
□ケンウッドのホームページ
http://www.kenwood.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.kenwood.co.jp/newsrelease/2006/20061129.html
□製品情報
http://www.kenwood.co.jp/j/products/home_audio/personal/hd10gb7/index.html
□関連記事
【11月29日】ケンウッド、世界最小のHDDオーディオプレーヤー
-高音質設計の「Media Keg」。WM DRM 10対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20061129/kenwood.htm
【10月27日】ケンウッド、高音質のメモリプレーヤー「Media Keg」
-「Supreme」搭載で高音質化。転送ソフトも不要に
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20061027/kenwood1.htm
【10月2日】ケンウッドの新HDDプレーヤー「HD30GB9」を使ってみた
-最高レベルの音質。使い勝手も向上した“孤高の1台”
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20061002/kenwood.htm
【9月11日】ケンウッド、HDDプレーヤーの最上位「Media Keg HD30GB9」
-プリ/パワーアンプ分離。「Supreme EX」搭載で高音質化
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20060911/kenwood.htm
(2006年12月15日)
[AV Watch編集部/yamaza-k@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
Copyright (c)2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.
