
第483回:極小レイテンシーの新プラグイン「VSL」とは?
~CPUベースで動作する「AudioBox 22VSL」で検証 ~
 |
| AudioBox 22VSL |
米PreSonusからドライバレベルで超低レイテンシーなエフェクトをかけることを可能にした「VSL」という新プラグイン技術を搭載したオーディオインターフェイスがリリースされた。国内ではエムアイセブンジャパンが代理店として3機種が発売されるが、第1弾として10月に発売されたローエンドモデル、「AudioBox 22VSL」を借りることができたので、VSLとはどんなものなのか試してみた。
■ オーディオインターフェイスの2つのトレンド
オーディオインターフェイスも、数多くのメーカーから非常に多くの種類の製品が発売されており、何を基準にどのように選べばいいのかなかなか難しくなってきているが、最近のトレンドを挙げると2つあるように思う。ひとつはFireWire(IEEE 1394)からUSB 2.0へという動きだ。当初オーディオインターフェイスはFireWire接続のものが主流であったが、FireWire非搭載のMacが登場したことが影響したのか、各メーカーもUSB 2.0シフトを進めており、現在の主流は完全にUSB 2.0になったように思う。
もうひとつのトレンドはオーディオインターフェイス本体にDSPを搭載し、PCのCPUパワーを使わなくてもエフェクトをかけられるような製品が増えていること。DSPが必要なことから、どちらかというとハイエンド製品で見られる傾向だが、PCに負荷がかからないということよりも、レイテンシーなくエフェクトが簡単にかけられるという点がウケているようだ。もっともDSPで処理しているわけだから、レイテンシーがまったくないわけではないが、PCに送ってプラグインで処理して戻すといったルーティングではないため、実質的には無視できるほどの遅れなのだ。
といっても、これらDSPで処理するエフェクトはVSTやAUのプラグインのように何でも自由にエフェクトが使えるというわけではない。チャンネルストリップ的なものが中心で、コンプレッサ/リミッター、EQが使えるというのが基本。中にはリバーブやディレイなどをサポートしているものもある、という感じだ。
たとえば、先日紹介したSteinbergのUR28MやUR824、RolandのQUAD-CAPTUREやOCTA-CAPTURE、Avid TechnologyのMboxシリーズといったところがエフェクト機能を搭載した機材。その内蔵エフェクトの利用法は機種によっていろいろで、あくまでもモニター用としてだけのもの、エフェクトを通した音をレコーディングできるものなどあるが、いずれもレイテンシーなくモニタリングできることを売りにしている。
そんな中、PreSonusも「StudioLive」シリーズというミキサータイプのオーディオインターフェイスを発売しており、ここにDSPを搭載してエフェクト処理できるようになっている。またそのStudioLiveシリーズはPCのソフトウェアでコントロールできるようになっており、そのソフトウェアのことを「Virtual StudioLiveソフトウェア」と呼んでいるのだが、この度、そのVirtual StudioLiveソフトウェアが新たな進化を果たし、DSPがないハードウェアでも利用できるようになったのだ。
それを実現した第1弾のハードウェアが「AudioBox VSL」シリーズというもの。具体的には「AudioBox 1818VSL(実売価格50,000円前後)」、「AudioBox 44VSL(実売価格30,000円前後)」、「AudioBox 22VSL(実売価格20,000円前後)」の3種類で、いずれも11月発売。名前からも想像できるとおり、上から最大で18IN/18OUT、4IN/4OUT、2IN/2OUTというスペックで、最高で24bit/96kHzまで扱えるというUSB 2.0対応のオーディオインターフェイスになっている。
 |  | |
| AudioBox 1818VSL | AudioBox 44VSL | AudioBox 22VSL |
■ AudioBox 22VSLを試す
今回借りたのは、ローエンドのAudioBox 22VSLで、1Uラックマウントの横幅が1/3という見た目にはいたってシンプルなオーディオインターフェイス。フロントにはマイク/ライン兼用のコンボジャックが2つ、リアには右からヘッドフォン出力、メイン出力のL/R、そしてMIDI入出力があり、USB 2.0でPCと接続するという仕様だ。この22VSLのみはUSBからの電源供給だけで動作するというのもポイントだ。
フロントの入力は+48Vのファンタム電源が利用できるので、コンデンサマイクが使えるほか、XMAXクラスAというマイクプリアンプが搭載されているため、「歪のないクリーンなマイクサウンドが得られる」という点もアピールされている。
 |  |
| フロントはマイク/ライン兼用のコンボジャック×2 | リアは右からヘッドフォン出力、メイン出力のL/R、MIDI入出力、USB端子 |
まあ、それだけであれば、既存のオーディオインターフェイスとあまり違いがないわけだが、面白いのはここから。ドライバ類をインストールすると、「AudioBox VSL」というユーティリティが利用できるようになる。これを起動すると、まず「AudioBox VSL Tips」という画面が現れ、一番右のツマミである「Mixer」を一番右に回すように表示される。指示通りにすることで、VSLで処理したサウンドをモニターできるようになる。
反対に、これを一番左に絞っていると入力した音がそのまま出力されるダイレクトモニタリングの状態になる。ここでOKをクリックすると7つのフェーダーが並んだミキサー画面が出てくる。
これはメイン出力およびヘッドフォンに何を出力するかを設定するためのバーチャルミキサーなのだが、初期状態では電源がオフになっていて、何も機能しない。そのままでも、何の変哲もない普通の2IN/2OUTのオーディオインターフェイスとして使えるのだが、画面上にあるパワースイッチをオンにするAudioBox 22VSLがエフェクト内蔵のミキサーへと変身するのだ。
 |  |
| 「AudioBox VSL Tips」画面右端のツマミ「Mixer」を一番右に回すように表示される | 7つのフェーダーが並んだミキサー画面 |
見ればだいたい想像がつくとおり、左からIn1/In2がフロントのコンボジャックへの入力、DAW1/DAW2がPCからAudioBox 22VSLへの出力となっている。その右にあるFX A/FX Bは2系統独立したセンド/リターン型のシステムエフェクト、一番右がメイン出力というわけだ。
また見ると分かるとおり、画面上側にはGATE、COMP、EQの3つのエフェクトが各チャンネル独立に搭載されており、それぞれ細かく設定できるようになっている。GATEをクリックすると、ノイズゲートの設定画面が登場し、THRESHノブを使うかグラフを直接クリックすることで、しきい値を設定できる。またFILTER側ではフェイザーを設定できるようになっており、FREQで効果を変えられる。
次のCOMPRESSORはTHRESH、RATIO、GAIN、ATACK、RELEASEと一通りのパラメータが揃ったコンプレッサで、設定した内容が右側のグラフで確認できるほか、反対にグラフを触って設定することも可能になっている。まずは画面右側にFAT CHANNELというプリセットがいっぱい並んでいるので、これをドラッグ&ドロップでもって来ることでお勧めの設定が得られるので、後は必要に応じて設定をいじってみるのがよさそうだ。
 |  |  |
| GATEをクリックするとノイズゲート設定画面でしきい値を設定できる | コンプレッサのグラフを触って設定することもできる | 画面右側の大量のプリセットをドラッグ&ドロップし、お勧めの設定を得られる |
最後のEQはHigh、Mid、Lowの3バンドのパラメトリックEQで、やはりグラフ表示されるようになっている。これもプリセットを使うのが分かりやすいだろう。
このGATE、COMP、EQの3セットでFAT CHANNELと呼んでおり、7系統独立して使えるようになっているのだ。さらに、前述のFX AおよびFX Bというシステムエフェクトがあるのだが、これはReverb、Delay、Stereo Delayの3種類があり、FX AとFX Bで独立して使える。このエフェクトへは各チャンネルからセンドできるようになっているのだ。
 |  |  |
| EQはHigh、Mid、Lowの3バンドのパラメトリックEQで、グラフ表示される | 独立したシステムエフェクトのFX AおよびFX BはReverb、Delay、Stereo Delayを使える | このエフェクトへは各チャンネルからセンド可能 |
■ DSPが行なう処理をCPUに橋渡し、レイテンシーを極小に
ここで重要になってくるのが、設定できる各種エフェクト処理がどこで行なわれているか、という点。PreSonusのStudioLiveシリーズでは、これと同等の画面でエフェクト&ミキシング操作ができ、その処理はハードウェアに内蔵されているDSPで行なっているのだが、前述のとおり、AudioBox 22VSLにはDSPが搭載されていない。
しかし新開発のドライバーを搭載していることで、DSPが行なう処理をCPUのパワーで行なえるようになっているのだ。もちろん、ここのVSTプラグインやAUプラグインなどを使うのではなく、PreSonusが開発した独自のものであり、アプリケーションレイヤーではなく、ドライバーのレイヤーで直接処理するので、レイテンシーが極めて小さいというのだ。
実測できないので、なんともいえないが、メーカーの説明によるとレイテンシーは設定によって1~4msecで処理できるという。これはSetup画面のPerformanceで行なうのだが、Fastestで1msec、Nomarlで2msec、Safeで4msecとのこと。これはASIOやCoreAudioのバッファサイズなどとはまったく別のパラメータとなっている。とくにFastestにしても動作において不安定になることはなく、聴いた感じではまさにDSP処理という感じでレイテンシーはまったく感じられなかった。
 |  |  |
| DSP非搭載のAudioBox 22VSLでは、本来DSPで行なう処理をCPUのパワーで代替する | レイテンシーの設定はSetup画面のPerformanceで行なう | レイテンシー設定はFastestで1msec、Nomarlで2msec、Safeで4msec |
なお、このVSLで設定した結果の音はヘッドフォンやメイン出力には反映されるが、DAW側へのレコーディングにはまったく影響はなく、そのまま素の音で入る設計となっていて、掛け録りはできない。
 |
| PreSonusのセールス・バイス・プレジデント、Rick Naqvi氏 |
現在のところ、VSLで利用できるエフェクトは、このミキサーに搭載されているGATE、COMPRESSOR、EQ、Reverb、Delay、Stereo Delayといった程度だが、そこに留めるわけではないようだ。先日、記者発表会で来日したPreSonusのセールス・バイス・プレジデント、Rick Naqvi氏によると、「VSLという新たなプラグイン規格として展開していく予定で、現在サードパーティーにもプラグインエフェクトの開発を呼びかけている」とのことだ。
また、現在CPUベースで動作するこのVSLが利用できるのはAudioBox VSLシリーズのみだが、「技術的にはハードウェアを限定するものではないので、ほかのオーディオインターフェイスへの展開も検討していきたい」という。まだ、すぐに他社へVSLをライセンスするという段階ではないようだが、プラグインが充実してきたら、それも面白そうだ。
いずれにしても、既存のプラグイン規格であるVSTやAU、RTASといったものと競合するものではなく、あくまでもダイレクトモニタリング時に利用するエフェクトというもののようだが、オーディオインターフェイスの用途が広がっていくという面では歓迎だ。
■ システム全体としてのレイテンシーや音質の実力を計測
 |
| ASIOバッファサイズを最小の32にすると、音を出すとまともな音にならなかった |
VSL単独でのレイテンシーの測定はできなかったが、システム全体としてのレイテンシーがどのくらいなのかを試してみた。例によってCentranceのASIO Latency Test Utilityを使い、44.1kHz、48kHz、96kHzのそれぞれでテストしてみた。ASIOバッファサイズをいろいろ変化させたところ、最小の32にすると驚くほど小さい値が出てきたが、実は問題があった。そう、バッファサイズが小さすぎて、音を出すとまともな音にならなかったのだ。
使っているPCはSandy BridgeのIntel Core-i7 2600Kなので、CPUパワーが不足しているということはないはず。Windows7 64bit環境で試してみたところ44.1kHzおよび48kHzでは256以上、96kHzでは512以上に設定しないと、音が割れてしまったので、それぞれこのバッファサイズでテストした。その結果が画面のとおりだ。当初、VSLのPerformanceを「Safe」にして行なったのだが、これを「Fastest」に設定したところ、実測値で6~7msecほど縮まった。この差がVSLのレイテンシーの違いということなのかもしれない。
 |  |  |
| 44.1kHz/256 samples(VSL Performance「Safe」時) | 48kHz/256 samples(同) | 96kHz/512 samples(同) |
 |  |  |
| 44.1kHz/256 samples(VSL Performance「Fastest」時) | 48kHz/256 samples(同) | 96kHz/512 samples(同) |
では、音質のほうはどうなのだろうか? いつものようにRMAA Proを使ってテストした結果を見ていただきたい。これはVSLのスイッチをオフにして単なるオーディオインターフェイスとして測定した結果だ。PreSonusはほかのオーディオインターフェイスも含め、ギターなどのプレイヤーが使うための機材、レコーディングのための機材ということで、オーディオリスニング用途のものではない。そのためか、HiFiという結果ではないが、周波数特性は非常によく、ダイナミックレンジも広いなど、そこそこの結果にはなっているように思う。
CPUでドライバーレベルでエフェクトを動作させるVSLという新たな規格に対応した第一弾の製品。今後どう発展していくのか楽しみだ。
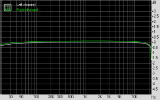 | 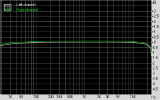 | 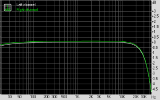 |
| 44.1kHz | 48kHz | 96kHz |
