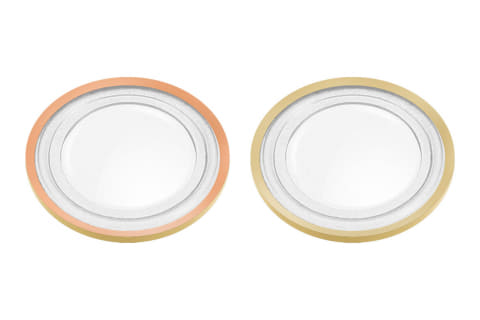鳥居一豊の「良作×良品」
第138回

常識を打ち破る“特殊ガラス振動板イヤフォン!”SIVGA「Que UTG 鵲」聴いてみた
2025年8月19日 08:00
今回はSIVGA「Que UTG 鵲」(直販価格1万5,980円)を取り上げる。本機の特徴はなんと言っても振動板に「特殊ガラス」を使ったこと。実際、ホームページなどをみても、“音響芸術の革命”という形容が出てくる。これがどう革命的なのか。まずはそこに触れていきたい。
筆者を含むご年配のオーディオマニアの間では、「ガラスの音は良くない」という思い込みがある。窓ガラスを叩いてみると「カンカン」とカン高い音がする。
スピーカーの振動板は紙や木材、樹脂などいろいろあるが、それらを叩いてみると(自分の所有するスピーカーで試しましょう)、素材によって多少の違いはあるものの、あまり固有の音はしないイメージだ。少なくともカン高いとかクセの強い音はしないこと。素材が振動すると素材特有の音はどうしても出てしまうが、そういうクセは少ない方がいい。
スピーカーメーカーは、おそらくはいろいろな素材を振動板として使えるかを試してきたはずだ。紙や木材、樹脂などが定番で現代ではアルミなどの金属系素材も使われている。もっとほかにもないか。そこでガラスの出番だ。
ガラスを使って音を出すという発想自体は決して珍しいものではない。ソニーはガラス管を使ったスピーカーとか、有機ELテレビの表面のガラスを振動させて音を出すスピーカーを発売している。こうしたソニーのスピーカーはさすがは現代のプロダクトで、ガラス特有のクセも減ってそれほど不自然な音はしない。だが、ガラスっぽい音がすると嫌う人は少なくない。
筆者はソニーのガラススピーカーの音が気に入っていたし、うまく使いこなせばガラスも決して悪くはないと思っているが、さすがにスピーカーの振動板そのものにガラスを採用となると、ちょっと心配にもなる。というわけでSIVGA Que UTG 鵲のガラス振動板について、いろいろと調べてみた。
ガラス振動板とはどんなものか
まず、ガラスはガラスでも特殊ガラスで、多くの人がイメージする窓ガラスのようなものとは別物ということ。素材の開発は日本電気硝子が行なった「Dinorex UTG」というガラスを使っており、それを台湾のGlass Acoustic innovationsが振動板の形状に成型。ヘッドフォン/イヤフォン用だけでなく、スピーカーのツイーター用、フルレンジ用、ウーファー用といったガラス振動板を商品化している。
どうやらQue UTG 鵲に採用されているのは、画面を折りたためるタイプのスマホに使われる特殊ガラスに近いものらしい。
正確に言えば異なる特殊ガラスではあるが、所有するiPhoneの画面のガラスを叩いてみると、あまりクセっぽい音はしない。どちらかというと樹脂系の素材に近い感じだ。
実際のところ、スマホの画面なんて透明なプラスチックかなにかだと思いがちだが、たまにみかける画面が割れたスマホを見ると、やっぱりガラスだとわかる。ガラスのようでガラスではない、特殊ガラスとはなかなか面白い物質だ。
ガラスというのは不思議なもので、まぎれもない個体なのだが分子構造をみると結晶化していない。つまり液体のように分子構造がランダムな状態のまま固体となっている物質でもある。調べていくと物質としては他にあまり類がなく、いろいろ試してみたくなる素材ではある。
余談だが、古いオーディオマニアはガラスが嫌いかというとそうでもなく、高級AVラックの天板にこぞって採用されていたこともあった。見た目の美しさや平面度が高いなどの理由もあったようだが、強化ガラスならば全体的な強度も高いし、物性としては振動に強いといった特徴もあるのかもかもしれない。
さておき、Que UTG 鵲に採用されている特殊ガラスの特徴を挙げていこう。
ヤング率(弾性率)が従来のプラスチック(PETなどの樹脂系素材)よりもはるかに高く、分割振動が発生しづらい。つまり高剛性だそうだ。そして、極薄加工技術によって剛性を維持しながらも薄く、軽量化ができる。応答速度が速く、ダイナミックレンジの改善にも有効。さらにダンピング特性が低いため、信号を正確に再現できるということのようだ。
気になるのは内部損失。調べてみると内部損失が高いので素材自体の固有音が少ないという文言はある。ただし、比較対象が金属振動板となっていて、メタル振動板よりは固有音が少ないようだ。
うがった見方をすれば紙や木材、樹脂よりは内部損失が少ないが金属よりは多いという感じだろうか? だが、今や金属系の素材もスピーカーやイヤフォンの振動板として使われている時代だ。特殊ガラスならばなおさら、ある程度素材の特性などもコントロールできるものと思われる。
Que UTG 鵲に採用された特殊ガラスは、形状自体もコーン型などではなく平面振動板だ。高級ヘッドフォンで多い平面型と違うのは、平面の振動膜を磁石でサンドイッチして駆動するのではなく、円形の平面振動膜の周囲にエッジがあり、構造自体はコーン型のドライバーに近いものになっていること。
もともと分割振動が発生しにくい高剛性のうえ、振動膜全体が均一に動くので不要な音を出さず音の質感を中耳に再現できるとのこと。長くなってしまったが、こうしてみると、決して悪い素材ではなさそうだ。
Que UTG 鵲は、この特殊ガラスを使った平面振動膜のフルレンジドライバーを搭載している。
振動板以外も凝った作り。ケーブルなども立派で装備は充実
難しいお話はここまでにして、実際に製品を見てみよう。外観はいわゆるカナル型のイヤフォンで外観の印象としてもオーソドックスなデザインだ。
ハウジングは亜鉛合金素材をダイカスト製法で製造。音質にも影響の大きいフェイスプレートには緑壇(グリーンサンダルウッド)を削り出して使用。と、なかなか凝った作りとなっている。
亜鉛合金のハウジングに触れてみると、カチっとした感触で強度も十分。緑壇の木目も印象的で天然の木材をフェイスプレートに採用するのはSIVGAに共通するデザインだ。
イヤーピースを外して音導管の部分を見てみると、出口付近に音響レンズのようなものがある。細かく音響チューニングされているのだろう。
付属のケーブルは高純度無酸素銅に銀メッキを施した線材をリッツ線構造で撚り合わせたもの。柔らかく使いやすく、しかもプレーヤーなどとの接続側の端子は交換式になっていて、3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスの2種類が用意されている。イヤフォン本体との接続はIEMで多く採用されている0.78mmの2ピン端子だ。
イヤーピースはシリコン製で3サイズ、白と黒の各1セットずつ付属。さらに、携帯用にイヤフォンケースまで付属しており、内部のポケットに付属品を収納することも可能。これで、手の届きやすい1万5,980円なのに、なかなか充実した装備だ。
手持ちのイヤフォンとも聴き比べながら、じっくりと音を聴いてみた
では音を聴いてみよう。プレーヤーはAstell& Kernの「PD10」を使用。PD10はクレードルが付属しており据え置きのヘッドフォンアンプなどともバランス接続できることが特徴のモデルだが、今回はPD10本体と直接接続して聴いている。
また、筆者が所有するDITA「dream」、テクニクスの「TZ700」などとも聴き比べ、Que UTG 鵲との音の違いをじっくりと確認してみた。
まずは聴き慣れた曲ということで、クルレンツィス/ムジカエテルナによる「チャイコフスキー/交響曲第6番「悲壮」」の第3楽章を聴いてみた。音源はPD10に転送したハイレゾ音源だ。
特殊ガラス採用ということで身構えてしまったが、音色はむしろ柔らかく耳当たりがいい。温かみのある自然な鳴り方だ。それでいてソフトな表現にならずに細かいところまできちんと出る。バイオリンなど個々の音色は色づけのないリアルな音だ。ガラス特有のクセを感じることはなく、高域はクリアーでありながら硬さを感じるどころかむしろ柔らかい感触でふくよかさがある。
低音も思ったよりもしっかりと力感が出て、最低音域の伸びもなかなか立派だ。空間再現も豊かで広いホールの響きもきちんと再現できるし、トータルのたたずまいが美しい。
DITAのdream(カーボンコーティングされたマルチコート・マイラー振動板)はより高解像度な印象で細部までより精密に描くがやや線が細い。音色は色づけの少ないニュートラルなもので、解像感の高さもあってモニター調の印象となる。低域の伸びもしっかりしているが、中低音の響きはやや少なめで力強いが細身な印象もある。
テクニクスのTZ700(アルミ振動板)は、低音の厚みとパワー感が印象的。そのせいもあってオーケストラ演奏のスケール感も雄大。そのぶん、中高域は素直な鳴り方だがちょっと落ちついた感じもする。また、各楽器の音色と響きが細かく再現され、空間の響きも豊かだ。だから、情報量は多いのだが、響きが多めで各楽器の音自体はちょっと遠い。
DreamもTZ700も単独で聴けばそれぞれに良いのだが、こうして聴き比べるとそれぞれの個性は大きく異なる。指揮台に立ったイメージで各楽器の音色を細かく聴きたいならばdreamがいいし、TZ700は上等な客席でホールの響きを含めて音楽全体を俯瞰するような楽しみ方になる。どちらも情報量は豊かだが、その聴かせ方はかなり異なっているのが面白い。
SIVGAのQue UTG 鵲は、まさにその“中間”。
各楽器の音をきちんと再現しながら、あまり近寄りすぎずに音の減衰やホールの響きなどもきちんとわかる。低音も十分に出ているが、バランスとして低音寄りと感じることもないし、中低音の響きで各楽器の音がマスクされてしまうようなこともない。つまり、とてもまとまりがいい音だと感じた。
DreamもTZ700も価格的にはかなり差がある高級モデルなので、個々の音の精密な描写とか、低音域の伸びやパワー感など、Que UTG 鵲ではちょっと及ばない部分も確かにある。しかし、解像度的にも低音の再現でも落差をあまり感じないし、トータルでのバランスが良いので物足りないという印象にならない。十分に健闘しているし、ちまたでの評判の良さにも納得するものがある。
よく聴く、他の楽曲でもいろいろと比較試聴したが、ボーカル曲での声の厚みと質感の豊かな再現が、Que UTG 鵲の大きな特徴だと感じた。アーティストによる声色の違いを丁寧に描き分けるし、ミキシングでのエコーの付加の違いなども明瞭にわかる。どちらかというと自然でソフトな音なのだが、情報量という点では決して他の高級イヤフォンに負けていない。
では、今回のメインとして「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌2曲を聴いてみよう。
まずはAimerの「太陽が昇らない世界」だが、ハスキーな歌声をクリアーに描き、歌詞もよくわかる。ビートの効いたテンションの高い曲だが、リズムを力強く鳴らしながらもボーカルが埋もれず、むしろボーカルが浮かび上がるような絶妙なバランスで再現する。
今までにないガラス振動板ということで、最先端とか現代的な高解像度サウンドになるかと思っていたが、聴けば聴くほどオーソドックスなバランスだとわかる。おおげさに言えば中域中心の昔のイヤフォンに近い印象。低域の力感や高域の空間描写が不足することはないのだが、声の帯域である中域の厚みと表情の豊かさが際立つ。周波数的なバランスというよりも音楽の聴かせ方のバランスが中域中心になっているように感じた。
そしてLiSAの「残酷な夜に輝け」。苦しい戦いがまだ続くなか、通り過ぎた激闘に思いをはせ、そしてさらなる強敵に挑む勇気を奮い立たせる曲だ。冒頭からいきなりクライマックスのテンションにもっていくAimerも凄い曲だと思ったが、3部作の第一部をきちんとしめくくりつつ、続く第2部への期待を煽る曲に仕上がっているのも凄い。
LiSAならではの情感たっぷりの歌唱が見事で、Que UTG 鵲はまさにLiSAそのものというリアルさと表情の豊かさで歌声が伝わる。主題歌の2曲とも、伴奏を含めて音数は多く、ガチャガチャしがちになる曲ではあるが、声の鳴り方にフォーカスした極上のバランスでしっかりと聴かせてくれるうまさがある。正直このバランスの良さと声の表現力には感動した。
コストパフォーマンスの良さだけでなく、音としてまとめ方のうまさが見事
我ながら年をとると、耳で聞く前に振動板がどうのと頭で理解しようとしてしまいがちだ。それは先入観になって実際の音の印象を歪めてしまって良くないと改めて実感した。
Que UTG 鵲は、ガラス振動板という新規性はひとつの売り文句だが、そんなことは気にせずにまずは音だけ聴いてみた方が良いかもしれない。今回の取材でもいろいろと聴いていくうちに、ガラス振動板というイメージはどんどん消えて、単純に“いい音がするイヤフォン”で音楽を楽しんでいた。
良い意味で、特殊ガラス振動板にはクセとかわかりやすい音の特徴はなく、ただただ“無色透明な音”と言っていいかもしれない。先入観も含めてこれはちょっと意外だった。
また、SIVGAに限らず中国製のイヤフォンやヘッドフォンは、当初こそ価格を度外視したとしか思えない高性能ドライバーの採用とか、珍しい素材を贅沢に採用したとか、特性とかスペックで勝負するタイプが多かった。
実際それでも音が良ければ問題ないのだが、現在の中国製ブランドのモデルにはSIVGAのように、トータルでの音の良さ、素材の良さをしっかりと引き出し、しかも誰が聴いても良い音に仕上げるという技術というより経験やノウハウが蓄積されてきたことがよくわかった。それがこの価格で商品化できてしまうのだから、世界を席巻するのも不思議ではない。中国メーカーというか、SIVGAというメーカーの底知れない実力の高さを改めて実感した。