藤本健のDigital Audio Laboratory
第542回:ネット生放送にも使える低価格USBオーディオの実力は?
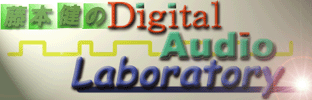
第542回:ネット生放送にも使える低価格USBオーディオの実力は?
24bit/192対応、自由度も高いTASCAM「US-366」
(2013/3/11 14:03)
2%のインフレターゲット…なんて話がニュースにはなっているが、DTM機材のほうは現在もデフレ進行中。3月4日にティアックのTASCAMブランドから発売されたUSBオーディオインターフェイス「US-366」は24bit/192kHzに対応して最大6IN/6OUT、さらにエフェクトも内蔵していながら、実売価格17,800円というのだ。
ニコ生(ニコニコ生放送)やUstreamといった生放送用に利用することもかなり意識して開発した製品のようだが、この価格で音質、性能的に問題はないのだろうか? 実際に使ってみるとともに、オーディオ性能やレイテンシーについてテストしてみた。
ネット生放送向けのモードも備えたミキサー機能装備。Cubase LE 6も同梱
既報のとおり、ティアックからUS-366と下位モデルのUS-322の2機種が発表され、3月4日より発売が開始された。いずれもオープン価格で、実売価格がそれぞれ17,800円、14,800円と3,000円程度の差がある。見た目はソックリなのだが、機能、性能的にはUS-366のほうが圧倒的に高く、この価格差が3,000円でいいのだろうか、と思ってしまうほどの内容になっている。スペック的にみても、US-322が最高24bit/96kHzの2IN/2OUTであるのに対し、US-366は最高24bit/192kHzで最大6IN/6OUT。絶対的にUS-366が魅力的だと思い、発売されたばかりの製品をすぐに借りて使ってみた。
【3月11日18時訂正】記事初出時、「US-322に搭載されていないエフェクトがUS-366にはいろいろと内蔵されている」としていましたが、実際はUS-322にもエフェクトが内蔵されておりました。お詫びして訂正いたします(編集部)
あまりにも面白い機材だったので、借りてすぐにブログでも記事にしてみたのだが、改めて基本的な機能から紹介していこう。
先ほどから「最大6IN/6OUT」という曖昧な書き方をしているのには大きな理由がある。それは設定の切り替えによって6IN/4OUTまたは4IN/6OUTになるというユニークな機材であるからだ。リアパネルを見ると、左からオプティカルの入出力、コアキシャルの入出力、アナログラインのL/R、そしてメイン出力となるTRSフォンジャックのステレオ出力と並んでいるのだが、このうちのアナログラインのL/Rというのが、入出力兼用になっているのだ。設定の変更はボトムにあるLINE I/Oというスイッチで行なう。また隣のDIGITAL INでは入力をオプティカルにするかコアキシャルにするかを選択する。ちなみに、このDIGITAL INは民生用のS/PDIFだけでなく、プロ用のAES/EBUにも対応している。どちらを使うかは、ドライバの設定画面でできるようになっている。
次にフロントパネルを見てみると、ここにはアナログの入力が2系統と、中央にヘッドフォン出力が用意されている。Lチャンネル、Rチャンネルともに、XLRのキャノン端子とTRSの標準フォン端子が1つずつ用意されているが、XLR/TRSのどちらかを使う形だ。ここにはマイクプリアンプが搭載されており、トップパネルにあるINPUT 1、INPUT 2でレベル調整が可能。また、48Vのスイッチをオンにすることにより、ファンタム電源の供給が可能になり、コンデンサマイクが利用できる。なおLチャンネルのTRSフォン入力のほうはライン入力にするかギター入力にするかを切り替えられるようになっている。
これだけの入出力を持ち、ファンタム電源の供給も可能ではあるが、US-366はUSBバス電源供給だけで動作するので、配線も簡単で手軽に使えるというのも大きな魅力だ。
メイン出力のレベルは、トップパネルにある大きなノブを使って調整するのだが、その右隣りにあるMIXERボタンを押すと、PCの設定画面上にミキサーが表示される。これがUS-366の肝ともいえる部分であり、ほかのオーディオインターフェイスとちょっと違う点でもある。
多くのオーディオインターフェイスは入力端子に入ってきたオーディオ信号はそのままDAWなどのアプリケーションへと入っていき、DAWの出力がそのまま出力端子から出ていく。それに対し、US-366ではこのようなDSPミキサーが介在しているので、初めて触ると、ちょっと混乱する面もあるとは思うが、簡単に解説していこう。
まず6IN/4OUTという設定の場合、左に6ch、右に4chで表示されるが、LINE I/OをOUTPUTに切り替えて4IN/6OUTにすると瞬時に左に4ch、右に6chの表示に切り替わる。またトップパネルのMON MIX、つまりモニターミックスがINPUT側に振ってあると、入力された信号がそのままレイテンシーなしにダイレクトモニタリングできるようなっている。
さて、ここでUS-366の非常に強力な機能として見ていきたいのが、ここに搭載されているエフェクト機能だ。まず画面上部にあるのがダイナミクス系のエフェクト。コンプレッサ、ノイズサプレッサ、ディエッサ、エキサイタ、EQの5種類があり、これを各チャンネルにインサーションの形で入れることができる。入力チャンネルに設定すれば、このままDAWへの掛け録りも可能になっているが、使えるのは5つあるうちの1つのみであり、また利用できるのも1chに限られる。ただし、LINKスイッチをオンにしてステレオチャンネル扱いにすれば、ステレオに対して掛けることが可能になる。
このダイナミクス系エフェクトとは独立して搭載されているのがリバーブだ。こちらはセンド/リターンの形となっていてリターン先はメイン出力となっており、掛け録りには使えないが、レコーディング時のモニターにはリバーブがかかるため、ボーカル録りなどには重宝しそうだ。タイプとしてはHALL、ROOM、LIVE、STUDIO、PLATEと5種類があり、PRE DELAY、REVERB TIMEという2つのパラメータも用意されている。
なお、これらの機能を存分に活用できるようにするソフトとして、Cubase LE 6がバンドルされているという点も見逃せないポイントだ。
ここまでの使い方はDAWで利用するための、MULTI TRACKモードなのだが、これとは別にSTEREO MIXというモードもある。これは、US-366をミキサーとして利用できるようにするためのものであり、ニコ生やUstreamなどで利用する場合はこのモードを使う。
6IN/4OUTの設定で、STEREO MIXモードに切り替えると、ミキサー画面がちょっぴり変わる。ここでは6つの入力とともに、PCのオーディオ出力の2chも加わって8INのミキサーとして機能し、出力は2chのみとなる。そして、この出力はヘッドフォン、メイン出力へと出ていくだけでなく、PCの入力としても使われるのだ。つまり、PCのプレーヤーソフトで音楽を再生しながら、マイクで歌ったりやギターで演奏したものをミックスすることができ、それをPCの別のソフトで取り込むことができるのだ。ここで放送用のソフトを使えば、そのまま放送できるし、録音ソフトを使えば、ミックス結果を録音できるというわけだ。
この際、PCの出力を含めたすべてのチャンネルにリバーブを掛けることができるし、いずれかのチャンネルにダイナミクスエフェクトを掛けることもできる。ここまで自由度の高いオーディオインターフェイスというのは、これまでなかったのではないだろうか。
低価格ながら音質も十分
17,800円という低価格なハードウェアでこれだけの機能がテンコ盛りになっているのも驚きだが、音質のほうはどうなのだろうか? とりあえず、マイクやギターを接続してレコーディングしてみると、非常にキレイなサウンドだし、エフェクトの効き具合もなかなか快適だが、いつものツールを使って測定してみてどうなるのだろうか?
MULTI TRACKモードにした上で、メイン出力とフロントのTRSフォン入力をループバックさせる形で接続し、RMAA PROを使って44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHzのそれぞれでテストを行なった。192kHzだけはうまく動作しなかったのでカットするが、それ以外の結果は以下のとおり。いずれの結果ともになかなか良好だ。リバーブのリターンを最大にすると、どうしてもノイズが入ってしまうが、ここではダイナミクス系もリバーブもエフェクトはすべてオフにして測定している。この価格で、これだけの音質を実現できていれば十分過ぎるのではないだろうか?
次にこの接続のまま、レイテンシーがどのくらいあるのかを測定してみた。こちらもいつも利用しているCENTRANCEのASIO Latency Test Utilityを用い、各サンプリングレートごとに行なってみた。ドライバの設定で、lowest latencyからhighest latencyまでの5段階で設定できたので、基本的には一番レイテンシーの小さい、lowest latencyで行なった。ただ、Cubase7を用いて使ってみた際には、いずれのサンプリングレートでもlowest latencyで問題はなかったのだが、なぜか44.1kHzと48kHzのときは、lowest latencyで測定することができなかったため、その上のlow latencyで測定している。
この結果を見ると、高級オーディオインターフェイスと比較すると、若干大き目なレイテンシーではあるが、実用上、問題ない範囲といっていいだろう。またニコ生などのネット放送用デバイスとして見た場合は、関係のないものだ。
ネット放送用にはじめてオーディオインターフェイスを購入する人にとって、このようなミキサー画面は最初、戸惑うかもしれないが、一度使い方を覚えてしまえば、あとは簡単。またミキサーとオーディオインターフェイスと、エフェクトと……というように複数の機材を接続するのに比較すれば、圧倒的に簡単で手軽に扱えるため、今後ネット放送用に必携の機材として広まっていきそうだ。
| US-366 |
|---|
