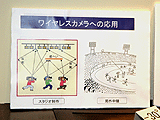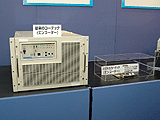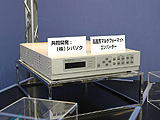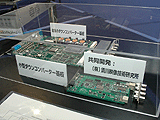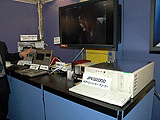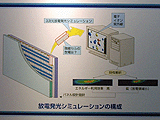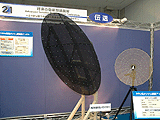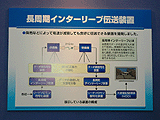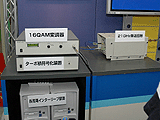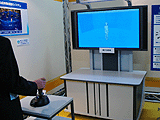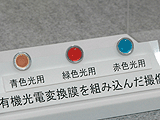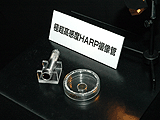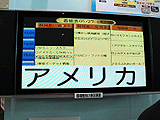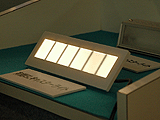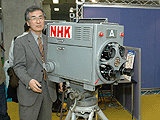| ||
|
◇ 最新ニュース ◇
|
||
|
【11月30日】 【11月29日】 【11月28日】 |
||
|
日本放送協会(NHK)は、東京・世田谷区のNHK放送技術研究所を一般公開する「技研公開2004」を27日から30日まで開催している。入場料は無料。 27日のレポートでは、地上デジタル放送関連の展示や、ハイビジョン光ディスクカメラなどを紹介した。今回はHD映像の無線配信が可能なカメラや、「JPEG2000」に準拠した映像製作用システムなど、番組制作に関する技術を中心にレポートする。
■ ミリ波を利用したコードレスハイビジョンカメラ
ミリ波と呼ばれる55GHzの電波を利用し、撮影したHD映像を無線で伝送するハイビジョンカメラの開発が進められている。ミリ波は帯域が広く、伝送できるデータ量が大きいという特徴があり、マルチパス妨害に強いOFDM方式を採用することで、床や壁、セットなどで電波が複雑に反射するスタジオ内でも安定した伝送が行なえるという。 さらに、OFDM信号のパイロットキャリアに、カメラごとの固有な符号を割り当てて伝送。受信側でデータを解析して混信波を分離することで、同じ周波数を複数のカメラで利用できるという。 また、複数の送受信アンテナを使って伝送路を複数確保し、伝送路に冗長性を持たせる「MIMO」(Multiple-Input Multiple-Output)と呼ばれる伝送方式を採用。電波の遮蔽やフェージングなどに強い耐性を持たせ、将来的にはスタジアムやマラソン中継など、屋外撮影も行なえる安定度を目指す。
ハイビジョン用機材の進化はカメラだけでなく、エンコーダやフォーマットコンバータ、ダウンコンバータなどにも及んでおり、従来機から大幅な小型化、省電力化、ローコスト化を実現している。ハイビジョンエンコーダは回路のLSI化などにより、'96年に開発したモデルと比べ、容積が200分の1、消費電力も100分の1になっている。サイズはハガキ大で、ハイビジョン伝送用機器への組み込みが容易になったという。 また、以前はPALとNTSCの変換や、HD(50i)とHD(59.94i)の変換など、方式ごとに専用のコンバータが必要だったが、1台ですべてのテレビ信号を相互変換できるマルチフォーマットコンバータをシバソクと共同で開発。省スペース化を実現しただけでなく、動き補正機能を搭載し、高画質な変換を実現したという。
■ 「JPEG2000」に準拠したHDTV番組制作システム
デジタル放送では、移動体向けの放送や、携帯端末向け放送、ブロードバンドでの配信など、1つのソースを様々な規格にエンコード、およびコンバートして放送する機会が多くなると考えられている。 しかし、現在の制作現場では複数の規格のVTRテープやノンリニア編集機、フォーマットが混在しており、これらを1つにまとめる研究も進められている。技術研究所が開発しているのは、高い圧縮率と、異なる解像度と画質の映像が取り扱える階層機能を持つ「JPEG2000」に対応したシステム。
昨年はHD映像をリアルタイム圧縮/伸張できるPC用拡張基板を展示していたが、今年はJPEG2000で符号化したデータを局内LANで伝送し、専用のハードウェアを使わずに映像素材の検索や閲覧などができるシステムを展示。「シングルソース・マルチユース」に向けての研究が順調に進んでいることを伺わせる。
■ PDPの高効率化技術
ハイビジョンを超える超高精細な動画を大画面PDPで表示するためには、一層の高効率化と高精細化が求められる。それらを実現するためには、微細セルの放電発光現象を詳細に解明し、新しいセル構造や駆動方法などを開発する必要があるため、研究所ではコンピュータによる放電発光シミュレーションの手法を開発した。
このシミュレータは、画素を構成する放電セル内の電子の動きや、蛍光体を光らせる紫外線の放電・発光過程をモデル化したもの。実験で測定することが難しい、放電エネルギーの量効率など、さまざまな放電特性の解析が可能で、放電セルの構造や駆動波形などの最適化に有効だという。また、放電現象を理解するために、計算結果をわかりやすく可視化表示する機能も備えている。
■ ハイビジョンを超える次世代放送サービス
ハイビジョンを超える高臨場感映像を配信する、次世代放送サービスに関する研究も始まっている。次世代放送には、現在よりもはるかに大容量のデータを伝送するシステムが必要になるが、研究所では2007年から衛星放送で利用できるようになる21GHz帯に注目している。
参考展示していたのは、反射鏡面を折り目が均等な炭素繊維による三軸織物で構成する「メッシュ反射鏡アンテナ」。大きな開口の反射鏡でも軽量化できるとともに、高い鏡面精度を実現し、21GHz帯で良好な反射特性が得られるという。 また、21GHzは降雨による電波の減衰が大きいことが問題になっており、これに対応するため、サービスエリアの降雨データを参考に、衛星からの電波を強くする方法が考えられている。さらに、送信側でデータの並びをランダムに入れ替えて伝送し、受信側でデータの並びを元に戻す誤り訂正技術を長期のサイクルで行なう「長周期インターリーブ伝送装置」も開発。雨天でも安定した伝送を行なうための研究を進めているという。
■ そのほか ほかにも、微小レンズを配列したレンズ板を使って撮影・表示を行なうことで、水平だけでなく、全方向に視差を持つ自然な立体映像を実現するという「インテグラル立体テレビ」の試作機。有機膜を撮像管に組み込んだ「有機撮像デバイス」を使い、光の3原色を分離することで、プリズムのいらない超小型カラーカメラが作れるという技術紹介となっている。 また会場には、最新の研究成果以外にも、テレビ放送開始当時の放送機材を使った撮影デモなど、多様な展示が行なわれている。
□NHK放送技術研究所のホームページ
(2004年5月28日) [AV Watch編集部/yamaza-k@impress.co.jp]
Copyright (c) 2004 Impress Corporation All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|