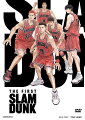鳥居一豊の「良作×良品」
第132回

ソニー驚異の立体音響が進化! 音質・インテリア性を高めた「BRAVIA Theatre Quad HT-A9M2」
2024年5月24日 08:00
かつて「俺の今までの苦労と投資をどうしてくれるんだ!!」とまで言わしめた音場再現の化け物「HT-A9」がマーク2に進化した。戦々恐々としながら新製品と対峙した筆者は、その予想外の変容に驚いた。
まずは概要から紹介しよう。ソニーのホームシアターシステム「HT-A9M2」(直販33万円)は、HDMI入出力を備える小さなコントロールボックスと4本のワイヤレススピーカーで構成される商品。4本のスピーカーは出荷時でペアリングが済んでおり、それぞれの電源を入れれば自動で起動して無線接続が行なわれる。
4本のスピーカーは実際にはフロントLR/サラウンドLRのスピーカーに加え、上部にトップスピーカーを備えており、合計8つのスピーカーでサラウンド再生を実現する。このサラウンドを再現する技術がソニー独自の立体音響技術「360 Sptial Sound Mapping」。8つの実スピーカーからの音の波面を合成し、実スピーカーの外側に複数のファントムスピーカーを生成する技術だ。
例えば、Dolby Atmosならば7.1.4ch、ソニーの360 Reality Audioならば前方9ch、後方6chなど、さまざまなサラウンドフォーマットに合わせて仮想音源を生成し、サラウンド音響を忠実に再現するというもの。
HT-A9の登場時には驚異的な新技術としてデビューした技術だったが、現在ではAVアンプ、サラウンドシステム、サウンドバーなどに採用され、ワイヤレスリアスピーカーの追加などによりサラウンド再生の効果を飛躍的に高める技術として普及している。
HT-A9M2のほかにも、HT-A9000、HT-A8000のサウンドバーの新モデルが登場しているので、4つのスピーカーによるシステムか、サウンドバー + ワイヤレスリアスピーカー(別売)のスタイルかを選ぶこともできる。
すべてのチャンネルを仮想音源とするこの方式のメリットは、実スピーカーの置き場所に依存しない柔軟なレイアウト性の実現にある。つまり、部屋の四方のどこに置いてもいい。ホームシアターでスピーカーが邪魔だと家人に文句を言われることもなく、部屋の邪魔にならない場所に置いたスピーカーから、映画館に匹敵するレベルの立体的な空間再現が可能になるのだ。これまでのスピーカーを使ったサラウンドシステムの常識を根底から覆す驚異的な製品なのだ。
接続安定性を高めた無線接続方式を採用
システムの中核となるコントロールボックスは、見た目もふくめてほぼそのままだ。だが、内部的には数々の進化を果たしている。
まずはAVアンプならばあって当然のホームメニューはなくなった。最初のセットアップや自動音場補正などはスマホアプリの「BRAVIA Connect」から行なう。アプリをインストールして画面の指示に従って設定するだけで、Wi-Fi接続設定や自動音場補正などの設定がすべて行なえるというわけだ。
HT-A9M2にはeARC対応のHDMI出力と1系統のHDMI入力しか備えないので、入力切り替えはリモコンからの切り替えで十分だし、外部スピーカーとしてはソニー製薄型テレビで一括して操作できるので、理にかなった仕様変更だろう。その他の入出力端子としてはLAN端子、S-センター出力があるだけだ。
大きく進化した点は接続安定性だ。4本のスピーカーを無線接続する仕様上、無線の干渉などが原因の音切れが生じることがあった。HT-A9の数少ない弱点だ。これを改善するため、各スピーカーに内蔵する受信用アンテナを1本から2本へ増強。さらに接続状態を常に監視し、電波干渉を検知するとあらかじめ確保していた空きチャンネルに切り替えて安定した接続を維持する「チャンネルホッピング」を実装した。
また、音楽ストリーミングサービスの普及に対応し、2チャンネル音源専用のアップミックス機能を追加。音楽再生だけでなく、テレビ放送のステレオ音源などもそれに適した立体音響で快適に楽しめるようになっている。これに合わせて、最大192kHz/24bitのハイレゾ音源に対応。CDや圧縮音源などをハイレゾ品質にまでアップスケールする「DSEE Ultimate」なども採用してステレオ音源の高音質化に対応している。
なお、HDMIは最新仕様で、4K/120pの入出力、可変リフレッシュレート(VBR)、自動低遅延モード(ALLM)といった機能に対応し、HDR信号はHDR10、HLG、Dolby Visionに対応する。UHD Blu-rayソフトの再生もOKだし、最新のゲーム機にも対応するものとなっている。
壁掛けがしやすい薄型・スリムなボックス形状の新スピーカー
驚いたのは、スピーカーが一新されていること。HT-A9の頃からスピーカーが思ったよりも大きいという印象だったし、スピーカーを小型にして欲しいというニーズもあったと思うが、逆にスピーカーは大きくなった。スピーカーが大きくなったのは高音質化のためで、従来は2ウェイ構成だったメインスピーカーは3ウェイ構成となった。ウーファーが85mm×85mmのX-Balancedスピーカー、ミッドレンジが口径60mm、ツイーターは19mmドーム型となっている。
小型スピーカーでは2ウェイ構成が主流だし、各ユニットの再生周波数帯域を考えても2ウェイで十分にカバーできる。大昔のオーディオがやたらと売れていた時代は商品価値をつけるためにステレオミニコンポのスピーカーを3ウェイ構成とすることも増えたが、あまりメリットはなかったし、小型スピーカーの名機と呼ばれるものはほとんどが2ウェイ構成だ。
ではなぜ、3ウェイかと言うと、もっとも感度の高い人の声の帯域をミッドレンジでカバーできるメリットがある。2ウェイ構成ではフルレンジ+スーパーツイーターという構成でもない限り、人の声がウーファーとツイーターがクロスオーバーする帯域になってしまうので、ふたつのユニットの音色の違い、位相特性の乱れなどによって人の声の再現性に差が出てしまうこともある。安価な製品ではそれが目立ちやすい。このあたりは筆者の想像だが、単純に3ウェイ化による広帯域化(低音再生能力の向上)だけでなく、人の声の再現性を重視した改善と思われる。
さて、スピーカーが大きくなってしまったからと言って、市場に残った在庫や中古品でHT-A9を探す必要はない。スピーカーの厚さは55mm。ずいぶんな薄型でピザボックス形状やパネル型と言ってもいいかもしれない。これによるメリットは壁掛けが容易なこと。部屋の四隅に配置するならばいっそのこと壁掛けしてしまえばよく、その意味ではこうしたパネル型の方が壁掛けがしやすい。それを意識して低音を増強するバスレフポートは底面に空いている。
製品に付属するスタンドはネジ止め式で取り外しが容易に行なえるし、背面には壁掛けのための取り付け用ネジ穴も空いていて、壁掛け時の取り付け用ブラケットとしても使えるようになっている。ワイヤレススピーカーをコンパクトにして設置をより容易にして欲しいというニーズにどう応えるかは難しい問題だと感じていたが、これはいいアイデアだと思う。これにより設置性はさらに高まったと言えるし、高音質化のための3ウェイ化も果たしたというのは妙案だ。
HT-A9は大きな話題となったぶん、電波干渉による音切れの問題のほか、緻密な立体音響にふさわしい基本的な音質の向上などのユーザーからの声が数多く集まったと思う。それにきちんと応えてさらに商品としての魅力を高めている。
このほか、上面を見ると、天井の反射を利用するトップスピーカーが配置されていることがわかる。写真ではわかりにくいが、斜め前方に向けて音が放射されるように角度を付けてあることがわかる。こうしたスピーカーが4つ用意されることで、実スピーカーとしては、4.0.4chの構成になっている。
設置は自由、音場補正機能も簡単でセットアップは簡単
スピーカーはすべてワイヤレスなのでそれぞれの電源のほかは接続不要。薄型形状で置き場所の自由度も高いので設置にも困らない。というわけで、設置などは非常に簡単に済んだ。接続も薄型テレビを常設していない自宅の試聴室では、BDプレーヤーと直接接続してHDMI出力をプロジェクターへ接続している。薄型テレビのユーザーならばeARC対応HDMI入力とコントロールボックスのHDMI出力を接続し、BDプレーヤーやゲーム機などは薄型テレビ側に接続すればいい。テレビの入力を切り替えれば音声も一緒に切り替わるし、マルチチャンネル信号を含めてハイレゾ音源にも対応するeARC対応なので、薄型テレビ側もeARC対応ならば、Apple TV 4Kのような動画ストリーミング端末を使っている場合でも、問題なくDolby Atmos音声やDTS:X音声などを受信できる。
自動音場補正も操作はアプリとなるが、基本的な操作は前作と同様。各スピーカーが測定用マイクも内蔵しているので、別途マイクを接続する必要はない。測定時に再生されるテストトーンの音を分析して、室内の家具の位置や壁、壁の材質などまで把握して最適な音響特性に補正する。筆者はこの瞬間が一番好きで、デモ用の環境音やメロディーを聴くと室内の音響が一変していることに驚く。
低音の充実度も優れるが、それ以上に声の厚みのある実体感のある音が好ましい
では聴いてみよう。まずはCD音源やネットワーク再生でのハイレゾ音源などによるステレオ音源を再生して聴いてみた。サウンドフィールド(以下SF)なしでは普通の小型スピーカーに近い音響になる。確かめてみるとリアスピーカーからも音は出ている。しかし後ろから音が出ていると気付くレベルではなく、あくまでステレオ再生の感触だ。
クラシックのオーケストラ演奏を聴いても、中低音に厚みがありスケール感もなかなか出る。金管楽器や木管楽器の音もキリっと輪郭のたったくっきりとした再現で音の粒立ちが良いし、音色の厚みもしっかりとしているのでひ弱な感じにならないのがよい。
低音域は必要ならば別売のワイヤレスサブウーファーを追加できることもあり、無理に低音域を欲張るような音にはしてない。リモコンで低音のボリュームを操作すると、LOW/MID/MAXの3段階あり、どちらかというと中低音域の厚みが変化する。それなりに音量を出せる環境ならば、音楽再生ではサブウーファーは必要ないと感じた。もちろん、サブウーファーを追加すればよりスケール感も大きくなるし、音の迫力も出るが、低音域のまとめ方が上手いので低音感はきちんと感じられるし、ひ弱さや物足りなさはあまり感じない。
なにより、ボーカル曲の声の再現性が良い。厚みのある声がしっかりとセンターに定位する。ボーカルが目の前に浮かぶような音場感も良いが、基本的な音質がしっかりとしているので声のニュアンスも良いし、抑揚というか声の出方などもよくわかる。
SFをオンにすると、音場がぐっと広がる。しかし、無理矢理に後ろにまで音が回り込むような作為的な音場にはならない。空間としての音場の広さや奥行きが豊かになる印象で、ステレオ音源として聴いていても違和感がない。音楽再生を意識したステレオ音源のサラウンド化という感じで、不自然さもなく気持ち良く音が広がる。そして、シンセサイザーによる浮遊感というか包まれるような広がり方をする音はしっかりと後方にまで音が回り込み、四方から音に包まれるような感覚が得られる。このあたりの立体音響のうまさはソニーならではと感じるものがある。
音楽ストリーミング再生での空間オーディオに近い鳴り方になるし、基本的な音質が向上していることもあって、音が広がっても個々の音像が薄まったりぼやけたりするようなこともなく、くっきりとした見通しのよい音場を楽しめる。
音楽再生での満足度もなかなかのものだと思うが、個人的に感心したのは深夜のアニメ。テレビアニメなので音質には差があるが、しっかりと作られた作品はこのまま劇場公開しても問題ないと感じるほどよく出来ているものが増えている。
そして、一番肝心な「声」がしっかりと力強く鳴るのが実に良い。筆者は特に推しの声優がいるような声優ファンではないが(釘宮病ではある)、個性的な声色や声の出し方など、きちんと感情を乗せた声の演技がよくわかるので、アニメファンはなかなか楽しい視聴になると思う。気になる人はソニーストアでの視聴などで、『「鬼滅の刃」 柱稽古編』、「葬送のフリーレン」、「ダンジョン飯」あたりを見ると、声の良さがよくわかってもらえると思う。
「THE FIRST SLAM DUNK」で、湘北高校バスケ部の歴史と青春を存分に味わう
今回視聴する「THE FIRST SLAM DUNK」は原作者自らが監督・脚本を担当し、まったくのオリジナルストーリーながらも見事に原作の持ち味を2時間ほどの時間に集約した傑作。バスケの動きを精密に再現するために3Dを積極的に活用。そればかりか、シェーディングやテクスチャーの工夫(実際のところどこまで手描きでどこまでCGなのかの区別がつかない)により、作者のカラーイラストがそのまま動いているかのような映像を実現している。
さらに驚異的なのが、音響だ。さんざん見直したが、決して特殊なことをしているわけではない。だが、Dolby Atmosの立体音響における個々の音の音質、音の定位や反響、細かく配置されるひとつひとつの音、それらの精度が極めて高い。そのため、屋外のコートで、体育館の中で、キャラクターがボールをドリブルしている時のボールが弾む音を聴くだけで、そこがどこなのかがわかる。誰でも一度は聴いたことがあるだろう、体育館という残響が非常に長く独特の音の響きを持つ空間でバスケットボールが弾む音が極めてリアルに再現されているのだ。
また、カットによって選手と選手が真っ正面から対峙するような近接したカット、コートのわきから見守る湘北バスケ部の控えのメンバーの視点、さらに俯瞰して応援席にいる観客達の視点、これらによってボールの弾む音、キュッ、キュッと鳴る独特な足音の響きや反響の量が変化している。だから、全国クラスの実力を持つ山王工業高校のプレッシャーも感じるし、一時は20点差という絶望的なスコアになるなか諦めずに声援を送る部員の気持ち、声援をおくる友人たちの気持ちになれる。サラウンド音響の魅力が臨場感だとするならば、これほど臨場感豊かなソフトは他にあまりない。
音場再現の化け物とでも言うべきHT-A9M2で楽しむには最適な作品だ。
再生では、音声はDolby Atmos、SFはオン、低音はMIDで聴いた。最初のトップメニュー(驚くべきことにチャプターメニューがない。チャプター自体はあるので手動で飛ばすことは可能)でボールが弾む音が鳴っているが、この時点でHT-A9M2が怖ろしいくらいの空間再現能力を持っていることがわかる。部屋の中が体育館に早変わりするのだ。
物語は原作でもクライマックスとなる山王工業高校との対戦を中心に描かれる。そこにそれまでの登場人物や湘北バスケ部の過去がクロスオーバーしていく構成だ。ここでは、バスケの試合シーンを中心に見ていこう。序盤、湘北、山王ともに初手から全力でのぶつかり合いになるが、空気感としてはまだまだ緩い。宮城リョータは相手のディフェンスの当たりの強さに閉口するが、実際身体が接触するときのバチっとした音が入っていて、緊張感がたっぷりだ。
こうした細かな音までくっきりとした音で再現するので、まだまだ温度は低いもののヒリヒリとした空気感はよく出ている。低音はボールの弾む音などがやや軽いが、アクション映画の爆発音や銃撃戦というわけではないので物足りなさは感じない。
試合が急展開するときに絶妙なタイミングでBGMが重なるが、この時のボーカルの叫ぶような歌声は厚みがあって聴き応えがある。ドラムなどのリズムはさすがにサブウーファーがあった方が迫力が出るが、出音の速さと勢いがしっかりと出るので、試合が一気に動くときのスピードやテンションの高まりがよく伝わる。
質の高い低音のポイントは絶対的なローエンドの伸びや量感ばかりではなく、このスピード感だと思う。HT-A9M2の低音は映画のLFEまで担当しようというと、ローエンドの伸びも量感も足りないが、スピードとキレ味があるので物足りなくはない。メインチャンネルの低音としては質が高く良い低音だ。
本作はすでにテレビアニメとしても放送されているが、キャスト陣は一新された。ほとんど情報が明かされなかった公開前の段階では声のイメージが違うなどの意見もあったが、劇場公開後にはおおむね好意的な反響だったと思う。
それはもちろん新キャスト陣の熱演によるものだと思うし、試合の中での彼らの声が原作そのものだった。ボソっと呟くような独り言、荒い息とともに絞り出す声、仲間を鼓舞する声、それらの演技はまさに真に迫ったものがある。そんな声が、実体感たっぷりに聞こえる。この声の再現性は大きな進化だと思う。
ボールが弾む音のリズム感、あらゆる方向へパスされるときの移動感、そういった音の定位や移動感も見事に再現するが、それ以上に感心するのがさまざまな音が一体となって空間を造っていることだ。
この空間再現は見事なもので、体育館という一般的な室内以上の広さと響きを感じるし、そこできちんとバスケの試合が行なわれている。作り手の狙いどおりの空間再現だと感じるし、その迫力と緊張感がよく伝わる。よくぞここまでと思える再現だ。
本作で一番の聴きどころは声だと思うが、彼らの人生におけるクライマックスと言える時間を熱演しそのエネルギーをいかんなく再現できている。荒れた息づかいを含めた細かな音の再現もくっきりと聴きやすく、情報量豊かだし、プレイ状況に応じて位置関係が目まぐるしく変化するバスケの試合の中で、声もしっかりと移動し定位するので状況の把握がしやすいし、プレイヤーへの感情移入度も高まる。
それらすべては「返せ」の一言に集約されるだろう。ネタバレになるので詳しくは説明しないが、その声が頭上からおおいかぶさるように聞こえる。本作をDolby Atmosで聴かなければ意味が無い理由がここにあるし、これが再現できないようならセッティングを見直した方がいい。その声をしっかりと印象的な存在感をもって再現してくれた。
映画の音を自宅で楽しみたいと思った人の善きパートナー
音を聴けば33万円という価格は決して高価ではないと言えるが、額面としての33万円は誰にでも出せる金額というわけではない。33万円の予算があれば、AVアンプとスピーカーでそれを超えることができるという人も居るだろう。このあたりは人それぞれに予算感も違うし、どこまで行くかの意識にも違いがある。
ただ、「THE FIRST SLAM DUNK」という作品をドルビーシネマやIMAXなどの劇場で鑑賞して、その音の印象をひとつの基準とするならば、HT-A9M2はその基準を満たしていると思うし、そのために経験や知識といったユーザーの技量も問わない。これは素晴らしいことだと思う。
BDソフト(おそらくは作り手側の意図であろう、本作は現時点でストリーミングサービスなどでの配信は行なわれていない)としても怪物的な作品だが、年内は王座に君臨しつづけると思っていたらまさに怪獣そのものである作品が発売されていて、その王座も危うい。ドルビーシネマなどのプレミアムな映画館が増えることに比例して、映画の音は飛躍的に良くなってきている。その音を自宅に持ち帰りたいと思った人は少なくないと思うし、決してホームシアターに詳しい人ばかりではないだろう。その時、HT-A9M2という製品があることは多くのファンにとっての最高のパートナーになるはずだ。