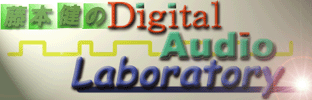
第415回:開発者に聞く、DSDレコーダ「MR-2」開発の背景
~一番力を入れたのはマイク部分 ~
 |
| 左からコルグの商品企画室レコーダー企画担当 西堀佑氏、開発部レコーダー開発担当マネージャー 永木道子氏、国内営業部レコーダー商品担当マネージャー 宮永和紀氏 |
インタビューは、コルグの国内営業部レコーダー商品担当マネージャー 宮永和紀氏、開発部レコーダー開発担当マネージャー 永木道子氏、そして商品企画室レコーダー企画担当 西堀佑氏の3名(以下敬称略)に答えていただいた。
■ 4年越しの進化ポイントとは?
藤本:MR-1から4年が経過しました。この間、世の中はポータブル・リニアPCMレコーダーブームともいえる状況になっていましたが、どのようにご覧になっていましたか?
 |
| 国内営業部レコーダー商品担当マネージャー 宮永和紀氏 |
同時に次の製品をどうするべきか社内で議論を重ねていました。4年という期間は長いように思われるかもしれませんが、私たちは着実に進化していく過程は見ていましたし、必要な4年間だったと考えています。その間、裾野が広がっていっただけに、本当にいい製品が完成すれば、買っていただけるはずだという確信もありました。
藤本:開発に4年間もかけるというのは、すごいと思いますが、MR-2はMR-1と比較して、何がどのように進化したのでしょうか?
 |
| 商品企画室レコーダー企画担当 西堀佑氏 |
西堀:初のポータブルタイプのDSDレコーダとしてMR-1を出したことによって、お客様からさまざまなフィードバックがありました。その中にはやはりいくつかの共通する改良すべき点があったため、それを解決したのがMR-2です。具体的に進化したのは大きく4点です。
まず、MR-1の記憶メディアが内蔵の20GBのHDDだったのをSD/SDHCに変更したこと。今なら最大で32GBのメディアがありますし、容易に交換もできるので、使い勝手は向上しました。2つ目は、リチウムイオン電池で駆動するものを単3電池2本で駆動するようにしたこと。内蔵バッテリだといざ使おうとしたときに充電切れで使えないといった問題を解決することができました。そして3つ目はマイクが外付けであったのを内蔵にしたこと。4つ目は、各シチュエーションですぐに使えるEQやリミッター、ステレオエンハンサーなどのプリセットを40種類、用意したことです。
■ 一番力を入れたのがマイク部分
 |
| DSDポータブルレコーダ「MR-2」 |
西堀:やはり一番力を入れたのがマイク部分です。せっかく最高の音質で録音することができるDSDのレコーダですから、それに相応しい音が録れるマイクにしなくてはならないので、かなり時間をかけて開発しました。
命題としてあったのは「ダイナミックレンジを大きくすること」、「細かなニュアンスもノイズに埋もれずに確実に捉えること」の2つ。これを実現するために数多くのマイクユニットの中から、目的にマッチしたものを選び出すとともに、それに合ったアナログ回路を構成していきました。
藤本:実際、そのマイクユニット選びでは、どのようにして行なったのでしょうか?
 |
| 開発部レコーダー開発担当マネージャー 永木道子氏 |
具体的には各種和楽器の演奏であったり、オペラであったりを、複数のユニットで録音したのです。和楽器は予想以上にダイナミックレンジが広く、小さい音から衝撃的な大音量までを捉えるのはなかなか大変でした。またオペラでは役者さんからの直接の音と、劇場の壁から反射してくる音の両方を捉えるわけです。しかし、これを普通のマイクで録ると、どうしても情報が多すぎて、どこから音が聴こえてきているのか分からなくなってしまいます。それを確実に捉えられるものとして、マイクユニットを決めました。
藤本:マイクユニットさえ決まれば、ほぼ完了となるのですか?
永木:いいえ、マイクは外側をどうするかつまりハウジングの形状構造によって、その特質は大きく変化します。具体的には、メッシュ形状となっているネットの穴の形状をどうするか、ネットの材質や厚みをどうするか、また穴の大きさは……と非常に数多くの要素があり、それによってマイクが捉える周波数帯域に大きな変化をもたらします。
西堀:当初、そのハウジング自体までを内部で作りこもうとしていたんです。さすがに、それでは時間がかかりすぎるだろうということで、ハウジングに関しては、マイクユニットメーカーも各社いろいろなノウハウを持っていますから、ユニットメーカーと協力しながらやりましょう、となりました。
永木:それでユニットメーカーさんの無響音室をお借りしてさまざまな測定をするなど、徹底的に調査をしながら、形状を決めていきました。
 |  |  |
| 上側、裏側と大きな面積がとられている | 光に透かして見ると、内側中央部分に浮くような形でマイクユニットが設置されている | |
■ マイクの向きが変えられるのは、社長の意見
藤本:ハウジングにおいて、音の良さを決めるポイントをひとつ挙げるとしたら、何になりますか?
 |
| 右サイドには8段階で210度回転するマイクダイヤル |
藤本:確かに、このマイクの向きを変えられるというのはユニークですよね。
西堀:実は、これ社長の意見でした。当初のプロトタイプでは方向は固定していたのですが、社長が「置いた状態でも、マイクがこちらに向くように」って。直感的に本質をつかれて、目から鱗でした。
確かに、マイク方向が固定されているのが、現在のポータブルレコーダの欠点ともいえます。その方向を少し変えるために、レコーダーごと動かさなくてはならないですから。MR-2には2箇所に三脚穴を用意しているのも、マイクの向きを自在に変化させられるための工夫のひとつです。
藤本:実際、他社のレコーダとの比較もされていると思いますが、マイクの音として、やはり勝ったという思いをお持ちですか?
永木:勝った、負けたではなく、やはりここは好みの問題だとは思います。ただし、DSDの性能を十分引き出せるマイクになったとは思っています。アコースティック楽器を録るのには非常に向いていますし、ライブを録るのにも最適で、両方ともいけるマイクですね。
藤本:そういえば、MR-1のときは外付けマイクの端子が特殊であるという問題もありました。
宮永:ミニ端子でLとRが別々であったため、使いにくいという声はいただいていました。もっとも、分岐ケーブルはオプションで販売していましたが、市販の三端子のマイクがそのまま使えるようにしてほしいという意見は多かったですね。今回、そのご要望に応えるとともに、プラグインパワーにも対応させています。ただ、そうすると、前の方がよかった、なんていう声も届いてくるので、なかなか難しいところです。
■ 細かい制御で、単3電池駆動を実現
 |
| 単3電池2本で駆動する |
永木:実はDSD対応のA/D、D/Aというのは消費電流が非常に大きく、それが載っているだけで、普通のICレコーダに相当する電流を食ってしまうのです。そのため、各モジュールごとに、使っていない回路の電源を切れるようにするなど、細かく制御することで、省電力化をし、なんとか普通の電池が使えるようにしました。
藤本:録音プリセットの話も出ていましたが。これはEQなどを使った掛け録りということですか?
西堀:はい、ここにはEQ、リミッター、ステレオエンハンサー、そしてローカットの4種類があり、これらをかけた音を録音するようになっています。ただし、他社の多くの製品と大きく違うのは、これらがすべてアナログ回路で構成されているということです。せっかくのDSDなのに、一旦PCMでA/D変換して、デジタルエフェクトを通してからD/A変換をかけるといったのでは、本末転倒ですからね。すべてアナログ回路で処理した音をそのままDSDでレコーディングするようになっています。
永木:しかも、そのアナログ回路のパラメータをデジタルで記録・再現できるようにしているので、この部分の開発にもかなり時間がかかりました。
藤本:ここまでお話の中心はマイクやアナログ回路が中心でしたが、DSDあるはリニアPCMのレコーダの仕様としては、とくにMR-1からの進化点というのはないですか?
永木:ええ、MR-1からすでにDSDIFF、DSF、WSDとすべてのDSDフォーマットを採用していますし、PCMもとくに違いはないですね。ただし、録音フォーマットという面では、MR-1にはなかったMP2が追加されています。
藤本:MP2って、規格があることは知っているものの、ほとんど使った経験がなく、あまり対応している機材を見たこともありません。あえて、これをMR-2に採用した理由はあるのですか?
西堀:これもMR-1ユーザーからの戻ってきた声を反映させたものです。確かに国内ではあまり使われていないMP2ですが、ヨーロッパのラジオ局ではMP2が標準的に使われており、MP2に対応して欲しいという声があったのです。ラジオの業務用途でもすぐに使えるようにと対応した次第です。
■ DSDの音の良さを体験できる「MR倶楽部」を創設
 |
| DSD以外にも、WAV、MP3にも対応している |
宮永:各社24bit/96kHz対応となっている中、24bit/192kHzで録音できるというのも、MR-2の大きな特徴です。
永木:DSDと192kHzのどちらが「いい音」かというと、好みの問題かと思います。ジャズやクラシックなどはDSD、ロック系などパンチの効いた音ならPCMがいいという方もいらっしゃいますし……。ただ、DSDは一番自然で空気感まで丸ごとありのままを録音できるフォーマットだと思いますので、まずは一度DSDで録音してみることをお勧めします。
後で付属ソフトのAudioGateで自由に変換することができるので、PCMに変換しDAW上で好みの音に加工できます。AudioGateVer2.0には新開発のKORG AQUAを使用して直接高音質CDを作成したりDSDディスクを作成する機能もありますので、ぜひいろいろと活用してみていただきたいと思います。
宮永:ぜひ、多くの方にMR、そしてDSDの音の良さを体験していただこうとMR倶楽部というものを作りました。これまでMR倶楽部ではMRのユーザーを対象に2回の録音会を行なってきました。
1回目は弦楽四重奏のレコーディング、2回目は明治神宮でのフィールドレコーディングを行なってきました。が、MR-2の発売を機に、対象を広げてMRをお持ちでない方も参加できる会にし、年に4回の録音会を開いていく予定です。参加できる人数には限りがあるものの、持っていらっしゃらない方にはこちらからお貸し出ししますので、ぜひ興味のある方にご参加いただきたいと思っています。まだ詳細は決まっておりませんが、Webなどを通じてお伝えしていく予定です。
藤本:本日はありがとうございました。
